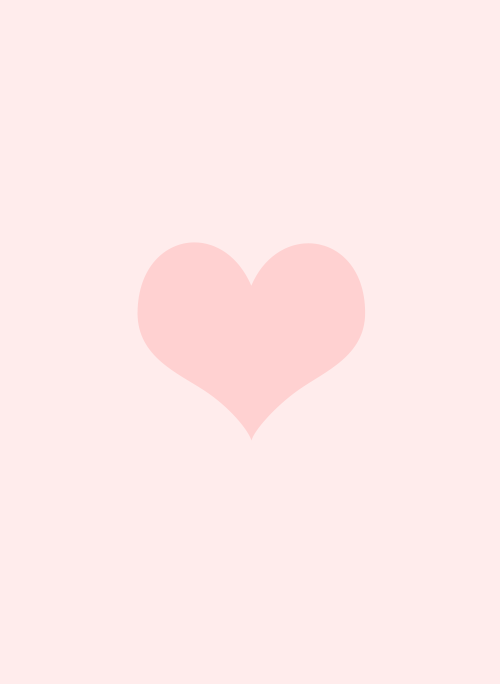Sweetie Sweetie Sweetie
リンの部屋からスタートした、十八歳。
その時、リンが話した提案を受け、デリバリーヘルスのキャストとして、本格的な“おシゴト”をすることになった。
リンが言っていた、高校生だけれど黙っていれば何とかなる店に入店して、高校には通っていない十八歳、という架空のプロフィールを作ったけれど、本当は、高校に通っている、という事実が、いつ、どこで、発覚するかわからないから、撮影は断り、顔出しNGというかたちでの在籍となった。
“おシゴト”の運びは順調で、あのリピートしたいと言っていた人が、さっそく指名をしてくれたし、新人期間中は、新規やフリーの客を、優先的に回してもらえるから、スケジュールはどんどん埋まっていった。
未収のために初めて“おシゴト”をした時は、壊れてしまいそうだと思った行為も、二回、三回、と繰り返すと慣れてきて、何より、店に在籍しているキャスト、という肩書きが、するべき業務をこなしているだけ、という本来の意味での『仕事』の感覚を与えてくれたから、楽に割りきることができた。
夏休みだったから、自由はあったけれど、この頃には、母親が父親のところから帰ってきていたから、無言で出かけるわけにはいかず、友達と遊ぶ、という定番のものから、塾に通いたい、というものまで、様々な理由をつけて、できた時間を使って、“おシゴト”に没頭した。
そうしていると、リンと同じ世界を生きているのだと実感できて、リンとの繋がりが、より確かで近くになったような気がして、安心できた。
一時は空っぽになってしまったお金も、徐々に増えてきて、また、リンの店に通えるようになった。
リンは、早く綺麗にしてあげたいから、と言って、いつも、アフターに誘ってくれた。
その場所は、もちろん、
夜景の綺麗な、静かで落ち着いた、
リンの部屋。
その時間が、傷の深いほど甘くなるのなら、
どれだけ傷ついてもいい、
なんて、思うこともあった。
「ミィちゃん、“おシゴト”頑張ってるみたいだね」
「うん」
「そんなに稼いで、どうするの?」
もっと強く、リンと繋がっていたいから。
「ねぇ、どうするの?」
「それは……」
そのための方法を、私は、もう、見つけていた。
「……まだ、内緒だよ」
そう、そのための方法は、
まだ、内緒だけれど……
★★★★★