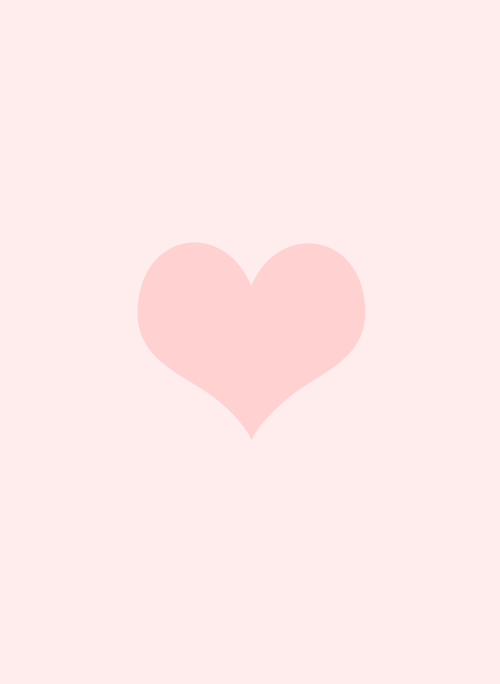もう一度、名前を呼んで2
……───
『それでまあ結局、エリクは出国できないしエドはビビってる、ってことでわたし1人で来たのよ。ついでに仕事も少し入れられたしちょうど良かったわ』
『そうだったんだ……』
帰宅した時は夕暮れ前だったにもかかわらず、窓の外はもう真っ暗だ。長い時間話し込んでいた。
あたしの知らない間にみんな色んな苦労をしていた…。エドはもちろん、エリクも、ジュリアも。リンとティルだってきっと凄く大変で、あたしは迷惑をかけてしまったんだと思う。
「こんなにたくさん迷惑をかけたのに、帰ってもいいのかな……」
あたしがまず思うのは、それだ。
みんなにこんなに苦労をかけたのに、のこのこ帰っていいんだろうか。許してくれる?みんなに許してもらえないのなら、ここで苦しみ続けた方がましだ。
『……帰れない、なんて思ってるんじゃないでしょうね?』
ジュリアは日本語はそんなに分からないから、あたしの小さな呟きなんか聞こえてないかと思ったけれど察したらしい。暗い表情を見ればわかるのかもしれない。
『アイナ、気に病む必要はないわ。わたしたちはあなたに戻って来てほしい一心でこんなに頑張ったのよ。あなたが居なければエドだけじゃない、みんな活気がなくて暗いままなの。あなたはわたしたちに必要なのよ』
ぎゅっと手を握られて、ジュリアのまっすぐな視線に射抜かれた。
『ああほら、泣かないの。こっちへいらっしゃい』
ありがとう、ありがとうジュリア……
あたしのほしい言葉をこんなに真っ直ぐに言ってくれるなんて。
『……帰りたい。アメリカに帰りたいよ……エドに会いたい』
そうすればこんなに途方も無い寂しさを感じることもない。きっと満たされてあたしは幸せに生きていける。エドの側で。何があっても。
『帰りましょう、わたしと一緒に』
『うん…うん……!』
暖かく抱きしめてくれるジュリアの胸で声をあげて泣いた。
どこに居ても寂しくて、ぽっかりと空いた穴がゆっくりと塞がって行く気がする。ジュリアやエドはあたしの家族だった。優しくて暖かくて、安心する"帰る場所だ"って思う。
だからこそ。
『あたしね、こっちでも大切な人たちがいるの』
悠唏たちに、話をしなきゃならない。
『それでまあ結局、エリクは出国できないしエドはビビってる、ってことでわたし1人で来たのよ。ついでに仕事も少し入れられたしちょうど良かったわ』
『そうだったんだ……』
帰宅した時は夕暮れ前だったにもかかわらず、窓の外はもう真っ暗だ。長い時間話し込んでいた。
あたしの知らない間にみんな色んな苦労をしていた…。エドはもちろん、エリクも、ジュリアも。リンとティルだってきっと凄く大変で、あたしは迷惑をかけてしまったんだと思う。
「こんなにたくさん迷惑をかけたのに、帰ってもいいのかな……」
あたしがまず思うのは、それだ。
みんなにこんなに苦労をかけたのに、のこのこ帰っていいんだろうか。許してくれる?みんなに許してもらえないのなら、ここで苦しみ続けた方がましだ。
『……帰れない、なんて思ってるんじゃないでしょうね?』
ジュリアは日本語はそんなに分からないから、あたしの小さな呟きなんか聞こえてないかと思ったけれど察したらしい。暗い表情を見ればわかるのかもしれない。
『アイナ、気に病む必要はないわ。わたしたちはあなたに戻って来てほしい一心でこんなに頑張ったのよ。あなたが居なければエドだけじゃない、みんな活気がなくて暗いままなの。あなたはわたしたちに必要なのよ』
ぎゅっと手を握られて、ジュリアのまっすぐな視線に射抜かれた。
『ああほら、泣かないの。こっちへいらっしゃい』
ありがとう、ありがとうジュリア……
あたしのほしい言葉をこんなに真っ直ぐに言ってくれるなんて。
『……帰りたい。アメリカに帰りたいよ……エドに会いたい』
そうすればこんなに途方も無い寂しさを感じることもない。きっと満たされてあたしは幸せに生きていける。エドの側で。何があっても。
『帰りましょう、わたしと一緒に』
『うん…うん……!』
暖かく抱きしめてくれるジュリアの胸で声をあげて泣いた。
どこに居ても寂しくて、ぽっかりと空いた穴がゆっくりと塞がって行く気がする。ジュリアやエドはあたしの家族だった。優しくて暖かくて、安心する"帰る場所だ"って思う。
だからこそ。
『あたしね、こっちでも大切な人たちがいるの』
悠唏たちに、話をしなきゃならない。