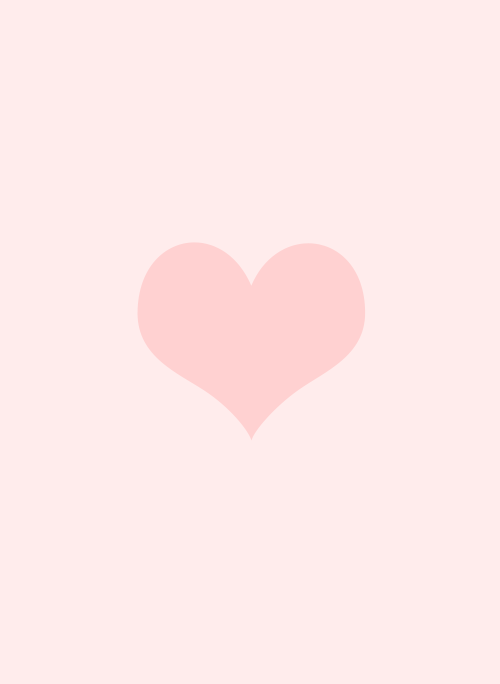「先生、愛してる」
そんなことだから、秋奈に「どうしたんですか。らしくないですよ」なんて笑われてしまった。まるで愛しい我が子を見つめるような微笑みだった。
「妙に嬉しそうに笑うね」
「ごめんなさい。先生でもそんな風に心配事なんてするんだと思ったら、何だか可愛らしくて」
年下の、しかも生徒に言われてしまってはまるで立場がないじゃないかと僕は眉を顰める。
「あまり僕をからかうんじゃない」
そう言うと、今度は声を出して笑った。頭を搔く。珍しく笑ったかと思えば僕をからかっているわけだから、心境としては複雑極まりなかった。
声を抑えると、秋奈は言った。
「大丈夫。私はどこへも行きませんよ。少なくとも、今がある限りは。先生も言っていたじゃないですか」
その言葉に、呟くほど小さな声で僕は同意した。
窓に映る夕暮れを背に立つ秋奈が、妙に儚く見えた。そこにいるのに、掴もうとすればすり抜けて、次に顔を上げた時には存在すら無くなってしまっていそうな。空間に消えゆく彼女を想像して、僕は否定的に目を瞑った。
「もう、帰る時間じゃないのか」
想像に見えた結末を避けるように、僕は言った。時計を見て秋奈も頷く。
帰宅準備を済ませた秋奈を見送ると、すぐに扉を閉めた。
彼女を帰すこの瞬間が、僕はどうしても嫌いだった。関係という見えない壁を表す一瞬のようで、扉を閉める度に心苦しい思いをする。溜め息を吐く。少しすると、秋奈が去っていく足音がした。
これが普通。これが当たり前。僕が学生だったあの頃のように触れ合うことは、もう二度と許されない。どれだけ彼女が愛おしくとも、守るべきものだけは明確にしておかなくてはならない。そんなこと、改めて考えなくとも分かっている。そうだろう、と自分に言い聞かせて心臓の辺りを強く掴んだ。
いや。少なくとも、その時が来るまでは。
思わず口角が上がった。