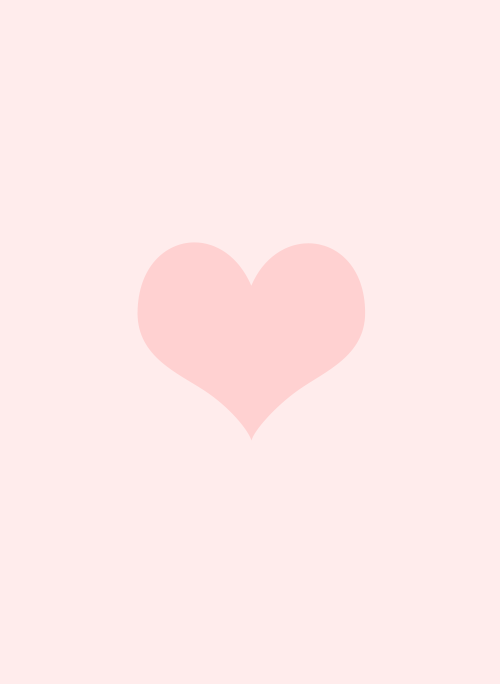真夏の青空、さかさまにして
わざと空けてくれているはずの隙はむしろ掛かり手を攻め立てているようだったし、普段と変わらないだろうのんびりとした声色は僕が掛かり手だったら、そんなのわかってるよ、ってイライラしてしまったかもしれない。
部員数たった6人の弱小部の主将だからって、ちょっと舐めてた。
あの人はとびきり剣道の腕が立つわけではないけど、さすが顧問がいないも同然らしい生徒だけの部活をひとりで引っ張っているだけある。ちゃんと、自分にも、周りにも厳しい人だ。
きっと今朝の練習でもあの菩薩みたいな顔で「まだ元気そうだからランニング追加しようか」とか鬼みたいなことを言い出したに違いない。うん、絶対そうだ。
「じゃ、手を合わせてください」
ぱちん、と数十分前の動作をもう一度繰り返すみんなの表情は満足げで、味噌汁を沸かした小鍋もおにぎりが大量に乗ってあった大皿ももうすべて空っぽだ。
手を合わせてから、あ、と声を漏らして真夏が僕のほうを振り向いた。だけど、僕を見てきょとんとしてから、すぐに「へへ」と嬉しそうに笑って前を向き直す。
なんだよ、言われる前に手を合わせただけだろう。嫌だったけどどうせやるから、仕方なく。それなのにあんな風に笑顔を向けられたら居心地が悪い。
「ごちそうさまでした」
「ごちそーさまでしたっ」
本当に思春期まっただ中の高校生の集まりなんだろうかと疑いたくなるくらい快活でまっすぐな声のかたまりに、僕は不本意を精一杯アピールした声を織り交ぜた。
だけど僕の小さな声だけが浮いて、混ざりきれなくて、「子どもみたい」だなんて言って一歩距離を置いた自分がこの中でいちばん子ども染みて思えた。