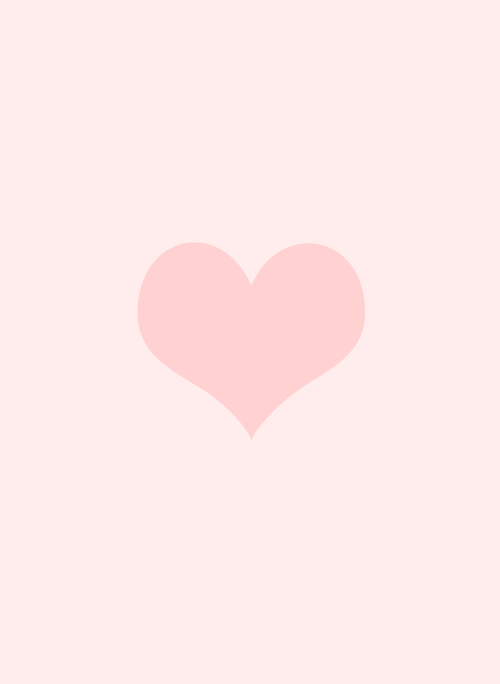極上恋慕~エリート専務はケダモノでした
「でも、今は知られたっていいんだから、もう少し堂々と万佑をかわいがろうかと思ってる」
「やめてください」
ゆっくりと仰向けに身体を倒され、環を真上に迎えた。
「冗談だよ。俺も立場があるし、公私混同はしないようにするつもり。だけど、万佑がそばにいるのに触れられない、俺の気持ちも分かって?」
「……うん」
星が瞬くような彼の瞳は、夜だけ特別な熱を伴って、永遠の恋を映す。
「万佑、愛してるよ」
「私のほうが、きっと愛してます」
「分かってるよ。だって、万佑は俺に惚れてるだろ? 出会ったあの夜から、ずっと俺のことを想ってた」
身体中に降り注ぐキスは真っ白な雪のように優しく、すぐに溶けて身体に溶けていく。
「ねぇ、今夜はどんなふうに愛されたいの?」
―fin―