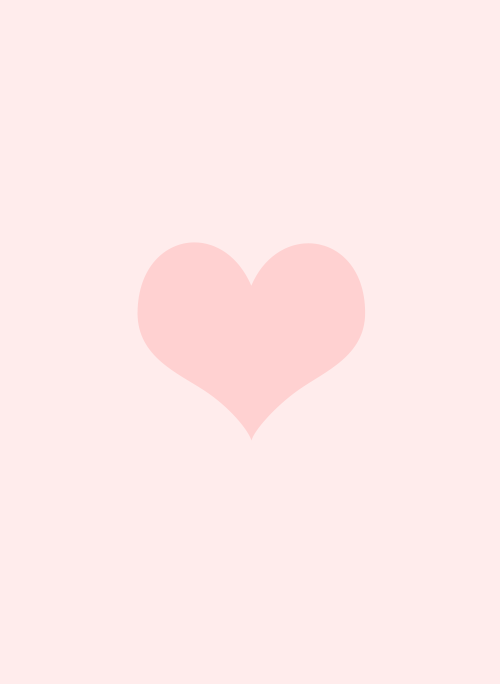蛍火
そっと彼女の背中に腕を回すと、その身体が思っていたよりも随分と小さいことを知った。ふわ、と香ったのは居間の畳の優しい匂い。
太陽の香りじゃなくなったのが少し寂しかったけれど、この香りも彼女らしくて可愛いと思った。
まるで全身が心臓になってしまったみたいに、鼓動が身体中で鳴り響くのを感じる。
ぎゅう、と腕に力を込めると、小さな身体は簡単に引き寄せられた。
ちらりと顔を伺うと、自分の視線に気づいたましろがぽすりと優夜の胸に額をあててその顔を隠してしまった。
その一連の動作が一瞬過ぎて表情が見れなかったのが悔やまれる。
あの赤い顔をしていたのかもしれないし、違うかもしれない。
それでも、自分と同じくときめいていれば嬉しいと思う。
太陽の香りじゃなくなったのが少し寂しかったけれど、この香りも彼女らしくて可愛いと思った。
まるで全身が心臓になってしまったみたいに、鼓動が身体中で鳴り響くのを感じる。
ぎゅう、と腕に力を込めると、小さな身体は簡単に引き寄せられた。
ちらりと顔を伺うと、自分の視線に気づいたましろがぽすりと優夜の胸に額をあててその顔を隠してしまった。
その一連の動作が一瞬過ぎて表情が見れなかったのが悔やまれる。
あの赤い顔をしていたのかもしれないし、違うかもしれない。
それでも、自分と同じくときめいていれば嬉しいと思う。