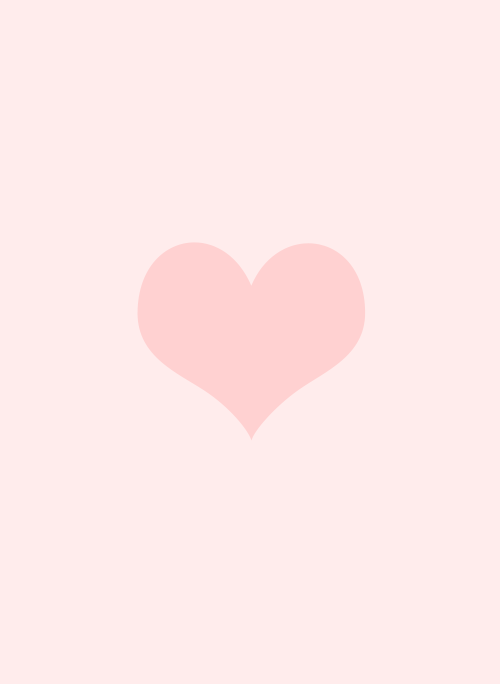夏色の初恋を君にあげる
「あの時から、俺はずっと凛子さんのことが好きで。シーブリーズもあれからずっとシトラスシャーベットを使ってるし、初めて図書室に行った時だって、凛子さんと接点を作るために雨宿りを口実にした」
「……っ」
全部、偶然じゃなかった。
ずっと由良くんは、私を見つめていてくれていたんだ。
「あの日、俺と出会ってくれてありがとう、凛子さん」
「由良くん……っ」
また泣き出す私の両手を、由良くんがそっと握りしめた。
「どこにも行かないで俺の隣にいてよ。それでこれからもずっと、その笑顔を独り占めさせて」
「ふ、う……」
「好きです。付き合ってください」
誠実でまっすぐな声が、それることなく届き、胸の中に波紋のように広がった。
由良くんは、いつだって日陰から私を引っ張り出してくれる。
胸を張って君の隣にいられるように、君という太陽を見つめているために、もう下ばっかり見ているのはやめるから。
「よろ、こんで……っ」
ぽろぽろと絶え間なく涙をこぼしていると、由良くんの柔らかい笑い声が聞こえてきて、力強い腕が再び私を抱きしめた。
彼からは、あの夏の日の匂いがした。
FIN