オトナだから愛せない
締めていたカーテンの隙間からでもチカチカと光が漏れて私にただただ恐怖を与える。
「え、もしかして、この辺に落ちたの……」
布団をぎゅっと握りしめる。小刻みに震える手が止まらない。
早く寝よう、寝てしまおう。朝になれば雷なんてどこかに行っているはずだ。
そう思うのに、それとは反対に私の目は冴えて全く寝付けない。
「……皐月、くん」
思わず、ぽつりと縋るように皐月くんの名前が溢れ落ちた。
皐月くんはきっとまだお仕事中だろう。高校生にもなって雷が怖いなんて情けない。
と、ピコン、と傍に置いていたスマホが鳴った。
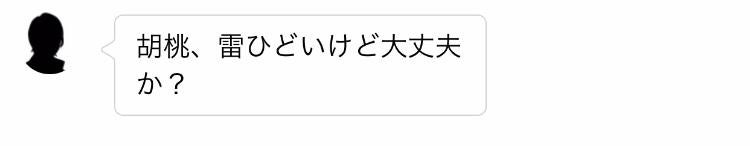
画面に表示されたのは皐月くんの名前。まるで計ったかのようにナイスなタイミングでのそれに、あなたは流石ですか?ヒーローですか?と恐怖に支配されていた私の感情にそんなことを考えるゆとりが生まれた。
皐月くんに大丈夫じゃない怖いって言ったら、どうなるんだろう。冷たくあしらわれるのかな。それに皐月くんは明日も早くからお仕事だから迷惑になるわけにはいかない。
