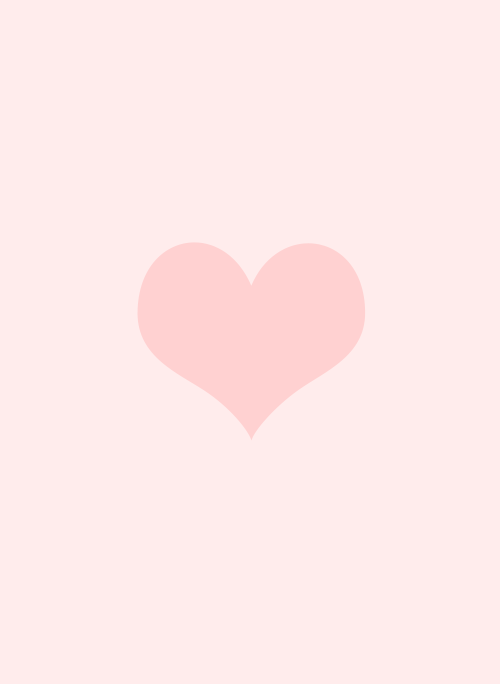情熱
荷造りをほとんど済ませて、里穂の日本での生活もあと1週間というときだった。
その日は突然宗一郎から連絡があったので、里穂はとても驚いた。
明日からは軽井沢の両親のところで過ごして、出国するまでの2日間は空港近くのホテルで過ごす予定になっていたのだ。学生時代から長く住んでいたマンションはもう生活の匂いをすっかり消していた。
宗一郎はまだ冬らしいコートを着て、いかにも仕事帰りという恰好で、大きなカバンを持って、すっかりサラリーマンという感じで現れた。でも出会った頃のように品のある穏やかで明るい笑顔で、少しも疲れた様子を見せなかった。
「タイミングいいのね。明日だったら私、軽井沢に行ってたのよ。出国する前日には東京に戻ってくるつもりだったんだけどね」
「いや、会えなくても仕方ないとは思っていたんだけどさ。でもよかったよ」
食器も調理器具も片付けてしまっていたので、駅のデパ地下で買ったお惣菜やパンを、まるでピクニックのように床に並べて食べることにする。
ワインが飲みたいと思いながら、使い捨てのコップを買うのが面倒なので、ビールで乾杯して、なんだかお花見みたいと二人で笑う。
ここのところ里穂は外食とコンビニが続いていてつまらなかったが、宗一郎がいてくれるとなれば少し違う。一人で食べるのとはまるで違う。誰かと一緒に食べる料理は、それだけで少しおいしい。
そして宗一郎と二人の食事の時間は、まるで子供の頃の思い出のように懐かしく、温かい。
春らしい菜の花と茹で卵やエビを使ったミモザサラダを口に運びながら里穂は聞いた。
「ところで、その渡すものって何なの?」
貴広に渡して欲しいものがある、と連絡をしてくれたのだ。
「いや、貴広のじゃないかもしれないんだけどさ。懐かしいCDが出てきてたんだよ。高校生の頃、部活のみんなとけっこう貸し借りしてて、こないだ会ったときにその話になったんだけど、結局誰のかわからないっていうことで。でもせっかくだし貴広にもらってもらおうかと思って。」
宗一郎はそれだけ言うと笑って気持ちよくビールを喉に通した。
「貴広と会ったの?」
貴広からは何も聞いていなかったので驚いた。
「うん、そう。ロンドンに発つ直前に。二人ではないけどね。高校時代の仲間で。十人くらい集まったよ」
「すごい。盛大なお別れ会だったのね」
「盛り上がったよ」
「そう、よかったわ」
これまでと同じ宗一郎の笑顔を見て里穂は安堵した。
自分と貴広が特別な関係になることで、宗一郎との関係まで変わってしまうことを里穂は恐れていた。それは自分と宗一郎とのことでもあったし、宗一郎と貴広とのことでもあった。もちろん桃子との四人の関係のことも。変わらずにいつまでもみんなずっと気の合う仲間のままでいたかった。
「里穂もよかったら聴いてみて。映画の主題歌だったし、きっと耳にしたことがあると思う。いい曲だよ。最近の気分の曲を7つ答えよと言われたら、俺はこれを入れるかな」
里穂の子どもの頃の7つの物語のエピソードを覚えていたのだなと思ったら、二人でつい笑ってしまった。懐かしい話はほんの少し懐かしい時間を与えてくれる。そして大切なものは何も失っていないのだと実感させてくれる。
「どんな曲かしら。私も聴いてみるわ」
今までと変わらない笑顔で里穂は言って、渡された紙袋を忘れないようにバッグの横に並べた。
それからはいつものように、宗一郎のマンションで過ごしたときのように、他愛ない日常の話や懐かしい思い出の話をして過ごした。平凡で、ありふれた、貴重なひととき。里穂は感謝した。日本を離れる前に最後に会えたことになるだろう友人が宗一郎であったことに。貴広と結婚してもこうやって二人で宗一郎と変わらずに会えたことに。
そして終電の時間が迫ってきたことに二人はちゃんと気づいた。こういうとき、自分たちは似ていると実感する。帰るべきときに、うっかりそのタイミングを逃してしまうようなことはなかった。真面目で、細かいことに気づいてしまって、そうやって気を遣い合って長い間大事にしてきた友情だった。
いつまでもこうしていたいという気持ちは、物語の続きを楽しみに待つように、大切に持っていようと思って、宗一郎の笑顔を里穂は目に焼き付けた。
さようならはいつだって言える。でも、もちろん言わない。
これからだって、また、きっと何度でも会えるはずなのだから。
変わらない友情を祈りながら笑顔を交わす。
「貴広によろしく。気を付けて、元気で」
「ありがとう。落ち着いたら連絡するわ。また絶対、みんなで会いましょうね。宗も体に気を付けて」
「ありがとう」
お互いにありがとうを言って、笑顔を見せあって、美しい別れの場面だった。もしもこれが永遠の別れになってしまっても後悔しないというほど、完璧だった。
宗一郎が靴を履いて玄関に立ち、里穂はその正面に立って「じゃあね」と言って彼を見送ろうとしたときだった。
宗一郎が里穂を抱き締めた。わずか三秒か、そのくらい。
その一瞬、初めて知る彼の腕の強さや胸の熱さに里穂は驚いて目を丸くした。その抱擁は、「愛している」という言葉と、あまりにもよく似ていた。
彼は体を離すと「じゃあ」とだけ言って、今までと変わらない笑顔で扉を開けて、立ち尽くす里穂を置いて行ってしまった。
渡されたCDはエアロスミスの名アルバムだった。そのなかのI don’t want to miss a thingの詞を、里穂は一人、何度も、何度も読み返した。