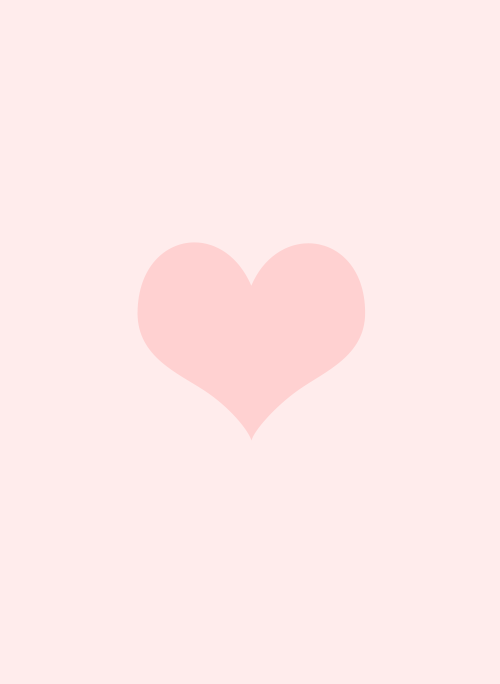河童
縁側に履き物は置いていないので、私は足袋のまま土を踏んで、東コートの袖を引いた。
「河童は目ではなく、頭の皿に水を溜めるものだと聞いてますが?」
「河童の目にも涙、とも言います」
薔子さんはうつむいて、指で目元を拭った。
「あなたなりに精一杯遠慮しているつもりなのでしょうけど、ひどい我が儘は昔から変わっていませんね」
鼻を啜る音がしたので、袂から手拭いを出して渡す。
先程顔を拭いたものであることは言わずにおいた。
「昼寝から起きたとき、私の迎えでないと部屋から出ないと駄々をこねた」
「五つのときのことです」
「仕事で遅れると伝えていたのに、私を待っていると言って聞かず、結局寝てしまって夕餉を食べ損ねたこともありました」
「それは七つか八つです」
「今だって差し伸べた手を断る。恋をされて、乞われて結婚するのでなければ嫌なのでしょう?」
日暮れの速度は早く、薔子さんの顔もどんどんぼんやりとしていく。
昔はしゃがんで合わせた目線は、ほんの少し腰を折るだけで合うようになっていた。
「我が儘なお嬢さまを満足させられるほど、私にも余裕はありません。『どんな苦労も厭わないから嫁にしてくれ』と頭を下げるなら、受け入れましょう」
薔子さんは顔を上げた。
その頭の雪を払う。
変わらない真っ直ぐな瞳に、つい笑みが漏れた。
「思い出しました。秀晴さまはお土産をくださるとき、必ず一度意地悪なさるんでした」
チョコレートをあげたときと同じ表情だった。
「記憶にありませんねぇ」
袂を探ると、煙草の箱が見つからなかった。
卓子の上だろう。
「寒いので中に入りませんか? お迎えはまだのようですし」
足袋を脱いで上がると、床板が氷のようにつめたかった。
薔子さんも素直についてきて戸を閉める。
私が煙草をくわえ、燐寸をすり、火をつけ、煙を吐き出すのを、おとなしく見ていた。
「麦飯は食べられますか?」
一瞬ぽかんとしてから、薔子さんはうなずいた。
「はい。しばらく白いご飯は見ておりません」
「水道は通っていますが、まだまだ井戸水も使っています」
「大丈夫です」
「風呂はありませんし、毎日は無理です」
「わかっています」
入り口でおとないを告げる声がした。
煙草を灰皿に押し付けて立ち上がる。
「今日のところは帰ってください。年が明けたら父に報告して、父から立花様に話してもらいます」
「わかりました」
草履を手にして、玄関で二度目となる暇を告げた。
「これから秀晴さまに好いてもらえる女性になれるよう努力いたします」
「まあ、大丈夫だと思いますよ」
薔子さんは飛び上がるように身体を起こした。
「本当に?」
「ええ。立花家にはもう義理も恩もありませんから子どもだろうが、河童だろうが、気に入ったものしか家には入れません」
薔子さんは腕を大きく振り振り帰っていった。
会社が倒産し、婚約も破談となったご令嬢の見せる顔ではなかった。
私の手拭いは持っていってしまった。
中にもどると、部屋がいつもとは違う匂いがする。
これまでにはない甘やかな匂いだ。
盥に鉄瓶の湯を差し、湯飲みや皿を洗ってから、卓子に戻って煙草に火をつける。
薔子さんはもう家に着いただろう。
風邪はひかなかっただろうか。
幼い頃は熱を出した薔子さんの見舞いに行くと、眠るまで帰してもらえなかった。
私の指を握っていた小さく熱い手は、うつくしく箸を使うようになっていた。
煙をひと吐きして、依頼されていた寸評に取りかかった。
こうして年が暮れていく。
鏡餅のない新年を迎えたら、我が儘なお嬢さまに愛を乞わねば。
了
「河童は目ではなく、頭の皿に水を溜めるものだと聞いてますが?」
「河童の目にも涙、とも言います」
薔子さんはうつむいて、指で目元を拭った。
「あなたなりに精一杯遠慮しているつもりなのでしょうけど、ひどい我が儘は昔から変わっていませんね」
鼻を啜る音がしたので、袂から手拭いを出して渡す。
先程顔を拭いたものであることは言わずにおいた。
「昼寝から起きたとき、私の迎えでないと部屋から出ないと駄々をこねた」
「五つのときのことです」
「仕事で遅れると伝えていたのに、私を待っていると言って聞かず、結局寝てしまって夕餉を食べ損ねたこともありました」
「それは七つか八つです」
「今だって差し伸べた手を断る。恋をされて、乞われて結婚するのでなければ嫌なのでしょう?」
日暮れの速度は早く、薔子さんの顔もどんどんぼんやりとしていく。
昔はしゃがんで合わせた目線は、ほんの少し腰を折るだけで合うようになっていた。
「我が儘なお嬢さまを満足させられるほど、私にも余裕はありません。『どんな苦労も厭わないから嫁にしてくれ』と頭を下げるなら、受け入れましょう」
薔子さんは顔を上げた。
その頭の雪を払う。
変わらない真っ直ぐな瞳に、つい笑みが漏れた。
「思い出しました。秀晴さまはお土産をくださるとき、必ず一度意地悪なさるんでした」
チョコレートをあげたときと同じ表情だった。
「記憶にありませんねぇ」
袂を探ると、煙草の箱が見つからなかった。
卓子の上だろう。
「寒いので中に入りませんか? お迎えはまだのようですし」
足袋を脱いで上がると、床板が氷のようにつめたかった。
薔子さんも素直についてきて戸を閉める。
私が煙草をくわえ、燐寸をすり、火をつけ、煙を吐き出すのを、おとなしく見ていた。
「麦飯は食べられますか?」
一瞬ぽかんとしてから、薔子さんはうなずいた。
「はい。しばらく白いご飯は見ておりません」
「水道は通っていますが、まだまだ井戸水も使っています」
「大丈夫です」
「風呂はありませんし、毎日は無理です」
「わかっています」
入り口でおとないを告げる声がした。
煙草を灰皿に押し付けて立ち上がる。
「今日のところは帰ってください。年が明けたら父に報告して、父から立花様に話してもらいます」
「わかりました」
草履を手にして、玄関で二度目となる暇を告げた。
「これから秀晴さまに好いてもらえる女性になれるよう努力いたします」
「まあ、大丈夫だと思いますよ」
薔子さんは飛び上がるように身体を起こした。
「本当に?」
「ええ。立花家にはもう義理も恩もありませんから子どもだろうが、河童だろうが、気に入ったものしか家には入れません」
薔子さんは腕を大きく振り振り帰っていった。
会社が倒産し、婚約も破談となったご令嬢の見せる顔ではなかった。
私の手拭いは持っていってしまった。
中にもどると、部屋がいつもとは違う匂いがする。
これまでにはない甘やかな匂いだ。
盥に鉄瓶の湯を差し、湯飲みや皿を洗ってから、卓子に戻って煙草に火をつける。
薔子さんはもう家に着いただろう。
風邪はひかなかっただろうか。
幼い頃は熱を出した薔子さんの見舞いに行くと、眠るまで帰してもらえなかった。
私の指を握っていた小さく熱い手は、うつくしく箸を使うようになっていた。
煙をひと吐きして、依頼されていた寸評に取りかかった。
こうして年が暮れていく。
鏡餅のない新年を迎えたら、我が儘なお嬢さまに愛を乞わねば。
了