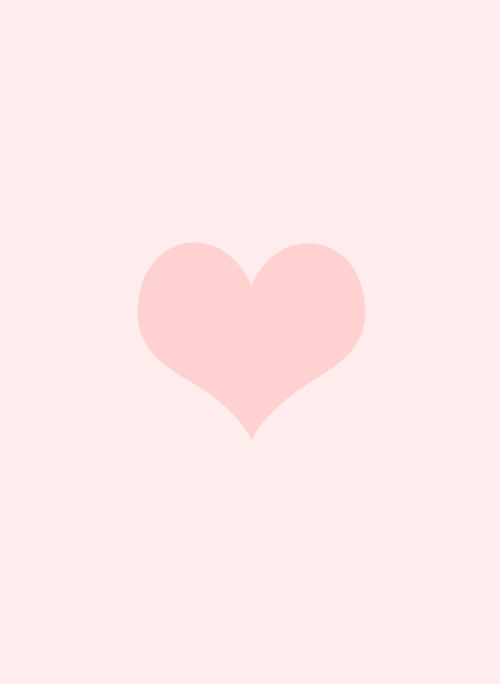カタストロフィ
ふと漏らしたキャロラインの呟きに、オムは顔を強張らせた。
しかしキャロラインは、オムの反応など気にすることなく独白を続ける。
「プロのヴァイオリニストという肩書きは素敵だけど、ダニエル様に相応しいものではないわ。あのような貴公子こそが爵位を継ぐべきよ。そう思わない?」
「お嬢様、さすがにダニエル様が爵位を継ぐのは無理があるかと……レイモンド様に何かあった時のために、同等の教育を受け、事業を手伝っていたマーカス様と、家業に関わったことのないダニエル様では比べものになりません。マーカス様との結婚に気乗りしないのはわかりますが、そのような無益なことを考えるのはおやめください」
「何よ、少し妄想するくらい良いじゃない!」
機嫌を悪くしてむくれてそっぽを向く様は、とても18歳に見えないほど幼稚だが、キャロライン自身には自覚が無かった。
夢から無理矢理現実に引き戻された彼女は、恨みがましい目でオムを見やる。
「わかっているわよ、こんなこと考えても仕方ないってことくらい。ダニエル様を想うのだって、結婚するまでよ」
「ダニエル様がシェフィールド家の方でなければ良かったのですけれどね。貴族ならば、結婚後の方が自由に恋愛が出来るでしょう?」
「オム、私をその辺の低俗な女たちと一緒にしないでちょうだい。例え不満の多い結婚だとしても、私は不貞を働いたりなどしないわ」
そろそろ出掛ける支度をしなければ、というキャロラインの一言に、オムは小さく頷き部屋を出て行った。
馬車を手配し、またこの部屋に呼びに来るまでおよそ10分はかかるだろう。
その10分の間は、家族も、メイドも、最も身近な従僕であるオムすらいない、
思う存分、甘い夢想に浸ることが出来る。
(今日のお茶会で、ダニエル様は私に話しかけてくださる。私は気の利いたことを言って、ダニエル様の気持ちを掴むの。お茶会が終わる頃には、ダニエル様はもっと私と話したくてたまらなくなっていて、私もマーカス様や他のご家族抜きでお会いしたいと熱望するのよ)
想像しただけでたまらなく幸せで、キャロラインは熱いため息をついた。
しかし悲しいことに、妄想はそこで行き詰まる。
婚約者でもない男性との距離の縮め方などわからないし、そもそもそんな機会など無いことがわかりきっているからだ。
2度目のため息は、先程とは違ってかなり温度が下がっていた。
そしてそのタイミングで、部屋のドアがノックされる。
「お嬢様、そろそろ出発のお時間です」
ダニエルに会えるのは嬉しい。
しかし、マーカスという障壁があることに気落ちして、結局キャロラインは憂鬱な気分のまま自宅を出発した。