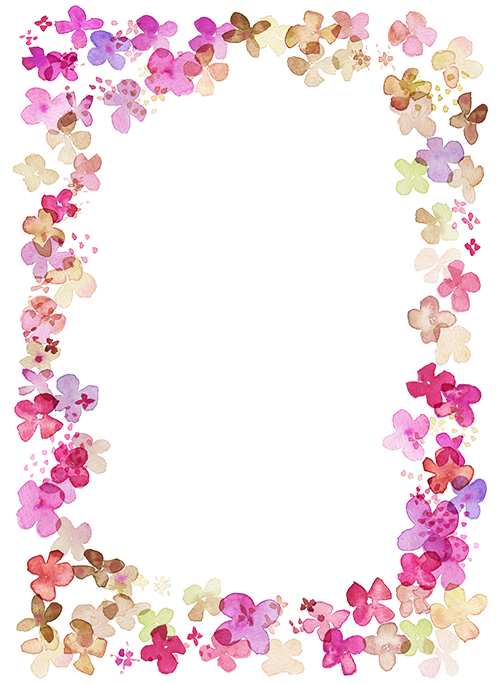もう一度あなたに恋したときの処方箋
「もう、それは言わせない。俺が選んだ人なんだよ、君は」
「は、はい」
私が自分を卑下したら、高木さんまで貶めてしまう。
初めてそのことに気が付いた私は、二度と『私なんか』と口にしないように心に誓った。
「父は、俺の前では正樹を溺愛し、正樹の前では俺を褒めていたらしい。そうすれば兄弟で切磋琢磨すると思っていたんだ」
「そんな……」
兄弟が互いに理解しあえなかったのはそのせいだったのだろうか。
「もうどうでもいいことさ。俺は君を大好きな人だって父に紹介するだけだ」
高木さんは今日一番の笑顔を向けてくれた。
「送るよ」
ご機嫌な調子で高木さん、いや憲一さんは私の手をもう一度握ると歩き出す。
「は…はい。ありがとうございます、憲一さん」
夜の歩道を並んで歩きだしてから、憲一さんが私の耳元に顔を寄せた。
「俺は君の力になりたい。これからはなんでもいいから頼って欲しい」
「病院でもそう言ってくれました。とっても嬉しかった」
「こんなセリフ、君にだけだぞ」
少し照れくさそうな憲一さんが優しい目で私を見てくれる。
「嬉しいです」
ゆっくり歩きながら、またどちらからともなく話し始める。
「俺たち、これからやり直しだな。いや、これから始めるんだ」
「はい」
「これから忙しくなるぞ」
高木さんの言葉に私も大きく頷いた。
木枯らしが冷たい夜だったけど、私は憲一さんに包まれているようで温かかった。
これからどんなことが起こるかわからないけれど、彼の手をずっと握っていたら大丈夫。
そんな気持ちが私の心に満ちていた。