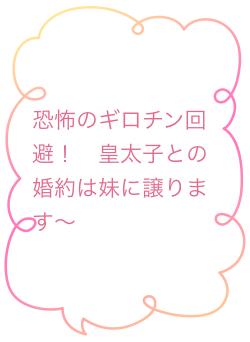魔力なし悪役令嬢の"婚約破棄"後は、楽しい魔法と美味しいご飯があふれている。
最終話
大将さん達にお別れの挨拶をして二階に戻る。出るとき、制服は私専用だから持っていっていいといってくれて、鍵は玄関の棚に置いていってくれと言われた。
先輩は部屋に入るなり整えた髪を、クシャッと崩した。
「ふぅ、緊張した――でも、いい人達だったな」
「うん、いい人達だったわ。女将さん達に会えて幸せだった」
「時間ができたら、また会いに来ような。さて、ラエルたちが待っている、行こうか」
「はい」
制服からワンピースに着替えて、いるものを詰め込んだマジックバッグを持って、思いだす。
「あ、先輩、要らないものを売りたいのだけど」
「いらないもの?」
私はマジックバッグからドレス、宝飾品、公爵家から持ってきた絵画、壺、貴金属製品を取り出した。
「けっこう、詰め込んだんだな。いつマジックバッグだってわかった?」
「えーっと、ドレスを入れたときかな……あのとき慌てていたから、驚く暇もなくて詰め込んだわ」
「だろうな……色々、ルーに渡しといてよかった。あのまま捕まっていたら、無理矢理王城に連れて行かれて……カロール殿下と結婚させられるか、側室に入れられていたかもな」
その先輩の言葉にうなずいた。よかった逃げて……先輩は最後の日に着ていたドレスを持ち「これ、売る前にいちど着てくれないか?」と言った。
私は"いいよ"と返した。
そのドレスに着替えの途中。
「シエルさん、髪をあげるから背中のファスナー上げて」
「わかった、これをあげるんだな」
「そうだけど……ん、んん?」
コルセットを付けていないからか、太ったからか、どんなに息を吐いても、ファスナーが背中半分で止まり、うえまで全部上がらない。
「……シエルさん、その、半年で太ったみたいです」
「…………」
こんな告白は恥ずかしい――だって、大将さんとニックさんのご飯が美味しくてたくさん食べたから。お菓子だって、読書中に寝転んで食べていた……
「ルーは太ってなんかいないぞ。まえは細すぎたんだ、普通になったんだよ」
「そうかな? ドレスを着る前につけるコルセットを付けてないのもあるけど……シエルさん、着けてくれる?」
「コルセット? コルセットってなんだ?」
え、知らない? ……そうか男性だもの知らないのかと、先輩にコルセットの説明したのだけど、着ける仕草の所で、もういいと止められた。
「じゃ、髪型はどうする?」
ポニーテールのままでいいといい、胸ポケットから銀のヘアピンをひとつ出して付けてくれた。そのピンは見覚えのある物だった。
「え、これって、シエルさん?」
このピンはいまから3年前くらい――王都の中央広場で魔法を披露していた、道化師に渡したヘアピンだ。どうして、先輩が持っているのだなんて――答えは一つしない。
「クク、いまから夢の様な魔法をご披露しよう!」
「う、嘘、あの時の道化師はシエルさんだったの?」
「そうだ……俺だ」
先輩は頷き、私の手を取り。
「高価なドレスの汚れなど気にせず地面に直に座って、俺の魔法を口を半開きで、キラキラな瞳をして見ていたよな」
口が半開き!
「うそ、恥ずかしい……だって、魔法をみたのは初めてだったの。当時、好きだったカロール殿下の婚約者で、王妃としての気質はあるが『魔力無し』かと両親、周りの人達に言われてつらかった――ぜひ、うちの"魔力有り"の娘を側室に選んでください。どうして私に魔力がないの! 魔法なんて大嫌い! だと持っていたのに……はじめて道化師の魔法をみて、心を奪われた」
あこがれ、羨ましくて、悔しくて、でもキレイだった。――辛い、王妃教育、周りの貴族の傷つく言葉、権力しか愛さない両親――それらを忘れられる時間だった。
「こいつ、魔法が相当好きなんだなって、魔法を見つめるルーを見ていてわかったよ」
「シエルさんだって、同じだったわ」
仮面で表情まではわからなかったけど、楽しそうに魔法を披露していたもの。勇気を出して話しかけた日、道化師はこれから王都の学園に通うといった。私は「1年後に、学園で道化師に会える」と思って大切なピンを渡したのだけど……1年後に入学して、探したけど道化師は見つからなかった。
――王都の中央広場にいっても会えなかった。
「…………」
「どうして、声を掛けなかったの? って思ってるだろ? できなかったんだ。カロール殿下の横で嬉しそうに笑う、ルーには近寄れなかった……」
「……え、」
「所詮、俺は他所者だ。いくら一目惚れをしても、いくら好きでも、声など掛けれなかった」
一目惚れ? 好き? 先輩はあの時から私を好き。
「だったら、書庫で出会ったとき"すっごく"嫌な顔をしたわ」
「い、嫌な顔じゃない。ビックリと会えた嬉しさに、顔がにやけない様にしただけだ」
「でも、邪魔だって追い返そうとした」
「これ以上、好きになったら、どうするんだよ!」
先輩に手を引かれて、彼に抱きしめられる。
「お、俺はルーが幸せであればそれでいいんだ。ほんとは、この想いを言わずに国に帰ると思っていた。だけどいま俺の腕の中にいる……俺だけのルーチェ、すごくキレイだ」
「……シエルさん」
+
そう……先輩の名前を呼んで、いい雰囲気だった。
「クク、ハハハッ、まさかな……」
「もう、シエルさんは笑わないで! 最初に太ったっていったじゃない」
「クックク……ごめん」
部屋を後にして、持ち物を売りに王都に行くまえ、帰りもずっと笑ってる、乗せていってくれた福ちゃんも。
「あまり笑っては……お嬢が可哀想だぞ」
と言っても。
「ウルラは全部、見ていないからな。フフ、ルーのあんなに慌てた顔をはじめてみた、すげぇ可愛かった」
何をそんなに笑っているかって? 部屋で先輩に抱きしめられている途中に、なんと! 耐えきれなくなったファスナーが"パンッ"と壊れて、ドレスが足元までストンと落ちたのだ。
「「…………!!」」
そして、買い取りの時も品物はいいのに……ファスナーが壊れているからと、売値が安くなってしまった。
「クク……」
「もう、可愛いとか言うけど、シエルさんはそんなこと、そんなに笑うんだもん、思っていない!」
「思ってる。パンとファスナーが壊れて、慌てて丸見えな下着を隠す姿、真っ赤な顔、こまった顔……とくに、な…… 」
「わー、わー、もう、言わなくていい、もうやめてぇ」
福ちゃんもいるのにと、それ以上は言わないでと、ポコポコ肩を叩いたけど。
「ハハハッ、可愛い」
この日、ずーっと先輩は楽しそうに笑っていた。
+
王都で換金した後、港街で今から私達の為に頑張る、福ちゃんとガット君の好物も買った。みんなでそろって早めの夕飯をとり。夕方日が沈む前に目立たない様に、ストレーガ国に向けて旅立つ。
魔法屋の看板をしまい、空き家になった店舗をみて、ラエルさんが言う。
「これで、片付けは終わったよ」
「じゃ、行くかルー」
「はい、シエルさん」
「オレ達の国へ帰るぞ、シエル、ラエル、そして、ルーチェちゃん!」
子犬ちゃん――ベルーガ王子の合図で私と先輩、子犬ちゃんを乗せた福ちゃんは飛び上がる。次にラエルさんを乗せてガット君も空に駆け上がった。
段々と生まれたアンサンテ国が――モール港街が小さく遠くなっていく。楽しいことも、悲しいこともたくさんあった。
これからは先輩、みんなが側にいてくれる。
先輩との新しい日々が始まるんだ。
私たちのストレーガ国までの帰路の旅は、いま始まったばかりだ。
え? あの後の2人?
偵察してきた福ちゃんとガット君の話では。2人の結婚は誓約書の通り、国王陛下、王妃様にも認められており、イアンはカロール殿下の側室に選ばれて泣いていたそうだ。
「姉さん、安心するっス。カロール殿下はリリーナ様の魅了にかかったままで、2人はラブラブだったっス」
「すぐに世継ぎもできるだろう」
だって。
先輩は部屋に入るなり整えた髪を、クシャッと崩した。
「ふぅ、緊張した――でも、いい人達だったな」
「うん、いい人達だったわ。女将さん達に会えて幸せだった」
「時間ができたら、また会いに来ような。さて、ラエルたちが待っている、行こうか」
「はい」
制服からワンピースに着替えて、いるものを詰め込んだマジックバッグを持って、思いだす。
「あ、先輩、要らないものを売りたいのだけど」
「いらないもの?」
私はマジックバッグからドレス、宝飾品、公爵家から持ってきた絵画、壺、貴金属製品を取り出した。
「けっこう、詰め込んだんだな。いつマジックバッグだってわかった?」
「えーっと、ドレスを入れたときかな……あのとき慌てていたから、驚く暇もなくて詰め込んだわ」
「だろうな……色々、ルーに渡しといてよかった。あのまま捕まっていたら、無理矢理王城に連れて行かれて……カロール殿下と結婚させられるか、側室に入れられていたかもな」
その先輩の言葉にうなずいた。よかった逃げて……先輩は最後の日に着ていたドレスを持ち「これ、売る前にいちど着てくれないか?」と言った。
私は"いいよ"と返した。
そのドレスに着替えの途中。
「シエルさん、髪をあげるから背中のファスナー上げて」
「わかった、これをあげるんだな」
「そうだけど……ん、んん?」
コルセットを付けていないからか、太ったからか、どんなに息を吐いても、ファスナーが背中半分で止まり、うえまで全部上がらない。
「……シエルさん、その、半年で太ったみたいです」
「…………」
こんな告白は恥ずかしい――だって、大将さんとニックさんのご飯が美味しくてたくさん食べたから。お菓子だって、読書中に寝転んで食べていた……
「ルーは太ってなんかいないぞ。まえは細すぎたんだ、普通になったんだよ」
「そうかな? ドレスを着る前につけるコルセットを付けてないのもあるけど……シエルさん、着けてくれる?」
「コルセット? コルセットってなんだ?」
え、知らない? ……そうか男性だもの知らないのかと、先輩にコルセットの説明したのだけど、着ける仕草の所で、もういいと止められた。
「じゃ、髪型はどうする?」
ポニーテールのままでいいといい、胸ポケットから銀のヘアピンをひとつ出して付けてくれた。そのピンは見覚えのある物だった。
「え、これって、シエルさん?」
このピンはいまから3年前くらい――王都の中央広場で魔法を披露していた、道化師に渡したヘアピンだ。どうして、先輩が持っているのだなんて――答えは一つしない。
「クク、いまから夢の様な魔法をご披露しよう!」
「う、嘘、あの時の道化師はシエルさんだったの?」
「そうだ……俺だ」
先輩は頷き、私の手を取り。
「高価なドレスの汚れなど気にせず地面に直に座って、俺の魔法を口を半開きで、キラキラな瞳をして見ていたよな」
口が半開き!
「うそ、恥ずかしい……だって、魔法をみたのは初めてだったの。当時、好きだったカロール殿下の婚約者で、王妃としての気質はあるが『魔力無し』かと両親、周りの人達に言われてつらかった――ぜひ、うちの"魔力有り"の娘を側室に選んでください。どうして私に魔力がないの! 魔法なんて大嫌い! だと持っていたのに……はじめて道化師の魔法をみて、心を奪われた」
あこがれ、羨ましくて、悔しくて、でもキレイだった。――辛い、王妃教育、周りの貴族の傷つく言葉、権力しか愛さない両親――それらを忘れられる時間だった。
「こいつ、魔法が相当好きなんだなって、魔法を見つめるルーを見ていてわかったよ」
「シエルさんだって、同じだったわ」
仮面で表情まではわからなかったけど、楽しそうに魔法を披露していたもの。勇気を出して話しかけた日、道化師はこれから王都の学園に通うといった。私は「1年後に、学園で道化師に会える」と思って大切なピンを渡したのだけど……1年後に入学して、探したけど道化師は見つからなかった。
――王都の中央広場にいっても会えなかった。
「…………」
「どうして、声を掛けなかったの? って思ってるだろ? できなかったんだ。カロール殿下の横で嬉しそうに笑う、ルーには近寄れなかった……」
「……え、」
「所詮、俺は他所者だ。いくら一目惚れをしても、いくら好きでも、声など掛けれなかった」
一目惚れ? 好き? 先輩はあの時から私を好き。
「だったら、書庫で出会ったとき"すっごく"嫌な顔をしたわ」
「い、嫌な顔じゃない。ビックリと会えた嬉しさに、顔がにやけない様にしただけだ」
「でも、邪魔だって追い返そうとした」
「これ以上、好きになったら、どうするんだよ!」
先輩に手を引かれて、彼に抱きしめられる。
「お、俺はルーが幸せであればそれでいいんだ。ほんとは、この想いを言わずに国に帰ると思っていた。だけどいま俺の腕の中にいる……俺だけのルーチェ、すごくキレイだ」
「……シエルさん」
+
そう……先輩の名前を呼んで、いい雰囲気だった。
「クク、ハハハッ、まさかな……」
「もう、シエルさんは笑わないで! 最初に太ったっていったじゃない」
「クックク……ごめん」
部屋を後にして、持ち物を売りに王都に行くまえ、帰りもずっと笑ってる、乗せていってくれた福ちゃんも。
「あまり笑っては……お嬢が可哀想だぞ」
と言っても。
「ウルラは全部、見ていないからな。フフ、ルーのあんなに慌てた顔をはじめてみた、すげぇ可愛かった」
何をそんなに笑っているかって? 部屋で先輩に抱きしめられている途中に、なんと! 耐えきれなくなったファスナーが"パンッ"と壊れて、ドレスが足元までストンと落ちたのだ。
「「…………!!」」
そして、買い取りの時も品物はいいのに……ファスナーが壊れているからと、売値が安くなってしまった。
「クク……」
「もう、可愛いとか言うけど、シエルさんはそんなこと、そんなに笑うんだもん、思っていない!」
「思ってる。パンとファスナーが壊れて、慌てて丸見えな下着を隠す姿、真っ赤な顔、こまった顔……とくに、な…… 」
「わー、わー、もう、言わなくていい、もうやめてぇ」
福ちゃんもいるのにと、それ以上は言わないでと、ポコポコ肩を叩いたけど。
「ハハハッ、可愛い」
この日、ずーっと先輩は楽しそうに笑っていた。
+
王都で換金した後、港街で今から私達の為に頑張る、福ちゃんとガット君の好物も買った。みんなでそろって早めの夕飯をとり。夕方日が沈む前に目立たない様に、ストレーガ国に向けて旅立つ。
魔法屋の看板をしまい、空き家になった店舗をみて、ラエルさんが言う。
「これで、片付けは終わったよ」
「じゃ、行くかルー」
「はい、シエルさん」
「オレ達の国へ帰るぞ、シエル、ラエル、そして、ルーチェちゃん!」
子犬ちゃん――ベルーガ王子の合図で私と先輩、子犬ちゃんを乗せた福ちゃんは飛び上がる。次にラエルさんを乗せてガット君も空に駆け上がった。
段々と生まれたアンサンテ国が――モール港街が小さく遠くなっていく。楽しいことも、悲しいこともたくさんあった。
これからは先輩、みんなが側にいてくれる。
先輩との新しい日々が始まるんだ。
私たちのストレーガ国までの帰路の旅は、いま始まったばかりだ。
え? あの後の2人?
偵察してきた福ちゃんとガット君の話では。2人の結婚は誓約書の通り、国王陛下、王妃様にも認められており、イアンはカロール殿下の側室に選ばれて泣いていたそうだ。
「姉さん、安心するっス。カロール殿下はリリーナ様の魅了にかかったままで、2人はラブラブだったっス」
「すぐに世継ぎもできるだろう」
だって。