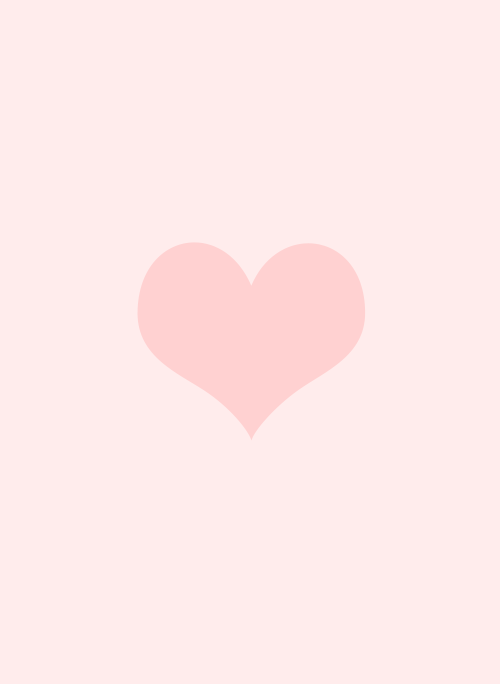奮闘記などと呼ばない (王道外れた異世界転生)
だから、“新米孤児”は、ジャン達だけじゃなかった。
毎回、新しい孤児達がやってくる度に、孤児達は、ジャン達が受けた孤児院の説明を受ける。
生活のルールや習慣を教わっていく。共同生活を習っていく。
ケンカする子供だっている。だが、「ケンカした後は、ちゃんと謝りましょう」 と、院長先生に言われ、仲裁され、嫌々でも、子供達は(一応) 謝罪し合う。
セシルにも仲裁されて、人と人の関係やら、付き合い方やら、なんやらと、(余計な) 説明を受ける羽目にもなる。
まだ子供なのに、子供が子供に説明(説教でもない) して言い聞かせる光景だって、あまりに謎な光景だった。
でも、セシルは、いつどこでも声を荒立てたことがない。
いつも(子供らしくないほどに) 落ち着いていて、あのどこまでも落ち着いた静かな藍の瞳が、じっと、相手を観察していた。
感情的にもならない。怒鳴り散らさない。暴力も振るわない(まあ、女の子で力がないのもあるが)。
ただ、セシルは、この領地の中で、誰よりも冷静で、落ち着いていて、いつも、絶対に態度が変わらない令嬢だったのだ。
孤児達がたくさんいて、態度が変わらない。
ジャン達と出会った時でも、態度は変わらなかった。
セシルは、ジャン達に「人として生きて、世界を見なさい」 と言った。
「人」 として生きる意味は――ジャン達には、今はよく分からない……。
でも――ジャン達は、この領地で生まれて初めて、虐げられることもなく、差別されることもなく、普通の孤児として生活していた。
半年以上が過ぎようとしていた。
でも、ジャン達の周りは何も変わらない――いや、たくさん、毎日が変わり過ぎていくほど、目まぐるしいほど忙しい。
でも――ジャン達は、普通の孤児として生活をしている。
普通の孤児――ってなんだ?
孤児に、普通も何もあるのか?
激しい疑問にたどり着いて、それで、定例のごとく、メンバーが、コソコソと、内緒話をしていると、
「普通の孤児、なんて、あるわけないじゃん」
とあまりにすっぱりと、フィロに切り落とされてしまった。
昔から、フィロは情緒もないし、感傷に浸るような子供でもないし、冷たくて、超がつくほどの現実的な子供だった。
「じゃあ、なんて言うんだよ。普通の孤児、じゃなかったら、なんなんだ?」
「そうだ」
「そうだ」
「今は……普通っぽく、暮らしてるじゃんか」
フィロの冷めた顔は、
「そんなの一々考える方がおかしいんじゃない?」
と、明らかに言いたげだ。
だが、四人から詰め寄られて、仕方なく、フィロも真面目に考えてみせる。
「普通の、子供? ――でいいんじゃない?」
「普通の子供?」
その響きは――どうやら、全員が嬉しかったらしい。言葉には出さなくても、その顔がにやけている。
それで、ジャン達は、この領地で、今は普通の子供っぽく暮らしている。
領地の領民として、受け入れてもらえたのだろうか?
そういうことは、誰一人言ってくれなかった。
でも、追い出されていない。蹴飛ばされていない。
だから――普通の子供として、領民になったのかもしれない。
半年でも、目まぐるしい毎日を送る。
ご飯が食べられる。スナックが当たる。
友達がいる。
帰れる家がある。できた。
勉強もしてる。字も習っている。計算も習っている。
貴族の子供でもなんでもないのに。
将来、独り立ちする時に必ず役に立つから、と言われた。「将来」 ――なんて単語は、大嫌いだった。
今は――――
時々、(本当に、ほんの時々だけ)考えてみてしまう。
一体、どんなんだろう? ――って。
そして、そのチャンスを、全部が全部、セシルがジャン達に与えてくれたものだった。
* * *
セシルに呼び出された五人は、セシルの執務室にやってきていた。
執務室にある大きな机の前には、長椅子が並べられていて、そこに座るように勧められる。
全員が座ると、セシルも長椅子の方に回ってきて、一人用の椅子に腰かけた。
「今日は、これからの問題で少し話し合いがしたくて、皆を呼んだの。これから、しばらく、少々、危険な任務についてもらいたいから、それの確認に」
「危険な任務? もしかして、盗みを働くとか?」
「えっ? 今更、盗み?」
「それって、マズイんじゃないの?」
「じゃあ、殺し?」
そして、さすがスラム街の子供達だけあって、危険な任務と聞いて、出てくる発想が(ユニークなほどに)違う。
「そんなことしたら、捕まった時に、この領地のことがバレちゃうじゃん。バカじゃないの?」
そして、その中でも相変わらず淡々として冷たく、現実的なフィロである。
この会話を聞きながら、セシルも、なんだか、少し口元を上げている。
「そう言った“危険”な仕事ではないんです。ただ、来年から二年間、私は領地を空けることが多くなるので、私の身近で動ける人材が必要なのよ」
全員が不思議そうな顔をする。
だが、一番に口を開いたのは、やはりフィロだった。
「どうしてですか? 領地を空けたら、領地の仕事はどうするんですか?」
「もちろん、継続していきます。ただ、来年からは、王都にある王立学園に通わなければならないのです。貴族の子供は、全員、通わなければならない学校なんですよ」
「それで、王都に戻るから、領地を空けるんですか?」
「そうです。学園は16歳から二年間。そして、その二年間が、私の最大の試練になるかしら」
「試練? マスターの?」
「ええ、そうね。その前に、少し確認をしたいことがあるの。この中で、大人に見つからず、隠れることが上手いのは誰?」
その質問に、全員がそれぞれに顔を見合わせて、その視線の先が、小さな少年に向けられる。
「大抵、トムソーヤが見張り役だけど――いえ、です。ちっこいから、隠れるのに一番なんです」
「ちっこいは、余計なのに……」
だが、一番年下で、体も背も小さく、チームの中では、小回りが利く役になることが多い。
「そう、トムソーヤなのね」
「でも、悪だくみはフィロです」
「そうです」
そして、全員一致の賛同を得る当たり、さすがフィロです。
「そう、フィロは賢いものね」
「悪だくみしてほしいんですか?」
「ええ、そうね」
「え? そうなんですか?」
このセシルから悪巧みを頼まれるなど、露にも思わなかったフィロだ。
「実はね、私には、子供の時から決められた婚約者がいるの」
「それは――聞いたことがあります」
領地内でも、たまに挙がってくる話題だった。
それで、なぜかは知らないが、
「さっさと婚約解消できればいいのにっ!」
などという憤慨も上がっている。
「卒業式まで二年間。最後の卒業式で、私は、婚約解消を絶対に勝ち取らなければならないんです」
「なんで、ですか?」
貴族のお嬢様の考えることは、フィロ達には、到底、理解できないものだ。
お貴族サマというのは、いいトコ同士で婚約だってするだろうし、結婚だって決められているのだろう。
スラム街の孤児だからと言って、その程度の習慣を知らないのではない。
「悪名高きホルメン侯爵家嫡男ジョーラン。横柄で、威張り散らすだけしかない、能の無いロクデナシ男」
「なるほど」
「私が子供の時に、伯爵家のワイン生産量の増加に目をつけて、向こうから、無理矢理、婚約を押し付けて来たんです。向こうは侯爵家ですからね。こちらとしても文句は言えず、それから、婚約資金やらなんやらと、我が伯爵家の資産を食い物にして、好き放題の浪費、贅沢のし放題、不正や賄賂など、日常茶飯事」
「最低ですね。早々と、婚約破棄すべきでしょう」
そこまでの説明だけで、すでに、その結論に達していたフィロである。
毎回、新しい孤児達がやってくる度に、孤児達は、ジャン達が受けた孤児院の説明を受ける。
生活のルールや習慣を教わっていく。共同生活を習っていく。
ケンカする子供だっている。だが、「ケンカした後は、ちゃんと謝りましょう」 と、院長先生に言われ、仲裁され、嫌々でも、子供達は(一応) 謝罪し合う。
セシルにも仲裁されて、人と人の関係やら、付き合い方やら、なんやらと、(余計な) 説明を受ける羽目にもなる。
まだ子供なのに、子供が子供に説明(説教でもない) して言い聞かせる光景だって、あまりに謎な光景だった。
でも、セシルは、いつどこでも声を荒立てたことがない。
いつも(子供らしくないほどに) 落ち着いていて、あのどこまでも落ち着いた静かな藍の瞳が、じっと、相手を観察していた。
感情的にもならない。怒鳴り散らさない。暴力も振るわない(まあ、女の子で力がないのもあるが)。
ただ、セシルは、この領地の中で、誰よりも冷静で、落ち着いていて、いつも、絶対に態度が変わらない令嬢だったのだ。
孤児達がたくさんいて、態度が変わらない。
ジャン達と出会った時でも、態度は変わらなかった。
セシルは、ジャン達に「人として生きて、世界を見なさい」 と言った。
「人」 として生きる意味は――ジャン達には、今はよく分からない……。
でも――ジャン達は、この領地で生まれて初めて、虐げられることもなく、差別されることもなく、普通の孤児として生活していた。
半年以上が過ぎようとしていた。
でも、ジャン達の周りは何も変わらない――いや、たくさん、毎日が変わり過ぎていくほど、目まぐるしいほど忙しい。
でも――ジャン達は、普通の孤児として生活をしている。
普通の孤児――ってなんだ?
孤児に、普通も何もあるのか?
激しい疑問にたどり着いて、それで、定例のごとく、メンバーが、コソコソと、内緒話をしていると、
「普通の孤児、なんて、あるわけないじゃん」
とあまりにすっぱりと、フィロに切り落とされてしまった。
昔から、フィロは情緒もないし、感傷に浸るような子供でもないし、冷たくて、超がつくほどの現実的な子供だった。
「じゃあ、なんて言うんだよ。普通の孤児、じゃなかったら、なんなんだ?」
「そうだ」
「そうだ」
「今は……普通っぽく、暮らしてるじゃんか」
フィロの冷めた顔は、
「そんなの一々考える方がおかしいんじゃない?」
と、明らかに言いたげだ。
だが、四人から詰め寄られて、仕方なく、フィロも真面目に考えてみせる。
「普通の、子供? ――でいいんじゃない?」
「普通の子供?」
その響きは――どうやら、全員が嬉しかったらしい。言葉には出さなくても、その顔がにやけている。
それで、ジャン達は、この領地で、今は普通の子供っぽく暮らしている。
領地の領民として、受け入れてもらえたのだろうか?
そういうことは、誰一人言ってくれなかった。
でも、追い出されていない。蹴飛ばされていない。
だから――普通の子供として、領民になったのかもしれない。
半年でも、目まぐるしい毎日を送る。
ご飯が食べられる。スナックが当たる。
友達がいる。
帰れる家がある。できた。
勉強もしてる。字も習っている。計算も習っている。
貴族の子供でもなんでもないのに。
将来、独り立ちする時に必ず役に立つから、と言われた。「将来」 ――なんて単語は、大嫌いだった。
今は――――
時々、(本当に、ほんの時々だけ)考えてみてしまう。
一体、どんなんだろう? ――って。
そして、そのチャンスを、全部が全部、セシルがジャン達に与えてくれたものだった。
* * *
セシルに呼び出された五人は、セシルの執務室にやってきていた。
執務室にある大きな机の前には、長椅子が並べられていて、そこに座るように勧められる。
全員が座ると、セシルも長椅子の方に回ってきて、一人用の椅子に腰かけた。
「今日は、これからの問題で少し話し合いがしたくて、皆を呼んだの。これから、しばらく、少々、危険な任務についてもらいたいから、それの確認に」
「危険な任務? もしかして、盗みを働くとか?」
「えっ? 今更、盗み?」
「それって、マズイんじゃないの?」
「じゃあ、殺し?」
そして、さすがスラム街の子供達だけあって、危険な任務と聞いて、出てくる発想が(ユニークなほどに)違う。
「そんなことしたら、捕まった時に、この領地のことがバレちゃうじゃん。バカじゃないの?」
そして、その中でも相変わらず淡々として冷たく、現実的なフィロである。
この会話を聞きながら、セシルも、なんだか、少し口元を上げている。
「そう言った“危険”な仕事ではないんです。ただ、来年から二年間、私は領地を空けることが多くなるので、私の身近で動ける人材が必要なのよ」
全員が不思議そうな顔をする。
だが、一番に口を開いたのは、やはりフィロだった。
「どうしてですか? 領地を空けたら、領地の仕事はどうするんですか?」
「もちろん、継続していきます。ただ、来年からは、王都にある王立学園に通わなければならないのです。貴族の子供は、全員、通わなければならない学校なんですよ」
「それで、王都に戻るから、領地を空けるんですか?」
「そうです。学園は16歳から二年間。そして、その二年間が、私の最大の試練になるかしら」
「試練? マスターの?」
「ええ、そうね。その前に、少し確認をしたいことがあるの。この中で、大人に見つからず、隠れることが上手いのは誰?」
その質問に、全員がそれぞれに顔を見合わせて、その視線の先が、小さな少年に向けられる。
「大抵、トムソーヤが見張り役だけど――いえ、です。ちっこいから、隠れるのに一番なんです」
「ちっこいは、余計なのに……」
だが、一番年下で、体も背も小さく、チームの中では、小回りが利く役になることが多い。
「そう、トムソーヤなのね」
「でも、悪だくみはフィロです」
「そうです」
そして、全員一致の賛同を得る当たり、さすがフィロです。
「そう、フィロは賢いものね」
「悪だくみしてほしいんですか?」
「ええ、そうね」
「え? そうなんですか?」
このセシルから悪巧みを頼まれるなど、露にも思わなかったフィロだ。
「実はね、私には、子供の時から決められた婚約者がいるの」
「それは――聞いたことがあります」
領地内でも、たまに挙がってくる話題だった。
それで、なぜかは知らないが、
「さっさと婚約解消できればいいのにっ!」
などという憤慨も上がっている。
「卒業式まで二年間。最後の卒業式で、私は、婚約解消を絶対に勝ち取らなければならないんです」
「なんで、ですか?」
貴族のお嬢様の考えることは、フィロ達には、到底、理解できないものだ。
お貴族サマというのは、いいトコ同士で婚約だってするだろうし、結婚だって決められているのだろう。
スラム街の孤児だからと言って、その程度の習慣を知らないのではない。
「悪名高きホルメン侯爵家嫡男ジョーラン。横柄で、威張り散らすだけしかない、能の無いロクデナシ男」
「なるほど」
「私が子供の時に、伯爵家のワイン生産量の増加に目をつけて、向こうから、無理矢理、婚約を押し付けて来たんです。向こうは侯爵家ですからね。こちらとしても文句は言えず、それから、婚約資金やらなんやらと、我が伯爵家の資産を食い物にして、好き放題の浪費、贅沢のし放題、不正や賄賂など、日常茶飯事」
「最低ですね。早々と、婚約破棄すべきでしょう」
そこまでの説明だけで、すでに、その結論に達していたフィロである。