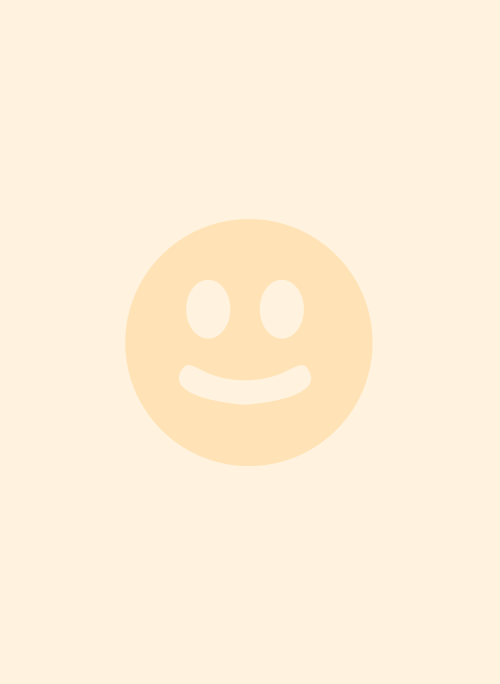気紛れ天使 【君に会えたあの夏へ戻りたい】
「純一郎さん。」 寛子は涙を浮かべた目で純一郎を見た。
「寛子ちゃん、、、。」 二人はそのまま見詰め合っている。
廊下を忙しなく歩き回る足音が聞こえる。 さっき到着した客を持て成しているらしい。
「先生、今夜もよろしくね。」 「おーおー、お前ら次第だ。 たっぷり弾んでやるから頼むぞ。」
「酔っぱらったからって寝ないでね。」 「お前次第だよ。 あはは。」
「また来たんですね。 あの人は先月も来てるはず、、、。」 「金持ちは女好きだからなあ。」
廊下を歩いて行くのは与党のお偉いさんだ。 バッヂを見せびらかして毎月遊んでいるらしい。
可愛がってる女中には10万でも100万でも握らせるらしい。 その代わりに選挙となると親子友人の票を全部掻っ攫っていくらしいけど、、、。
でもあの議員もそろそろ終わりだろうなあ。 賄賂が発覚しちゃったからね。
5時を過ぎて純一郎はまたまた露天風呂に入っていった。 今日は寛子も同伴である。
さっき、抱いた体が隣に居る。 湯に浸かった純一郎は空を見上げた。
「8月と言えば獅子座だね。 寛子ちゃんは何だい?」 「私は乙女座です。」
「乙女化。 俺は水瓶なんだよ。」 「真冬の生まれですか?」
「そうなんだ。 でもさ冬生まれの冬嫌いなんだ。 困っちゃうよなあ。」 「私は初秋なんですよね。」
「秋が一番好きだな。 暑くもなく寒くもなく、、、。」 「そうですよね。 どっか寂しいけど。」
秋の夕暮れほど寂しい時は無いだろう。 長く引きずる影を見ているとどことなくセンチメンタルになってしまう。
夕方なら夏のほうがまだいい。 遅くなってもまだまだ明るいしね。
どこかで秋田音頭がまた聞こえてきた。 さすがは秋田だな。
体を洗うと寛子はまた純一郎の隣に体を沈めた。 黙っているのに二人して何かを感じているらしい。
その頃、東京の我が家では?
「あの人は何をしてるんだろう?」 ぼんやりと時計を眺めてはテレビに目を移す。
それでも何となく重たい気分になって頬杖を突く。 「早く帰ってこないかな?」
美紀はワインを飲みながらそう呟くのである。 この家に家事手伝いで住み込んだ時、父親の清川清二は言った。
「純一郎と仲良くやってくれよ。」 それだったからか、清二は美紀には手も触れなかったという。
「純一郎さんと夫婦になれってことなのかなあ?」 とはいえ、家政婦の身分で純一郎に手を出すわけにはいかない。
会社でも純一郎が一目置かれる存在になってきた頃、清二が病気に倒れた。 「純一郎、いいか。 これからはお前が表に出るんだ。 これまで世界を飛び回ってきたんだから凡その国は分かっただろう。 任せたぞ。」
それが清二の遺言だった。 そして母親を追い掛けるようにして死んでしまった。
四十九日が来て納骨を済ませた夜、美紀は純一郎の部屋に入ってきた。 「どうしたんだい?」
「何だかすごく寂しくて、、、。」 彼女はそう言うと純一郎の膝に座った。
「おいおい、それは、、、。」 「いいの。 お父さんも居なくなったし後は純一郎さんだけなのよ。 私、隠してたけどずっと好きだったの。」
「だからって、、、。」 「いいのよ。 お父さんにもあなたと仲良くするようにって言われてたの。 我慢してたのよ。 今まで、、、。」
純一郎は初めて美紀の気持ちを知った。 そしてその夜、初めて絡み合ったのである。
目覚めた時、美紀は生まれ変わったような顔で優しく笑っていた。 「これからは二人で頑張りましょうね。」
「寛子ちゃん、、、。」 二人はそのまま見詰め合っている。
廊下を忙しなく歩き回る足音が聞こえる。 さっき到着した客を持て成しているらしい。
「先生、今夜もよろしくね。」 「おーおー、お前ら次第だ。 たっぷり弾んでやるから頼むぞ。」
「酔っぱらったからって寝ないでね。」 「お前次第だよ。 あはは。」
「また来たんですね。 あの人は先月も来てるはず、、、。」 「金持ちは女好きだからなあ。」
廊下を歩いて行くのは与党のお偉いさんだ。 バッヂを見せびらかして毎月遊んでいるらしい。
可愛がってる女中には10万でも100万でも握らせるらしい。 その代わりに選挙となると親子友人の票を全部掻っ攫っていくらしいけど、、、。
でもあの議員もそろそろ終わりだろうなあ。 賄賂が発覚しちゃったからね。
5時を過ぎて純一郎はまたまた露天風呂に入っていった。 今日は寛子も同伴である。
さっき、抱いた体が隣に居る。 湯に浸かった純一郎は空を見上げた。
「8月と言えば獅子座だね。 寛子ちゃんは何だい?」 「私は乙女座です。」
「乙女化。 俺は水瓶なんだよ。」 「真冬の生まれですか?」
「そうなんだ。 でもさ冬生まれの冬嫌いなんだ。 困っちゃうよなあ。」 「私は初秋なんですよね。」
「秋が一番好きだな。 暑くもなく寒くもなく、、、。」 「そうですよね。 どっか寂しいけど。」
秋の夕暮れほど寂しい時は無いだろう。 長く引きずる影を見ているとどことなくセンチメンタルになってしまう。
夕方なら夏のほうがまだいい。 遅くなってもまだまだ明るいしね。
どこかで秋田音頭がまた聞こえてきた。 さすがは秋田だな。
体を洗うと寛子はまた純一郎の隣に体を沈めた。 黙っているのに二人して何かを感じているらしい。
その頃、東京の我が家では?
「あの人は何をしてるんだろう?」 ぼんやりと時計を眺めてはテレビに目を移す。
それでも何となく重たい気分になって頬杖を突く。 「早く帰ってこないかな?」
美紀はワインを飲みながらそう呟くのである。 この家に家事手伝いで住み込んだ時、父親の清川清二は言った。
「純一郎と仲良くやってくれよ。」 それだったからか、清二は美紀には手も触れなかったという。
「純一郎さんと夫婦になれってことなのかなあ?」 とはいえ、家政婦の身分で純一郎に手を出すわけにはいかない。
会社でも純一郎が一目置かれる存在になってきた頃、清二が病気に倒れた。 「純一郎、いいか。 これからはお前が表に出るんだ。 これまで世界を飛び回ってきたんだから凡その国は分かっただろう。 任せたぞ。」
それが清二の遺言だった。 そして母親を追い掛けるようにして死んでしまった。
四十九日が来て納骨を済ませた夜、美紀は純一郎の部屋に入ってきた。 「どうしたんだい?」
「何だかすごく寂しくて、、、。」 彼女はそう言うと純一郎の膝に座った。
「おいおい、それは、、、。」 「いいの。 お父さんも居なくなったし後は純一郎さんだけなのよ。 私、隠してたけどずっと好きだったの。」
「だからって、、、。」 「いいのよ。 お父さんにもあなたと仲良くするようにって言われてたの。 我慢してたのよ。 今まで、、、。」
純一郎は初めて美紀の気持ちを知った。 そしてその夜、初めて絡み合ったのである。
目覚めた時、美紀は生まれ変わったような顔で優しく笑っていた。 「これからは二人で頑張りましょうね。」