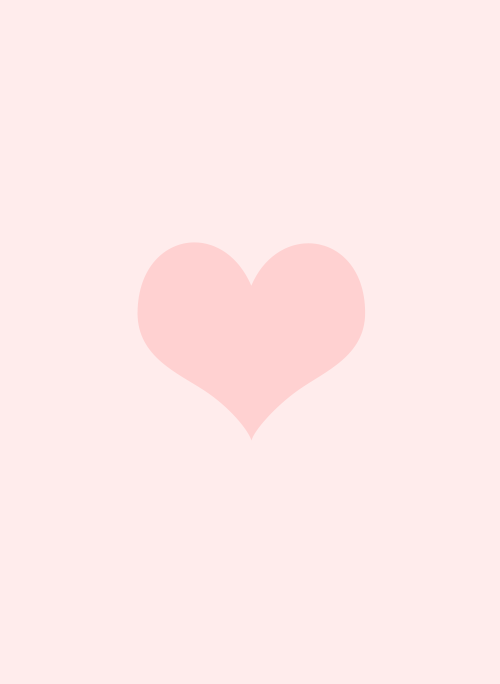悪役令嬢として真実の愛を『本気で』応援したら、とんでもないことになりました!
『星降る夜に真実の愛を』という歌劇がある。
没落した男爵家の令嬢が、若き王子に見初められ、紆余曲折の末に結ばれるという恋愛劇だ。
大筋としてはありきたりなストーリー。けれど、若い女子の憧れを集約した設定と展開のおかげで、王都でこの演目を知らない女性はいない。
脚本の筋をなぞった小説は何度も重版され、劇中の衣装や小物類に似せた商品は、店頭から飛ぶように売れていく。
果ては主人公と同じ赤茶の巻き髪の女性たちで、休日の城下があふれかえるほどだった。
私も付き合いで、その劇を見に行ったことがある。
まあ、人気が出るのもわかるな、というくらいにはよくできていて、クライマックスのシーンは不覚にもうるっときてしまった。
王子の婚約者である年増の公爵令嬢は、実は魔女が成り代わっていて、王子は彼女の魔力で逆らうことができない。
主人公の男爵令嬢は、自らの聖なる力でその呪縛を解き放ち、最後は王子と力を合わせて魔女を討ち倒す。
盛り上がりが最高潮に達する婚約破棄の断罪シーンは、役者の熱演もかなりのもので、うちのメイドなどは感動のあまり台詞を諳んじて私に聞かせようとするくらいだった。
そんなだから、私も劇の台詞を少しばかり覚えてしまっていた。
もちろん、自分でなりきって演じたりはしないけど、誰かがその台詞を言いかけたら「あ、これって」と、思うくらいにはわかってしまう。
そう、わかってしまうのだ。
だから、私の目の前で、婚約者であるコリン王子殿下が、その歌劇と同じように赤い髪の令嬢と手をつないで、私に向かって何かを宣言しようとした時、すぐにそのシーンの再現だということに気づいてしまった。
「カレン・セルデン公爵令嬢! 僕たちの真実の愛は、あなたなどに屈しはしない! 僕は今、この場においてあなたとの婚約を──」
王宮の夜会。貴族たちが集まる定例の催しの場において。
殿下は声高らかにその台詞を言いかけた。
劇を見ていて本当に良かったと思った。台詞を知っていなければ、殿下が錯乱したと勘違いして騒ぎを大きくしてしまっていただろうから。
そして、続く言葉を言わせないようとっさに声を上げられたことも、私にとっては幸運だった。
「まーっ! まぁまぁまぁ、殿下ったら!」
「えっ」
大仰なしぐさで彼をさえぎり、早足で彼に近づく。
こちらの甲高い声に一瞬ひるみ、殿下はあっけにとられて台詞を止めた。
「殿下もあの歌劇をご存じだったのですね!? 素敵ですよねぇ、クライマックスのシーンなんて、感動で涙してしまうほどに! 私も幾度となく劇場に足を運んで観に行きましたわ! 何度観ても新鮮で、本当に素晴らしい物語ですわよね!」
「えっ、あ、ああ」
馬鹿みたいに興奮した口調でまくしたて、二の句を継がせない。
口では適当な嘘をつらつらと並べながら、私はどうして彼らはこんな愚行を犯そうとしたのか、並行して考えを巡らせていた。
一体どうしてか。それはすぐにわかることだった。
つまり、彼らは未熟なのだ。
殿下も、隣にいるミシェル嬢もまだ十四歳。演劇にお熱になって、現実でも同じことが可能と思ってしまうくらいには幼いのである。
対して私は、適齢期を過ぎた二十三の年増女。
しかも、二人の教育係も兼任している。いくつかの理由から殿下の婚約者に収まってはいるけど、こんな年の離れた小姑とはいい加減関係を断ち切りたかったのだろう。これまでの関係から、それは容易に想像できた。
件の歌劇は、まるで私たちをモデルにしたかのように、ほぼ立ち位置が似通っていた。
コリン殿下は主役の少女と結ばれるヒーロー。
赤い髪のミシェル嬢は、同じく赤髪の主人公の少女。
そして、私、カレン・セルデンは、婚約破棄される年上の公爵令嬢。
ミシェル嬢が由緒正しい侯爵家の令嬢であることを除けば、それ以外はほぼ同じで、勘違いしてしまうのも無理はない。
ただ、現実は劇のように甘くはない。
衆目の場で前準備もなしに婚約破棄を宣言すれば、周りからどう見られるか、そこまで考えが及ばないのは愚かとしか言いようがなかった。
(とりあえず、後でお説教ね……)
だから私は、歌劇談義にかこつけて、殿下たち二人をこのホールから退場させることにした。
「わたくし、実を申しますと、あの物語の良さを語りあえる同志を探しておりましたの! こんな近くにいらっしゃるなんて、予想外の僥倖ですわ! うぅん、ミシェル嬢も! こんなところで立ち話もなんですし、いっそのこと、小部屋をお借りしてそこで語りあいませんこと? そうね、それがいいわ、そうしましょう!」
「えっ、か、カレン嬢、ちょっと待って」
「あ、あの、カレン様?」
私は殿下とミシェル嬢の手をぐいと引く。
「さぁさぁ、お二人とも、こちらにいらっしゃって! あ、そこのあなた、ちょっと来ていただけるかしら? 確か二階の端に休憩室が設けられているはずなのだけど、そこまでわたくしたちを案内して下さらない? そう、そこの帯剣している騎士さん、あなたよ」
続いて、近くにいた騎士らしき男性に声をかける。
その男性は驚いた様子で、「お、俺ですか?」と視線で私に問い返した。
うなずき、私は彼に近づいて耳打ちする。
「緊急事態よ。どうも殿下は乱心されているみたいなの。別室へお連れするから、そこまでの警護をお願いできるかしら」
えっ、と眼を見開き、振り返って殿下を見る男性騎士。
「剣をちらつかせて随行するだけでいいから」と私が言うと、すぐに真剣な瞳になって「了解した」と応じてくれた。
こんな無理矢理な勢いだけで、ずっと二人を抑えられるはずもない。
褐色肌のその騎士は、上背も高く、物理的な抑止力としては申し分ないように思われた。
私たちはそのままホールを出て、四人で二階の休憩室に入る。
バタンと扉を閉め、殿下たちが逃げ出さないよう、騎士には部屋内の扉付近に立ってもらうよう小声で頼んだ。
そうして準備を整えた後で、私はスッといつもの表情──無愛想な冷徹女の顔に戻り、静かに二人へと問いかける。
「──さて、殿下にミシェル嬢。一体どういうつもりなのか、うかがってもよろしいかしら?」
そこでさっと青くなる、コリン殿下とミシェル嬢。
彼らはようやく私の意図を理解したようだった。