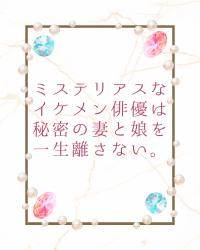呪われて、初恋。
1.
初恋はある種呪いだと思う。
いつまでも私の心に棲みついて、時に狂おしいくらいに震わせる。
未だに初恋は私にとって特別な思い出であり、呪いだった。
* * *
美しい夜景が望める高層階ビルの中にあるレストラン。外は凍えるような冷気に包まれながら、煌びやかなイルミネーションの灯りがロマンチックなホリデーナイトを演出していた。
恋人たちのクリスマスとは誰が言ったか、このレストランに訪れている客もほとんどがカップルだ。
美澄理宇も婚約者である高菱|我道とクリスマスデートを楽しんでいた。いや、実際のところ全く楽しくはない。
運ばれるフレンチのフルコースも赤ワインもとても美味しいのに、今一つ味を感じることができない。それは高菱との間に会話が全くないからだろう。
先程からカチャカチャというフォークとナイフの音しか聞こえない。
「高菱さん、お仕事は忙しいですか?」
「ああ」
「父が言っていました、高菱さんが顧問弁護士をしてくださるようになってとても助かっているって。流石ですね」
「当然のことをしているまでだよ」
「……」
こちらから話を振っても、会話はすぐに途切れてしまう。沈黙の時間の方が圧倒的に多い。
「理宇さん、悪いがこの後仕事がある」
「え……」
「今進めている裁判がなかなか厄介でな、年内にできる限り片付けたい」
「そうなんですね……大変ですね」
「ああ」
せっかくのクリスマスデートは食事をする一時間半くらいで終了、そのまま解散。これは最早デートと呼べるのだろうか。
事務的な仕事の延長と変わらないと思った。
(高菱さんにとって私とのデートは仕事と変わらないのかもしれない……)
一応デートに誘ってくれたが、これも婚約者としての体裁を保つための会食なのだろう。甘やかなものなんて期待してはいけない。
それでももしかして、万が一ということを考えて下着を新調したが全くの無駄になってしまった。
「それでは、気をつけて」
「はい、高菱さんも……」
高菱が呼んでくれたタクシーに一人乗り込み、理宇は溜息をつく。運転手もクリスマスイヴに一人で帰らされる哀れな女だと思っているのだろうと思った。
理宇と高菱は理宇の父で美澄商事社長の紹介で見合いをし、その後婚約に至った。
美澄商事の顧問弁護士を務めていた高菱は現在三十五歳。そろそろ結婚適齢期だろう、うちの娘はどうかと父自ら勧めてきた縁談だった。
今年で二十九、来年三十歳になる理宇は日頃から「良い相手はいないのか」と口酸っぱく言われていた。そんな時に優秀な顧問弁護士が未だ独身貴族と知り、これ好機と思ったのだろう。
とりあえず会ってみるだけ、と父の顔を立てるためにも理宇は見合いをした。大人の男の余裕を漂わせる高菱は、初対面から好印象だった。
優しくスマートにエスコートされる度、微かに心が踊るような感覚を覚えた。
(こんな感覚、高校生以来かも……)
見合いが終わり、背筋を正した高菱に「僕と結婚してください」とはっきり言われた。この日が初めてとはいえ、理宇は「はい」と返事をした。
正直に言えば、高菱に恋愛的な意味で惹かれていたのかと言われるとわからない。ただ三十を目前に控え、そろそろ結婚したいと思っていたのは事実だった。
父の勧める男性だ、素敵な人であることには違いない。
忘れられない初恋を引きずり続けてここまできてしまったが、いい加減精算せよということなのだとも思った。
(今頃何しているのかな……もしかしたら彼も結婚してるかもね)
そう考えるだけで胸が痛む情けない自分とは決別しよう。両親にも正式に婚約する旨を伝え、大いに祝福された。
これで良いのだと思った。
しかし高菱が優しかったのは最初だけだった。
月に一度は必ずデートをしているが、いつも形式的なものだ。最初はそれなりに会話があったが、段々と口数は減り高菱は理宇と目も合わせなくなった。
そのくせ父の前ではとても朗らかに笑い、いかにも理宇を大切にしますというように丁重に扱う。
「あなたは僕の婚約者ですが、尊敬する美澄社長の大切なお嬢さんでもある。誠実なお付き合いをしたいので、結婚するまでは清い交際をしましょう」
最初にそう言われた時は少しびっくりしたが、嬉しくもあったし安堵する気持ちもあった。
何しろこの年になるまで男性経験のない理宇は、婚約者とは言え好きとは言えない男性とは……という抵抗がどうしてもあった。
これからこの人を好きにならなければいけないという思いもあったが、怖いという気持ちもあった。
だがそれも今となっては自分に全く関心を持たれていないのだと思い、複雑な気持ちになってしまう。
直接言われたわけではないが、高菱にとってこの婚約はビジネスの一貫なのだろうと思う。お世話になっているクライアントの要望に応えるのと大差ないのかもしれない。
これからこの人と夫婦にならなければいけないのに、不安しかなかった。
高菱は理宇に興味がないが、婚約を取りやめるつもりもない。それは父への態度を見ていればわかる。
(私って何なんだろう)
美澄商事の社長令嬢として生まれた理宇は、美澄商事にコネで入社した。当たり前のように大学を卒業したら美澄商事に入社するという手続きが進められ、当たり前のように理宇の席が用意されていた。
理宇が美澄商事の社長令嬢であることは全社員周知の事実だし、やりにくいだの気を遣うだの陰口を叩かれていることも知っていた。
それでも他の会社に移る勇気もなく、能力がないのにコネで入社したと思われないために必死で頑張った。
自分なりに必死でやっているつもりだが、毎日自分の足らなさに落ち込む日々だ。
何とか自分自身に価値を見出したくて精一杯やっているつもりだけど、婚約者にこうも興味を持たれていないとやはり自分とは無価値な人間なのか、はたまた女としての魅力に欠けるのかと心が沈む。
「……すみません、ここで降ろしてもらえますか」
自宅までまだだいぶ距離があるが、理宇はタクシーを降りた。
イルミネーションが美しく光り輝く道を、理宇は一人で歩く。一度だけ、イルミネーションデートをしたことがある。
凍えるような寒さも彼が隣にいるというだけで体が熱く感じた。あの高揚感は二度と味わえないものだと思った。
(……一人寂しく初恋の思い出に浸るなんて、ほんとに私って痛い女)
自嘲気味に光の道を練り歩く中、ふと目の前を見覚えのある人物が横切った。というより、先程まで一緒にいた人物だった。
「高菱さん……?」
婚約者の高菱が見知らぬ女と腕を組んで歩いていた。理宇にはまるで気づかず、寄り添い合いながら闇の深い方へと消える。あちらの方向にあるものは、ホテル街だ。
理宇は不思議と冷静だった。心のどこかではそうなんじゃないかと思っていた。
もしかしたら近くにまだ理宇がいるかもしれないと思わなかったのだろうか。それとも見られても構わないと思ったのだろうか。
自分如きなどいくらでも説き伏せられると舐められているのだろうか。
思い浮かぶ想像がすべて答えのような気がして、虚しくなった。婚約者の浮気現場を見ても何もできない自分が情けない。
「……っ」
鼻の奥がツンとした。光り輝く光景がグニャリと歪む。
何に対して哀しいのか、それとも悔しいのか。自分のことなのに自分の感情がわからない。それでも一度溢れた涙はとめどなくこぼれ落ちる。
バッグからハンカチを取り出そうとして、弾みで何かが転がり落ちた。ここに来る前に片方落としてしまったピアスのもう片方だった。
いつの間にか耳から消えていて、もう片方も外してしまっていたのだった。アスファルトの上を転がり進むピアスをぼうっと見つめながら、もういいかと思った。
どうせ片方なくしてしまったのだ、片方だけ持っていても意味がない。
「――はい、どうぞ」
転がるピアスを大きな手が掬い上げ、理宇の目の前に差し出された。
いらないと思っていたのに少し戸惑いながら、理宇はピアスを受け取る。
「ありがとうございます……えっ」
「あれ……もしかして、美澄?」
「あ、藍都くん……」
その涼やかで優しい眼差しを忘れたことなどなかった。十年以上経っても彼を見間違うことなどなかった。
理宇が初めてにして唯一恋した人。何年経っても色褪せない想いを思い出させてくれる、憧れ続けた人。
理宇の初恋の人――菅田藍都その人だった。
「うわあ、久しぶり。元気だったか?」
「本当に久しぶり。まあぼちぼち元気だよ」
「何だよそれ。うわあ、ほんとに会えると思わなかったわ」
「え?」
「仕事帰りにイルミネーション見てさ、高校の時を思い出してたんだ。美澄と一緒に見たなぁって」
とくん、と忘れかけていたときめきが蘇る。
まさか自分と同じことを考えていてくれたなんて思わなかった。
「私も、同じこと思い出してた……」
「えっほんとに? すげえ嬉しいんだけど」
藍都は高校生の時と比べるとグッと大人っぽくなった。パリッとしたスーツを着こしているせいでもあると思うが、十代の頃にはなかった大人の男の色香を漂わせている。
クラクラしそうな良い匂いは香水なのだろうか。当時は知らなかった藍都がいる。だが、屈託のない笑顔はあの頃と変わっていなかった。
理宇の大好きな笑顔のままだった。
「なぁ美澄。この後時間ある?」
「え?」
「せっかく会えたんだし、軽く飲んで行かね?」
自分は仮にも婚約者のいる身だ。その婚約者は別の女性との逢瀬を楽しんでいるわけだが、だからといって自分も似たようなことをすべきではないと思う。
頭では理性が働いていても、本能に抗うことができなかった。
「行く、行きたい」
柔らかく微笑んだ彼を見て、もう何も考えられなくなっていた。
*
二人が訪れたのは雰囲気のあるバーだった。一杯目のカクテルグラスをカチンと鳴らし、乾杯する。
「メリークリスマス」
おどけた口調で笑うだけで心臓が狂ったようなリズムで鼓動する。
「メリー、クリスマス」
「ぎこちなっ」
「だって」
緊張しているのだから仕方ない。こんな風にドギマギしているのは自分だけだと思うが。
心臓の音をなるべく聞かないようにしながら、あくまで自然体で尋ねた。
「今何してるの?」
「国際弁護士」
「国際弁護士!?」
「そう、ついこの前までロスにいた」
だから時差ボケなんだよね、と笑う藍都が眩しく感じる。
高菱も弁護士だが、国際弁護士の方が遥かに難しく大変だろうことは理宇でも察しがついた。
「美澄は?」
「私は、父の会社に就職したよ」
「ってことは美澄商事? すげえな」
「すごくなんかないよ……」
コネ入社の自分と自力で国際弁護士になった藍都では雲泥の差があると思った。
バーのカウンターで並んで座っているのが何だか恥ずかしく思えてしまう。
「なんで? すごいだろ。毎日頑張ってるんだから」
「え?」
「美澄は昔から頑張り屋だもんな」
自分に自信がないと、頑張っても頑張ってもまだ足りないような気がしてしまう。他人と比べては自分のできなさ加減に落ち込んでしまう。
藍都はそんな理宇のことを「頑張ってて偉いな」と見ていてくれていた。
その一言だけで嬉しかった。自分の存在を認めてくれるような、ここにいてもいいんだよと言ってくれているような気がして。
藍都の包み込むような優しさにはいつも救われる。昔からどうしようもなく惹かれてしまう。
何年経ってもこの想いだけは色褪せない。灰色だった世界に色がついたみたいだ。
初恋とはある種呪いだと思う。いつまでも理宇の心に棲みついて、時に狂おしいくらいに震わせる。
こんな気持ちにさせてくれるのは、後にも先にも藍都だけだった。
「――ねぇ、もう少し時間ある?」
藍都の声のトーンが少しだけ低くなる。理宇の目を覗き込む彼の瞳は、やや緊張が感じ取れた。まるで断られることを恐れるみたいに。
「……あるよ」
このまま飲まれてはいけないと思った。でも飲まれてしまいたかった。度数強めのカクテルのせいにしたかった。
「よかった……」
藍都は安堵したように微笑み、そっと理宇の手に自らの手を重ねる。大きくてゴツゴツとした温かい手が触れるだけで、言いようのない高揚感で全身が震えそうになる。
今夜はクリスマスイヴだから――そんな言い訳がまかり通るとは思わないけれど、今日だけは目を瞑らせて欲しい。
理宇はするりと藍都の長い指に自分の指を絡ませた。
* * *
隣で眠る彼女の柔らかな長い髪を指で梳き、起こさないように静かにベッドから起き上がる。
ベランダに出て、煙草に火をつける。煙を吹かしながら、もう片方の手でスマホをいじる。
何通かメッセージが届いており、その中には写真も添付されていた。
「メリークリスマス♥︎」
「サリナはアイトのものだからね♥︎」
大胆に胸をアップにした下着姿の写真を見ても何も感じない。むしろ萎えるなぁとすら思う。
後ろには男の横顔が映り込んでいる。とりあえずやることはやってくれていたようだ。
「……バカな女」
好きな男のために好きでもない男と寝るなんて。まあやらせる自分もどうかとは思うが。
とりあえず動かざる証拠はいくつも用意できた。あとはこれをどうやって使うかだ。
これは美澄理宇を手に入れるため、裏で入念に準備を進めていたことだった。
美澄商事の社長令嬢がある弁護士と婚約したという話が耳に入ったのは、帰国して間もなくのことだった。知人の弁護士伝いで知ったのだ。
その弁護士は美澄商事の顧問弁護士を務める高菱という男。真面目な男に見えるが、かなりのギャンブル好きで実はそれなりの額の借金がある。ヤクザに金を借りているという噂もある程金に困っているらしい。
そんな時に美澄商事の社長令嬢との婚約は願ってもない話だったことだろう。
借金があることを社長にバラし、すぐに破談してもよかった。だが金のことしか頭にない高菱は婚約者の理宇にはまるで関心を示さず、社長の前でだけ良い婚約者として振る舞っていた。
密かに盗聴した会話では、こんなことを言っていた。
「俺の婚約者は美澄商事の社長令嬢であること以外取り柄がない。地味で色気もないし、抱いてもつまらなそうだ」
その時、あることを思いついた。
この男には堕ちるところまで破滅してもらおうと。そして理宇には婚約者のことで傷ついてもらおうと。
藍都はある人物に連絡した。弁護士仲間に数合わせで行かされた合コンで出会ったサリナという女だった。
「サリナ、俺の言うことなんでも聞くってやつ、本気でできる?」
サリナは初対面からかなりグイグイ迫っていたが、適当にあしらっていた。それでも諦めてくれず、仕事場まで待ち伏せされるようになってうんざりしていたところだ。
何でも言うことを聞くから付き合ってとせがまれた時は、流石に通報しようかと思ったが利用できるかもしれないと言った。
本当に何でもできると言うのなら。
「できるよ! サリナをアイトのものにしてくれるなら」
「じゃあ、この男落とせる?」
好きな男に他の男を落とせと言われたら流石に拒否するだろうと思った。だがサリナは乗ってきた。
「俺の言う通りにしてくれたらサリナのものになるよ」
「本当に!?」
バカだなと思いつつ、良い手駒ができたと思った。サリナはすぐに高菱に接近した。
高菱がサリナになびかない可能性もあるとは思っていたが、簡単に転がり落ちてくれた。まんまと仕掛けた罠にハマってくれたのだ。
高菱にとっては好都合だったことだろう。金のある婚約者と結婚し、その裏では愛人と浮気三昧。今自分の人生は薔薇色だと高笑いが止まらないはずだ。
この夜が本当の意味での最後だというのに。
すべては理宇を手に入れるためだった。初めて恋をし、唯一愛した彼女を手に入れるため。
ひだまりみたいな優しさと愛らしさを持つ健気で努力家の彼女のことが、愛おしくてたまらない。狂おしい程に彼女が欲しい。
あの日手に入れられなかったからこそ、彼女を強く求めた。二度と離したくないと思ったから、クリスマスイヴに婚約者の浮気を目撃させた。タクシーでそのまま帰ってしまう可能性が高かったが、これは賭けだった。
高校の時に一緒にイルミネーションを見たイヴを思い出してくれたら――そんな思惑が見事に当たってくれた。
小動物みたいな愛らしさはそのままに、蛹が蝶へと変わっていた。鼻を赤くさせ少し潤んだ瞳がかわいくて、抱きしめてどこかに閉じ込めてしまいたい衝動を抑え込むのに必死だった。
あくまで偶然を装い、紳士的かつ運命的に。
「……もう絶対に逃がさない」
理宇にはまだ気づかれてはいけない。こんなにもドロドロとした執着的な愛を抱いていることは。
まだまだこれからだ。じっくり愛でてドロドロに甘やかして捕らえて逃がさない。そしてこのカラダに刻み込みたい。
初恋はある種呪いだ。いつまでも心に棲みつき、狂わせる。これ程までに執着するのは、理宇だからなのか。
藍都はサリナからのメッセージは削除した。彼女からの連絡がくる度に削除している。
吸い殻を捨て、消臭スプレーで匂いを消した。理宇が起きる前にシャワーを浴び、痕跡はすべて消そうと思った。
理宇の前では爽やかで紳士的な同級生であるために。
内に秘めたる執着的で独占的な毒はまだ花開く時を待っている。
.