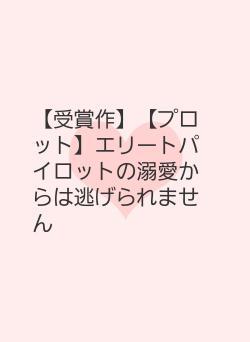怜悧な裁判官は偽の恋人を溺愛する
実はこの食事会で、優流は私のことを婚約者として太一たちに紹介する予定なのだ。
よし。これで素敵な婚約者……に見えるはず。
化粧直しを終えた自分の顔に魔法をかけるように、私は心の中で呟いた。
「やだ、忘れるところだったわ」
ウエットティッシュで手を拭いてから、私はバッグにしまっていた婚約指輪を左手の薬指にはめた。
ダイヤモンド付きのホワイトゴールドの指輪は、指の上でキラキラと輝いている。立派な指輪をプレゼントされるのは人生で始めてのことであり、まだ着け慣れていないのが正直なところだ。しかし、この指輪が似合うような女性に、少しずつなれるよう努力していこうと思う。
私は優流の偽の交際相手ではなくて、本物の婚約者なのだから。
「じゃあね、お先失礼します。お疲れ様」
「お疲れ様でーす!」
ロッカールームにいるスタッフたちに挨拶してから、私は早足で百貨店の裏口から外へ出た。
「優流さん、お待たせしました!」
「いえ、お疲れ様です。……おや」
「どうしましたか?」
「いえ、やっぱりその指輪、よく似合ってるなと思っただけです」
私の左手に目を向けて、優流はそう褒めてくれた。
「あ、ありがとうございます」
褒められるのは嬉しいものの、まだ指輪に釣り合う女性である自信はないので、少しくすぐったい気分なのが本音だ。そんな私に、優流は穏やかに微笑んでくれた。
「夜道は危ないので、お手をどうぞ」
「……は、はい」
差し出された手に、私はおずおずと手を重ねた。こうして手を繋ぐのも、まだ練習中なのだ。
「じゃあ、行きましょうか」
左手の婚約指輪は、さっき見た時よりもより一層輝いて見えた。
私と優流は手を繋いだまま、待ち合わせ場所であるレストランへと向かった。
終
よし。これで素敵な婚約者……に見えるはず。
化粧直しを終えた自分の顔に魔法をかけるように、私は心の中で呟いた。
「やだ、忘れるところだったわ」
ウエットティッシュで手を拭いてから、私はバッグにしまっていた婚約指輪を左手の薬指にはめた。
ダイヤモンド付きのホワイトゴールドの指輪は、指の上でキラキラと輝いている。立派な指輪をプレゼントされるのは人生で始めてのことであり、まだ着け慣れていないのが正直なところだ。しかし、この指輪が似合うような女性に、少しずつなれるよう努力していこうと思う。
私は優流の偽の交際相手ではなくて、本物の婚約者なのだから。
「じゃあね、お先失礼します。お疲れ様」
「お疲れ様でーす!」
ロッカールームにいるスタッフたちに挨拶してから、私は早足で百貨店の裏口から外へ出た。
「優流さん、お待たせしました!」
「いえ、お疲れ様です。……おや」
「どうしましたか?」
「いえ、やっぱりその指輪、よく似合ってるなと思っただけです」
私の左手に目を向けて、優流はそう褒めてくれた。
「あ、ありがとうございます」
褒められるのは嬉しいものの、まだ指輪に釣り合う女性である自信はないので、少しくすぐったい気分なのが本音だ。そんな私に、優流は穏やかに微笑んでくれた。
「夜道は危ないので、お手をどうぞ」
「……は、はい」
差し出された手に、私はおずおずと手を重ねた。こうして手を繋ぐのも、まだ練習中なのだ。
「じゃあ、行きましょうか」
左手の婚約指輪は、さっき見た時よりもより一層輝いて見えた。
私と優流は手を繋いだまま、待ち合わせ場所であるレストランへと向かった。
終