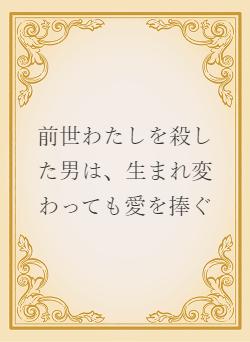恋人である私を捨てて王女様と結婚した騎士様と再婚することになりました
「仕方がなかったんだ」
王命だから。逆らえないから。
三年。いや、それ以上か。ルイーズ・フェリングが目の前で言い訳する男のために費やしてきた時間。労力。
男爵家の娘に生まれ、ケクラン伯爵家の次男であるシクストとは何かと不釣り合いだと嘲笑され、それでも挫けず前を歩き続けたのは、シクストが自分を愛してくれており、必ず結婚してくれると約束してくれたからである。
それなのに――
「陛下の頼みなんだ。俺の父も結局きみとの結婚を許してはくれず、恋人止まりのままだった」
だから仕方がないんだ。
男の顔はわかってくれ、と図々しく訴えていた。王宮での舞踏会。可憐な王女殿下を守るように寄り添って。
周囲の視線が嫌でも突き刺さってくる。こんな大勢の前で。まるでルイーズに恥をかかせ、断れない状況を作るために。
本当に、つくづく……。
「馬鹿みたい」
ルイーズの小さな呟きは、彼の耳に辛うじて届いたかどうかだった。
「ルイーズ?」
後ろに撫でつけた銀色の髪に切れ長の青色の瞳。
微かに眉根を寄せるシクストの表情は惚れ惚れとするほど美しい。彼の顔を見るたびにかつての自分は頬を染め、恥ずかしげに話をしたものだった。
「何か言ったらどうなん――」
ぱしん、とルイーズは音を立てて男の頬を叩いた。一瞬水を打ったように辺りが静まり返った気がしたけれど、気のせいかもしれない。
「ルイーズ……」
ぶたれた男は頬に手を当て、信じられないようにルイーズを見つめた。元婚約者は、決してこのようなことをする女ではなかったから。
「あなたって本当に最低な人ね」
腹の底から声を出すように、ルイーズは言ってやった。吐き捨てる、というよりは、事実を淡々と述べるように。
「王女殿下と結婚なさるのなら、どうしてもっと早く言ってくれなかったの?」
「そ、それは王命で、まだ正確に決まったことではなかったから……」
感情的にならない女の指摘に、かえって男の方が動揺する。
「それでも、それとなく伝えることはできるのではなくて? いいえ。そもそも、受けるつもりがあるのならその時点で断っておくべきだわ」
「その時はまだ、きみと結婚するつもりでいた」
嘘ね、とルイーズは微笑んだ。
「あなた、手紙すら出さなかったじゃない。いくら忙しくても、一言何も心配ない、僕の心はきみにあると伝えてくだされば、私は眠れないほどの不安に押しつぶされることはなかったわ」
あなたが王女殿下と結婚するかもしれないと人伝に聞いた時の私の気持ちがわかる? 護衛として王女殿下と一緒にいる姿を偶然見てしまって、王女殿下に微笑みかけるあなたを見て、噂は本当かもしれないと思った私の気持ちがあなたに――
「わかるというの?」
「それは……」
わからない。わかるはずがない。だったら今こんな状況になっていない。
「ルイーズ。本当に、すまなかった」
「本当ね、あなたを妄信していた時間を返してほしいわ」
でも、と彼女は優しく言い放つ。
「あなたみたいな人と結婚しなくて正解だったかも」
きっともっと苦労したことでしょうから。
「王女殿下のこれからの苦労がうかがえるわね」
ルイーズはそこでようやく、シクストの隣にいる王女に目を向けた。だがそれも一瞬で、彼にまた視線を戻す。
「もう少し、相手のことを考えた方がよろしいと思いますわ」
自分だけで完結せず。
「私が伝えたいことはそれだけです」
どうかお幸せに。
お辞儀をして、たくさんの視線を浴びながらも、ルイーズは気にもせずその場を後にしたのだった。
――それが、五年前の出来事。シクストは予定通り結婚し、ルイーズも結婚した。苦い失恋の思い出として葬り去られようとしたが、事態はそうはいかなかった。
シクストと結婚していた王女が病で儚くなられた。そして、ルイーズの夫も天国に旅立ってしまった。国王が退位されて、新しい国王となった王太子がルイーズたちの状況を知って、
「お前たち、互いに再婚してはどうだ」
と何気なく勧めたことで、ルイーズはまた面倒事に巻き込まれるのだった。
両親は若くして未亡人になった娘の将来を惜しみ、再婚を勧めた。
ルイーズは逆らわなかった。
「……きみがよければ、俺も構わない」
だが本当にいいのか? とシクストは困惑した様子でルイーズに確認する。
ルイーズはにっこり微笑んだ。
「ええ、構いませんわ。これから、よろしくお願いしますね」
とんとん拍子に事は進んでいき、ルイーズはシクストと再婚し、夫婦として一夜を過ごした。
我慢しようとして抑えきれない声をあげ、何かに耐えるように悩ましい表情を浮かべ、シクストの大きく逞しい身体にしがみついた。触れ合った身体はどちらも汗ばんで、熱かった。
ルイーズの思い違いでなければ、自分の痴態にシクストも心を乱されて、その気になってくれたと思う。
明け方近く、数時間程しか眠っていないが、何だか目が冴えてしまったルイーズは寝台から下り、身を清めて身支度を済ませると、温室へ向かった。
ささやかな式を終えて滞在している場所は、ルイーズの父であるフェリング男爵が所有していた屋敷である。
落ち着いたら引っ越すことを提案されるかもしれないが、ルイーズはどちらでもよかった。
再婚した次の日とは思えぬほど凪いだ心で、黙々と花の手入れをしていた。没頭して作業しているうちに空はすっかり明るくなり、シクストが起きてきて自分を見ていることにすら気づかなかった。
「あら、目が覚めたの」
どこか呆けたような表情でいるシクストにルイーズはまだ眠いのかしら、と思った。
今日は特にすることもないので後で二度寝でもするといいだろう。
ルイーズはそんなことを思いながら活けようとしていた薔薇を花瓶に戻し、シクストに近寄った。距離を詰めるルイーズになぜか彼は動揺した様子を見せる。
「そんな所に突っ立っていないで、朝食にしましょうよ」
「あ、ああ……」
呼び鈴を鳴らし、ルイーズは使用人たちに朝食を運ばせた。ベーコンエッグ、トースト、紅茶、フルーツと、白いテーブルクロスをかけたテーブルには次々と料理が並べられる。そして使用人たちは用意が終わると、すぐに下がり、ルイーズとシクストの二人きりにさせた。
特に話すことなく、淡々と食事をする。
「昨日はよく眠れた?」
半分ほど食べ終えた頃、不意にルイーズはシクストに尋ねてみた。
ごほっと紅茶を飲んでいたシクストはむせてしまう。
「大丈夫?」
「だ、大丈夫だ……」
んんっ、と何とか息を整え、改めてシクストがルイーズを見る。
「きみに聞きたいことがある」
「何かしら」
「……どうして俺と再婚してくれたんだ?」
「どうして再婚しないと思ったの?」
「いや、それは……」
シクストの目が逸らされ、やがて辛いことを思い出すように伏せられた。
「五年前、俺はきみを傷つけて、きみも……俺のことを許さないと思ったからだ」
そう。五年前、シクストは王命で王女であるセラフィーナを娶った。もちろん最初、彼は断ろうとしてくれた。当時の彼には、ルイーズ・フェリングという婚約者がいたのだから。
しかし王家の意向は強く、シクストは逆らうことができなかった。ルイーズは別れを切り出された。大勢の人間が集まる舞踏会で、お姫様の隣で。
「本当に、後悔している。きみの言う通り、自分のことばかり考えて、未熟だった」
シクストの表情を見ていると、その言葉は嘘ではないように思えた。
「だからきみが俺との再婚を引き受けてくれて、嬉しく思う。これからは――」
「シクスト」
大事なことを伝えようとするシクストの言葉を、ルイーズは遮った。
「私、別にあなたのことを許したから再婚に応じたわけではないわ」
「え」
ではなぜ、と問いかけるシクストの顔を、ルイーズは面白そうに見つめる。
「私が再婚したのは、あなたを愛する必要がないと思ったからよ」
愛する必要がない。
シクストはオウムのように呆然とルイーズの言葉を繰り返した。
「それは、一体……」
「私が愛しているのは、亡くなった夫だけよ」
はっきりと告げられ、シクストは目を見開いた。
「だが、きみは、昨夜……」
「私の家にはまだ後継者がいない。子どもを作らないまま修道院に入ることを、お父様はお許しにならなかった。だから、それまではあなたに協力してほしいの」
つまり種馬になってほしいと、ルイーズは言っているのだ。
「子どもができたら、あなたも好きにしていいわ。再婚して、子どもまで作ったのだもの。さすがに誰も何も言わないでしょうよ」
「ま、待て、ルイーズ。きみの話はいろいろと飛躍しすぎている! そもそも、嫌なら断ればよかっただろう!?」
無理よ、とルイーズは微笑んだ。
「だって王命だもの」
仕方ないのよ、という言葉は温室内に冷たく響き渡った。
王命だから。逆らえないから。
三年。いや、それ以上か。ルイーズ・フェリングが目の前で言い訳する男のために費やしてきた時間。労力。
男爵家の娘に生まれ、ケクラン伯爵家の次男であるシクストとは何かと不釣り合いだと嘲笑され、それでも挫けず前を歩き続けたのは、シクストが自分を愛してくれており、必ず結婚してくれると約束してくれたからである。
それなのに――
「陛下の頼みなんだ。俺の父も結局きみとの結婚を許してはくれず、恋人止まりのままだった」
だから仕方がないんだ。
男の顔はわかってくれ、と図々しく訴えていた。王宮での舞踏会。可憐な王女殿下を守るように寄り添って。
周囲の視線が嫌でも突き刺さってくる。こんな大勢の前で。まるでルイーズに恥をかかせ、断れない状況を作るために。
本当に、つくづく……。
「馬鹿みたい」
ルイーズの小さな呟きは、彼の耳に辛うじて届いたかどうかだった。
「ルイーズ?」
後ろに撫でつけた銀色の髪に切れ長の青色の瞳。
微かに眉根を寄せるシクストの表情は惚れ惚れとするほど美しい。彼の顔を見るたびにかつての自分は頬を染め、恥ずかしげに話をしたものだった。
「何か言ったらどうなん――」
ぱしん、とルイーズは音を立てて男の頬を叩いた。一瞬水を打ったように辺りが静まり返った気がしたけれど、気のせいかもしれない。
「ルイーズ……」
ぶたれた男は頬に手を当て、信じられないようにルイーズを見つめた。元婚約者は、決してこのようなことをする女ではなかったから。
「あなたって本当に最低な人ね」
腹の底から声を出すように、ルイーズは言ってやった。吐き捨てる、というよりは、事実を淡々と述べるように。
「王女殿下と結婚なさるのなら、どうしてもっと早く言ってくれなかったの?」
「そ、それは王命で、まだ正確に決まったことではなかったから……」
感情的にならない女の指摘に、かえって男の方が動揺する。
「それでも、それとなく伝えることはできるのではなくて? いいえ。そもそも、受けるつもりがあるのならその時点で断っておくべきだわ」
「その時はまだ、きみと結婚するつもりでいた」
嘘ね、とルイーズは微笑んだ。
「あなた、手紙すら出さなかったじゃない。いくら忙しくても、一言何も心配ない、僕の心はきみにあると伝えてくだされば、私は眠れないほどの不安に押しつぶされることはなかったわ」
あなたが王女殿下と結婚するかもしれないと人伝に聞いた時の私の気持ちがわかる? 護衛として王女殿下と一緒にいる姿を偶然見てしまって、王女殿下に微笑みかけるあなたを見て、噂は本当かもしれないと思った私の気持ちがあなたに――
「わかるというの?」
「それは……」
わからない。わかるはずがない。だったら今こんな状況になっていない。
「ルイーズ。本当に、すまなかった」
「本当ね、あなたを妄信していた時間を返してほしいわ」
でも、と彼女は優しく言い放つ。
「あなたみたいな人と結婚しなくて正解だったかも」
きっともっと苦労したことでしょうから。
「王女殿下のこれからの苦労がうかがえるわね」
ルイーズはそこでようやく、シクストの隣にいる王女に目を向けた。だがそれも一瞬で、彼にまた視線を戻す。
「もう少し、相手のことを考えた方がよろしいと思いますわ」
自分だけで完結せず。
「私が伝えたいことはそれだけです」
どうかお幸せに。
お辞儀をして、たくさんの視線を浴びながらも、ルイーズは気にもせずその場を後にしたのだった。
――それが、五年前の出来事。シクストは予定通り結婚し、ルイーズも結婚した。苦い失恋の思い出として葬り去られようとしたが、事態はそうはいかなかった。
シクストと結婚していた王女が病で儚くなられた。そして、ルイーズの夫も天国に旅立ってしまった。国王が退位されて、新しい国王となった王太子がルイーズたちの状況を知って、
「お前たち、互いに再婚してはどうだ」
と何気なく勧めたことで、ルイーズはまた面倒事に巻き込まれるのだった。
両親は若くして未亡人になった娘の将来を惜しみ、再婚を勧めた。
ルイーズは逆らわなかった。
「……きみがよければ、俺も構わない」
だが本当にいいのか? とシクストは困惑した様子でルイーズに確認する。
ルイーズはにっこり微笑んだ。
「ええ、構いませんわ。これから、よろしくお願いしますね」
とんとん拍子に事は進んでいき、ルイーズはシクストと再婚し、夫婦として一夜を過ごした。
我慢しようとして抑えきれない声をあげ、何かに耐えるように悩ましい表情を浮かべ、シクストの大きく逞しい身体にしがみついた。触れ合った身体はどちらも汗ばんで、熱かった。
ルイーズの思い違いでなければ、自分の痴態にシクストも心を乱されて、その気になってくれたと思う。
明け方近く、数時間程しか眠っていないが、何だか目が冴えてしまったルイーズは寝台から下り、身を清めて身支度を済ませると、温室へ向かった。
ささやかな式を終えて滞在している場所は、ルイーズの父であるフェリング男爵が所有していた屋敷である。
落ち着いたら引っ越すことを提案されるかもしれないが、ルイーズはどちらでもよかった。
再婚した次の日とは思えぬほど凪いだ心で、黙々と花の手入れをしていた。没頭して作業しているうちに空はすっかり明るくなり、シクストが起きてきて自分を見ていることにすら気づかなかった。
「あら、目が覚めたの」
どこか呆けたような表情でいるシクストにルイーズはまだ眠いのかしら、と思った。
今日は特にすることもないので後で二度寝でもするといいだろう。
ルイーズはそんなことを思いながら活けようとしていた薔薇を花瓶に戻し、シクストに近寄った。距離を詰めるルイーズになぜか彼は動揺した様子を見せる。
「そんな所に突っ立っていないで、朝食にしましょうよ」
「あ、ああ……」
呼び鈴を鳴らし、ルイーズは使用人たちに朝食を運ばせた。ベーコンエッグ、トースト、紅茶、フルーツと、白いテーブルクロスをかけたテーブルには次々と料理が並べられる。そして使用人たちは用意が終わると、すぐに下がり、ルイーズとシクストの二人きりにさせた。
特に話すことなく、淡々と食事をする。
「昨日はよく眠れた?」
半分ほど食べ終えた頃、不意にルイーズはシクストに尋ねてみた。
ごほっと紅茶を飲んでいたシクストはむせてしまう。
「大丈夫?」
「だ、大丈夫だ……」
んんっ、と何とか息を整え、改めてシクストがルイーズを見る。
「きみに聞きたいことがある」
「何かしら」
「……どうして俺と再婚してくれたんだ?」
「どうして再婚しないと思ったの?」
「いや、それは……」
シクストの目が逸らされ、やがて辛いことを思い出すように伏せられた。
「五年前、俺はきみを傷つけて、きみも……俺のことを許さないと思ったからだ」
そう。五年前、シクストは王命で王女であるセラフィーナを娶った。もちろん最初、彼は断ろうとしてくれた。当時の彼には、ルイーズ・フェリングという婚約者がいたのだから。
しかし王家の意向は強く、シクストは逆らうことができなかった。ルイーズは別れを切り出された。大勢の人間が集まる舞踏会で、お姫様の隣で。
「本当に、後悔している。きみの言う通り、自分のことばかり考えて、未熟だった」
シクストの表情を見ていると、その言葉は嘘ではないように思えた。
「だからきみが俺との再婚を引き受けてくれて、嬉しく思う。これからは――」
「シクスト」
大事なことを伝えようとするシクストの言葉を、ルイーズは遮った。
「私、別にあなたのことを許したから再婚に応じたわけではないわ」
「え」
ではなぜ、と問いかけるシクストの顔を、ルイーズは面白そうに見つめる。
「私が再婚したのは、あなたを愛する必要がないと思ったからよ」
愛する必要がない。
シクストはオウムのように呆然とルイーズの言葉を繰り返した。
「それは、一体……」
「私が愛しているのは、亡くなった夫だけよ」
はっきりと告げられ、シクストは目を見開いた。
「だが、きみは、昨夜……」
「私の家にはまだ後継者がいない。子どもを作らないまま修道院に入ることを、お父様はお許しにならなかった。だから、それまではあなたに協力してほしいの」
つまり種馬になってほしいと、ルイーズは言っているのだ。
「子どもができたら、あなたも好きにしていいわ。再婚して、子どもまで作ったのだもの。さすがに誰も何も言わないでしょうよ」
「ま、待て、ルイーズ。きみの話はいろいろと飛躍しすぎている! そもそも、嫌なら断ればよかっただろう!?」
無理よ、とルイーズは微笑んだ。
「だって王命だもの」
仕方ないのよ、という言葉は温室内に冷たく響き渡った。