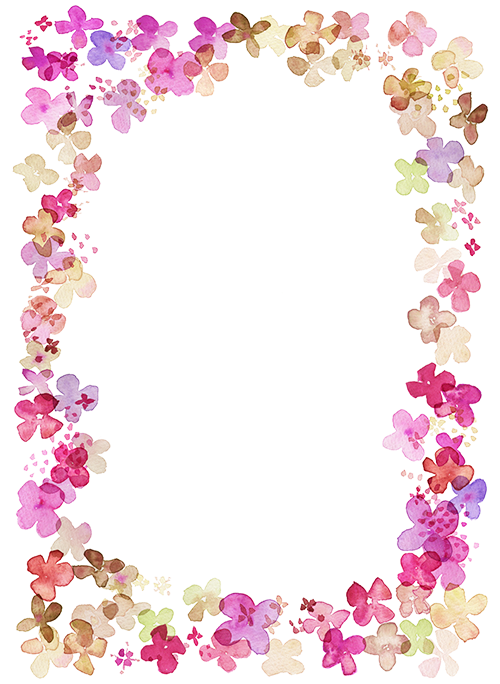秘密のカーテンコール〜人気舞台俳優の溺愛〜
9.エピローグ
柊木さんが何とか帰そうとした佐々木さんと、結局三人で夕食を食べた。私が支度をしているあいだに持ち帰った荷物を片付けるのを手伝ってくれたから、なんだかんだ佐々木さんにいてもらわなかったら大変だったはずだ、と諭したけれど、それよりも早く二人きりになりたかったと小声で囁かれてしまえば、照れくさくて、でもそれ以上に嬉しくて何も言い返せない。
それでも佐々木さんは夕食の後素早く席を立ったから、やっぱり柊木さんのことをよくわかっているのだと思う。
後片付けを終わらせ、リビングのソファに並んで座った。
これまでここは雇主のスペースと思っていたから、考えてみれば座るのは初めてだ。
最初は少し離れていたけれど、柊木さんがぐいっと距離を詰めてきて腕を引かれたので、今、私の頭は大きな肩に乗っている。
時々柔らかく頭を撫でてくれるのが気持ち良い。
「今日、泊まってく?」
「えっと……、帰ります」
「えー?」
「お父さんに説明しないと」
時々自分の前髪を梳きながら、私の髪をくるくると弄んでいた柊木さんの手が、ぴたりと止まった。
「そっか。そうだよな」
「気まずいですか?」
「ううん。っていうか、俺から挨拶に行くよ」
「え?」
「多分、征さん気づいてるし」
「え!?」
「だから俺バレバレだったんだって。柚さん以外に」
叔父には何やかんやと口を挟まれたけれど、父には何も言われなかったから予想外だった。
父親に彼氏を紹介なんて今までしたことがないから、やたら気恥ずかしい。
うーんと唸っていると、知らぬ間に伸びてきた指に顎を掬われた。
ちゅっと軽く口付けられて、びくりと肩が震える。
それでも目を閉じれば、今度はしっとりと唇が重なった。
時折啄むように舐められ、逃げようとしてもあっさりと捕まって、今度は宥めるように優しく口付けられる。
「んっ……」
何度も繰り返して息苦しくなってきた頃、ようやく唇が離れていった。
間近に柊木さんの濡れた唇が見えて、かっと体が熱くなる。
そんな私に気づいてか、柊木さんはそっと背中を撫でてくれた。
「ね、柚さん。不安があったら何でも言って」
「……え」
「お互いに何でも言って何でも聞く。それだけ約束しよ」
私が子どもの頃に感じた恐怖は、置いていかれることと、言葉を嘘だと知ってしまうことだった。
でもそれは多分、柊木さんには当てはまらない。母と柊木さんは違う人間だから。
考えれば当たり前のことなのに、時々立ち竦むように捕われてしまう私に、柊木さんは約束をしてくれる。
「はい、ありがとうございます」
「ん」
満足そうに頷いた柊木さんは、また唇を寄せてくる。
今度はさっきよりも強く。ぎゅっと閉じた唇を抉じ開けるように舌先が動く。
ぞわりと背筋に快感が走って、思わず柔らかいソファの上を後ずさった。
「やっ……」
「ごめん、それは聞けないかも」
「何でもって言ったのに……」
「じゃ、まず本当に嫌か聞かせて」
そう言って、もう何度も目にした笑みを浮かべた柊木さんは、長い指で私の唇をなぞる。
深い瞳に捕われて目を逸せない私の方が、明らかに不利だ。
「好きだよ」と囁く声に、抗うことはもうできなかった。
何度も落ちてくる唇を受け止める。
キスの合間に何度も「あー、帰したくないな」と言う悠真さんに思わず笑って、私の方から強く抱きついた。
End.
それでも佐々木さんは夕食の後素早く席を立ったから、やっぱり柊木さんのことをよくわかっているのだと思う。
後片付けを終わらせ、リビングのソファに並んで座った。
これまでここは雇主のスペースと思っていたから、考えてみれば座るのは初めてだ。
最初は少し離れていたけれど、柊木さんがぐいっと距離を詰めてきて腕を引かれたので、今、私の頭は大きな肩に乗っている。
時々柔らかく頭を撫でてくれるのが気持ち良い。
「今日、泊まってく?」
「えっと……、帰ります」
「えー?」
「お父さんに説明しないと」
時々自分の前髪を梳きながら、私の髪をくるくると弄んでいた柊木さんの手が、ぴたりと止まった。
「そっか。そうだよな」
「気まずいですか?」
「ううん。っていうか、俺から挨拶に行くよ」
「え?」
「多分、征さん気づいてるし」
「え!?」
「だから俺バレバレだったんだって。柚さん以外に」
叔父には何やかんやと口を挟まれたけれど、父には何も言われなかったから予想外だった。
父親に彼氏を紹介なんて今までしたことがないから、やたら気恥ずかしい。
うーんと唸っていると、知らぬ間に伸びてきた指に顎を掬われた。
ちゅっと軽く口付けられて、びくりと肩が震える。
それでも目を閉じれば、今度はしっとりと唇が重なった。
時折啄むように舐められ、逃げようとしてもあっさりと捕まって、今度は宥めるように優しく口付けられる。
「んっ……」
何度も繰り返して息苦しくなってきた頃、ようやく唇が離れていった。
間近に柊木さんの濡れた唇が見えて、かっと体が熱くなる。
そんな私に気づいてか、柊木さんはそっと背中を撫でてくれた。
「ね、柚さん。不安があったら何でも言って」
「……え」
「お互いに何でも言って何でも聞く。それだけ約束しよ」
私が子どもの頃に感じた恐怖は、置いていかれることと、言葉を嘘だと知ってしまうことだった。
でもそれは多分、柊木さんには当てはまらない。母と柊木さんは違う人間だから。
考えれば当たり前のことなのに、時々立ち竦むように捕われてしまう私に、柊木さんは約束をしてくれる。
「はい、ありがとうございます」
「ん」
満足そうに頷いた柊木さんは、また唇を寄せてくる。
今度はさっきよりも強く。ぎゅっと閉じた唇を抉じ開けるように舌先が動く。
ぞわりと背筋に快感が走って、思わず柔らかいソファの上を後ずさった。
「やっ……」
「ごめん、それは聞けないかも」
「何でもって言ったのに……」
「じゃ、まず本当に嫌か聞かせて」
そう言って、もう何度も目にした笑みを浮かべた柊木さんは、長い指で私の唇をなぞる。
深い瞳に捕われて目を逸せない私の方が、明らかに不利だ。
「好きだよ」と囁く声に、抗うことはもうできなかった。
何度も落ちてくる唇を受け止める。
キスの合間に何度も「あー、帰したくないな」と言う悠真さんに思わず笑って、私の方から強く抱きついた。
End.