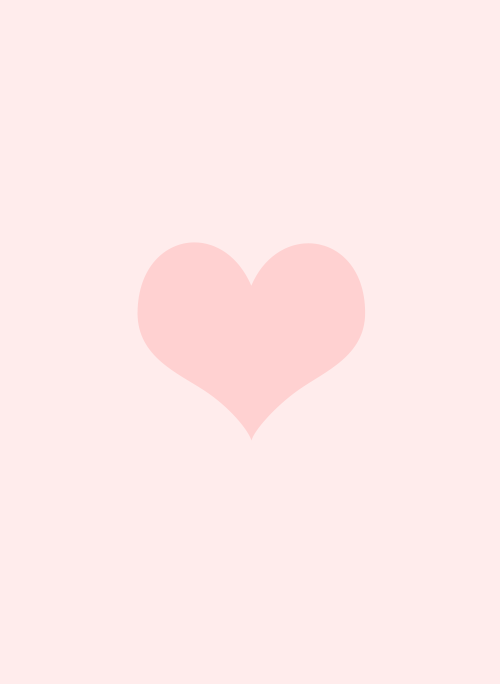永遠の終わりに花束を
EPILOGUE
「――なので、縁談はお断りします」
緊張に指先を冷やしながら頭を下げる。
この身勝手を、それでも押し通すと決めたから。
実家のダイニングで重々しく切り出した私の話を聞き、父と母は押し黙ったままだ。この場に浮遊する空気が重々しい。普段は気にならない時計の秒針の音がやけに響いて。
「その、滝沢さんって人と付き合ってるのか?」
「…ごめんなさい」
「どうして謝るんだ?」
父の落ち着いた声が窘めるような色を孕む。それに思わず顔を上げると、普段と変わらない優しい瞳と目が合った。
「付き合ってることを親に謝らなければならないような相手なのか?」
「ち、違い、ます、そんなひとじゃ」
「なら今の言葉はその相手に失礼なことだよ」
取引先の方とのゴルフ帰りでポロシャツ姿の父が鷹揚にそう呟いてから、「まあ血は争えないってことかな」と隣に座っていた母に話を振る。それに母は困ったように眉尻を垂らし、そうかもしれませんねと笑った。
「あなたと私の娘ですから」
「縁談で結婚するタマじゃなかったか」
「お義父様と大喧嘩して家出までしてきたあなたに比べたら、こうして相談してくれるだけ佳乃のほうがよっぽどマシよ」
母との結婚を周囲から大反対された父は、一時期実家を飛び出して行方をくらませたことがあるらしい。その時は母と北海道のほうに逃亡して、割りと過激な反抗期だったのだという話を寝物語に何度も父からは聞かされた。
懐かしそうに目を合わせるふたりは娘の私が恥ずかしくなってしまうほど、今に至るまで仲の良い夫婦だ。神妙だった空気はゆっくりとほどけ、いつもの家族の空気に戻る。まるで武勇伝みたいな父と母の昔話を黙って聞きながら、何故だか胸の奥が熱くなった。
「熊谷さんには私からも頭を下げておくよ」
「はい、あの、迷惑ばかりで――」
「迷惑をかけられる親がいる間はいくらでも好きに生きたらいいさ」
そのうち嫌でも私たちのほうが先にくたばるんだからな、と笑って、立ち上がった父が冷蔵庫からビールを取り出してくる。
「その滝沢さんはどこにお勤めなんだ?」
「あ、実は彼もクワタにお勤めで、夕鷹の直接の上司に当たるんだって」
「なんだ、なら豊川さん家の悪ガキの紹介か?」
「そういうわけでもなくて…」
偶然知り合った相手が奇縁なことに夕鷹の直属の上司だっただけだというと、すごい偶然だと父が目を丸くしながらアルミ缶に口を付ける。私や母とは違って、父はお酒が好きな割りにあまり強くないので早速顔が赤い。
「でも佳乃と同い年で夕鷹くんの上役なら随分な出世頭じゃないか?あのイタズラ坊主もあれで結構仕事のほうは優秀だって聞くし、確か、去年昇進したんじゃなかったか」
「さあ、私は仕事のことはあまり…」
「なら今度彼のことをうちに連れてきなさい」
真剣に付き合うつもりなら将来のことは考えてもらわないと困るからな、と言って、どこか厳格な目で父が私を見る。瞳の奥の覚悟を探られているようなその視線に小さく肩を震わせながら、でも確かに頷いた。
滝沢にも、それは事前に伝えてある。
これから色んな苦労を掛けてしまうだろうから。
「でも、まだ付き合いはじめでしょう?」
「だからって無責任な気持ちで付き合うつもりの相手に大事な娘を預けられるか」
「あまり過保護すぎるのもどうかと思いますよ」
「なにを今さら」
俺が過保護なのは今にはじまったことじゃないだろうと開き直る父を、母が呆れたように流し見て肩を竦めた。キッチンからワイングラスをふたつ持って来た母は、その片方を私の前に置き、そこに白ワインを注ぐ。
「だって、そんな堅苦しい仕事の話より、もっと恋バナが聞きたいじゃない?」
「なにが恋バナだ、それこそくだらん」
「あなた、佳乃に彼氏ができて寂しいんでしょ」
「そんなわけあるか」
赤らんだ顔で思い切り眉をしかめる父の肩を軽く叩いて、母が楽しげな声を立てる。私はそんな両親のやり取りを傍観しながら、滝沢との付き合いをふたりから反対されずに済んだことに、ほっと胸を撫で下ろした。
ううん、きっと、本当は違うけれど。
何も言わずにいてくれるのはふたりの優しさだ。
「ねえ、佳乃」
昼間から飲んですっかり酔い潰れた父をリビングに残して、日が暮れる前に家を出ようとした私を後ろから母が呼び止めた。
「あんまり思い詰めないでね?」
「…うん、お母さんにもまた苦労かけるけど」
「そんなの佳乃が気にすることじゃないわよ」
まるで小さな子供にでもするような仕種で私の頭を撫でる母の細い手首が酷く頼りなくて、とても逞しく見えた。優しげなその目尻には、柔らかな皺が刻まれている。
「あなたがまた心から好きだと思える相手と恋をしてくれて、本当によかった」
目頭が熱くなって、視界が涙で滲む。
今までどれだけの心配を掛けてきたんだろう?
ごめんね、不出来な娘で。意固地に立ち止まったままの私をもどかしく思うことだってあったはずなのに、今までなにも言わずに見守ってくれて本当にありがとう。
「楽しみにしてるね、佳乃の好きな人に会うの」
「…う、ん、ありがと、お母さん」
「気を付けて帰るのよ」
にっこりと微笑む母に頷いて家を出た。
少し西に傾きはじめた太陽の光が僅かに黄色味を帯び始めている。目の淵に溜まった涙がこぼれてしまわないよう瞬きを我慢しながら、私はゆっくりと歩き出した。
𓂃𓂃𓍯𓈒𓏸𓂂𓐍◌ 𓂅𓈒𓏸𓐍
灰色の風景には馴染みがない。
荘厳な佇まいの建物の前で私は腕時計を見た。
少しだけ仕事を抜け出してきてくれるという彼の言葉に甘えてしまったけど、さすがに忙しい平日の昼間から迷惑だっただろうかと、胸の奥で罪悪感が揺れた。
「すみません、お待たせしました」
そんなことを考えていた背後から聞き覚えのある声がして、振り返るとそこには、見慣れない背広姿の熊谷が、軽く手を振りながらこちらまで小走りに駆け寄ってくる。
「いえ、こちらこそお仕事中に押しかけて…」
「全然大丈夫なんでお気になさらず」
「あの、さっきうちの両親には今回の縁談の件を報告してきたので、多分また父から連絡がいくと思うんですが、それより先に私からも熊谷さんに謝っておかなければと」
破談の件について、どこかで時間をもらえないかと熊谷に連絡を入れたところ、『変に先伸ばしにしても落ち着かないでしょうから、もしお時間あれば俺の勤め先の近くまで来れますか?』とすぐに返信が届いた。
「あはは、そんな律儀に。ちゃんと俺のこと悪者にして言い訳しました?」
「…ただ、ありのままを伝えただけです」
「そうだろうと思ってました」
嘘つくの下手ですもんね、と笑った熊谷が近くのベンチに腰掛けるようにと言ってから、すぐ傍に停まっていたキッチンカーのサンドイッチ屋さんに売っていたコーヒーを買って手渡してくれる。
熊谷はこのあとすぐまた会議が入っているのであまり時間がないのだという。さすが、官吏の方はお忙しい。そう暢気に感心しながら受け取った紙コップに口を付けると、香ばしいコーヒーの香りが鼻に抜けた。
「あ、そうだ、直樹く──じゃなくて、滝沢さんとお会いになりました?」
「佳乃さんを送り届けたあと偶然コンビニでね」
「あの、なにか誤解があったのか──」
「彼はちゃんと貴方の元に行ったみたいですね」
口元に湛えた笑みをにっこりと深めた熊谷が私を見つめてそう呟くのを、きょとんと見つめた。滝沢は結局あまり詳しいことを教えてくれなかったから、私はふたりの間で交わされた会話の詳細を知らないままだ。
ふたりでどんな話をしたんだろう?
直樹くんは何を聞いても知らなくていいという。
「俺、佳乃さんに謝らないとなんですよ」
「え?どういうことですか?」
「あの時、俺、彼に佳乃さんの悪口言っちゃったので。悪い男の引き出しなんか全然ないくせに格好付けちゃって、あとから死ぬほど後悔したんですけど、ふたりのこと傍から見てると、どうにももどかしくて咄嗟に…」
今思い出しても最悪です、と苦笑する。
初夏の凛とした風が熊谷の薄い頬を掠め過ぎた。
優しい人は、どんな時でも優しい。申し訳ないと小さく頭を下げる熊谷に謝ってもらわなければならないことなんて、どの場面を切り取ったって存在しようもないのに。
「…熊谷さん、優しすぎると損しちゃいますよ」
「別に優しさの裏には打算もありますよ」
「そんなの誰だってそうです」
「まあ、でも、あの瞬間だけでも彼が騙されてくれたなら下手な芝居を打った甲斐もあったですかね?煙草なんか学生以来ぶりに吸ったんで咽るかと思いましたもん」
多分あれめちゃくちゃ重いの吸ってるので今後の健康被害に気を付けてくださいね、なんて言って熊谷が楽しげに笑う。それに釣られて、私もつい身に纏ってきたはずの緊張がほどけてしまうからどうにも締まらない。
「あと、あの滝沢さんはちょっと顔とか色々格好良すぎますよね、狡いですよ。お互いの親からのお墨付きってカードしか持たずに競わされる俺の身にもなって欲しい」
「え、そんな、熊谷さんだって格好良いのに…」
「なら今から俺に乗りまえます?」
「そっ、れは、えっと……」
「はは、冗談ですよ」
今さらふたりの恋路の邪魔して余計な傷を負うのは俺も勘弁なので、とおどけながら、ふと左手首に巻かれた腕時計に視線を落とした熊谷が気だるげに立ち上がった。
「すみません、そろそろ会議の時間で」
「こちらこそお忙しい時に押しかけてしまって」
「多分今度こそ最後になると思いますけど、でも会えてよかったです。泣き顔も可愛かったですけど、やっぱり笑顔のほうが数倍素敵なので、俺の失恋の餞になりました」
屈託なく笑う彼には、夏のはじまりが似合う。
どうかお元気でと差し出された熊谷の大きな手に応えて握手をすると、ひとつの季節がゆるやかに終わりを告げた。それはとても穏やかで、ほんのりと切ない終幕だった。
𓂃𓂃𓍯𓈒𓏸𓂂𓐍◌ 𓂅𓈒𓏸𓐍
公園のベンチで少しそわそわしてしまう。
今さらながら、ここできちんと約束を取り付けて滝沢と待ち合わせをするのは初めてだ。週末には大体顔を合わせるルーティンだったけど、それはあくまで偶発的に発生するご近所さんとの遭遇に過ぎなかったので。
「別に今さら緊張する必要ある?」
「だって、付き合ってから会うの初めてだし…」
「仕事立て込んでて会えなかったの怒ってる?」
「え!そんな、怒ってないよ!」
勇み足なアルに引っ張られながら公園に現れた滝沢と落ち合って、散歩コースを一緒に巡る。朝の爽やかな風が気持ちいいのか、アルはふさふさの尻尾を揺らして機嫌が良さそうだ。
先週の滝沢は仕事が立て込んで毎日のように帰りが遅かったので、結局会えずじまいだった。すぐ近所に住んでいるんだから会おうと思えばいくらでも会えただろうけど、疲れている滝沢の負担になるのも嫌で。
「ほんとなあ、この春から部署異動してさすがに残業増えすぎてんだよな」
「…それは、アルも寂しいよね」
「まじで最近それが一番の悩みかもしんない」
この春に社内の部署異動で夕鷹と同じ部門に配属された滝沢は、それ自体は昇進なのでめでたいことだが、おかげで残業が増えたと不満げだ。今は一日の大半をアルにひとりで留守番させなければならない状況になっているらしく、確かにそれは心配だろう。
「ペットシッターとかも考えたけど今さらそんなの逆にストレスかなあとか」
「見知らぬ人と急にっていうのもね…」
「だからって今のタイミングで転職もだしな…」
小難しそうに眉根を顰める滝沢を横目でちらりと伺いながら、舌の上に転がっている提案を口に出すか迷って二の足を踏む。付き合っているからと踏み込むことを許されるラインがどこまでか、判断が難しくて。
「…あ、あの、えっと」
図々しいと思われたらどうしよう。
立ち止まった私を滝沢が不思議そうに振り返る。
「ん?どうかした?」
「も、もし、迷惑じゃなければ、だけど……」
パタパタと私の足元に駆け寄ってきたアルが手の甲を無邪気に舐めた。まだ人の気配の少ない公園は静かで、緑を濃くした木々の葉の隙間から差し込む日差しは柔らかい。
「わ、たしの家で、アルのこと預かっておくのはどうかなと思って……」
私は大した仕事もしていないから基本的には毎日家にいるし、多少はアルも気を許してくれていると思うから適任じゃないかって。しどろもどろに言い募りながら、でも、滝沢の顔を怖くてちゃんと見られない。
密かに抱いた下心を見破られそうで。
なんだかアルをダシに使ってるみたいかなって。
「そ、それと、あと、そしたら毎日直樹くんにも会えるなって、邪なことも、ほんのちょっとだけ考えてます……」
結局隠しておけずに白状するのだから、最初から正直に伝えればいいものを。無意味な回り道のあとで滑稽に着地した私のひとり相撲は、滝沢には鬱陶しいだけだろう。
「…ほんと勘弁して」
「ご、ごめん、なさい、わたし」
「そうじゃなくて俺の心臓が持たないから」
はぁー…と大袈裟なくらい大きなため息をついた滝沢の顔を咄嗟に見上げると、その頬がほのかに赤く染まっていて、それを隠すみたいに右腕で口元を覆っている。
「俺がそっちの家に入り浸ってもいいわけ」
「えっ、あの、それって」
「てか佳乃ばっかり会いたいと思ってるみたいな勘違いもやめてくれる?」
唐突に私の手を握ってズンズンと歩きはじめた滝沢の足元で、アルが飼い主を揶揄うみたいに跳ね回る。耳まで真っ赤にした滝沢の手が珍しく熱を帯びているから、つい自惚れそうになって、私の顔まで熱い。
どうしよう、調子に乗ってしまう。
直樹くんも私と同じ気持ちのかもしれないって。
「アルの面倒見てくれるのは正直すげえ有難いけどさ、やっぱ負担じゃない?」
「……それは、どういう意味でしょうか?」
「正直俺が入り浸る自信しかない」
顔を真っ赤にした犬連れの男女がふたりして池の周りを周遊するという世にもシュールなお散歩を乗り越え、帰宅してひと息ついたところで滝沢がさっきの話を掘り返す。
「だって、佳乃のことだから、どうせ俺の帰りが遅かったら心配して飯とか準備するだろ?そんで飯食ったら帰るのもだるくなって、まあ今日は泊まるかとか言うのが立て続くうちにずるずるここに入り浸る自分の未来が鮮明に想像できて今から普通に申し訳ない」
「む、むしろ、それは大歓迎で……」
「まじで何食ったらこんな素直な子に育つの?」
最早呆れを通り越して感心したような顔をする滝沢に見下ろされると、ちょっと居た堪れない。朝食の準備をはじめようとして取り出したトマトを輪切りにしようとした私の背中から、滝沢がお腹のあたりに腕を回した。
きゅ、と抱き締められるだけで体温が上昇する。
恋人同士の距離にまだ慣れなくて。
胸が詰まって苦しい。
「あとから後悔しても知らねえからな」
窘めるようにそう囁いた滝沢の唇がそっと私のそれを塞ぐと、くらくらと眩暈がした。甘い接触に溺れてしまいそうな朝は――無機質なチャイムの音に遮られた。
こんな朝から、誰だろう?
顔を見合わせながらふたりして首をかしげる。
「え、夕鷹と万緒ちゃん?」
インターホンのカメラ越しに映る夕鷹と万緒がなにやら大騒ぎしているけど、いまいちよく聞き取れなかったので、とりあえずオートロックを解除することにした。
「どうしたんだろ、こんな朝から」
「佳乃、豊川くんに俺らのことなんか言った?」
「昨日お父さんたちに報告してきたから、それを夕鷹にもさっきラインして」
「もう確実にそれだろ、絶対面倒臭い」
露骨にげんなりした顔をする滝沢の心情とは裏腹に、再び鳴らされたインターホン。勢いよく玄関先に駆けていくアルのあとを私たちも追って、鍵を開錠すると――、
「おい!滝沢さんと付き合ったってまじかよ!」
こちらからドアを開ける間もなくバン!と夕鷹が部屋に飛び込んできて、びっくり仰天する。するとその後ろから万緒も、「佳乃さんと滝沢さんが付き合い出したって、この馬鹿が!」と興奮したように顔を出した。
「相変わらず賑やかだねえ、君ら」
「なんっで滝沢さんが佳乃の部屋にいんだよ!」
「お前が今言ったんだろ、付き合い出したって」
「俺そんなん聞いてないんだけど?!」
職場ではそんなことひと言も言ってなかったじゃねえか!と無遠慮にドスドスと上がり込んできた夕鷹が滝沢に詰め寄る。
「俺、君と違って公私混同はしない主義だから」
「報連相がこの世で一番大事だろうが!」
「だから俺、一応お前の上司な」
最早、夕鷹にシャツの襟元を掴み上げられている滝沢は明後日の方向に顔を背け、あからさまに鬱陶しそうだ。しかし夕鷹はそれにめげることなくガミガミと罵声を飛ばしている。
完全に呆気に取られていた私が玄関先で立ち尽くしていると、ふと服の袖口を引っ張られた。それに顔を上げれば、私のほうを見つめる万緒の大きな瞳の中に、うるうると涙の膜が張っていたからぎょっとする。
「え、万緒ちゃんどうしたの!?」
「よ、よしのさん、ほんとにたきざわさんと付き合ったんですか……?」
ボロボロと目の淵からこぼれ出した万緒の涙にひとりで動転していると、さすがに夕鷹と滝沢も何事かとこちらに駆け寄ってきて、大のオトナが密集してオドオドする。
「ううぅ~~~…ほんとよかった、よしのさんが幸せになって、わたし、ゆたかのこと横取りしてすごい迷惑かけたのによしのさん恨み言のひとつも言わないんだもん~~~~」
小さな子供みたいにうわぁんと大泣きする万緒に思い切り抱き着かれて、茫然としたあと、思わず大きな声で笑ってしまう。ごめんね、そんな風に万緒ちゃんが気に病まなきゃいけないことなんて何もなかったのに。
「そんな泣かないでよぉ、万緒ちゃん」
「よじのさんだいずぎでずぅ、おめでどぉぉぉ」
「…お前、まじで鼻水きったねえぞ」
「ほんと豊川くんってデリカシーとかないよね」
綺麗な顔をぐしゃぐしゃにして泣いている万緒を抱き締める肩越しに、げんなりしたような顔の夕鷹と、それに呆れたような視線を向ける滝沢。可笑しな朝の一コマは、それでもなごやかな幸福に満ちている。
ひとまず万緒が落ち着くのを待ってからふたりを部屋に招くことにして、朝食を準備した。それを滝沢が手伝ってくれている横から、「優しい彼氏の振りしやがってクソがッ!」と夕鷹が理不尽に非難していて本当に子供みたいだ。
サンドイッチとサラダの横にコーヒーを添えた簡素な朝食を食卓に並べ、それぞれ席に着いた。しかし私が滝沢の隣に座ろうとしたら、「佳乃は俺の横!」と何故か夕鷹に腕を引っ張られ、何故か私と夕鷹、万緒と滝沢が横並びになる妙な配置となってしまった。
「ほんとあんたいい加減きもいわよ」
「先に言っとくけど俺はまだ全ッ然ふたりのこと認めてねえからな!」
「だからどの立場から物言ってんの?」
「うるっせえ!幼馴染みは親より偉いんだよ!」
「んなわけあるか」
万緒が軽蔑の視線を夕鷹に送っている。
その両横で私と滝沢は、もう諦めムード全開だ。
朝食を食べながら夕鷹と万緒の賑やかな喧嘩を諦観しつつ、足元でサンドイッチを狙うアルにも警戒する。滝沢の膝の上には、ちょこんとハナが鎮座していて可愛い。
「そんで何勝手に付き合ってんだよ」
「佳乃と付き合うのに君の許可がいるの?」
「当たり前だろ!てかなに佳乃とか呼んでんだよ馴れ馴れしいな控えろ!」
「お前、遂に敬語すら捨て始めたな」
凍りそうに冷ややかな声音で応戦する滝沢に私のほうがハラハラしてしまうからやめて欲しい。右隣の夕鷹の背中を軽く叩けば、痛ぇな!と大きな声を出されたけど、痛みを感じるような強さでは絶対叩いてない。
「もう、ほんとやめてよ夕鷹」
「大体佳乃のこと一度は振った男だぞ!」
「振ったら振ったで散々文句つけに来たくせして付き合ったら付き合ったで納得しないの、ほんと死ぬほど面倒臭いよな」
心の底から億劫がっているのが目に見えてわかる滝沢なんて、ものすごく稀有だ。その横では万緒も完全に『なんだコイツ』みたいな顔をしていて私まで居た堪れない。
「で、なら君はどうしたら認めてくれるわけ?」
「…ちゃんと佳乃のこと好きですか?」
「馬鹿だねえ、君も」
優美な所作で頬杖を突いた滝沢の瞳がどこか挑発的に細められる。ゆるり、と弧を描いた口元から紡がれる声はどこか愉しげなのに、硬質な意志を帯びているようで。
何故だろう、胸が鳴ってしまう。
その透き通った琥珀の瞳に何度だって焦がれて。
「――君のお兄さんにだって負ける気はないよ」
𓂃𓂃𓍯𓈒𓏸𓂂𓐍◌ 𓂅𓈒𓏸𓐍
「ほんと昨日は災難だったな」
さすがに飲みすぎて体が怠いと大儀そうに呟いた滝沢がソファーに沈む。私はキッチンでふたり分のコーヒーを淹れてから滝沢の横に行き、片方のマグを手渡した。
「大丈夫?二日酔いじゃない?」
「翌日には残んないほうだから平気、佳乃は?」
「私は元々酔わない体質だから全然大丈夫」
「昨日もケロッとしてたもんな」
結局昨日はあれから夕鷹と万緒が我が家でやけ酒と祝杯を始め、それに私たち付き合わされる形でお昼間から夜遅くまで延々とお酒を飲んでいた。
珍しく夕鷹のほうまでしたたかに酔っ払っていたので滝沢は散々絡まれてはお酒を注がれ、かなりの量を飲んでいた。滝沢もアルコールにはかなり免疫があるほうみたいだけど、だからと言って限度があるので。
「ごめんね、夕鷹が迷惑掛けちゃって」
「今までどんな教育してたわけ、お宅の弟さん」
「子供の頃からやんちゃ坊主すぎてちょっと私の手には負えなかったの」
ありがとうとお礼を言ってマグを受け取った滝沢が、背凭れに預けていた背中を気怠げに起こしてコーヒーを口に含む。
「目に浮かぶよ、豊川くんの幼少期」
「まあ、今とそんなに変わってないからね…」
「カブトムシとか取るの上手そう」
「川で取ってきたザリガニおばさんの鞄に入れて追いかけ回されてた」
「絵に描いたようなクソガキだな…」
あれで野木の跡取りが務まるの?と呆れたように笑った滝沢の腕が伸びてきて、ことりと私の肩に額が落ちてくる。窓辺ではすっかりこの部屋にも慣れた様子のアルがお腹を見せながら日向ぼっこをしていて、途方もなく可愛い。
繊細に揺れるレースカーテン越しに広がる空は群青で、夏の色だ。窓の向こうには彼と出会った公園の風景が佇んでおり、朝の爽やかな風がその気配をここまで運んで来てくれる。この部屋の朝が私はとても好きだ。
「今度ね、お父さんが直樹くんのこと家に連れて来なさいって言ってて…」
「もちろん、いつでも伺うよ」
「…こんな付き合いはじめなのに嫌じゃない?」
「元々覚悟の上に決まってるでしょ」
甘やかすように私の髪をくしゃりと撫でた滝沢が眦にキスをくれる。その些末な仕草だけで、胸の奥が締め付けられるから。
「佳乃の縁談ぶち壊しちゃったしね」
「そんな、あれは別に直樹くんのせいじゃ…」
「俺のせいじゃないの?佳乃が俺のこと大好きな証明かと思ってたのに」
くすりと愉快気に笑みをこぼす。
本当に、直樹くんばっかり余裕綽々でずるい。
ただ意味もなく重いだけの荷物を、優しい彼に背負わせたくなんかないのに。でも私は強欲で身勝手だから、あれもこれもと握り締めたまま、何も手放せなくて。
「手放さなくていいよ、佳乃の大事な荷物だろ」
「でも、負担ばっかり掛けちゃって…」
「またすぐ泣くんだから」
目尻に滲んだ涙を拭ってくれる指先が穏やかで。
私は彼の前でいつも泣いてばかりだ。
繋がれた滝沢の手から伝わるひんやりとした体温を、綺麗な朝のひかりが照らす。そのまばゆさが途方もなく愛しくて。
「一緒に持つよ、最後まで」
移りゆく季節の中で、その瞳に映した春だけがなにひとつ変わることがないまま。それを永遠の中に閉じ込めて、いつまでだって抱き締めていても許されるだろうか?
あなたを巻き込んでごめんなさい。
でも、それでもその言葉に――どうか縋らせて。
「代わりに俺の人生の後始末は佳乃に責任取ってもらわなきゃなんねえけど」
「…ふふ、うん、なんでもするよ」
「じゃあとりあえず疲れたから充電させて」
君の厄介な幼馴染みのおかげで俺の貴重な休日が潰されたからな、と嘯いて、滝沢が私を腕の中に閉じ込める。まだ今は不慣れで少しどぎまぎするけど、早くこんな風に過ごす時間がありふれた風景になるといい。
臆病に立ち止まったままの心をほどいてあなたが抱き締めてくれたこと、本当にね、奇跡のように思っているの。閉ざされた私の庭が柔らかな光に照らされて、ああ、こんなに綺麗だったんだって今さらになって気付けたから。
これからはあなたと一緒にその美しい庭を手入れして、守っていきたい。疲れて帰ってくるだろうあなたの心の拠り所になれるような、季節の花々が色鮮やかに咲き誇る、そんな素敵な庭を造って待っているから。
「そういえばアルの世話の件だけど」
「あ、うん、とりあえず明日から預かろっか?」
「ついでに俺の面倒も見てくれない?佳乃は俺の責任も取らないとだし」
明日も、またここに帰ってきていい?
そう甘えるみたいな声音で囁いて無邪気に笑う。
明日も、明後日も、その次の日も。新しい永遠を貴方の傍で過ごしてもいいかな?あなたが連れ出してくれた若葉色の季節に、私はいつまでだって恋をしていたい。
「美味しいもの作ってアルとハナと待ってるね」
「…最早仕事行きたくねえな、それ」
「お仕事頑張って、課長さん」
「もう降格していいからサボりてえわ…」
項垂れるように私の首筋に顔を埋める滝沢の背中に腕を回した。窓から吹き込む甘い風に揺られる柔らかな髪がほほをくすぐる。どこからともなく窓辺に現れたハナが、ぐっすりと眠るアルの傍に身を寄せて目を閉じた。
いつかの春に、また帰ってこよう。
永遠のはじまりに飾った、この朝のひかりまで。
緊張に指先を冷やしながら頭を下げる。
この身勝手を、それでも押し通すと決めたから。
実家のダイニングで重々しく切り出した私の話を聞き、父と母は押し黙ったままだ。この場に浮遊する空気が重々しい。普段は気にならない時計の秒針の音がやけに響いて。
「その、滝沢さんって人と付き合ってるのか?」
「…ごめんなさい」
「どうして謝るんだ?」
父の落ち着いた声が窘めるような色を孕む。それに思わず顔を上げると、普段と変わらない優しい瞳と目が合った。
「付き合ってることを親に謝らなければならないような相手なのか?」
「ち、違い、ます、そんなひとじゃ」
「なら今の言葉はその相手に失礼なことだよ」
取引先の方とのゴルフ帰りでポロシャツ姿の父が鷹揚にそう呟いてから、「まあ血は争えないってことかな」と隣に座っていた母に話を振る。それに母は困ったように眉尻を垂らし、そうかもしれませんねと笑った。
「あなたと私の娘ですから」
「縁談で結婚するタマじゃなかったか」
「お義父様と大喧嘩して家出までしてきたあなたに比べたら、こうして相談してくれるだけ佳乃のほうがよっぽどマシよ」
母との結婚を周囲から大反対された父は、一時期実家を飛び出して行方をくらませたことがあるらしい。その時は母と北海道のほうに逃亡して、割りと過激な反抗期だったのだという話を寝物語に何度も父からは聞かされた。
懐かしそうに目を合わせるふたりは娘の私が恥ずかしくなってしまうほど、今に至るまで仲の良い夫婦だ。神妙だった空気はゆっくりとほどけ、いつもの家族の空気に戻る。まるで武勇伝みたいな父と母の昔話を黙って聞きながら、何故だか胸の奥が熱くなった。
「熊谷さんには私からも頭を下げておくよ」
「はい、あの、迷惑ばかりで――」
「迷惑をかけられる親がいる間はいくらでも好きに生きたらいいさ」
そのうち嫌でも私たちのほうが先にくたばるんだからな、と笑って、立ち上がった父が冷蔵庫からビールを取り出してくる。
「その滝沢さんはどこにお勤めなんだ?」
「あ、実は彼もクワタにお勤めで、夕鷹の直接の上司に当たるんだって」
「なんだ、なら豊川さん家の悪ガキの紹介か?」
「そういうわけでもなくて…」
偶然知り合った相手が奇縁なことに夕鷹の直属の上司だっただけだというと、すごい偶然だと父が目を丸くしながらアルミ缶に口を付ける。私や母とは違って、父はお酒が好きな割りにあまり強くないので早速顔が赤い。
「でも佳乃と同い年で夕鷹くんの上役なら随分な出世頭じゃないか?あのイタズラ坊主もあれで結構仕事のほうは優秀だって聞くし、確か、去年昇進したんじゃなかったか」
「さあ、私は仕事のことはあまり…」
「なら今度彼のことをうちに連れてきなさい」
真剣に付き合うつもりなら将来のことは考えてもらわないと困るからな、と言って、どこか厳格な目で父が私を見る。瞳の奥の覚悟を探られているようなその視線に小さく肩を震わせながら、でも確かに頷いた。
滝沢にも、それは事前に伝えてある。
これから色んな苦労を掛けてしまうだろうから。
「でも、まだ付き合いはじめでしょう?」
「だからって無責任な気持ちで付き合うつもりの相手に大事な娘を預けられるか」
「あまり過保護すぎるのもどうかと思いますよ」
「なにを今さら」
俺が過保護なのは今にはじまったことじゃないだろうと開き直る父を、母が呆れたように流し見て肩を竦めた。キッチンからワイングラスをふたつ持って来た母は、その片方を私の前に置き、そこに白ワインを注ぐ。
「だって、そんな堅苦しい仕事の話より、もっと恋バナが聞きたいじゃない?」
「なにが恋バナだ、それこそくだらん」
「あなた、佳乃に彼氏ができて寂しいんでしょ」
「そんなわけあるか」
赤らんだ顔で思い切り眉をしかめる父の肩を軽く叩いて、母が楽しげな声を立てる。私はそんな両親のやり取りを傍観しながら、滝沢との付き合いをふたりから反対されずに済んだことに、ほっと胸を撫で下ろした。
ううん、きっと、本当は違うけれど。
何も言わずにいてくれるのはふたりの優しさだ。
「ねえ、佳乃」
昼間から飲んですっかり酔い潰れた父をリビングに残して、日が暮れる前に家を出ようとした私を後ろから母が呼び止めた。
「あんまり思い詰めないでね?」
「…うん、お母さんにもまた苦労かけるけど」
「そんなの佳乃が気にすることじゃないわよ」
まるで小さな子供にでもするような仕種で私の頭を撫でる母の細い手首が酷く頼りなくて、とても逞しく見えた。優しげなその目尻には、柔らかな皺が刻まれている。
「あなたがまた心から好きだと思える相手と恋をしてくれて、本当によかった」
目頭が熱くなって、視界が涙で滲む。
今までどれだけの心配を掛けてきたんだろう?
ごめんね、不出来な娘で。意固地に立ち止まったままの私をもどかしく思うことだってあったはずなのに、今までなにも言わずに見守ってくれて本当にありがとう。
「楽しみにしてるね、佳乃の好きな人に会うの」
「…う、ん、ありがと、お母さん」
「気を付けて帰るのよ」
にっこりと微笑む母に頷いて家を出た。
少し西に傾きはじめた太陽の光が僅かに黄色味を帯び始めている。目の淵に溜まった涙がこぼれてしまわないよう瞬きを我慢しながら、私はゆっくりと歩き出した。
𓂃𓂃𓍯𓈒𓏸𓂂𓐍◌ 𓂅𓈒𓏸𓐍
灰色の風景には馴染みがない。
荘厳な佇まいの建物の前で私は腕時計を見た。
少しだけ仕事を抜け出してきてくれるという彼の言葉に甘えてしまったけど、さすがに忙しい平日の昼間から迷惑だっただろうかと、胸の奥で罪悪感が揺れた。
「すみません、お待たせしました」
そんなことを考えていた背後から聞き覚えのある声がして、振り返るとそこには、見慣れない背広姿の熊谷が、軽く手を振りながらこちらまで小走りに駆け寄ってくる。
「いえ、こちらこそお仕事中に押しかけて…」
「全然大丈夫なんでお気になさらず」
「あの、さっきうちの両親には今回の縁談の件を報告してきたので、多分また父から連絡がいくと思うんですが、それより先に私からも熊谷さんに謝っておかなければと」
破談の件について、どこかで時間をもらえないかと熊谷に連絡を入れたところ、『変に先伸ばしにしても落ち着かないでしょうから、もしお時間あれば俺の勤め先の近くまで来れますか?』とすぐに返信が届いた。
「あはは、そんな律儀に。ちゃんと俺のこと悪者にして言い訳しました?」
「…ただ、ありのままを伝えただけです」
「そうだろうと思ってました」
嘘つくの下手ですもんね、と笑った熊谷が近くのベンチに腰掛けるようにと言ってから、すぐ傍に停まっていたキッチンカーのサンドイッチ屋さんに売っていたコーヒーを買って手渡してくれる。
熊谷はこのあとすぐまた会議が入っているのであまり時間がないのだという。さすが、官吏の方はお忙しい。そう暢気に感心しながら受け取った紙コップに口を付けると、香ばしいコーヒーの香りが鼻に抜けた。
「あ、そうだ、直樹く──じゃなくて、滝沢さんとお会いになりました?」
「佳乃さんを送り届けたあと偶然コンビニでね」
「あの、なにか誤解があったのか──」
「彼はちゃんと貴方の元に行ったみたいですね」
口元に湛えた笑みをにっこりと深めた熊谷が私を見つめてそう呟くのを、きょとんと見つめた。滝沢は結局あまり詳しいことを教えてくれなかったから、私はふたりの間で交わされた会話の詳細を知らないままだ。
ふたりでどんな話をしたんだろう?
直樹くんは何を聞いても知らなくていいという。
「俺、佳乃さんに謝らないとなんですよ」
「え?どういうことですか?」
「あの時、俺、彼に佳乃さんの悪口言っちゃったので。悪い男の引き出しなんか全然ないくせに格好付けちゃって、あとから死ぬほど後悔したんですけど、ふたりのこと傍から見てると、どうにももどかしくて咄嗟に…」
今思い出しても最悪です、と苦笑する。
初夏の凛とした風が熊谷の薄い頬を掠め過ぎた。
優しい人は、どんな時でも優しい。申し訳ないと小さく頭を下げる熊谷に謝ってもらわなければならないことなんて、どの場面を切り取ったって存在しようもないのに。
「…熊谷さん、優しすぎると損しちゃいますよ」
「別に優しさの裏には打算もありますよ」
「そんなの誰だってそうです」
「まあ、でも、あの瞬間だけでも彼が騙されてくれたなら下手な芝居を打った甲斐もあったですかね?煙草なんか学生以来ぶりに吸ったんで咽るかと思いましたもん」
多分あれめちゃくちゃ重いの吸ってるので今後の健康被害に気を付けてくださいね、なんて言って熊谷が楽しげに笑う。それに釣られて、私もつい身に纏ってきたはずの緊張がほどけてしまうからどうにも締まらない。
「あと、あの滝沢さんはちょっと顔とか色々格好良すぎますよね、狡いですよ。お互いの親からのお墨付きってカードしか持たずに競わされる俺の身にもなって欲しい」
「え、そんな、熊谷さんだって格好良いのに…」
「なら今から俺に乗りまえます?」
「そっ、れは、えっと……」
「はは、冗談ですよ」
今さらふたりの恋路の邪魔して余計な傷を負うのは俺も勘弁なので、とおどけながら、ふと左手首に巻かれた腕時計に視線を落とした熊谷が気だるげに立ち上がった。
「すみません、そろそろ会議の時間で」
「こちらこそお忙しい時に押しかけてしまって」
「多分今度こそ最後になると思いますけど、でも会えてよかったです。泣き顔も可愛かったですけど、やっぱり笑顔のほうが数倍素敵なので、俺の失恋の餞になりました」
屈託なく笑う彼には、夏のはじまりが似合う。
どうかお元気でと差し出された熊谷の大きな手に応えて握手をすると、ひとつの季節がゆるやかに終わりを告げた。それはとても穏やかで、ほんのりと切ない終幕だった。
𓂃𓂃𓍯𓈒𓏸𓂂𓐍◌ 𓂅𓈒𓏸𓐍
公園のベンチで少しそわそわしてしまう。
今さらながら、ここできちんと約束を取り付けて滝沢と待ち合わせをするのは初めてだ。週末には大体顔を合わせるルーティンだったけど、それはあくまで偶発的に発生するご近所さんとの遭遇に過ぎなかったので。
「別に今さら緊張する必要ある?」
「だって、付き合ってから会うの初めてだし…」
「仕事立て込んでて会えなかったの怒ってる?」
「え!そんな、怒ってないよ!」
勇み足なアルに引っ張られながら公園に現れた滝沢と落ち合って、散歩コースを一緒に巡る。朝の爽やかな風が気持ちいいのか、アルはふさふさの尻尾を揺らして機嫌が良さそうだ。
先週の滝沢は仕事が立て込んで毎日のように帰りが遅かったので、結局会えずじまいだった。すぐ近所に住んでいるんだから会おうと思えばいくらでも会えただろうけど、疲れている滝沢の負担になるのも嫌で。
「ほんとなあ、この春から部署異動してさすがに残業増えすぎてんだよな」
「…それは、アルも寂しいよね」
「まじで最近それが一番の悩みかもしんない」
この春に社内の部署異動で夕鷹と同じ部門に配属された滝沢は、それ自体は昇進なのでめでたいことだが、おかげで残業が増えたと不満げだ。今は一日の大半をアルにひとりで留守番させなければならない状況になっているらしく、確かにそれは心配だろう。
「ペットシッターとかも考えたけど今さらそんなの逆にストレスかなあとか」
「見知らぬ人と急にっていうのもね…」
「だからって今のタイミングで転職もだしな…」
小難しそうに眉根を顰める滝沢を横目でちらりと伺いながら、舌の上に転がっている提案を口に出すか迷って二の足を踏む。付き合っているからと踏み込むことを許されるラインがどこまでか、判断が難しくて。
「…あ、あの、えっと」
図々しいと思われたらどうしよう。
立ち止まった私を滝沢が不思議そうに振り返る。
「ん?どうかした?」
「も、もし、迷惑じゃなければ、だけど……」
パタパタと私の足元に駆け寄ってきたアルが手の甲を無邪気に舐めた。まだ人の気配の少ない公園は静かで、緑を濃くした木々の葉の隙間から差し込む日差しは柔らかい。
「わ、たしの家で、アルのこと預かっておくのはどうかなと思って……」
私は大した仕事もしていないから基本的には毎日家にいるし、多少はアルも気を許してくれていると思うから適任じゃないかって。しどろもどろに言い募りながら、でも、滝沢の顔を怖くてちゃんと見られない。
密かに抱いた下心を見破られそうで。
なんだかアルをダシに使ってるみたいかなって。
「そ、それと、あと、そしたら毎日直樹くんにも会えるなって、邪なことも、ほんのちょっとだけ考えてます……」
結局隠しておけずに白状するのだから、最初から正直に伝えればいいものを。無意味な回り道のあとで滑稽に着地した私のひとり相撲は、滝沢には鬱陶しいだけだろう。
「…ほんと勘弁して」
「ご、ごめん、なさい、わたし」
「そうじゃなくて俺の心臓が持たないから」
はぁー…と大袈裟なくらい大きなため息をついた滝沢の顔を咄嗟に見上げると、その頬がほのかに赤く染まっていて、それを隠すみたいに右腕で口元を覆っている。
「俺がそっちの家に入り浸ってもいいわけ」
「えっ、あの、それって」
「てか佳乃ばっかり会いたいと思ってるみたいな勘違いもやめてくれる?」
唐突に私の手を握ってズンズンと歩きはじめた滝沢の足元で、アルが飼い主を揶揄うみたいに跳ね回る。耳まで真っ赤にした滝沢の手が珍しく熱を帯びているから、つい自惚れそうになって、私の顔まで熱い。
どうしよう、調子に乗ってしまう。
直樹くんも私と同じ気持ちのかもしれないって。
「アルの面倒見てくれるのは正直すげえ有難いけどさ、やっぱ負担じゃない?」
「……それは、どういう意味でしょうか?」
「正直俺が入り浸る自信しかない」
顔を真っ赤にした犬連れの男女がふたりして池の周りを周遊するという世にもシュールなお散歩を乗り越え、帰宅してひと息ついたところで滝沢がさっきの話を掘り返す。
「だって、佳乃のことだから、どうせ俺の帰りが遅かったら心配して飯とか準備するだろ?そんで飯食ったら帰るのもだるくなって、まあ今日は泊まるかとか言うのが立て続くうちにずるずるここに入り浸る自分の未来が鮮明に想像できて今から普通に申し訳ない」
「む、むしろ、それは大歓迎で……」
「まじで何食ったらこんな素直な子に育つの?」
最早呆れを通り越して感心したような顔をする滝沢に見下ろされると、ちょっと居た堪れない。朝食の準備をはじめようとして取り出したトマトを輪切りにしようとした私の背中から、滝沢がお腹のあたりに腕を回した。
きゅ、と抱き締められるだけで体温が上昇する。
恋人同士の距離にまだ慣れなくて。
胸が詰まって苦しい。
「あとから後悔しても知らねえからな」
窘めるようにそう囁いた滝沢の唇がそっと私のそれを塞ぐと、くらくらと眩暈がした。甘い接触に溺れてしまいそうな朝は――無機質なチャイムの音に遮られた。
こんな朝から、誰だろう?
顔を見合わせながらふたりして首をかしげる。
「え、夕鷹と万緒ちゃん?」
インターホンのカメラ越しに映る夕鷹と万緒がなにやら大騒ぎしているけど、いまいちよく聞き取れなかったので、とりあえずオートロックを解除することにした。
「どうしたんだろ、こんな朝から」
「佳乃、豊川くんに俺らのことなんか言った?」
「昨日お父さんたちに報告してきたから、それを夕鷹にもさっきラインして」
「もう確実にそれだろ、絶対面倒臭い」
露骨にげんなりした顔をする滝沢の心情とは裏腹に、再び鳴らされたインターホン。勢いよく玄関先に駆けていくアルのあとを私たちも追って、鍵を開錠すると――、
「おい!滝沢さんと付き合ったってまじかよ!」
こちらからドアを開ける間もなくバン!と夕鷹が部屋に飛び込んできて、びっくり仰天する。するとその後ろから万緒も、「佳乃さんと滝沢さんが付き合い出したって、この馬鹿が!」と興奮したように顔を出した。
「相変わらず賑やかだねえ、君ら」
「なんっで滝沢さんが佳乃の部屋にいんだよ!」
「お前が今言ったんだろ、付き合い出したって」
「俺そんなん聞いてないんだけど?!」
職場ではそんなことひと言も言ってなかったじゃねえか!と無遠慮にドスドスと上がり込んできた夕鷹が滝沢に詰め寄る。
「俺、君と違って公私混同はしない主義だから」
「報連相がこの世で一番大事だろうが!」
「だから俺、一応お前の上司な」
最早、夕鷹にシャツの襟元を掴み上げられている滝沢は明後日の方向に顔を背け、あからさまに鬱陶しそうだ。しかし夕鷹はそれにめげることなくガミガミと罵声を飛ばしている。
完全に呆気に取られていた私が玄関先で立ち尽くしていると、ふと服の袖口を引っ張られた。それに顔を上げれば、私のほうを見つめる万緒の大きな瞳の中に、うるうると涙の膜が張っていたからぎょっとする。
「え、万緒ちゃんどうしたの!?」
「よ、よしのさん、ほんとにたきざわさんと付き合ったんですか……?」
ボロボロと目の淵からこぼれ出した万緒の涙にひとりで動転していると、さすがに夕鷹と滝沢も何事かとこちらに駆け寄ってきて、大のオトナが密集してオドオドする。
「ううぅ~~~…ほんとよかった、よしのさんが幸せになって、わたし、ゆたかのこと横取りしてすごい迷惑かけたのによしのさん恨み言のひとつも言わないんだもん~~~~」
小さな子供みたいにうわぁんと大泣きする万緒に思い切り抱き着かれて、茫然としたあと、思わず大きな声で笑ってしまう。ごめんね、そんな風に万緒ちゃんが気に病まなきゃいけないことなんて何もなかったのに。
「そんな泣かないでよぉ、万緒ちゃん」
「よじのさんだいずぎでずぅ、おめでどぉぉぉ」
「…お前、まじで鼻水きったねえぞ」
「ほんと豊川くんってデリカシーとかないよね」
綺麗な顔をぐしゃぐしゃにして泣いている万緒を抱き締める肩越しに、げんなりしたような顔の夕鷹と、それに呆れたような視線を向ける滝沢。可笑しな朝の一コマは、それでもなごやかな幸福に満ちている。
ひとまず万緒が落ち着くのを待ってからふたりを部屋に招くことにして、朝食を準備した。それを滝沢が手伝ってくれている横から、「優しい彼氏の振りしやがってクソがッ!」と夕鷹が理不尽に非難していて本当に子供みたいだ。
サンドイッチとサラダの横にコーヒーを添えた簡素な朝食を食卓に並べ、それぞれ席に着いた。しかし私が滝沢の隣に座ろうとしたら、「佳乃は俺の横!」と何故か夕鷹に腕を引っ張られ、何故か私と夕鷹、万緒と滝沢が横並びになる妙な配置となってしまった。
「ほんとあんたいい加減きもいわよ」
「先に言っとくけど俺はまだ全ッ然ふたりのこと認めてねえからな!」
「だからどの立場から物言ってんの?」
「うるっせえ!幼馴染みは親より偉いんだよ!」
「んなわけあるか」
万緒が軽蔑の視線を夕鷹に送っている。
その両横で私と滝沢は、もう諦めムード全開だ。
朝食を食べながら夕鷹と万緒の賑やかな喧嘩を諦観しつつ、足元でサンドイッチを狙うアルにも警戒する。滝沢の膝の上には、ちょこんとハナが鎮座していて可愛い。
「そんで何勝手に付き合ってんだよ」
「佳乃と付き合うのに君の許可がいるの?」
「当たり前だろ!てかなに佳乃とか呼んでんだよ馴れ馴れしいな控えろ!」
「お前、遂に敬語すら捨て始めたな」
凍りそうに冷ややかな声音で応戦する滝沢に私のほうがハラハラしてしまうからやめて欲しい。右隣の夕鷹の背中を軽く叩けば、痛ぇな!と大きな声を出されたけど、痛みを感じるような強さでは絶対叩いてない。
「もう、ほんとやめてよ夕鷹」
「大体佳乃のこと一度は振った男だぞ!」
「振ったら振ったで散々文句つけに来たくせして付き合ったら付き合ったで納得しないの、ほんと死ぬほど面倒臭いよな」
心の底から億劫がっているのが目に見えてわかる滝沢なんて、ものすごく稀有だ。その横では万緒も完全に『なんだコイツ』みたいな顔をしていて私まで居た堪れない。
「で、なら君はどうしたら認めてくれるわけ?」
「…ちゃんと佳乃のこと好きですか?」
「馬鹿だねえ、君も」
優美な所作で頬杖を突いた滝沢の瞳がどこか挑発的に細められる。ゆるり、と弧を描いた口元から紡がれる声はどこか愉しげなのに、硬質な意志を帯びているようで。
何故だろう、胸が鳴ってしまう。
その透き通った琥珀の瞳に何度だって焦がれて。
「――君のお兄さんにだって負ける気はないよ」
𓂃𓂃𓍯𓈒𓏸𓂂𓐍◌ 𓂅𓈒𓏸𓐍
「ほんと昨日は災難だったな」
さすがに飲みすぎて体が怠いと大儀そうに呟いた滝沢がソファーに沈む。私はキッチンでふたり分のコーヒーを淹れてから滝沢の横に行き、片方のマグを手渡した。
「大丈夫?二日酔いじゃない?」
「翌日には残んないほうだから平気、佳乃は?」
「私は元々酔わない体質だから全然大丈夫」
「昨日もケロッとしてたもんな」
結局昨日はあれから夕鷹と万緒が我が家でやけ酒と祝杯を始め、それに私たち付き合わされる形でお昼間から夜遅くまで延々とお酒を飲んでいた。
珍しく夕鷹のほうまでしたたかに酔っ払っていたので滝沢は散々絡まれてはお酒を注がれ、かなりの量を飲んでいた。滝沢もアルコールにはかなり免疫があるほうみたいだけど、だからと言って限度があるので。
「ごめんね、夕鷹が迷惑掛けちゃって」
「今までどんな教育してたわけ、お宅の弟さん」
「子供の頃からやんちゃ坊主すぎてちょっと私の手には負えなかったの」
ありがとうとお礼を言ってマグを受け取った滝沢が、背凭れに預けていた背中を気怠げに起こしてコーヒーを口に含む。
「目に浮かぶよ、豊川くんの幼少期」
「まあ、今とそんなに変わってないからね…」
「カブトムシとか取るの上手そう」
「川で取ってきたザリガニおばさんの鞄に入れて追いかけ回されてた」
「絵に描いたようなクソガキだな…」
あれで野木の跡取りが務まるの?と呆れたように笑った滝沢の腕が伸びてきて、ことりと私の肩に額が落ちてくる。窓辺ではすっかりこの部屋にも慣れた様子のアルがお腹を見せながら日向ぼっこをしていて、途方もなく可愛い。
繊細に揺れるレースカーテン越しに広がる空は群青で、夏の色だ。窓の向こうには彼と出会った公園の風景が佇んでおり、朝の爽やかな風がその気配をここまで運んで来てくれる。この部屋の朝が私はとても好きだ。
「今度ね、お父さんが直樹くんのこと家に連れて来なさいって言ってて…」
「もちろん、いつでも伺うよ」
「…こんな付き合いはじめなのに嫌じゃない?」
「元々覚悟の上に決まってるでしょ」
甘やかすように私の髪をくしゃりと撫でた滝沢が眦にキスをくれる。その些末な仕草だけで、胸の奥が締め付けられるから。
「佳乃の縁談ぶち壊しちゃったしね」
「そんな、あれは別に直樹くんのせいじゃ…」
「俺のせいじゃないの?佳乃が俺のこと大好きな証明かと思ってたのに」
くすりと愉快気に笑みをこぼす。
本当に、直樹くんばっかり余裕綽々でずるい。
ただ意味もなく重いだけの荷物を、優しい彼に背負わせたくなんかないのに。でも私は強欲で身勝手だから、あれもこれもと握り締めたまま、何も手放せなくて。
「手放さなくていいよ、佳乃の大事な荷物だろ」
「でも、負担ばっかり掛けちゃって…」
「またすぐ泣くんだから」
目尻に滲んだ涙を拭ってくれる指先が穏やかで。
私は彼の前でいつも泣いてばかりだ。
繋がれた滝沢の手から伝わるひんやりとした体温を、綺麗な朝のひかりが照らす。そのまばゆさが途方もなく愛しくて。
「一緒に持つよ、最後まで」
移りゆく季節の中で、その瞳に映した春だけがなにひとつ変わることがないまま。それを永遠の中に閉じ込めて、いつまでだって抱き締めていても許されるだろうか?
あなたを巻き込んでごめんなさい。
でも、それでもその言葉に――どうか縋らせて。
「代わりに俺の人生の後始末は佳乃に責任取ってもらわなきゃなんねえけど」
「…ふふ、うん、なんでもするよ」
「じゃあとりあえず疲れたから充電させて」
君の厄介な幼馴染みのおかげで俺の貴重な休日が潰されたからな、と嘯いて、滝沢が私を腕の中に閉じ込める。まだ今は不慣れで少しどぎまぎするけど、早くこんな風に過ごす時間がありふれた風景になるといい。
臆病に立ち止まったままの心をほどいてあなたが抱き締めてくれたこと、本当にね、奇跡のように思っているの。閉ざされた私の庭が柔らかな光に照らされて、ああ、こんなに綺麗だったんだって今さらになって気付けたから。
これからはあなたと一緒にその美しい庭を手入れして、守っていきたい。疲れて帰ってくるだろうあなたの心の拠り所になれるような、季節の花々が色鮮やかに咲き誇る、そんな素敵な庭を造って待っているから。
「そういえばアルの世話の件だけど」
「あ、うん、とりあえず明日から預かろっか?」
「ついでに俺の面倒も見てくれない?佳乃は俺の責任も取らないとだし」
明日も、またここに帰ってきていい?
そう甘えるみたいな声音で囁いて無邪気に笑う。
明日も、明後日も、その次の日も。新しい永遠を貴方の傍で過ごしてもいいかな?あなたが連れ出してくれた若葉色の季節に、私はいつまでだって恋をしていたい。
「美味しいもの作ってアルとハナと待ってるね」
「…最早仕事行きたくねえな、それ」
「お仕事頑張って、課長さん」
「もう降格していいからサボりてえわ…」
項垂れるように私の首筋に顔を埋める滝沢の背中に腕を回した。窓から吹き込む甘い風に揺られる柔らかな髪がほほをくすぐる。どこからともなく窓辺に現れたハナが、ぐっすりと眠るアルの傍に身を寄せて目を閉じた。
いつかの春に、また帰ってこよう。
永遠のはじまりに飾った、この朝のひかりまで。