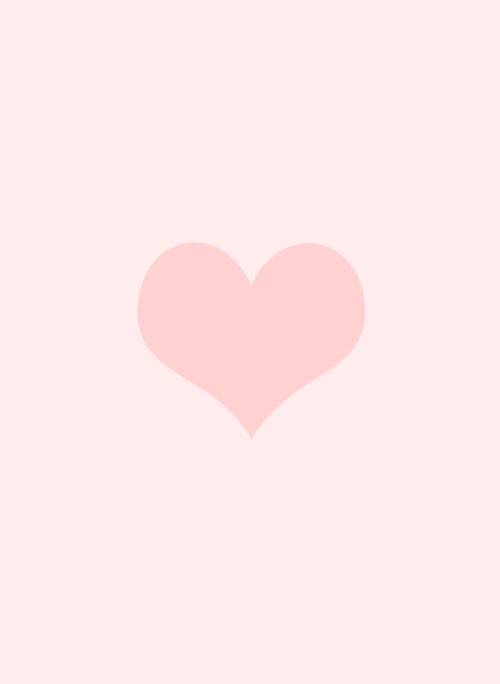三年目の別離、そして――
エピローグ
春の風は、冬の名残をそっと溶かすように柔らかかった。
バルコニーから見える街路樹の新芽は、淡い緑色をまとい始めている。
湯気の立つマグカップを手に、私はその景色を眺めていた。
背後から、温かな気配が近づく。
腕がそっと肩を包み、低い声が耳に届いた。
「外はまだ少し冷える。風邪をひくな」
「大丈夫。……あなたこそ、もうすぐ出張でしょう?」
「ああ。でも、今日は一日、君といる」
振り返ると、司がわずかに目を細めて笑っていた。
数か月前まで、こんな表情を自分に向けられる日が来るなんて思いもしなかった。
何度も諦めそうになり、何度も距離を取った。
それでも――今、彼はここにいる。
「……あの頃、あなたが何を考えていたのか、全部は分からない」
「全部を言葉にできる自信もない」
「でも、少しずつでいい」
「少しずつ、俺を知ってくれ」
差し出された手を握り返す。
その温もりは確かで、鼓動は静かに寄り添っていた。
風に乗って、街の喧騒が遠くから届く。
まるで過去のざわめきが、少しずつ遠ざかっていくようだった。
私はマグカップをテーブルに置き、彼の胸に身を預ける。
司の腕がさらに強く私を抱きしめ、頬に落ちた唇の感触が、胸の奥まで温かさを運んできた。
「これからは、もっとちゃんと見ていて」
「ずっと、見ている」
約束のように交わされたその言葉が、私の中の長い冬を終わらせた。
空は、春の青をたたえて広がっていた。
―― 終 ――