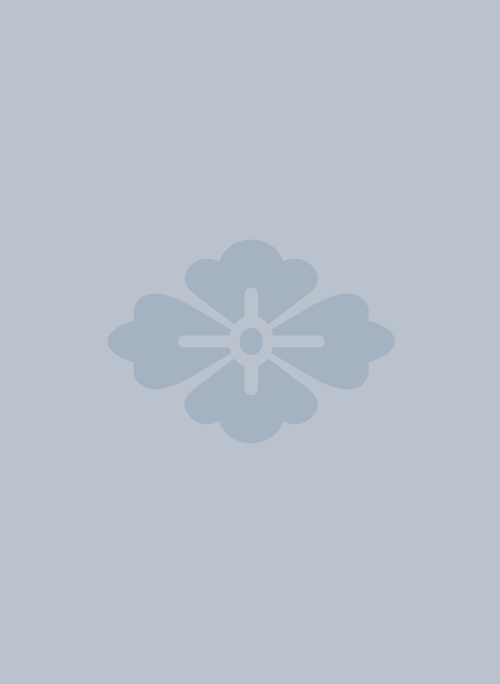国民的アイドルが現実世界も異世界でもILoveYou!
ラブ×6~花柄の便箋が運んだ赤いリボン~
僕は小鳥遊さんが撮影の仕事をしている間に車を走らせている、実家に預けている犬を受け取りに来たのだ。両親が明日から旅行に行くとの事で、それに小鳥遊さんに犬の散歩を誘ったけど。
「よく考えたら、小鳥遊さんを外で会ったりしたらやばいよな」と気付き、ちょうどいいから小鳥遊さんに見せようと思った。僕は実家の玄関を開けると「わん!」と嬉しそうにしっぽ振るクランがお出迎えしてくれた。
「よしよし!クランいい子にしてたか?」
「くーん!」
相変わらず毛がもふもふだ。
「あら、おかえり!咲夜来てたのね!」
母さんが声かけるまで、つい夢中でクランを撫でてしまった。
「あ、うん、ただいま。仕事合間ぬって。クラン引き取りに来た」
「そうなの、せっかくお夕飯作ったのに。あ!お弁当にしちゃおうか!そうしましょう!」
母さんはパタパタとキッチンへ行ってしまった。
「咲夜、帰ってたのか」
母さんの入れ替わりで、父さんが来た。
「父さん、うん。仕事抜けてきたからすぐ出ちゃうけど。」
「そうか。その…大丈夫か。」
「え?」
「仕事順調か?なにか困っていたりとかしていないか?」
父さんにも随分心配かけてしまったんだよな。こっそり帰ろうとしているところに、天気が晴れているのにもトイレでバケツに水を浴びてしまった僕は、ずぶ濡れで帰って来たのを父さんと母さんに見付かって。
「どうしたの!?咲夜。」といつも朗らかな母さんの大きい声を初めて聞いた瞬間は忘れられない。
濡れたせいで毎日殴られ蹴られているからワイシャツの下は傷だらけ部分が見えたりとかて、「正直に言え。」と父さんの言葉と目に逃げられなくて、話したら虐めた相手に対して僕より父さんの方が怒っていた気がするし、母さんは悲しんでくれた。
「大丈夫だよ!」
でも今はハレン社長や先輩たちも優しくて、前マネージャーの引き継ぎした時の小鳥遊さんのスケジュール調整の時も僕を指導してくれた先輩と同期が手伝ってくれたんだ。
「そうか。」
ーーーピロリンとスマホが鳴り、ズボンのポケットからスマホ画面をタップすると小鳥遊さんからのメッセージだった。
『もうすぐ撮影終わります。』
『了解です!』
小鳥遊さんにそう返事を返す。
「咲夜、これお弁当!」
「ありがとう、母さん。」
母さんから紙袋を受け取るとずっしり。これは弁当以外にも入ってるな、と思いながら黙って受け取った。
「あら、その子が今咲夜がマネージャーしてる子?」
たまたまスマホの画面がついていたから見えたのだろう。小鳥遊さんのメッセージを開いたままにしていたから。
「あ、うん。そうだよ!」
「今人気の小鳥遊 夢唯ちゃんじゃないの!」
リビングでたまたま付いてたテレビがColoRuNeAのCD宣伝のCMが流れた。
「え、咲夜。お前その子のマネージャーやっているのか?!今CMのColoRuNeAのか?」
母さんと父さん世代でも小鳥遊さんを知っているなんて、小鳥遊さんが恐ろしいな。
「まあね!」
「私も朝ドラに一時期ハマってて、妖怪のドラマとかにもよく出てたわね!」
「今でもよくバラエティとかテレビ番組でもよく見るよな、母さん!」
確かに俺が改善する前のスケジュールはそんなスケジュールだったかもしれないなと少し苦笑する。
「えぇ!そうね!それに咲夜あんたが落ち込んでいた時、手紙を送った子じゃない!」
母さんに便箋と紙をもらったときに「誰かに渡すの?」と言ったから。母さんにだけ「夢ちゃんって子に!」と話したことある。
「え?」
「その子昔は子役朝ドラに出てると番宣で番組とかで出るとよく周りの大人から"夢ちゃん"と呼ばれていたのよ!今は大きくなって夢唯ちゃんと呼ばれているけど、咲夜知らない?」
…………は?
「なんで母さんがそんなこと、知ってんだよ。」
僕全然気づかなかったのに。確かに小鳥遊さんの名前は夢唯だけど!
「だって、私とお父さん夢唯ちゃんファンなのよ!ほら!ColoRuNeAのCDも買っているのよ!!」
母さんが棚から出したのは、ColoRuNeAの最近発売された甘いイタズラのシングルCDだった。
「は!?」
僕こんな声張ったの初めてかも。しかも母さんが開けたままにしている棚が薄紫に染まっている…まさに夢唯色に染まっていると過言ではない。
「最初はお父さんが好きだったんだけどね!お父さんが持っているColoRuNeAの武道館ライブDVDを見たらね!アイドルはあまり興味なかったんだけどね、もう別格に可愛くてね!」
「それに息子の背中を押してくれた、俺は夢ちゃんに感謝している。歌とダンスも上手だ、この前の月曜日のドラマも素晴らしい演技だった。」
じわっと浮かび上がる昔布団に籠ってぼんやり見ていたテレビでは確か歌ってて。
「なんだよ…それ。」
あまりにも衝撃過ぎて頭が思いつかない。
「咲夜が見たの歌番組って言ってたわよね!これよ、ゆらゆらカーテンお化けを歌ってた時のなのよ!」
母さんがCDを入れて流し始めた曲は確かにあの時聴いた夢ちゃんの歌だった。
「確かに…僕が聴いた曲だ。」
「ふふ、この頃から上手だったわよね〜!お父さん!」
「ああ。何と言うか楽しそうに歌うんだよな。あの笑顔を見て俺は夢ちゃんの白いハネに夢が届いて俺はファンになったんだ。」
父さんが幸せそうなのはいいが…またCMでながれた小鳥遊さんのCMどんだけ出るんだよ。
「楽しそうに歌っているか…」
僕の記憶が頭に浮かんだ。それは確かに楽しそうに笑って歌っている夢ちゃんで。それを見て本当にきらきら輝いていて…それをホルメンで助けた時に笑ってくれた子供を思い出して。僕はマネージャーになりたいと思ったんだ。
「…小鳥遊さん。」
凄あのテレビで流れているドラマのDVD宣伝では笑っているけど本当は小鳥遊さん。
「本当に凄いや。」
小鳥遊さんだって大変だったはずなのに、辛そうだとかの素振りは全然見えなくて…あの時楽屋の前で小鳥遊さんとシライアさんが話している遭遇しなかったら僕が聞かなかったら知らないままだったと思うと恐怖で体が震えそうだ。
「わんわん!!」
クランの鳴き声ではっとして、スマホの時計を見ると。
「ああ!やっば!僕もう行かないと!」
もうここを出なくては行けない時間だった、間に合うけど。小鳥遊さんの迎えに遅刻はまずい。
「あらあらごめんなさいね、引き止めちゃって」
クランをケースに入れて、僕はケースと荷物を持って車に乗り込む。
「ううん、まだ間に合うから大丈夫!じゃ、お弁当ありがとう!」
僕は車を走らせようと思ったんだけど。
「くーん?」
「なんだよ…ずるいよ。クランも小鳥遊さんも。」
ケースから首を傾げるクランが可愛すぎるからなのか、目頭が熱くなりそうだ。
「こんなことで僕は泣いてちゃダメなんだ。」
僕も頑張らなきゃいけないな、ソロアイドルへと高く飛び立とうとしている小鳥遊 夢唯に精一杯応えなくては!!
「よし!行くよ、クラン!」
「わんわん!!」
元気よくしっぽを振るクランを見て、僕は車のアクセルをゆっくりと踏んだ。
「いた。」
今は撮影中の休憩中でカバンから化粧ポーチを出そうと思ったら証拠を警察に突き出そうと思っていた学校の下駄箱に入っていた物騒な物が入っているカッターの刃が光る白い便箋で指を切ってしまった。
「最悪。絶対警察に突き出す。」
嫉妬ってなんでこうも醜いのかしらね。昔は嫌だったけどもう諦めた、私が出続ける限り終わらないことだと。
「でもね、あんたたちの為に辞めてやらないわ。私はあんたたちよりも世界に飛び立つんだから。」
またカバンを漁ると奥にちらっと見えた、おばあちゃんと行った神社の赤いお守りがあった。
「懐かしいわね。見つからないと思ってたらずっと奥にあったんだ。」
確かこの中に。
「あったあった。昔のファンレター…あれ。」
折りたたんだ便箋の中身を開くと下の方に来栖と書かれていた。このカバンおばあちゃんに買って貰ってずっと使っているんだけど、子供の時は読めなかったけど。
「そっか、このファンレター来栖さんのだったんだ。」
私は来栖さんの優しさがここにもあったなんて。でも不思議と納得してしまう…彼の誠意は見させてもらっているし。
「来栖さん見てるとクルリ思い出すのよね」
クルリが私のためにジャスミンティーを入れてくれたり、お香を持ってくるあの気遣いとか。来栖さんのせいじゃないのに私を想っての土下座してくれた勇ましさと優しさとか。
『ドレイン!』「小鳥遊さん!」
無垢に笑う感じというか素直な感じが似てる。
ーーーコンコンとノックされた。
「はい!」
開けてきたのはスタッフだ。休憩終わりかな、丁度メイク治し終わったところなのよ。ナイスタイミング。
「小鳥遊さーん!そろそろ!」
「わかりました!今行きます!」
お守りをカバンに閉まって。ロッカーの鍵を閉めた。
「もしかして、来栖さんがクルリだったりして。」
もしそうだとしたら、少し嬉しい。私は仕事へ足を運んだ。
「本日の撮影は終了でーす!」
「ありがとうございましたー!お疲れ様です!」
私は小鳥遊と書かれた楽屋に戻ってドアを開けると来栖さんがいたのと。
「…小鳥遊さん。これ。」
楽屋部屋がとっちらかっている惨状だった。
「あー…見られちゃいましたか。」
私は散らかった物を拾って行きながら、部屋の中に進む。これやられると足の踏み場に困るのよね。
「どういうこと!?まさか小鳥遊さん!」
私より慌てるなんてますますクルリみたい。クルリもこれ見たら来栖さんと同じ反応しそうね。
「落ち着いたください!荷物や私服とかはロッカーに鍵かけてるから無事ですよ!ほら!」
けど…ロッカーの鍵もいよいよ信用したらダメかもしれないな。
「なんで…そんな笑ってる場合じゃないよ!」
「気にするだけ無駄ですからね。もういいかなって、まぁ警察には通報しますけどね。立派な犯罪ですしー?」
「僕が今すぐ連絡する!!」
来栖さんが素早く警察に通報してくれているみたいだ。しばらくして警察が来て取り合ってくれた。
「あ、すいません!お巡りさん♡」
警察の人に駆け寄り、思い出してカバンを漁る。
「なんでしょう?」
例の白い便箋をカバンから取り出すが、不覚にもカッターの刃にまた触ってしまったみたいで皮膚にピリッと伝わる。
「これもついでに調べてくれますか?」
「わかりました。」
便箋に無謀に触れようとする警察。
「あ、持つ時に気をつけて下さいね!カッターの刃が入っているので!」
一応警告とこれには事件性があると主張しといた。
「あとは、お願いしますね♡」
「はい。お任せ下さい!」
「行きましょう!来栖さーん!」
私はさっさとくだらない部屋を出たい。
「あ!ちょっと、小鳥遊さん!?」
傷が無い方の手で来栖さんのカバンと腕を引っ張って楽屋を出て、廊下を歩いてテレビ局を後にした。
「…小鳥遊さん。どうぞ乗って。」
「わざわざ後部座席のドア開けてくれるなんて、ありがとうございます!」
来栖さんの車に乗り込むと
「わんわん!!」
ゲージを開けろと言わんばかりに元気に鳴き声を上げるポメラニアンがいた。
「あれ、この犬もしかして来栖さんがこの前見せてくれたワンチャンですか?」
「うん。実家から引き取って来たんだ。」
「やっぱり確か、クランくんだっけ?」
撫でたいけど、まだ手当していないんだよね。
「はい。ティッシュと消毒液と絆創膏。」
「ティッシュはともかく、なんで車内に救急箱があるんですか?」
普通はないよね。
「芸能人も人間だから体調崩したり、怪我したりするから一応念の為に持ってるんだ。」
私は来栖さんの好意を有難く、ティッシュと絆創膏を受け取った。傷を見るとさっきの傷はもう塞がっていた、さすがに本番で絵が繋がらなくなるから軽い手当てしかしなかったんだけど。
「ありがとうございます。なんか来栖さん怒ってます?」
「ごめん。もっと僕が早く来ていればこんなことにならなくて良かったかもしれないのに。」
そんなこと思うんだ。来栖さん責任感強すぎでしょ。
「大丈夫ですよ。来栖さんは悪くないので。」
珍しくなかなか運転しようとしないなと思いながら消毒液で湿らせたティッシュを血がついた指を拭き取って絆創膏を貼った。
「怒ってる、どうしてそんな平然としてられるの?僕の立場だったらきっと辛かった。」
よく見ると来栖さんの背中姿は震えてて、車のライトで頬が光っていた。
「なんで…来栖さんが、泣いてるんですか。仕方ないことですよ。」
まさかそんな顔してくれるなんて、泣いてくれるなんて思わなかった。
「仕方なく無いよ。僕が泣いてるなんて変だよね…ごめんね。」
なんか来栖さんが泣く姿は嫌だな。
「僕も昔虐められていたから」
「え?」
虐められた、、、来栖さんが…?
「水ぶっ掛けられたり、殴られたことあるから小鳥遊さんの傷の全てをわかることはできないけど、少しわかるんだ。これをされることがどんなに苦しいことなのか!」
私みたいな皮肉な人ならまだしも、来栖さんみたいな人を虐めるなんて、来栖さんの優しさとかわかってないんだな。
「どうなっているんでしょうね!本当に!でも、そんなことよりも仕事の方が大事ですよ。」
私はスマホの電源を入れた。おーおーSNSのメッセージが沢山なこと。
「そんなわけない。自分より仕事が大事なんてそうやって言ってると自分が壊れちゃうよ。」
「私は壊れませんよ。アイドルの頂点にすら立ててないんですから。こんなところで壊れてなんてられません!」
いきなり肩を掴まれてびっくりして、スマホから顔を上げると
「そうかもしれないけど!」
ボロボロと飴色の瞳が涙を零しながら、私を見つめる。
「せめて何も無いふりして、見ないふりをして笑うのやめなよ!まだマネージャーの僕に信用出来ないと思う。でも僕の前で偽る必要も飾る必要ないよ!」
やめてよ、そんな純粋な目で。真っ直ぐな言葉はいらない。
「君はアイドルだけど人間なんだ、どんなに平気でも痛いものは痛いし。」
私の醜い何かを溶かしてしまいそうな目で、私を見ないで。温めないでよ。
「夢ちゃん。」
「え?昔の私の呼び名をなんで来栖さんが。」
「虐められて引きこもっていた、僕を引っ張り出して、小鳥遊は外に出る勇気をくれた。そんか君に僕が今度は助けたいんだ。」
助けたい…私だって。あなたに助けられたのに…?
「これ、くれたの来栖さんでしょ?」
赤いお守りから出したのは花柄の便箋だ。
「私も折れそうだった時、あなたのこのメッセージに救われたんですよ!」
「そのファンレター…」
あなたに救われたのに?もう十分なのにこれ以上何を救われればいいの?
「私お守りとして持ってたんです…私も来栖さん。あなたに救われていたんです。十分優しくしてくれてもらいましたから、私の事で来栖さんが傷つく必要なんてないのよ。」
ミラー越しに見える来栖さんからの視線を逸らしたのに、なぜかクランからも視線を感じながら窓の景色を見ていた。
……To be continued