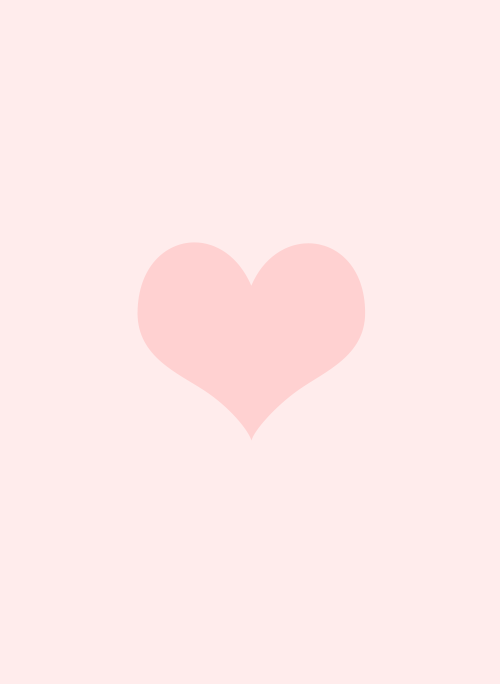明日からちゃんと嫌いになるから
六花は深刻な問題はないのだと明るく言った。
『解決だって?』
泉は、たちまち険のある声になる。怯みそうになるが、電話越しの泉の機嫌など気にしていない素振りで、六花は続ける。
「正樹さん、相手の女性と別れるって。だから、結婚は予定通り。これからはお互い、いい夫婦になれるよう努力していく。だから心配いらないの」
『そんなの信じられるわけないだろう。そのうち隠れて会うようになるのが目に見えてる』
「でも彼だけが悪いんじゃないよ。昨日、正樹さんは正樹さんの好きな人と一緒にいて、私はいっちゃんといた。……それでおあいこじゃない」
こういう言い方は卑怯だとわかっている。でも事実だ。六花の好きな人が誰なのか、泉は嫌になるほど知っているから。それぞれが好きな人と、一緒に過ごしていただけだ。
違うのは、正樹は両思いの相手で、六花は片思いの相手と一緒にいたという些細なこと。泉とクリスマスイブに二人で食事ができて、六花は心の底から喜んでいたのだから自分も正樹に対して少しも誠実ではない。
「でも怒ってくれたことは、嬉しかった。ありがとう……お兄ちゃん」
彼は兄だった者として、六花をほおっておけないのだから、あえてそう呼んだ。
泉は長い間沈黙していた。一分か、二分か……六花が根気強くまっていると、さっきまでの怒りを消した柔らかい声が聞こえてくる。
『……いつからそんなに強くなったんだ?』
「いつからだろう。わからないや……」
本当はちっとも強くなんかない。強がっているだけだ。でも、強くなったように見えているなら、少しは成長したということなのか?
泉はこれ以降、結婚を祝うような言葉をくれることはなかったが、反対を口にすることもなかった。もとから日々連絡を取り合うような関係ではなくなっていたから、顔を合わせることすらなく日々が過ぎていく。
発送してあった招待状の返事が「出席」で届いたとき、なんとなく区切りがついた気がした。
§
祖母の退院に合わせて一度実家に戻った六花は、そのまま独身最後のお正月を家族で過ごした。
正樹は一度そこに挨拶に来てくれ、二人で初詣にも行った。なんだか普通の婚約者の関係らしくなってくる。ただ相変わらず人混みでも手を繋いだり、腕を組んで歩いたりすることはない。
(結婚したら、どうなるのかな……)
六花は初詣の帰り道に、ふとそんなことを考えた。
利害関係の一致での結婚では、当然子どもに関する期待がある。はたして自分たちは夫婦の営みができるのだろうか? まったく想像できなくて、一人苦笑いする。
(最悪、人工授精になるのかな……)
男女の営みを知らないまま、妊娠するのはなかなか悲惨だ。そうならないように努力しなければと思いつつ、いっそ「あり」だと思えてしまった。
お正月明けには、ドレスの小物を合わせに結婚式場に二人で足を伸ばし、帰りは正樹にマンションまで送ってもらった。
異変があったのはその翌日のことだ。
明け渡しも間近なので、六花はマンションと実家を行き来するようになっていたのだが……この日はマンションに戻っていて、昼頃買い物をしようと外に出た。
すると建物の出入り口付近に、一人の女性が立っていた。最初は具合でも悪い人なのかと思い、声をかけるべきかと六花は一歩近づく。そこではっとした。
(この人……)
相手も六花の存在に気づき、じっとこちらを見つめてくる。先に口をひらいたのは女性のほうだった。
「宮下六花さんですね?」
「…………そう、です」
『解決だって?』
泉は、たちまち険のある声になる。怯みそうになるが、電話越しの泉の機嫌など気にしていない素振りで、六花は続ける。
「正樹さん、相手の女性と別れるって。だから、結婚は予定通り。これからはお互い、いい夫婦になれるよう努力していく。だから心配いらないの」
『そんなの信じられるわけないだろう。そのうち隠れて会うようになるのが目に見えてる』
「でも彼だけが悪いんじゃないよ。昨日、正樹さんは正樹さんの好きな人と一緒にいて、私はいっちゃんといた。……それでおあいこじゃない」
こういう言い方は卑怯だとわかっている。でも事実だ。六花の好きな人が誰なのか、泉は嫌になるほど知っているから。それぞれが好きな人と、一緒に過ごしていただけだ。
違うのは、正樹は両思いの相手で、六花は片思いの相手と一緒にいたという些細なこと。泉とクリスマスイブに二人で食事ができて、六花は心の底から喜んでいたのだから自分も正樹に対して少しも誠実ではない。
「でも怒ってくれたことは、嬉しかった。ありがとう……お兄ちゃん」
彼は兄だった者として、六花をほおっておけないのだから、あえてそう呼んだ。
泉は長い間沈黙していた。一分か、二分か……六花が根気強くまっていると、さっきまでの怒りを消した柔らかい声が聞こえてくる。
『……いつからそんなに強くなったんだ?』
「いつからだろう。わからないや……」
本当はちっとも強くなんかない。強がっているだけだ。でも、強くなったように見えているなら、少しは成長したということなのか?
泉はこれ以降、結婚を祝うような言葉をくれることはなかったが、反対を口にすることもなかった。もとから日々連絡を取り合うような関係ではなくなっていたから、顔を合わせることすらなく日々が過ぎていく。
発送してあった招待状の返事が「出席」で届いたとき、なんとなく区切りがついた気がした。
§
祖母の退院に合わせて一度実家に戻った六花は、そのまま独身最後のお正月を家族で過ごした。
正樹は一度そこに挨拶に来てくれ、二人で初詣にも行った。なんだか普通の婚約者の関係らしくなってくる。ただ相変わらず人混みでも手を繋いだり、腕を組んで歩いたりすることはない。
(結婚したら、どうなるのかな……)
六花は初詣の帰り道に、ふとそんなことを考えた。
利害関係の一致での結婚では、当然子どもに関する期待がある。はたして自分たちは夫婦の営みができるのだろうか? まったく想像できなくて、一人苦笑いする。
(最悪、人工授精になるのかな……)
男女の営みを知らないまま、妊娠するのはなかなか悲惨だ。そうならないように努力しなければと思いつつ、いっそ「あり」だと思えてしまった。
お正月明けには、ドレスの小物を合わせに結婚式場に二人で足を伸ばし、帰りは正樹にマンションまで送ってもらった。
異変があったのはその翌日のことだ。
明け渡しも間近なので、六花はマンションと実家を行き来するようになっていたのだが……この日はマンションに戻っていて、昼頃買い物をしようと外に出た。
すると建物の出入り口付近に、一人の女性が立っていた。最初は具合でも悪い人なのかと思い、声をかけるべきかと六花は一歩近づく。そこではっとした。
(この人……)
相手も六花の存在に気づき、じっとこちらを見つめてくる。先に口をひらいたのは女性のほうだった。
「宮下六花さんですね?」
「…………そう、です」