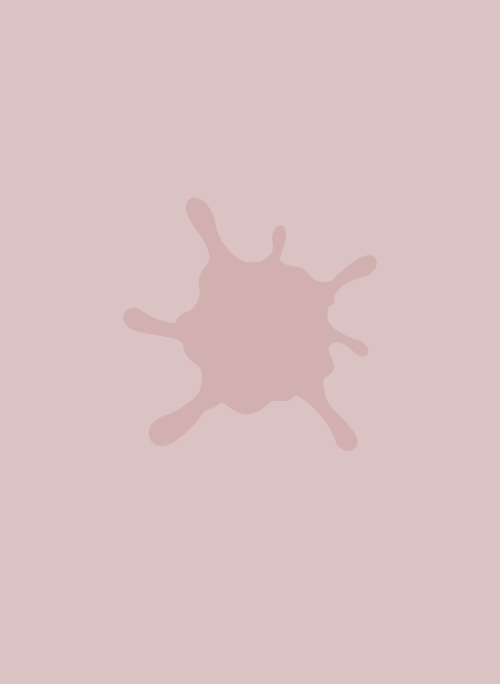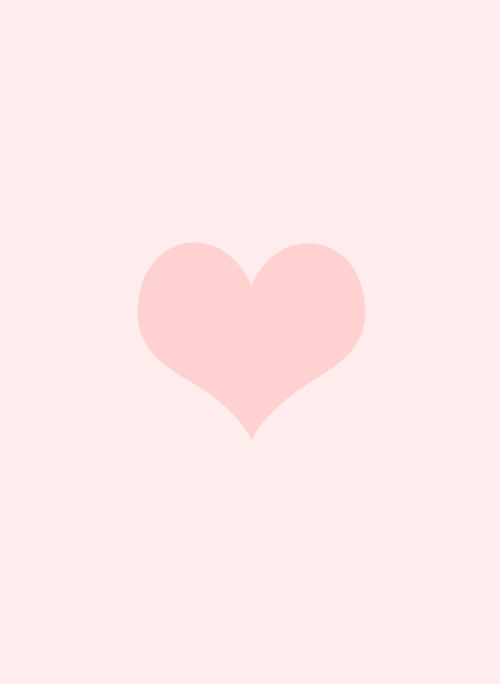キミの隣は俺の場所
。
「じゃあ、文化祭の出し物、そろそろ決めていこっかー!」
担任の宮田先生が、教卓の前で手をパンと叩いた。
教室の空気が、一気にわちゃわちゃしはじめる。
「定番だけど、やっぱりカフェ系じゃない?」
「お化け屋敷もいいよな~。手軽だし」
「劇も候補に入れてほしい!演技やってみたい!」
教室のあちこちで、意見が飛び交う。
楓は私の隣の席に座りながら、プリントにメモを取っていた。
「……なんか、久しぶりにうるさいな」
「それ、楓がずっと寝込んでたから静かだっただけだよ」
「まじで? 俺の存在ってそんなに影響力あったの?」
「うるさい意味でね」
「ひど」
そんな小声のやりとりにも、前より自然に笑い合えるようになった。
付き合ってからも、私たちは“いつも通り”を大事にしている。
でも、ちょっとした目線や距離感に、特別なものが滲むのは隠せない。
「はい、じゃあ黒板に意見まとめてくよ~。代表、書いてー」
クラスメイトの一人が前に出て、黒板にチョークを走らせる。
・喫茶店
・お化け屋敷
・劇(恋愛/ホラー)
・縁日風屋台
・迷路
・ライブパフォーマンス(バンド・ダンス)
「陽菜は何がいいと思う?」
楓が私のノートを覗き込むようにしながら聞いてきた。
「うーん……劇、ちょっと気になるかも」
「お、意外。陽菜って表に出るの苦手そうなイメージ」
「見てる方で、って意味だよ。裏方ならやってみたい」
「なるほど。じゃあ俺、主演やろうかな」
「やめて。絶対アドリブで台無しにするやつ」
「それを支えるのが陽菜の役目でしょ?」
「責任重いわ」
そんな冗談を言い合っていたら、前の席の沙耶がくるっと振り返った。
「えー、なになに、陽菜と楓ってさ、もう普通に“彼氏彼女感”出してるじゃん~」
「は?」
「え?」
二人して同時に間抜けな声を出してしまった。
沙耶はニヤニヤしながら、肘で私の机をつつく。
「隠す気あるの? 普通に目線とか、距離とか、バレバレだからね?」
「別に、隠してはないけど……」
「だって言ってないだけだしな。……なあ?」
楓があっさりと認めて、教室の数人から「えーっ!」と声が上がった。
「ほんとに付き合ってたのかよ! ずる! 美男美女かよ!」
「いつからいつから!? どこで告白したの!? 陽菜から!? 楓から!?」
「はいはい、文化祭の話に戻すよー!」
先生の声にかき消されながらも、しばらくワイワイと盛り上がる教室。
私はちょっとだけ頬が熱くなるのを感じながら、
楓と目が合った瞬間、ふっと笑った。
「……バレちゃったね」
「別にいいだろ。どうせ、そのうち言おうと思ってたし」
「いつの“そのうち”だったの?」
「文化祭終わったあとくらい?」
「おっそ……」
ふたりで小さく笑い合いながら、私はもう一度黒板を見た。
「でも、なんか……いいね。みんなでこうやって決めてくの」
「うん、わかる」
文化祭――
いつもの日常とはちょっとだけ違う、大きなイベント。
この先、どんな準備が待ってるのか、想像するとワクワクしてくる。
楓の隣で過ごす初めての文化祭。
ちょっとだけ特別な思い出になりそうな予感がした。
「じゃあ、文化祭の出し物、そろそろ決めていこっかー!」
担任の宮田先生が、教卓の前で手をパンと叩いた。
教室の空気が、一気にわちゃわちゃしはじめる。
「定番だけど、やっぱりカフェ系じゃない?」
「お化け屋敷もいいよな~。手軽だし」
「劇も候補に入れてほしい!演技やってみたい!」
教室のあちこちで、意見が飛び交う。
楓は私の隣の席に座りながら、プリントにメモを取っていた。
「……なんか、久しぶりにうるさいな」
「それ、楓がずっと寝込んでたから静かだっただけだよ」
「まじで? 俺の存在ってそんなに影響力あったの?」
「うるさい意味でね」
「ひど」
そんな小声のやりとりにも、前より自然に笑い合えるようになった。
付き合ってからも、私たちは“いつも通り”を大事にしている。
でも、ちょっとした目線や距離感に、特別なものが滲むのは隠せない。
「はい、じゃあ黒板に意見まとめてくよ~。代表、書いてー」
クラスメイトの一人が前に出て、黒板にチョークを走らせる。
・喫茶店
・お化け屋敷
・劇(恋愛/ホラー)
・縁日風屋台
・迷路
・ライブパフォーマンス(バンド・ダンス)
「陽菜は何がいいと思う?」
楓が私のノートを覗き込むようにしながら聞いてきた。
「うーん……劇、ちょっと気になるかも」
「お、意外。陽菜って表に出るの苦手そうなイメージ」
「見てる方で、って意味だよ。裏方ならやってみたい」
「なるほど。じゃあ俺、主演やろうかな」
「やめて。絶対アドリブで台無しにするやつ」
「それを支えるのが陽菜の役目でしょ?」
「責任重いわ」
そんな冗談を言い合っていたら、前の席の沙耶がくるっと振り返った。
「えー、なになに、陽菜と楓ってさ、もう普通に“彼氏彼女感”出してるじゃん~」
「は?」
「え?」
二人して同時に間抜けな声を出してしまった。
沙耶はニヤニヤしながら、肘で私の机をつつく。
「隠す気あるの? 普通に目線とか、距離とか、バレバレだからね?」
「別に、隠してはないけど……」
「だって言ってないだけだしな。……なあ?」
楓があっさりと認めて、教室の数人から「えーっ!」と声が上がった。
「ほんとに付き合ってたのかよ! ずる! 美男美女かよ!」
「いつからいつから!? どこで告白したの!? 陽菜から!? 楓から!?」
「はいはい、文化祭の話に戻すよー!」
先生の声にかき消されながらも、しばらくワイワイと盛り上がる教室。
私はちょっとだけ頬が熱くなるのを感じながら、
楓と目が合った瞬間、ふっと笑った。
「……バレちゃったね」
「別にいいだろ。どうせ、そのうち言おうと思ってたし」
「いつの“そのうち”だったの?」
「文化祭終わったあとくらい?」
「おっそ……」
ふたりで小さく笑い合いながら、私はもう一度黒板を見た。
「でも、なんか……いいね。みんなでこうやって決めてくの」
「うん、わかる」
文化祭――
いつもの日常とはちょっとだけ違う、大きなイベント。
この先、どんな準備が待ってるのか、想像するとワクワクしてくる。
楓の隣で過ごす初めての文化祭。
ちょっとだけ特別な思い出になりそうな予感がした。