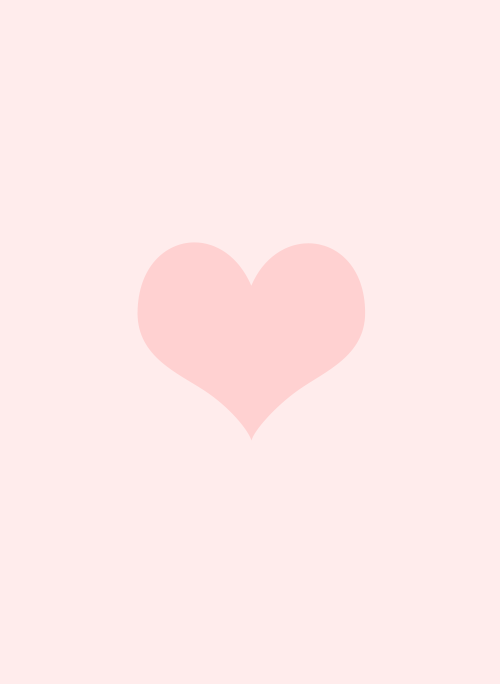0時の鐘はあなたへ――推しと先輩が重なる夜
第6話「二つの声、ひとつの家」
噂は、湯気みたいに見えないのに、肌に触れると確かに熱い。
朝いちの社内チャットに、匿名掲示板のリンクが貼られ、誰かが「見ないほうがいい」と言い、別の誰かが「事実関係の整理が先」と返す。画面の端で、未読の数が静かに増えていく。私はマグに紅茶を注ぎ、蜂蜜を一本だけ落とした。ミルクは入れない。重くならないように。
「行こう」
雨宮先輩――いや、仕事中だからやっぱり「先輩」と呼ぶべきだ――が、会議室の前で待っていた。
扉を開けば、いつもの白い長机、プロジェクターの光。違うのは、席の配置だった。コンプライアンス部、法務、広報、そして関係部署のマネージャー。空調の音まで硬い。
「はじめます」
コンプラの担当者が進行を告げ、先輩が前に出た。
いつもなら、無駄な言葉を削りきった短いフレーズで済ませる人が、その日は、言葉を尽くす側に立った。
「まず、プロジェクトの評価指標を開示します」
スクリーンに、時系列の表とログが映る。
誰が、いつ、どの版で、どの文言を決めたか。編集履歴の差分。社外・社内の承認経路。
彼の声は低く、穏やかで、しかし一点の曖昧さもなく、「事実の列」を一本の道のように並べていった。
「成果はすべてチームに帰属します。個人の功と罪は、規程に従って評価されるべきです。匿名掲示板上の推測に、私的な感情で反応しないこと。――個人への不当な中傷は、許しません」
許しません、の「り」の音が、珍しく強かった。
室内の空気が、すこしだけ音を立てずに動いた。
私は自分の手のひらに汗が滲んでいることに気づき、膝の上でそっと拭う。
この人が「許さない」と明確に言った回数を、私はたぶん、片手で数えられる。
「なお、特別回での発言に関しては、匿名領域のルールに基づき、社内の決裁とは切り離して取り扱います。副業規定・交際の申請は、事前/事後ともに適正に行っています。詳細はここに」
添付のリンクが、画面の右に並ぶ。
法務の佐伯さんが頷き、コンプラの担当者が簡潔に補足を入れる。
私は目を伏せて、一拍だけ呼吸を整えた。
四つ吸って、六つ吐く。
蜜柑の皮を指でめくるときみたいに、胸の中の固さが少しずつほどける。
「質問は?」
沈黙。
椅子が一脚、わずかに軋む。
やがて、広報の先輩が静かに手を上げた。
「言わせてください。……一花さんの五行、いつも助かってます」
唐突な方向から投げられた言葉に、頬が熱くなる。
別の席から「うちもです」と続き、会議室の空気が、予定にない箇所でふっとやわらいだ。
「以上です。個別の案件は引き続き僕が受けます。彼女への直接の連絡は、業務上必要なものに限ってください」
先輩はそう締めくくると、プロジェクターを落とした。白い光が消え、ガラス窓の向こうの朝が戻る。
席から立ち上がるとき、彼の手が私の手を――堂々と――取った。
驚くほど自然に、机の角を避けるような手の動きで。
手のひらの熱が、掌紋の細い溝を伝ってこちらへ流れてくる。
「行こう」
「……はい」
扉を出るまでの短い廊下。
いつもより多くの目がこちらを見た。
その視線の中に、好意も、嫉妬も、驚きも、噂も、全部あった。
けれどその全部の上に、彼の手の温度が毛布みたいにかかって、私は胸の奥でひとつ頷けた。
右隣は、空いている。たぶん、これからも。
*
引っ越しの日は、晴れていた。
新居のリビングには、まだ段ボールが小さな街みたいに積まれていて、カッターの銀色が太陽を細く弾いた。
床にレジャーシートを敷いて、蜜柑箱をひっくり返す。
そこに、マイク、ポップガード、オーディオインターフェース、ヘッドホン、吸音パネルをパズルみたいに並べていく。安価な吸音材は、さわるとマシュマロみたいにすこし沈む。
「スタンド、六角レンチ……」
「ここ」
彼が工具箱を開け、猫の背中を撫でるみたいな動作でパーツを組み合わせる。
私はケーブルを束ね、結束バンドの余りを爪先でぱちんと切った。
簡易のブースは、卵の殻みたいな頼りなさで立ち上がる。
でも、頼りない殻だからこそ、抱えた声を丁寧に扱える。
「テスト」
彼がマイクに向かい、私がPCのレベルを確認する。
ラ――ソ――ミ。
録音ボタンを押す直前に、胸の内側で鐘が鳴った。
今日から、家で鳴る。
「じゃあ、最初のテイク。……“0:00の鐘、妻だけに”」
“妻”。
音の粒ひとつ分、時間が静止する。
彼は微かに照れた目でこちらを見、けれど手元は仕事の速度を崩さない。
私は口角の熱を手の甲に逃がして、レベルの針がきれいに立つのを見た。
「もう一回」
「“0:00の鐘、妻だけに”」
録音を止め、二人でヘッドホンを分ける。片耳ずつ。
いつかのブースでの「音を立てない」キスが、耳の奥のどこかで笑っている。
私は彼の肩に額を寄せ、彼は目だけで「もう一回」と合図する。
「“0:00の鐘、妻だけに”」
三テイク目で、ふたりの呼吸がちょうど良く重なった。
保存。ファイル名は、迷わず「bell_wife_01」。
「ねえ、“Lin-∞”のピアノ版、今夜流す?」
「流す。……指輪も、零時に」
「うん」
テーブルの上に置かれた小さな箱。
ふたりで選んだ、細いリング。
金色の糸が輪になっただけみたいな、軽い指輪だ。
私はそれを指に当ててみて、はめる瞬間をいったんやめる。
零時まで、取っておく。
甘いものは、最後に食べる。
夕方、残りの段ボールを崩し、食器だけを最低限並べた。
シンクに茶碗とマグと、蜂蜜の小瓶。
カーテン越しの風が、部屋の埃を一度だけ持ち上げて、すぐに落とす。
彼は電源タップの配線を隅で整え、私はカレーを煮た。
具は人参と玉ねぎと鶏むね。
小川糸さんの本で読んだ「焦がさない炒め方」を思い出して、弱火でゆっくり。
手のひらで香辛料の小さな瓶を振ると、部屋の匂いが一段だけ深くなる。
「いい匂い」
「先輩が配線してるあいだに、できました」
「配線は終わらない」
「でしょうね」
笑いながら、皿を二枚並べる。
スプーンがすこしだけ音を立て、湯気がふたりの間で揺れる。
こういうとき、幸福は派手にしゃべらない。
ただ、テーブルの木目をやさしく撫で、口の中を少し熱くしていく。
「明日の朝の紅茶、蜂蜜一本?」
「半分でいい。声に膜が張りすぎないように」
「了解」
食べ終わった皿を水に浸し、時計を見る。
「23:54」。
特別回は終わった。今夜は配信はない。
けれど、家の中にあるマイクは、小さく息をしている。
零時までの六分間が、糸巻きの上の糸みたいに静かに減っていく。
「行こうか」
「うん」
蜜柑箱の上に置かれたマイクの前に、ふたり並んで座る。
ヘッドホンはひとつ。片耳ずつ。
PC画面の録音ソフトに、新しいトラックを用意する。
BGMに「Lin-∞_piano」をロード。
心拍と同じ速度でカウントが進む。
「あと一分」
「あと三十秒」
「十」
窓の外の暗さが、ほんのわずかに深くなる。
時間は目に見えないけれど、零時は、毎日ちょっとした音を立てる。
「零時」
私は指輪の箱を開けた。
彼の左手を取る。
薄い輪を、薬指に通す。
彼の喉の奥で、小さくラ――ソ――ミが鳴った気がした。
続けて、彼が私の手を取る。
指先が少し震えている。
震えたまま、でも一度も引っ込めずに、最後まで通す。
「“0:00の鐘、妻だけに”」
ピアノがそっと乗る。
∞の曲は、輪の結び目がほどけないように、やさしく何度も同じところを撫でる。
ふたりで目を閉じた。
私は小さく笑って、彼の肩に額を預ける。
「ただいま」
「おかえり」
それだけで、家になった。
簡易のブースに、ふたり分の呼吸が充満する。
窓ガラスに映る室内の暗さが、ふたりの影と重なって、やわらかくひとつに溶けた。
*
週が明けても、仕事は待ってくれない。
職場では変わらず、厳格な先輩と、五行で走る私。
会議室で彼は、必要なときだけ肯定を置き、不要な飾りを容赦なく削る。
昼の私は削る手にためらいがなくなり、夜の私は言葉を選ぶ手に余白を作れるようになった。
それは、ひとつの道を、一緒に何度も歩いたからだ。
「“子守歌 with Lin”、今週は木曜でいい?」
「いいよ。朗読は短め、トーク長め?」
「逆にしよう。風邪の人、多い」
「じゃあ読み聞かせ多めに」
家に帰ってからの打ち合わせは、鍋の湯気と同じ速度で進む。
週一のペア配信。「with Lin」のタグが定着して、チャット欄には新規さんと常連さんがうまく混じるようになった。
風邪の夜、彼の読み聞かせに私は小さな囁きで「おやすみ」を返す。
囁くために、昼の声をちゃんと使い切る。
昼と夜、二つの声の使い方は違うけれど、どちらも私たちの家事みたいに、分担が自然だった。
ときどき、夜の合間に小さな事件は起きる。
匿名で辛いことを書き込む人がいたり、社内で噂の尾がひらひらしたり。
そのたびに、彼は順序を守って対処し、私は五行で整えた。
「堂々とする」の練習は、毎日が本番で、だから毎日が練習でもあった。
*
その夜の配信は、いつもより少し長くなった。
読み聞かせのあと、トークの最後に、私は彼を見た。
彼も私を見た。
目の中の小さな合図は、同じ形だった。
『エンディングです。――言いたいことは、ひとつだけ』
私はマイクに顔を寄せ、彼はBGMをほんの少しだけ下げる。
『右隣は、いつでも安全地帯』
ふたり同時に、小声で。
合図は、もう外に漏れてもいい。
家の鍵を、少し大きめに掲げるみたいに。
チャット欄に、祝福のスタンプが降り注いだ。
ハート、拍手、花束、∞。
見知らぬ誰かの夜に、小さな安全地帯が増える音がした。
「おつかれ」
「おつかれ」
配信を切って、ヘッドホンを外す。
リビングの静けさが戻り、私たちは床に座り込んだ。
彼が私の右隣に座る。
いつもの定位置。
私は肩を寄せ、彼は肩を貸す。
「ねえ」
「うん」
「“推しと両想い”って、言葉にするとちょっと照れるね」
「言葉にするとね」
「でも、日常にすると、ちょうどいい」
「ちょうどいい」
彼の答えが、まるで自分の喉から出たみたいに自然で、笑い合う。
窓の外で、夜風がカーテンをほんの少し持ち上げた。
その風の温度がちょうどよくて、私は思う。
二つの声が、ひとつの家になった。
合図の鐘は、今夜も同じ音で鳴る。
ラ――ソ――ミ。
明日も、たぶん、同じ。
*
――完。
朝いちの社内チャットに、匿名掲示板のリンクが貼られ、誰かが「見ないほうがいい」と言い、別の誰かが「事実関係の整理が先」と返す。画面の端で、未読の数が静かに増えていく。私はマグに紅茶を注ぎ、蜂蜜を一本だけ落とした。ミルクは入れない。重くならないように。
「行こう」
雨宮先輩――いや、仕事中だからやっぱり「先輩」と呼ぶべきだ――が、会議室の前で待っていた。
扉を開けば、いつもの白い長机、プロジェクターの光。違うのは、席の配置だった。コンプライアンス部、法務、広報、そして関係部署のマネージャー。空調の音まで硬い。
「はじめます」
コンプラの担当者が進行を告げ、先輩が前に出た。
いつもなら、無駄な言葉を削りきった短いフレーズで済ませる人が、その日は、言葉を尽くす側に立った。
「まず、プロジェクトの評価指標を開示します」
スクリーンに、時系列の表とログが映る。
誰が、いつ、どの版で、どの文言を決めたか。編集履歴の差分。社外・社内の承認経路。
彼の声は低く、穏やかで、しかし一点の曖昧さもなく、「事実の列」を一本の道のように並べていった。
「成果はすべてチームに帰属します。個人の功と罪は、規程に従って評価されるべきです。匿名掲示板上の推測に、私的な感情で反応しないこと。――個人への不当な中傷は、許しません」
許しません、の「り」の音が、珍しく強かった。
室内の空気が、すこしだけ音を立てずに動いた。
私は自分の手のひらに汗が滲んでいることに気づき、膝の上でそっと拭う。
この人が「許さない」と明確に言った回数を、私はたぶん、片手で数えられる。
「なお、特別回での発言に関しては、匿名領域のルールに基づき、社内の決裁とは切り離して取り扱います。副業規定・交際の申請は、事前/事後ともに適正に行っています。詳細はここに」
添付のリンクが、画面の右に並ぶ。
法務の佐伯さんが頷き、コンプラの担当者が簡潔に補足を入れる。
私は目を伏せて、一拍だけ呼吸を整えた。
四つ吸って、六つ吐く。
蜜柑の皮を指でめくるときみたいに、胸の中の固さが少しずつほどける。
「質問は?」
沈黙。
椅子が一脚、わずかに軋む。
やがて、広報の先輩が静かに手を上げた。
「言わせてください。……一花さんの五行、いつも助かってます」
唐突な方向から投げられた言葉に、頬が熱くなる。
別の席から「うちもです」と続き、会議室の空気が、予定にない箇所でふっとやわらいだ。
「以上です。個別の案件は引き続き僕が受けます。彼女への直接の連絡は、業務上必要なものに限ってください」
先輩はそう締めくくると、プロジェクターを落とした。白い光が消え、ガラス窓の向こうの朝が戻る。
席から立ち上がるとき、彼の手が私の手を――堂々と――取った。
驚くほど自然に、机の角を避けるような手の動きで。
手のひらの熱が、掌紋の細い溝を伝ってこちらへ流れてくる。
「行こう」
「……はい」
扉を出るまでの短い廊下。
いつもより多くの目がこちらを見た。
その視線の中に、好意も、嫉妬も、驚きも、噂も、全部あった。
けれどその全部の上に、彼の手の温度が毛布みたいにかかって、私は胸の奥でひとつ頷けた。
右隣は、空いている。たぶん、これからも。
*
引っ越しの日は、晴れていた。
新居のリビングには、まだ段ボールが小さな街みたいに積まれていて、カッターの銀色が太陽を細く弾いた。
床にレジャーシートを敷いて、蜜柑箱をひっくり返す。
そこに、マイク、ポップガード、オーディオインターフェース、ヘッドホン、吸音パネルをパズルみたいに並べていく。安価な吸音材は、さわるとマシュマロみたいにすこし沈む。
「スタンド、六角レンチ……」
「ここ」
彼が工具箱を開け、猫の背中を撫でるみたいな動作でパーツを組み合わせる。
私はケーブルを束ね、結束バンドの余りを爪先でぱちんと切った。
簡易のブースは、卵の殻みたいな頼りなさで立ち上がる。
でも、頼りない殻だからこそ、抱えた声を丁寧に扱える。
「テスト」
彼がマイクに向かい、私がPCのレベルを確認する。
ラ――ソ――ミ。
録音ボタンを押す直前に、胸の内側で鐘が鳴った。
今日から、家で鳴る。
「じゃあ、最初のテイク。……“0:00の鐘、妻だけに”」
“妻”。
音の粒ひとつ分、時間が静止する。
彼は微かに照れた目でこちらを見、けれど手元は仕事の速度を崩さない。
私は口角の熱を手の甲に逃がして、レベルの針がきれいに立つのを見た。
「もう一回」
「“0:00の鐘、妻だけに”」
録音を止め、二人でヘッドホンを分ける。片耳ずつ。
いつかのブースでの「音を立てない」キスが、耳の奥のどこかで笑っている。
私は彼の肩に額を寄せ、彼は目だけで「もう一回」と合図する。
「“0:00の鐘、妻だけに”」
三テイク目で、ふたりの呼吸がちょうど良く重なった。
保存。ファイル名は、迷わず「bell_wife_01」。
「ねえ、“Lin-∞”のピアノ版、今夜流す?」
「流す。……指輪も、零時に」
「うん」
テーブルの上に置かれた小さな箱。
ふたりで選んだ、細いリング。
金色の糸が輪になっただけみたいな、軽い指輪だ。
私はそれを指に当ててみて、はめる瞬間をいったんやめる。
零時まで、取っておく。
甘いものは、最後に食べる。
夕方、残りの段ボールを崩し、食器だけを最低限並べた。
シンクに茶碗とマグと、蜂蜜の小瓶。
カーテン越しの風が、部屋の埃を一度だけ持ち上げて、すぐに落とす。
彼は電源タップの配線を隅で整え、私はカレーを煮た。
具は人参と玉ねぎと鶏むね。
小川糸さんの本で読んだ「焦がさない炒め方」を思い出して、弱火でゆっくり。
手のひらで香辛料の小さな瓶を振ると、部屋の匂いが一段だけ深くなる。
「いい匂い」
「先輩が配線してるあいだに、できました」
「配線は終わらない」
「でしょうね」
笑いながら、皿を二枚並べる。
スプーンがすこしだけ音を立て、湯気がふたりの間で揺れる。
こういうとき、幸福は派手にしゃべらない。
ただ、テーブルの木目をやさしく撫で、口の中を少し熱くしていく。
「明日の朝の紅茶、蜂蜜一本?」
「半分でいい。声に膜が張りすぎないように」
「了解」
食べ終わった皿を水に浸し、時計を見る。
「23:54」。
特別回は終わった。今夜は配信はない。
けれど、家の中にあるマイクは、小さく息をしている。
零時までの六分間が、糸巻きの上の糸みたいに静かに減っていく。
「行こうか」
「うん」
蜜柑箱の上に置かれたマイクの前に、ふたり並んで座る。
ヘッドホンはひとつ。片耳ずつ。
PC画面の録音ソフトに、新しいトラックを用意する。
BGMに「Lin-∞_piano」をロード。
心拍と同じ速度でカウントが進む。
「あと一分」
「あと三十秒」
「十」
窓の外の暗さが、ほんのわずかに深くなる。
時間は目に見えないけれど、零時は、毎日ちょっとした音を立てる。
「零時」
私は指輪の箱を開けた。
彼の左手を取る。
薄い輪を、薬指に通す。
彼の喉の奥で、小さくラ――ソ――ミが鳴った気がした。
続けて、彼が私の手を取る。
指先が少し震えている。
震えたまま、でも一度も引っ込めずに、最後まで通す。
「“0:00の鐘、妻だけに”」
ピアノがそっと乗る。
∞の曲は、輪の結び目がほどけないように、やさしく何度も同じところを撫でる。
ふたりで目を閉じた。
私は小さく笑って、彼の肩に額を預ける。
「ただいま」
「おかえり」
それだけで、家になった。
簡易のブースに、ふたり分の呼吸が充満する。
窓ガラスに映る室内の暗さが、ふたりの影と重なって、やわらかくひとつに溶けた。
*
週が明けても、仕事は待ってくれない。
職場では変わらず、厳格な先輩と、五行で走る私。
会議室で彼は、必要なときだけ肯定を置き、不要な飾りを容赦なく削る。
昼の私は削る手にためらいがなくなり、夜の私は言葉を選ぶ手に余白を作れるようになった。
それは、ひとつの道を、一緒に何度も歩いたからだ。
「“子守歌 with Lin”、今週は木曜でいい?」
「いいよ。朗読は短め、トーク長め?」
「逆にしよう。風邪の人、多い」
「じゃあ読み聞かせ多めに」
家に帰ってからの打ち合わせは、鍋の湯気と同じ速度で進む。
週一のペア配信。「with Lin」のタグが定着して、チャット欄には新規さんと常連さんがうまく混じるようになった。
風邪の夜、彼の読み聞かせに私は小さな囁きで「おやすみ」を返す。
囁くために、昼の声をちゃんと使い切る。
昼と夜、二つの声の使い方は違うけれど、どちらも私たちの家事みたいに、分担が自然だった。
ときどき、夜の合間に小さな事件は起きる。
匿名で辛いことを書き込む人がいたり、社内で噂の尾がひらひらしたり。
そのたびに、彼は順序を守って対処し、私は五行で整えた。
「堂々とする」の練習は、毎日が本番で、だから毎日が練習でもあった。
*
その夜の配信は、いつもより少し長くなった。
読み聞かせのあと、トークの最後に、私は彼を見た。
彼も私を見た。
目の中の小さな合図は、同じ形だった。
『エンディングです。――言いたいことは、ひとつだけ』
私はマイクに顔を寄せ、彼はBGMをほんの少しだけ下げる。
『右隣は、いつでも安全地帯』
ふたり同時に、小声で。
合図は、もう外に漏れてもいい。
家の鍵を、少し大きめに掲げるみたいに。
チャット欄に、祝福のスタンプが降り注いだ。
ハート、拍手、花束、∞。
見知らぬ誰かの夜に、小さな安全地帯が増える音がした。
「おつかれ」
「おつかれ」
配信を切って、ヘッドホンを外す。
リビングの静けさが戻り、私たちは床に座り込んだ。
彼が私の右隣に座る。
いつもの定位置。
私は肩を寄せ、彼は肩を貸す。
「ねえ」
「うん」
「“推しと両想い”って、言葉にするとちょっと照れるね」
「言葉にするとね」
「でも、日常にすると、ちょうどいい」
「ちょうどいい」
彼の答えが、まるで自分の喉から出たみたいに自然で、笑い合う。
窓の外で、夜風がカーテンをほんの少し持ち上げた。
その風の温度がちょうどよくて、私は思う。
二つの声が、ひとつの家になった。
合図の鐘は、今夜も同じ音で鳴る。
ラ――ソ――ミ。
明日も、たぶん、同じ。
*
――完。