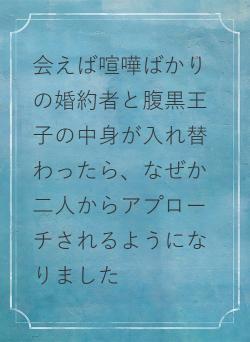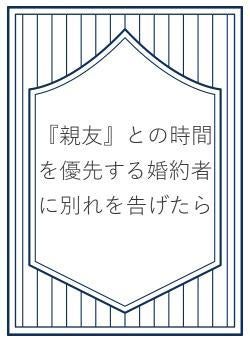私があなたを好きだということだけ知っていてくれたら、それでいい。(うそ、本当はあなたの一番になりたい)
第四話
ガードレール近くに立っていたのは、五十嵐君だった。これは夢かと思わず己の頬をつねったが、痛みはしっかり感じた。
「い、五十嵐君?」
声をかければ、彼がこちらを見た。一瞬息が詰まる。が、すぐに何でもない顔で彼に近づいた。
「どうしたの? なにか用事でもあった?」
「はい。姫川さんと、話がしたいと思いまして」
「話……」
「帰りながらで結構ですので」
「う、うん」
「お仕事、お疲れ様です」
「あ、ありがとう。まあ、お仕事っていうか、お手伝い程度なんだけど」
「いえ、ご家族のために、立派なことだと思います」
「う、うん」
五十嵐君の言葉がくすぐったくて、続きの言葉が出てこない。
(今までどういう感じで接していたっけ)
「姫川さんは」
「うん?」
「陽太さんのことを好きになったんですか?」
「はい?」
思わぬ言葉に立ち止まった。五十嵐君も足を止める。
目と目があう。こうしてしっかり視線を合わせるのもいつぶりだろう。
「仮に……私が陽太さんを好きになったとして、五十嵐君に関係あるかな?」
意地悪な返しなのは百も承知だ。けれど、五十嵐君が悔しげな表情を浮かべたのを見て、喜ぶ自分がいた。まさか、私のことで五十嵐君がその顔をするとは思っていなかった。
「なんで、そんな顔」
「……僕、今どんな顔をしていますか?」
「まるで、私の事好き、みたいな顔してる……」
「よく、わかりましたね。……僕、感情がわかりにくい、と言われることが多いんですけど」
「それは」
私が五十嵐君のことを好きだから。と、ふと思考が止まる。
(え? 『よくわかりましたね』? それってつまり……)
茫然と五十嵐君の顔を見つめる。
「姫川さんの思っている通りですよ」
「え?」
「僕は、姫川さんが好きです」
(五十嵐君が私を好き?)
そんな都合のいい展開が起きるわけがない。と、乾いた笑い声が漏れた。
「五十嵐君が好きなのはあの赤いスポーツカーの人でしょ?」
「以前も言いましたが、あの方は僕の『好きだった』方です。もう、過去の人ですよ」
「五十嵐君はすぐ嘘をつく」
「……たしかに、あの時。沙耶さんが旦那さんと一緒にいるのを見た時には、まだ気持ちは残っていたのだと思います。でも、彼女が僕の学校まできた日。あの日には、もう完全に吹っ切れていました」
「うそ」
「本当です」
「なら、どうしてあの人について行ったの。あの場で断ることだってできたでしょ」
そうせず、私を置いて行ったのは五十嵐君じゃないか、と言外に伝えれば、五十嵐君が悔いるような顔になる。
「そうですね。あの時の僕の判断は間違っていました。姫川さんの優しさに甘え、僕は自分の復讐心を優先させました。それで、あなたを失うことになるなんて、考えもしなかったから……」
「復讐心?」
「はい。僕をあっさり捨てたあの人への。もともとあの人にとって僕はただの遊び相手でした。そのことに気づいたのは、恥ずかしながら別れた後だったんですが……、思いの外僕は傷ついていたようで」
「それは当然のことでしょ」
私の言葉に、五十嵐君は嬉しそうな、悲しそうな笑みを浮かべる。
「でも、そのことであの人になにか言うつもりはなかったんです。あの日、あの人が僕の前に再び現れるまでは。僕には、あの人の魂胆がなんとなくわかっていました。旦那さんと喧嘩でもして、もしくは仕事で大きな失敗でもして、その憂さ晴らしに僕を利用しようとしているんだろうな、と。正直、腹が立ちました。だから、それに付き合うフリをして、嫌味の一つや二つをぶつけて、完全に縁を切ってやろうと……したんです」
「そう、だったんだ」
「はい。でも、その結果、姫川さんは……姫川さん」
「は、はい」
「まだ、あなたの気持ちは変わっていませんか? いえ、変わっていたとしてもかまいません。今度は僕から気持ちを伝えますから。好きです。僕は姫川さんが好きです。僕の気持ちを受け入れてほしい、なんて都合のいいことはいいません。ですが、どうかあなたを想うこの気持ちは、許してはいただけないでしょうか?」
「それは……というか、五十嵐君……本当に? 本当に私のことを?」
「はい。姫川さんが好きです」
何度五十嵐君の口から聞いても信じられない。
でも、彼の表情からは、真剣な想いが伝わってくる。
苦しい。切ない。それでも、好きなんです。そんな気持ちが。
私と――同じだ。
「五十嵐君。私の気持ちは変わってないよ」
「それは……つまり」
「私も好き。五十嵐君が」
「本当、ですか? 陽太さんより?」
「なんでそこで陽太さんの名前が出てくるかわからないけど。私は比べるまでもなく、五十嵐君が好きだよ」
その言葉を告げた時、五十嵐君の目から涙が流れた。その涙に見惚れる。が、すぐに我に返った。
「い、五十嵐君。大丈夫?!」
「あ、すみません」
目をこすろうとする彼を慌てて止めようとして、その手を取られた。
「嫌なら、避けてくださいね」
「え、」
近づいてくる顔。キスされる。そう思った時には目を閉じていた。柔らかい唇が重なる。きっとそれは数秒。けれど、私には長い時間に感じた。
「すみません。我慢できませんでした」
「我慢……」
五十嵐君はもっとこういうことはスマートにするんだと思っていた。今みたいに衝動的にするんではなく。でも、だからこそ、とても嬉しく感じた。
「しなくていいよ。その方が嬉しいから」
「……いいんですか?」
「うん」
「姫川さん。好きです」
「うん。私も五十嵐君が好き」
頬に触れる彼の手の上から己の手を重ねる。再び近づいてくる顔。目を閉じる。二度目の口付けは一度目よりも長かった。頬に触れる手とは反対の手が私の体を抱きしめるように背中に回る。私も答えるように五十嵐君の背中に手を回した。
覆い被さるような彼の勢いに押され、首がぐいっと反ってしまい若干苦しいけど、でもそれすらも嬉しく感じた。五十嵐君の一番になれたのだと、そう実感できるから。
「い、五十嵐君?」
声をかければ、彼がこちらを見た。一瞬息が詰まる。が、すぐに何でもない顔で彼に近づいた。
「どうしたの? なにか用事でもあった?」
「はい。姫川さんと、話がしたいと思いまして」
「話……」
「帰りながらで結構ですので」
「う、うん」
「お仕事、お疲れ様です」
「あ、ありがとう。まあ、お仕事っていうか、お手伝い程度なんだけど」
「いえ、ご家族のために、立派なことだと思います」
「う、うん」
五十嵐君の言葉がくすぐったくて、続きの言葉が出てこない。
(今までどういう感じで接していたっけ)
「姫川さんは」
「うん?」
「陽太さんのことを好きになったんですか?」
「はい?」
思わぬ言葉に立ち止まった。五十嵐君も足を止める。
目と目があう。こうしてしっかり視線を合わせるのもいつぶりだろう。
「仮に……私が陽太さんを好きになったとして、五十嵐君に関係あるかな?」
意地悪な返しなのは百も承知だ。けれど、五十嵐君が悔しげな表情を浮かべたのを見て、喜ぶ自分がいた。まさか、私のことで五十嵐君がその顔をするとは思っていなかった。
「なんで、そんな顔」
「……僕、今どんな顔をしていますか?」
「まるで、私の事好き、みたいな顔してる……」
「よく、わかりましたね。……僕、感情がわかりにくい、と言われることが多いんですけど」
「それは」
私が五十嵐君のことを好きだから。と、ふと思考が止まる。
(え? 『よくわかりましたね』? それってつまり……)
茫然と五十嵐君の顔を見つめる。
「姫川さんの思っている通りですよ」
「え?」
「僕は、姫川さんが好きです」
(五十嵐君が私を好き?)
そんな都合のいい展開が起きるわけがない。と、乾いた笑い声が漏れた。
「五十嵐君が好きなのはあの赤いスポーツカーの人でしょ?」
「以前も言いましたが、あの方は僕の『好きだった』方です。もう、過去の人ですよ」
「五十嵐君はすぐ嘘をつく」
「……たしかに、あの時。沙耶さんが旦那さんと一緒にいるのを見た時には、まだ気持ちは残っていたのだと思います。でも、彼女が僕の学校まできた日。あの日には、もう完全に吹っ切れていました」
「うそ」
「本当です」
「なら、どうしてあの人について行ったの。あの場で断ることだってできたでしょ」
そうせず、私を置いて行ったのは五十嵐君じゃないか、と言外に伝えれば、五十嵐君が悔いるような顔になる。
「そうですね。あの時の僕の判断は間違っていました。姫川さんの優しさに甘え、僕は自分の復讐心を優先させました。それで、あなたを失うことになるなんて、考えもしなかったから……」
「復讐心?」
「はい。僕をあっさり捨てたあの人への。もともとあの人にとって僕はただの遊び相手でした。そのことに気づいたのは、恥ずかしながら別れた後だったんですが……、思いの外僕は傷ついていたようで」
「それは当然のことでしょ」
私の言葉に、五十嵐君は嬉しそうな、悲しそうな笑みを浮かべる。
「でも、そのことであの人になにか言うつもりはなかったんです。あの日、あの人が僕の前に再び現れるまでは。僕には、あの人の魂胆がなんとなくわかっていました。旦那さんと喧嘩でもして、もしくは仕事で大きな失敗でもして、その憂さ晴らしに僕を利用しようとしているんだろうな、と。正直、腹が立ちました。だから、それに付き合うフリをして、嫌味の一つや二つをぶつけて、完全に縁を切ってやろうと……したんです」
「そう、だったんだ」
「はい。でも、その結果、姫川さんは……姫川さん」
「は、はい」
「まだ、あなたの気持ちは変わっていませんか? いえ、変わっていたとしてもかまいません。今度は僕から気持ちを伝えますから。好きです。僕は姫川さんが好きです。僕の気持ちを受け入れてほしい、なんて都合のいいことはいいません。ですが、どうかあなたを想うこの気持ちは、許してはいただけないでしょうか?」
「それは……というか、五十嵐君……本当に? 本当に私のことを?」
「はい。姫川さんが好きです」
何度五十嵐君の口から聞いても信じられない。
でも、彼の表情からは、真剣な想いが伝わってくる。
苦しい。切ない。それでも、好きなんです。そんな気持ちが。
私と――同じだ。
「五十嵐君。私の気持ちは変わってないよ」
「それは……つまり」
「私も好き。五十嵐君が」
「本当、ですか? 陽太さんより?」
「なんでそこで陽太さんの名前が出てくるかわからないけど。私は比べるまでもなく、五十嵐君が好きだよ」
その言葉を告げた時、五十嵐君の目から涙が流れた。その涙に見惚れる。が、すぐに我に返った。
「い、五十嵐君。大丈夫?!」
「あ、すみません」
目をこすろうとする彼を慌てて止めようとして、その手を取られた。
「嫌なら、避けてくださいね」
「え、」
近づいてくる顔。キスされる。そう思った時には目を閉じていた。柔らかい唇が重なる。きっとそれは数秒。けれど、私には長い時間に感じた。
「すみません。我慢できませんでした」
「我慢……」
五十嵐君はもっとこういうことはスマートにするんだと思っていた。今みたいに衝動的にするんではなく。でも、だからこそ、とても嬉しく感じた。
「しなくていいよ。その方が嬉しいから」
「……いいんですか?」
「うん」
「姫川さん。好きです」
「うん。私も五十嵐君が好き」
頬に触れる彼の手の上から己の手を重ねる。再び近づいてくる顔。目を閉じる。二度目の口付けは一度目よりも長かった。頬に触れる手とは反対の手が私の体を抱きしめるように背中に回る。私も答えるように五十嵐君の背中に手を回した。
覆い被さるような彼の勢いに押され、首がぐいっと反ってしまい若干苦しいけど、でもそれすらも嬉しく感じた。五十嵐君の一番になれたのだと、そう実感できるから。