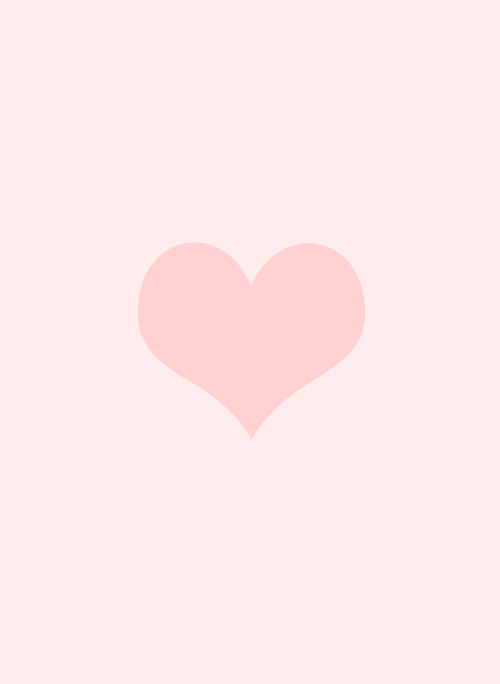『沈黙のプリズム ―四人の約束―』
最終章「光の庭、再び」
四月の午後、光は薄く金色を帯びていた。
“光の庭”――記念植樹で新しくなったアーチの下、噴水は相変わらず一定の拍で水を跳ね上げ、粒になった日差しを宙へ放つ。ジャスミンの若い蔓が白い蕾を抱き、甘い香りが風にほどけていく。
「緊張してる?」
隣で足を止めた悠真が、少し照れたように笑った。シダーの穏やかな香りが、春の空気に薄く混じる。
「少しだけ。……でも、ここに戻ってくるって決めたのは、私だから」
「じゃあ、いつもの順番でいこう」
「順番?」
「約束の確認」
「ふふ。――逃げない、言う、並んで歩く、そして“信じ続ける”」
「合格」
ふたりで噴水の縁に腰をおろす。水面がきらりと割れ、光の破片が頬に触れた。
「桐山学園“庭の再生”式典、そろそろ始まるらしいよ」
「うん。……ねえ、今日は“あれ”も」
「わかってる」
瑠奈は鞄から古びた封筒を取り出した。五年前の、未封の手紙。角は少し黄ばんでいる。
「これは、今日で手放す。私がどこから来たのかを忘れないために、一度だけ目を閉じて――それから前を見ます」
「付き合うよ」
「ありがとう」
風が方向を変え、ジャスミンが香りを強めた。
「よっ、二人とも」
声に振り向くと、拓也が軽く手を挙げていた。グレーのスーツに、相変わらず真っ直ぐな目。
「ベンチ、寄贈したんだ。銘板つき。――“静かな時間のために”って」
「拓也さんらしい」
「こっちは“騒がしい時間担当”だからな」
悠真が肩を竦め、二人の間に自然な笑いが落ちた。
「元気そうで何より」
「君もな。……瑠奈、泣いたら、俺は黙って見ていないって言ったけど」
「泣く前に話すから大丈夫」
「なら安心だ。……じゃ、式典で」
握手は短く、温度は確かだった。過去の棘は、いつのまにか角を丸めていた。
アーチの向こうから、控えめなヒールの音。
「間に合ったみたいね」
麗華が白い小花の苗を抱えて現れた。スーツは淡いベージュ、目元の光は柔らかい。
「麗華さん、その花……」
「ジャスミンの兄弟分。香りは控えめだけど、強い。ここに欲しかったの」
スコップで土を割ると、黒い土の匂いがふわりと立った。
「ありがとう」
「礼を言われることじゃないわ。――私も、ようやく自分を許せたから」
「うん」
「そして、二人を祝福できる場所をやっと見つけたの」
「麗華」悠真が小さく会釈する。「来てくれて、ありがとう」
「もう“影”で戦うのはやめたの。光のそばにいれば、自然に静かになれるものね」
三人は顔を見合わせ、言葉で飾らない微笑みを交わした。
式典が始まる。
校長の短い挨拶、弦楽四重奏の前奏。新設の銘板が布から現れる――
《光の庭――“沈黙は、歩き出すための静けさ”》
拍手が風に混ざって広がった。
その隙に、瑠奈は噴水脇の小さなガラス箱へ向かう。
「学園史アーカイブ:寄贈資料」と刻まれている。
係員に手渡された薄い封筒に、黄ばみの手紙をそっと収める。添えるのは新しい一枚――彼女の文字は迷いなく滑った。
『沈黙は私たちのはじまりでした。
そして言葉は、私たちの歩幅になりました。』
封を押さえる瑠奈の指に、悠真の影が重なる。
「大丈夫?」
「うん。軽くなった」
噴水がひときわ高く音をたてた。水滴が跳ね、花びらに丸い光が宿る。
式典後。
四人――瑠奈、悠真、麗華、拓也――は新しいベンチへ移動した。
「写真、撮っておきましょうか」
麗華がスマホを構え、笑った。
「いい?――はい、光の庭!」
シャッター音が響く。同時に、遠くの校舎でチャイムが鳴った。
「ねえ、今の音、卒業式のメロディに似てる」
「不思議だな。時間が輪になって戻ってくるみたいだ」
「輪なら、繋ぎ直せる」
拓也が空を仰ぐ。「それぞれの場所で、ちゃんと繋ごう」
「ええ」麗華が頷く。「沈黙で切らずに、言葉で」
風が通り抜け、四人の影を長く撫でていった。
夕暮れ。式典は解散し、人の気配が薄くなる。
噴水の縁に、再び二人。
瑠奈は、指先で水面をそっと弾いた。
「冷たい」
「前も同じこと言ってた」
「変わらないことが、好きになったのかもしれない」
「変わった君も、好きだよ」
その言葉は、もうどこにも引っかからない。
まっすぐ落ちて、水の底で小さく光った。
「明日からも忙しくなるね」
「うん。だからこそ、確認」
「また“約束の順番”?」
「最後に一つ、増やして」
「まだ増えるの?」
「“迷ったら、手を取る”」
「……採用」
指先が触れ、自然に絡む。
噴水の音が拍手のように高くなった。
(光の庭は、もう“過去”を映す鏡じゃない。
私たちがこれから歩く“道”を、ここから照らす灯台だ)
西の空に、残光が細い帯を残している。
帰ろうと立ち上がった二人の影は、別々の向きへ伸びながら、同じ光に包まれていた。
「また、来年の花の季節に」
「もちろん」
歩き出す足音が揃う。
沈黙は、もう距離ではない――歩幅を合わせるための、やさしい合図だった。
“光の庭”――記念植樹で新しくなったアーチの下、噴水は相変わらず一定の拍で水を跳ね上げ、粒になった日差しを宙へ放つ。ジャスミンの若い蔓が白い蕾を抱き、甘い香りが風にほどけていく。
「緊張してる?」
隣で足を止めた悠真が、少し照れたように笑った。シダーの穏やかな香りが、春の空気に薄く混じる。
「少しだけ。……でも、ここに戻ってくるって決めたのは、私だから」
「じゃあ、いつもの順番でいこう」
「順番?」
「約束の確認」
「ふふ。――逃げない、言う、並んで歩く、そして“信じ続ける”」
「合格」
ふたりで噴水の縁に腰をおろす。水面がきらりと割れ、光の破片が頬に触れた。
「桐山学園“庭の再生”式典、そろそろ始まるらしいよ」
「うん。……ねえ、今日は“あれ”も」
「わかってる」
瑠奈は鞄から古びた封筒を取り出した。五年前の、未封の手紙。角は少し黄ばんでいる。
「これは、今日で手放す。私がどこから来たのかを忘れないために、一度だけ目を閉じて――それから前を見ます」
「付き合うよ」
「ありがとう」
風が方向を変え、ジャスミンが香りを強めた。
「よっ、二人とも」
声に振り向くと、拓也が軽く手を挙げていた。グレーのスーツに、相変わらず真っ直ぐな目。
「ベンチ、寄贈したんだ。銘板つき。――“静かな時間のために”って」
「拓也さんらしい」
「こっちは“騒がしい時間担当”だからな」
悠真が肩を竦め、二人の間に自然な笑いが落ちた。
「元気そうで何より」
「君もな。……瑠奈、泣いたら、俺は黙って見ていないって言ったけど」
「泣く前に話すから大丈夫」
「なら安心だ。……じゃ、式典で」
握手は短く、温度は確かだった。過去の棘は、いつのまにか角を丸めていた。
アーチの向こうから、控えめなヒールの音。
「間に合ったみたいね」
麗華が白い小花の苗を抱えて現れた。スーツは淡いベージュ、目元の光は柔らかい。
「麗華さん、その花……」
「ジャスミンの兄弟分。香りは控えめだけど、強い。ここに欲しかったの」
スコップで土を割ると、黒い土の匂いがふわりと立った。
「ありがとう」
「礼を言われることじゃないわ。――私も、ようやく自分を許せたから」
「うん」
「そして、二人を祝福できる場所をやっと見つけたの」
「麗華」悠真が小さく会釈する。「来てくれて、ありがとう」
「もう“影”で戦うのはやめたの。光のそばにいれば、自然に静かになれるものね」
三人は顔を見合わせ、言葉で飾らない微笑みを交わした。
式典が始まる。
校長の短い挨拶、弦楽四重奏の前奏。新設の銘板が布から現れる――
《光の庭――“沈黙は、歩き出すための静けさ”》
拍手が風に混ざって広がった。
その隙に、瑠奈は噴水脇の小さなガラス箱へ向かう。
「学園史アーカイブ:寄贈資料」と刻まれている。
係員に手渡された薄い封筒に、黄ばみの手紙をそっと収める。添えるのは新しい一枚――彼女の文字は迷いなく滑った。
『沈黙は私たちのはじまりでした。
そして言葉は、私たちの歩幅になりました。』
封を押さえる瑠奈の指に、悠真の影が重なる。
「大丈夫?」
「うん。軽くなった」
噴水がひときわ高く音をたてた。水滴が跳ね、花びらに丸い光が宿る。
式典後。
四人――瑠奈、悠真、麗華、拓也――は新しいベンチへ移動した。
「写真、撮っておきましょうか」
麗華がスマホを構え、笑った。
「いい?――はい、光の庭!」
シャッター音が響く。同時に、遠くの校舎でチャイムが鳴った。
「ねえ、今の音、卒業式のメロディに似てる」
「不思議だな。時間が輪になって戻ってくるみたいだ」
「輪なら、繋ぎ直せる」
拓也が空を仰ぐ。「それぞれの場所で、ちゃんと繋ごう」
「ええ」麗華が頷く。「沈黙で切らずに、言葉で」
風が通り抜け、四人の影を長く撫でていった。
夕暮れ。式典は解散し、人の気配が薄くなる。
噴水の縁に、再び二人。
瑠奈は、指先で水面をそっと弾いた。
「冷たい」
「前も同じこと言ってた」
「変わらないことが、好きになったのかもしれない」
「変わった君も、好きだよ」
その言葉は、もうどこにも引っかからない。
まっすぐ落ちて、水の底で小さく光った。
「明日からも忙しくなるね」
「うん。だからこそ、確認」
「また“約束の順番”?」
「最後に一つ、増やして」
「まだ増えるの?」
「“迷ったら、手を取る”」
「……採用」
指先が触れ、自然に絡む。
噴水の音が拍手のように高くなった。
(光の庭は、もう“過去”を映す鏡じゃない。
私たちがこれから歩く“道”を、ここから照らす灯台だ)
西の空に、残光が細い帯を残している。
帰ろうと立ち上がった二人の影は、別々の向きへ伸びながら、同じ光に包まれていた。
「また、来年の花の季節に」
「もちろん」
歩き出す足音が揃う。
沈黙は、もう距離ではない――歩幅を合わせるための、やさしい合図だった。