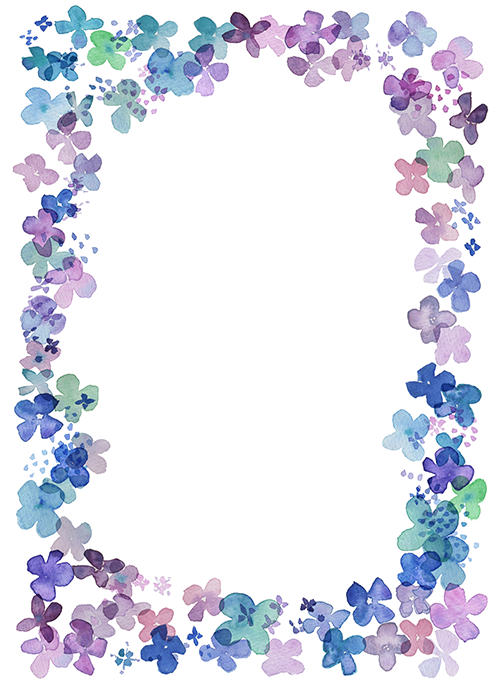物語の序盤で処刑される悪役女王に転生したので、息子を大切に育てたいと思います。
第一話
落ちてきたギロチンの勢いで首が飛んだ。遅れて血しぶきが舞う。
舞った血しぶきが、女王の汚れの知らない真珠のような白髪を真っ赤に染め上げた。
処刑人が頭を無造作に掴んで、声高らかに宣言する。
「アルティナ・ローゼルはここに処刑された! 我々を苦しめた魔女はもうこの世に存在しない!」
十数年も国民を苦しめた魔女の最期とは思えぬほど呆気ない死に、呼吸を忘れていた民衆たちが遅れて歓声を挙げる。
轟く歓声に、王座に腰かけた新しい王は、母だった罪人と同じ深紅の瞳を見開いた。
「……いま、笑っていた?」
首を刎ねられる直前、女王は確かに笑っていた。
心の底から満ち足りたような、どこか憎悪すら感じる笑顔だった。
女王である母親に隣国に追放された元王子であり反乱軍の長を担ったアベルは、母親の最期の笑みに疑問を持つ。
(どうして、笑っていたんだ?)
ふと、幼いころの記憶がよみがえる。
女王としてローゼル王国に君臨していた、アルティナ。
彼女は息子を虐げていた。
教育とは思えない残忍な方法で息子を躾けた。
鞭で打ったり、冬の寒い中裸で外に放りだされたこともある。
アベルはそんな母親に恐怖して、震えることしかできなかった。
アルティナは、アベルを虐げるたびに笑みを浮かべていた。
楽しくて仕方がないというような、子供が無邪気に遊び回るような笑い声を。
「これは復讐よ」
彼女は事あるごとにそう繰り返した。
女王アルティナ・ローゼルは、この王国を破滅に導いた魔女だ。
王国の貴重な資源を盾に近隣諸国から金を巻き上げたかと思えば、隣国に戦争を仕掛けた。戦争により疲弊し、病気や飢餓に喘ぐ民衆の姿など見えないかのように、アルティナは贅の限りを尽くした。
この国を滅ぼす寸前まで壊した魔女を、やっと処刑したというのに。
アルティナの死は解放をもたらすどころか、アベルの心にさらに濃い闇を残しただけだった。
――――これが、私が死ぬ直前に読んでいた、ロマンス小説のプロローグだ。
◇◆◇
薔薇宮からさほど離れていないところにある、蕾宮。
そこは、王位継承者が過ごす宮殿でもあった。
私は屋敷の入り口からこっそりと中に入ると、音を立てずに階段を上る。もうすでに使用人たちに私の存在はバレているのだけれど、それに構っている余裕はない。
どこか緊張した面持ちの使用人に声をかけると、彼女は暗い顔をしながらも目的の人物がどこにいるのか教えてくれた。
どうやら彼は、いまは勉強の時間みたいだ。
これまで名前のない離宮にいたときは、食事も満足に与えられていなくて痩せこけた手足をしていた。本来なら受けていてもおかしくない教育も満足に受けられなかったからか、言葉もたどたどしく、文字も読めないようだった。――と言っても、私はまだ会話すらしたことがないので、これは伝え聞いた話だ。
あれからまだ一ヶ月しか経っていない。
勉強といっても、まだ読み書きの範囲だろう。
「……今日は、大丈夫かしら」
そんな淡い期待を浮かべながらも、私は部屋の扉をゆっくりと開いた。
なるべく彼を刺激しないように、そっと開いたつもりだったのだけれど。
扉を開いた先で、私と同じ深紅の瞳の持ち主と目が合ってしまった。
「あ」
と声を出す間もなく、まだ五歳と幼い少年の瞳に涙が溢れていく。
「う、うわあああん」
私の顔を見た瞬間、息子のアベルは大きな声をあげて泣いたかと思うと、猛ダッシュで部屋の奥に逃げてしまった。
「あ、アベルー」
名前を呼ぶが、もちろん出てくることはない。
「怖くないよー」
安心させようと上げた言葉も、アベルからすると恐怖そのものに聞こえるだろう。
「……やっぱり、駄目なようね」
アルティナの真珠のような白髪も、真っ赤な薔薇のような深紅の瞳も、アベルからすると目にするのも嫌なトラウマなのだ。
それをたった一言二言話すだけで、心を開いてくれるわけがない。
「……ほんっと、アルティナめ。あなたのせいで……」
いまは私がアルティナなのに、つい愚痴ってしまう。
部屋の中にいた家庭教師が怯えたように私に頭を下げていて、さらに憂鬱になる。
それでも、私は諦めるわけにはいかなかった。
この小説の世界に転生したからには、アベルを大切に育てることが私の宿命なんだと、そう信じているからだ。
◆
ウェブで話題だったロマンス小説『枯れた黒薔薇騎士と夜明けの廃聖女』の世界に転生したことに気づいたのは、いまから一か月ほど前のことだった。
私はそのロマンス小説で序盤に処刑される悪役女王――アルティナ・ローゼルに転生していた。
「なんで、よりによってアルティナなのよ!」
自分が転生した人物が誰かを知ったとき、咄嗟に出てきたのがその言葉だった。
アルティナは血の繋がったたった一人の息子を、あろうことか虐待して捨てた悪女だ。
物語の序盤で処刑されるものの、彼女は死後も息子のアベルを苦しめた。
その苦しみを和らげたり、たまに衝突したりするのが小説のヒロインであるエリシアの役割だった。
エリシアの見た目は、驚くことに真珠のような白髪に澄んだ赤色の瞳だった。
その姿に憎んでいた母の面影を重ねたアベルは、周囲が止めるのを聞かずに彼女をそばに置くことに決める。その間に葛藤があったりするのだけれど、エリシアの力がアベルの癒しになっていたり、ヤキモキする要素もあった。
二人の綱渡りのような関係は、時にハラハラしたりと目が離せないものが多く、それまで他者をまともに信じられなかったアベルが、エリシアの根気強い説得と愛情により徐々に他人を受け入れることができる展開には、つい前世の自分の境遇と重ね合わせて涙を流したこともある。
最終的にアベルは母親の重い面影を振り払うことができて、エリシアとお互いの気持ちを確かめ合い、そして二人は結婚して暮らしました、というめでたしめでたしのハッピーエンドだった。
私はこの小説が大好きで、ポロポロと涙を流しながらも何度も何度も読み返した。
熱いコメントを送ったことも少なくない。
でも、その小説で唯一許せないキャラがいた。
アベルの母であり、私が転生した悪役女王アルティナだ。
前世の日本で小林いばらとして過ごしていた私は、親元を離れて小学一年生のころから児童養護施設で暮らしていた。
当時は幼く、自分の境遇を理解していなかったこともあるけれど、後から聞いた話では親から放置されていたそうだ。
児童養護施設には様々な事情を抱えた子供たちが暮らしている。
中には虐待されたことのある子供たちもいて、そういう子供たちは心に深い傷を抱えていた。
そんな子供たちと共に成長して、私は児童養護施設を卒業したのだ。
だから、私は余計にアルティナに憤ってしまったのかもしれない。
自分の息子を虐待して死に追いやろうとしたなんて、いくら小説の登場人物だとしてもそんな大人がいることが信じられなかったのだ。
『子供は幸せに生きなければならないんです。不幸な子供なんて、存在してはいけないんですよ』
それは私を育ててくれた、児童養護施設の先生の言葉だ。
私はその言葉を胸に、自分も将来児童養護施設で働きたいと考えて、資格を取得するために福祉施設で働くことが決まった矢先に、事故に遭ってしまったのだ。
「転生するにしても、なんでよりによってアルティナなのよぉおお! いつか息子に処刑されるキャラに転生するなんて……。前世でも、結婚どころか子供もいなかったのに。家族だって……」
はあ、と落ち込んでいても仕方がない。
アルティナに転生したということは、いつか私は死んでしまう。
その未来をどうにかしなければいけない。
「……そうだ。アルティナは悪政で国民を苦しめて、なおかつアベルを虐待したから報復も込めて処刑されるのよね? ……それなら女王として真っ当に国政を担って、アベルを大切に育てれば処刑されなくても済むんじゃない?」
咄嗟に思い付いたことだけれど、良い案かもしれない。
いつまでもベッドの上でグダグダしていても仕方がない。
アベルを救済するためにも動き出そうと、まずは侍女を呼び出すことにした。
「お呼びでしょうか?」
やってきた侍女は、そうとわかるぐらい震えていた。
アルティナは、お世話をしてくれる侍女だろうと使用人だろうと、ひとつでもミスをしたり気に入らないことがあれば容赦なく罰を与えた。よっぽどのことがない限り命を奪うことまではしないが、それでもアルティナに辞めさせられた侍女や使用人の多くは路頭に迷うことになる。
侍女たちからすると、アルティナは恐怖の対象なのだ。
「聞きたいことがあります」
つい前世と同じように敬語で話しかけてしまったのが悪かったのかもしれない。
侍女は大きく目を見開くと、なぜかガタガタと震え出した。
「ど、どうして私にそんな丁寧に話されるのですか? ……も、もしかして私、何かやってしまいましたか?」
「ち、違うのよ。ただ、聞きたいことがあるの。それに答えてくれればいいだけだから」
「わ、私はどうなっても構わないので、家族のことは許してくださいぃぃ」
侍女は両手を組み合わせると、床に頭をつけた。
あまりにも動きが素早すぎて、止める暇もなかった。
「あなたを罰したりはしないわ。私は、ただアベルの居場所が知りたいだけよ」
突然キャラを変えるとこの侍女みたいに余計に怖がられるかもしれない。
だからアルティナっぽく振る舞うと、彼女は分かりやすくホッとした顔になった。
「王子殿下でしたら、離宮にいらっしゃると思います」
「離宮?」
王宮にはいくつかの建物があるから、その内のひとつだろうか。
「それなら、私をそこに案内してちょうだい」
「……え、会われるのですか?」
侍女は信じられないものを見るような顔つきになった。
そのとき、ガツンと頭が殴られたような感覚がして、脳裏に記憶が流れ込んでくる。
『アレは、離宮にでも閉じ込めておきなさい。私の視界に入れないで』
これは、アルティナの記憶だ。この体に転生した時もそうだったのだが、断続的にアルティナの記憶が脳裏に過ぎっていくことがある。
私は痛む頭を押さえながらも、驚いている侍女に命令する。
「いいから早く、アレのところに私を案内しなさい」
「ッ、承知しました!」
そのあと、頭痛は何事もなかったかのように引いていた。
なんだろうとは思ったものの、アルティナの記憶も完全ではない。
生き残るためにも、彼女の記憶は助けになる。
「……でも、肝心な記憶が抜けているのよね。アルティナは、どうしてアベルを虐待していたのかしら」
アルティナの幼少期の記憶やアベルを生んだ前後の記憶だけはなぜかごっそり抜けているのだ。それ以降もまだ断片的にしか思い出せない。
疑問に思うものの、いま考えても仕方のないことだと割り切ることにした。
それからしばらくして、私はアベルとの初対面をすることになったのだが――。
顔を会わせたアベルは、私の姿を見た瞬間に気絶してしまい、会話もできなかった。
よっぽど恐怖していたのだろうと思うのと同時に、アベルをここまで追い詰めたアルティナに改めて怒りが湧いた。
アベルの暮らしていた離宮は酷いところだった。
ろくな手入れもされていない古く朽ち果てた建物に、数人の使用人を残していたにすぎない。
アベルは食事もまともに取れていないのか、五歳にしては体が小さく、立っているのがやっとの様子だった。
いくらなんでも酷すぎるとは思ったものの、それをしたのは私が転生したアルティナだ。
それに、前世に暮らしていた施設にも、似たような境遇の子供たちがいた。
彼らは職員や年上の子供たちにより少しずつ心を開いていったけれど、本来ならそんな光景はないほうがいいに決まっている。
「――私は、思い違いをしていたようね」
私のつぶやきになぜか侍女が震えだす。
でも、そんなことも気にならないぐらい、私は苛立ちと、それから自分に対する不甲斐なさでいっぱいだった。
私がアベルに会いに来たのは、自分の死の運命を回避するためだった。
でも、それはただの自己満足でしかない。
『子供は幸せに生きなければならないんです。不幸な子供なんて、存在してはいけないんですよ』
私を育ててくれた先生の言葉が脳裏を過ぎる。
どうしてこんな大切なことを忘れていたのだろう。
「……先生。私、やってみるわ。アベルを、幸せにしてみせる」
もう私の未来なんて関係なかった。
たとえどんな未来になろうとも、私がアベルを幸せにしてみせる。
それが、私がアルティナに転生した理由なのだから。
◇
私は、まずアベルの生活環境を整えることから始めた。
古い離宮ではなく、王位継承者用の蕾宮を与えた。その話をしたとき臣下たちは驚いていたけれど、アルティナの言葉に反論する者はいなかった。むしろ、やっと陛下も息子のことに興味を持ったのかと安堵する者もいた。
使用人の数も増やして、特に食事には気を遣うように専門知識のある料理人も迎え入れた。
ここが小説の世界だということもあり、食事の味付けは前世とはそう変わらなかった。食事マナーも手づかみということはなくナイフやフォークを使っていて、蕾宮には浴場もあって毎日のお風呂にも困らないだろう。
アベルはいままで放置されていたということもあり、最初は少しずつ食べる量を増やしていくことになった。
困ったのが読み書きがまだ何もできないことだけれど、そこも有能な家庭教師を雇うことによって、少しずつ覚えていけばいいだろう。
でも、それよりも問題は――。
「……どうしたら、アベルと仲良くできるんだろう」
一か月間、なるべくアベルと顔を会わせることにしていた。
だけど、アベルは私の姿を見た瞬間に、気を失ったり逃げてしまったり、言葉を交わす余裕もなかった。
「当然よね。いままで虐げていた人に、心を許すことなんてできないわ」
アベルの記憶には、もうすっかりアルティナに対する恐怖が刷り込まれている。
私がアルティナの姿をしている限り、アベルと信頼関係を築くことはできないかもしれない。
一番いいのは、陰から支援するだけで、自分の姿を見せないことだろう。
「でも、それだと、ずっとアベルは母親に対して恐怖と憎悪を持ったままだわ」
たとえ物語通りに私が処刑されたとしても、アベルの心にはずっと影が付きまとって苦しむことになるだろう。
できれば、それだけは阻止したい。
「アベルに家族からの愛情を知ってほしいわ」
アベルの家族はいまは私だけだ。アベルの父――アルティナの元王配は、罪人として遠くにいて、いまはまだ会いに行くことはできない。
家族からの愛情がすべてではないにしても、幼い心に負った傷は生涯付きまとうこともある。
なるべくアベルには健やかに過ごしてほしい。
そのためにも、アルティナに対する恐怖を少しでも和らげたい。
「私を見ると逃げ出してしまうし、どうしたらいいのかしら」
蕾宮からの帰り道、私は馬車に揺られながらそんなひとりごとを呟いていた。
窓の外に流れる景色は、前世の日本とは全然違った。
宮殿の庭園は広いという言葉だけでは表せないほど広大で、道の先に何が続いているのか思いを馳せるだけでも楽しかった。
景色を堪能していると、頭もすっきりしてきて、ふと妙案を思いつく。
「……アルティナの姿を隠して、アベルに近づいて、少しずつ距離を縮めていけば……。いや、でもそのためにはどうしたら……あ」
アルティナの宮殿に着いたときには、私の頭の中でひとつの作戦が組み上がっていた。
馬車を降りた私は、入り口で出迎えてくれている使用人一同を見渡して、その中で最も近くにいるお仕着せ姿の使用人の前で立ち止まった。
「ねえ、あなた」
顔を上げた彼女の顔は、恐怖で青ざめていた。
私はつい威圧的になりそうになっていた顔に、にぃっと笑みを浮かべる。
すると、使用人はもういまにも倒れそうな様子になってしまい、慌てて笑みを消す。
コホンと咳をしてから、なるべく威圧的にならないように使用人に訊ねる。
「そのお仕着せ、私に貸してくれない?」
「えっ!? い、いますぐここで脱げということですか!? そ、それは、勘弁してくださいぃ」
「あ、違うのよ。予備の服でいいから――って」
顔面蒼白になった使用人は、床に頭を垂れていた。まるで命乞いでもしているかのようだ。
周囲を見渡すと、ほかの使用人も次は自分じゃないのかと震えている。
私は発言を間違えてしまったらしい。
いや、それ以前に、アルティナの顔が私が思っているよりも怖いことを失念していたのだ。
「……もう、そうじゃないのに」
私はただ、アルティナの姿を隠すためにも使用人に変装して、少しでもアベルに近づこうと思っただけだ。
それなのに――。
どうやらアルティナのこの姿はアベルだけではなく、ほかの使用人たちにとっても恐ろしいものだったらしい。
どうしたら誤解が解けるのか。
私はさらに頭を悩ませるのだった。
舞った血しぶきが、女王の汚れの知らない真珠のような白髪を真っ赤に染め上げた。
処刑人が頭を無造作に掴んで、声高らかに宣言する。
「アルティナ・ローゼルはここに処刑された! 我々を苦しめた魔女はもうこの世に存在しない!」
十数年も国民を苦しめた魔女の最期とは思えぬほど呆気ない死に、呼吸を忘れていた民衆たちが遅れて歓声を挙げる。
轟く歓声に、王座に腰かけた新しい王は、母だった罪人と同じ深紅の瞳を見開いた。
「……いま、笑っていた?」
首を刎ねられる直前、女王は確かに笑っていた。
心の底から満ち足りたような、どこか憎悪すら感じる笑顔だった。
女王である母親に隣国に追放された元王子であり反乱軍の長を担ったアベルは、母親の最期の笑みに疑問を持つ。
(どうして、笑っていたんだ?)
ふと、幼いころの記憶がよみがえる。
女王としてローゼル王国に君臨していた、アルティナ。
彼女は息子を虐げていた。
教育とは思えない残忍な方法で息子を躾けた。
鞭で打ったり、冬の寒い中裸で外に放りだされたこともある。
アベルはそんな母親に恐怖して、震えることしかできなかった。
アルティナは、アベルを虐げるたびに笑みを浮かべていた。
楽しくて仕方がないというような、子供が無邪気に遊び回るような笑い声を。
「これは復讐よ」
彼女は事あるごとにそう繰り返した。
女王アルティナ・ローゼルは、この王国を破滅に導いた魔女だ。
王国の貴重な資源を盾に近隣諸国から金を巻き上げたかと思えば、隣国に戦争を仕掛けた。戦争により疲弊し、病気や飢餓に喘ぐ民衆の姿など見えないかのように、アルティナは贅の限りを尽くした。
この国を滅ぼす寸前まで壊した魔女を、やっと処刑したというのに。
アルティナの死は解放をもたらすどころか、アベルの心にさらに濃い闇を残しただけだった。
――――これが、私が死ぬ直前に読んでいた、ロマンス小説のプロローグだ。
◇◆◇
薔薇宮からさほど離れていないところにある、蕾宮。
そこは、王位継承者が過ごす宮殿でもあった。
私は屋敷の入り口からこっそりと中に入ると、音を立てずに階段を上る。もうすでに使用人たちに私の存在はバレているのだけれど、それに構っている余裕はない。
どこか緊張した面持ちの使用人に声をかけると、彼女は暗い顔をしながらも目的の人物がどこにいるのか教えてくれた。
どうやら彼は、いまは勉強の時間みたいだ。
これまで名前のない離宮にいたときは、食事も満足に与えられていなくて痩せこけた手足をしていた。本来なら受けていてもおかしくない教育も満足に受けられなかったからか、言葉もたどたどしく、文字も読めないようだった。――と言っても、私はまだ会話すらしたことがないので、これは伝え聞いた話だ。
あれからまだ一ヶ月しか経っていない。
勉強といっても、まだ読み書きの範囲だろう。
「……今日は、大丈夫かしら」
そんな淡い期待を浮かべながらも、私は部屋の扉をゆっくりと開いた。
なるべく彼を刺激しないように、そっと開いたつもりだったのだけれど。
扉を開いた先で、私と同じ深紅の瞳の持ち主と目が合ってしまった。
「あ」
と声を出す間もなく、まだ五歳と幼い少年の瞳に涙が溢れていく。
「う、うわあああん」
私の顔を見た瞬間、息子のアベルは大きな声をあげて泣いたかと思うと、猛ダッシュで部屋の奥に逃げてしまった。
「あ、アベルー」
名前を呼ぶが、もちろん出てくることはない。
「怖くないよー」
安心させようと上げた言葉も、アベルからすると恐怖そのものに聞こえるだろう。
「……やっぱり、駄目なようね」
アルティナの真珠のような白髪も、真っ赤な薔薇のような深紅の瞳も、アベルからすると目にするのも嫌なトラウマなのだ。
それをたった一言二言話すだけで、心を開いてくれるわけがない。
「……ほんっと、アルティナめ。あなたのせいで……」
いまは私がアルティナなのに、つい愚痴ってしまう。
部屋の中にいた家庭教師が怯えたように私に頭を下げていて、さらに憂鬱になる。
それでも、私は諦めるわけにはいかなかった。
この小説の世界に転生したからには、アベルを大切に育てることが私の宿命なんだと、そう信じているからだ。
◆
ウェブで話題だったロマンス小説『枯れた黒薔薇騎士と夜明けの廃聖女』の世界に転生したことに気づいたのは、いまから一か月ほど前のことだった。
私はそのロマンス小説で序盤に処刑される悪役女王――アルティナ・ローゼルに転生していた。
「なんで、よりによってアルティナなのよ!」
自分が転生した人物が誰かを知ったとき、咄嗟に出てきたのがその言葉だった。
アルティナは血の繋がったたった一人の息子を、あろうことか虐待して捨てた悪女だ。
物語の序盤で処刑されるものの、彼女は死後も息子のアベルを苦しめた。
その苦しみを和らげたり、たまに衝突したりするのが小説のヒロインであるエリシアの役割だった。
エリシアの見た目は、驚くことに真珠のような白髪に澄んだ赤色の瞳だった。
その姿に憎んでいた母の面影を重ねたアベルは、周囲が止めるのを聞かずに彼女をそばに置くことに決める。その間に葛藤があったりするのだけれど、エリシアの力がアベルの癒しになっていたり、ヤキモキする要素もあった。
二人の綱渡りのような関係は、時にハラハラしたりと目が離せないものが多く、それまで他者をまともに信じられなかったアベルが、エリシアの根気強い説得と愛情により徐々に他人を受け入れることができる展開には、つい前世の自分の境遇と重ね合わせて涙を流したこともある。
最終的にアベルは母親の重い面影を振り払うことができて、エリシアとお互いの気持ちを確かめ合い、そして二人は結婚して暮らしました、というめでたしめでたしのハッピーエンドだった。
私はこの小説が大好きで、ポロポロと涙を流しながらも何度も何度も読み返した。
熱いコメントを送ったことも少なくない。
でも、その小説で唯一許せないキャラがいた。
アベルの母であり、私が転生した悪役女王アルティナだ。
前世の日本で小林いばらとして過ごしていた私は、親元を離れて小学一年生のころから児童養護施設で暮らしていた。
当時は幼く、自分の境遇を理解していなかったこともあるけれど、後から聞いた話では親から放置されていたそうだ。
児童養護施設には様々な事情を抱えた子供たちが暮らしている。
中には虐待されたことのある子供たちもいて、そういう子供たちは心に深い傷を抱えていた。
そんな子供たちと共に成長して、私は児童養護施設を卒業したのだ。
だから、私は余計にアルティナに憤ってしまったのかもしれない。
自分の息子を虐待して死に追いやろうとしたなんて、いくら小説の登場人物だとしてもそんな大人がいることが信じられなかったのだ。
『子供は幸せに生きなければならないんです。不幸な子供なんて、存在してはいけないんですよ』
それは私を育ててくれた、児童養護施設の先生の言葉だ。
私はその言葉を胸に、自分も将来児童養護施設で働きたいと考えて、資格を取得するために福祉施設で働くことが決まった矢先に、事故に遭ってしまったのだ。
「転生するにしても、なんでよりによってアルティナなのよぉおお! いつか息子に処刑されるキャラに転生するなんて……。前世でも、結婚どころか子供もいなかったのに。家族だって……」
はあ、と落ち込んでいても仕方がない。
アルティナに転生したということは、いつか私は死んでしまう。
その未来をどうにかしなければいけない。
「……そうだ。アルティナは悪政で国民を苦しめて、なおかつアベルを虐待したから報復も込めて処刑されるのよね? ……それなら女王として真っ当に国政を担って、アベルを大切に育てれば処刑されなくても済むんじゃない?」
咄嗟に思い付いたことだけれど、良い案かもしれない。
いつまでもベッドの上でグダグダしていても仕方がない。
アベルを救済するためにも動き出そうと、まずは侍女を呼び出すことにした。
「お呼びでしょうか?」
やってきた侍女は、そうとわかるぐらい震えていた。
アルティナは、お世話をしてくれる侍女だろうと使用人だろうと、ひとつでもミスをしたり気に入らないことがあれば容赦なく罰を与えた。よっぽどのことがない限り命を奪うことまではしないが、それでもアルティナに辞めさせられた侍女や使用人の多くは路頭に迷うことになる。
侍女たちからすると、アルティナは恐怖の対象なのだ。
「聞きたいことがあります」
つい前世と同じように敬語で話しかけてしまったのが悪かったのかもしれない。
侍女は大きく目を見開くと、なぜかガタガタと震え出した。
「ど、どうして私にそんな丁寧に話されるのですか? ……も、もしかして私、何かやってしまいましたか?」
「ち、違うのよ。ただ、聞きたいことがあるの。それに答えてくれればいいだけだから」
「わ、私はどうなっても構わないので、家族のことは許してくださいぃぃ」
侍女は両手を組み合わせると、床に頭をつけた。
あまりにも動きが素早すぎて、止める暇もなかった。
「あなたを罰したりはしないわ。私は、ただアベルの居場所が知りたいだけよ」
突然キャラを変えるとこの侍女みたいに余計に怖がられるかもしれない。
だからアルティナっぽく振る舞うと、彼女は分かりやすくホッとした顔になった。
「王子殿下でしたら、離宮にいらっしゃると思います」
「離宮?」
王宮にはいくつかの建物があるから、その内のひとつだろうか。
「それなら、私をそこに案内してちょうだい」
「……え、会われるのですか?」
侍女は信じられないものを見るような顔つきになった。
そのとき、ガツンと頭が殴られたような感覚がして、脳裏に記憶が流れ込んでくる。
『アレは、離宮にでも閉じ込めておきなさい。私の視界に入れないで』
これは、アルティナの記憶だ。この体に転生した時もそうだったのだが、断続的にアルティナの記憶が脳裏に過ぎっていくことがある。
私は痛む頭を押さえながらも、驚いている侍女に命令する。
「いいから早く、アレのところに私を案内しなさい」
「ッ、承知しました!」
そのあと、頭痛は何事もなかったかのように引いていた。
なんだろうとは思ったものの、アルティナの記憶も完全ではない。
生き残るためにも、彼女の記憶は助けになる。
「……でも、肝心な記憶が抜けているのよね。アルティナは、どうしてアベルを虐待していたのかしら」
アルティナの幼少期の記憶やアベルを生んだ前後の記憶だけはなぜかごっそり抜けているのだ。それ以降もまだ断片的にしか思い出せない。
疑問に思うものの、いま考えても仕方のないことだと割り切ることにした。
それからしばらくして、私はアベルとの初対面をすることになったのだが――。
顔を会わせたアベルは、私の姿を見た瞬間に気絶してしまい、会話もできなかった。
よっぽど恐怖していたのだろうと思うのと同時に、アベルをここまで追い詰めたアルティナに改めて怒りが湧いた。
アベルの暮らしていた離宮は酷いところだった。
ろくな手入れもされていない古く朽ち果てた建物に、数人の使用人を残していたにすぎない。
アベルは食事もまともに取れていないのか、五歳にしては体が小さく、立っているのがやっとの様子だった。
いくらなんでも酷すぎるとは思ったものの、それをしたのは私が転生したアルティナだ。
それに、前世に暮らしていた施設にも、似たような境遇の子供たちがいた。
彼らは職員や年上の子供たちにより少しずつ心を開いていったけれど、本来ならそんな光景はないほうがいいに決まっている。
「――私は、思い違いをしていたようね」
私のつぶやきになぜか侍女が震えだす。
でも、そんなことも気にならないぐらい、私は苛立ちと、それから自分に対する不甲斐なさでいっぱいだった。
私がアベルに会いに来たのは、自分の死の運命を回避するためだった。
でも、それはただの自己満足でしかない。
『子供は幸せに生きなければならないんです。不幸な子供なんて、存在してはいけないんですよ』
私を育ててくれた先生の言葉が脳裏を過ぎる。
どうしてこんな大切なことを忘れていたのだろう。
「……先生。私、やってみるわ。アベルを、幸せにしてみせる」
もう私の未来なんて関係なかった。
たとえどんな未来になろうとも、私がアベルを幸せにしてみせる。
それが、私がアルティナに転生した理由なのだから。
◇
私は、まずアベルの生活環境を整えることから始めた。
古い離宮ではなく、王位継承者用の蕾宮を与えた。その話をしたとき臣下たちは驚いていたけれど、アルティナの言葉に反論する者はいなかった。むしろ、やっと陛下も息子のことに興味を持ったのかと安堵する者もいた。
使用人の数も増やして、特に食事には気を遣うように専門知識のある料理人も迎え入れた。
ここが小説の世界だということもあり、食事の味付けは前世とはそう変わらなかった。食事マナーも手づかみということはなくナイフやフォークを使っていて、蕾宮には浴場もあって毎日のお風呂にも困らないだろう。
アベルはいままで放置されていたということもあり、最初は少しずつ食べる量を増やしていくことになった。
困ったのが読み書きがまだ何もできないことだけれど、そこも有能な家庭教師を雇うことによって、少しずつ覚えていけばいいだろう。
でも、それよりも問題は――。
「……どうしたら、アベルと仲良くできるんだろう」
一か月間、なるべくアベルと顔を会わせることにしていた。
だけど、アベルは私の姿を見た瞬間に、気を失ったり逃げてしまったり、言葉を交わす余裕もなかった。
「当然よね。いままで虐げていた人に、心を許すことなんてできないわ」
アベルの記憶には、もうすっかりアルティナに対する恐怖が刷り込まれている。
私がアルティナの姿をしている限り、アベルと信頼関係を築くことはできないかもしれない。
一番いいのは、陰から支援するだけで、自分の姿を見せないことだろう。
「でも、それだと、ずっとアベルは母親に対して恐怖と憎悪を持ったままだわ」
たとえ物語通りに私が処刑されたとしても、アベルの心にはずっと影が付きまとって苦しむことになるだろう。
できれば、それだけは阻止したい。
「アベルに家族からの愛情を知ってほしいわ」
アベルの家族はいまは私だけだ。アベルの父――アルティナの元王配は、罪人として遠くにいて、いまはまだ会いに行くことはできない。
家族からの愛情がすべてではないにしても、幼い心に負った傷は生涯付きまとうこともある。
なるべくアベルには健やかに過ごしてほしい。
そのためにも、アルティナに対する恐怖を少しでも和らげたい。
「私を見ると逃げ出してしまうし、どうしたらいいのかしら」
蕾宮からの帰り道、私は馬車に揺られながらそんなひとりごとを呟いていた。
窓の外に流れる景色は、前世の日本とは全然違った。
宮殿の庭園は広いという言葉だけでは表せないほど広大で、道の先に何が続いているのか思いを馳せるだけでも楽しかった。
景色を堪能していると、頭もすっきりしてきて、ふと妙案を思いつく。
「……アルティナの姿を隠して、アベルに近づいて、少しずつ距離を縮めていけば……。いや、でもそのためにはどうしたら……あ」
アルティナの宮殿に着いたときには、私の頭の中でひとつの作戦が組み上がっていた。
馬車を降りた私は、入り口で出迎えてくれている使用人一同を見渡して、その中で最も近くにいるお仕着せ姿の使用人の前で立ち止まった。
「ねえ、あなた」
顔を上げた彼女の顔は、恐怖で青ざめていた。
私はつい威圧的になりそうになっていた顔に、にぃっと笑みを浮かべる。
すると、使用人はもういまにも倒れそうな様子になってしまい、慌てて笑みを消す。
コホンと咳をしてから、なるべく威圧的にならないように使用人に訊ねる。
「そのお仕着せ、私に貸してくれない?」
「えっ!? い、いますぐここで脱げということですか!? そ、それは、勘弁してくださいぃ」
「あ、違うのよ。予備の服でいいから――って」
顔面蒼白になった使用人は、床に頭を垂れていた。まるで命乞いでもしているかのようだ。
周囲を見渡すと、ほかの使用人も次は自分じゃないのかと震えている。
私は発言を間違えてしまったらしい。
いや、それ以前に、アルティナの顔が私が思っているよりも怖いことを失念していたのだ。
「……もう、そうじゃないのに」
私はただ、アルティナの姿を隠すためにも使用人に変装して、少しでもアベルに近づこうと思っただけだ。
それなのに――。
どうやらアルティナのこの姿はアベルだけではなく、ほかの使用人たちにとっても恐ろしいものだったらしい。
どうしたら誤解が解けるのか。
私はさらに頭を悩ませるのだった。