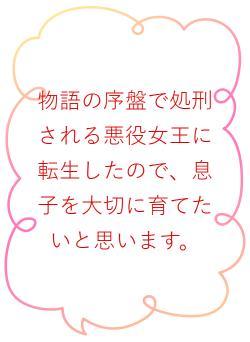身代わりの番ですが、本当の愛は誰にも渡しません。
第一話
「【番】でなくてもかまわない。オレは、心の底からあなたを愛してしまったんだ」
海のような澄んだ碧い瞳は、嘘を言っているようには思えなかった。
その瞳は、まぎれもなく目の前にいるセレサを見つめている。
(ああ、これはもう、間違いないのね……)
彼の言葉に、喜ぶ自分がいる。
自分の内から溢れる思いを、もうセレサは我慢できなかった。
「ディラン」
勢いのまま呼びかける。
一瞬、言葉が喉の奥で絡まった。
だけど、これは必ず伝えなければいけない。
最初は、ただ身代わりで婚姻したに過ぎなかった。
一年という月日の中で、セレサは彼の優しさや温かさを知った。
ディランは、セレサが偽物だということを知っていながらも、大切な宝物のように扱ってくれた。
はじめは隠していた気持ちも、彼のまっすぐな眼差しを見てしまったら、もう隠すことはできなくなる。
「私も、あなたのことが好きよ」
「……本当か?」
疑うような言葉をかけながらも、彼の相好が嬉しそうにほころぶ。
「ええ、あなたを愛しているの」
口にした瞬間、体中が熱くなる。
思ったよりも、緊張していたのかもしれない。
「これは、夢のようだ!」
いつもは冷静沈着なディランが子供のようにはしゃぐ声をあげる。
そのままセレサの腰に手を伸ばし、高い高いするように体を持ち上げてくる。
「ちょっと、ディラン!」
足が空中に浮いて慌てるセレサを地面に降ろすと、彼の逞しい腕にセレサの体は包まれていた。
腰に伸ばされた手に温もりを感じて、その温もりをもう離さないとセレサ自身も手を伸ばす。
お互いがお互いを離すまいとする抱擁は、決意の表れだった。
(絶対に、この温もりは離さないわ)
たとえ何があろうとも、彼のそばに居続けるのだと。
もう誰にも奪わせはしないと。
そして、その日――婚姻をしてから一年後、セレサとディランは本当の意味で結ばれたのだった。
◇◆◇
澄んだ空気と綺麗な星空が魅力的で、観光名所としても名を馳せている、スカイン王国。
魔術師を多く輩出している国としても有名なその国で、セレサはアスター公爵家の長女として生まれた。
公爵家の長女として何不自由ない生活が約束されていたセレサは、三歳のころまで家族の愛情を独占してすくすくと成長した。
そんなセレサの日常に暗雲が立ち込めたのは、次女であるフィーナが生まれたころだろうか。
フィーナはセレサと同じ桜色の髪をしていたが、その瞳は魔力が豊富な証と謂われる「金色」だった。
それを喜んだ両親は、次第にセレサに対する関心が薄まり、フィーナに心頭していくことになった。
セレサのお世話は使用人に任せ、両親はフィーナのことばかり。
甘やかされて育ったフィーナは、いつしかわがままが叶えられて当然の子供に成長していた。
両親の愛情も周りの関心も、フィーナのもの。
両親がセレサに求めるのは、王太子の婚約者として優秀であることのみ。
セレサは常に奪われる人生を送っていた。
フィーナが欲しいといったぬいぐるみもお気に入りのドレスも、誕生日のケーキだって、すべて妹に奪われてきた。
だから、きっと必然だったのだと思う。
「お姉様、羨ましいわ。私も、王太子殿下の婚約者になりたい」
そんなフィーナの言葉により、王太子の婚約者の座まで奪われてしまったのは。
王太子とセレサの婚約は、生まれる前から決まっていたことだった。
セレサが一足先に生まれただけで、フィーナにもその資格はあった。
だから王家は、公爵家からの申し出に悩むこともなく承諾した。
フィーナの瞳が金色だから、というのも大きかったのかもしれない。
幼い頃から王太子に嫁ぐために受けてきた厳しい教育。
真面目に、貞淑に。
両親の愛が得られないのなら、せめてこれだけはと。
いつも優先される妹よりも、優秀でありたいとそう思っていたのに。
その座はあまりにもあっけなく奪われてしまった。
両親はどうしてフィーナのわがままは聞いて、セレサのお願いは聞いてくれないのだろうか。
子供の頃から何度も考えたその答えを、突きつけられたような気がした。
(私は、これからも妹に奪われ続けるのね)
自分の未来には暗雲しかないと、セレサが絶望しかけた頃だった。
スカイン王国に、隣国リュータイン帝国の第三皇子が来訪したのは。
リュータイン帝国の皇族は竜人だ。
竜人の強力な力により帝国を治めており、スカイン王国はかの国の属国でもあった。
竜人には【番】が必要とされていて、皇族は自国だけではなく、他国にまでその【番】を求めにやってくる。
第三皇子のために、王国では連日のようにパーティーが行われた。
王国中から貴族や平民問わず、娘たちが日替わりで集められたそのパーティーにより、第三皇子の【番】は無事に見つかった。
しかもその【番】というのが、驚くことにフィーナだったのだ。
だが――。
「いやよ。どうして私が【番】なの? あんな……あんな冷たい瞳の男に嫁いだら、殺されるに決まっているわっ。……ねえ、セレサお姉様も知っているでしょう?」
フィーナは第三皇子との婚姻を拒んだ。
竜人には、悪い噂があったからだ。
「竜人は、【番】に子供ができたら、殺すのでしょう?」
「……それは、ただの噂よ」
「噂でもいやよ。それに私には、王太子殿下がいるのよ」
噂は噂だと、そう言いきれればよかったのだけれど、竜人の【番】になった娘が早くに亡くなっているのは本当のことだった。
もう十五歳になるのに、いやいやと首を振って駄々をこねる子供のような姿に、セレサはため息をつくことしかできない。
だが、いくらわがままを言おうとも、今回ばかりは両親も簡単に首を振ることはできないようだ。
帝国との関係が悪くなることを恐れているのだろう。
王国としては、帝国に恩を売っておきたい。
そのためにも、第三皇子との婚姻だけは何としても成し遂げたいようだった。
(かわいそうだけど、こればかりはどうしようもないわ)
同情しながらも、どこか胸がすくような気分だった。
いやいやと泣いていたフィーナは、ふと顔を上げた。
泣き腫らした金色の双眸でセレサを見つめると、いいことを思いついた子供のように顔を輝かせた。
「そうだ。お姉様が嫁げばいいのよ」
「……え?」
「だって、お姉様は私と同じ髪色で、身長もたいして変わらないから、きっと顔を隠せば気づかれないわ。ねえ、いいでしょう、お父様?」
「……しかし」
「私はずっとお父様のそばにいたいわ。帝国に嫁いだら会えなくなるのよ? だから、お願い」
父は眉を顰めたが、フィーナのお願い攻撃には抗えなかったようだ。
「わかった。セレサを嫁がせよう」
両親の中ではもう決まってしまったようだった。
フィーナがこっそりと、セレサに聞こえる声で言う。
「今回は、お姉様に譲るわ」
悪戯を企むような声だった。
こうして、セレサは妹の身代わりとして嫁ぐことになった。
それも、リュータイン帝国第三皇子ディランの身代わりの【番】として。
◇
スカイン王国での結婚式は滞りなく終えることができた。
顔はベールで覆われたままだったけれど、ディランには気づかれなかったようだ。
その日の内に、多くの王国民たちに見送られて、セレサとディランを乗せた馬車はスカイン王国を出た。
帝国に向かう馬車の中で、ディランはセレサに告げた。
「帰国したら、パレードがある。そのあと、空中庭園で帝国流の結婚式を行うことになる」
ふと顔をあげる。ベール越しで合った碧い瞳はひんやりとするほど冷たく、こちらを値踏みしているようでもあった。
バレるのを恐れて慌てて俯くが、ディランはそのあと口を開くことなく、馬車の中は静かだった。
帝国の国境を越えて、ひとつ目の村からすでにお祭りムードだった。
どの村や町でもセレサは【番】として歓迎されて、帝都に着く頃には第三皇子の婚姻をお祝いするパレードは人数も増えて盛大になっていた。
第三皇子殿下、おめでとうございます。
妃殿下、帝国にようこそ。
今更、自分が偽物だとは言えない雰囲気だった。
空中庭園は、帝都の中心にあった。
皇族である竜人やその伴侶のみがしか立ち入れないそこで、セレサたちは改めて結婚式を挙げた。
魔法で咲き乱れる青色の花たち。まるで海の中のような光景だったけれど、セレサは感動する余裕なんてなかった。
海のように深い碧い瞳は、セレサに向けられていたが、肝心な言葉はかけられなかった。安堵と共に、不安が押し寄せてくる。
その不安は、初夜の席まで続いた。
竜人にとって、【番】とは替えが効かないものだ。
なぜなら、竜人は【番】との婚姻によって、その力の真価を発揮するからだ。
初夜は、竜人にとって神聖な儀式だ。
その大切な儀式を、偽りの嘘で汚すわけにはいかない。
だから、セレサはとうとう告げることにした。
薄暗い部屋の中、ほのかな明かりに照らされたベッドの上で。
セレサは、自分の正体を明かした。
「私の名前は、セレサです。アスター公爵家の長女で、フィーナの姉の。……私は、あなた様の【番】ではないのです。騙してしまい、申し訳ございません。どんな罰だろうと、甘んじて受けるつもりです」
頭を下げながら紡いだ言葉の後、部屋の中には静寂だけが残った。
怒って殺されるかもしれないと、そうされるだけの罪は犯しているのだと、体を震えさせることしかできなかった。
長いようにも思える静寂の後、ディランの静かな声が聞こえてきた。
「知っている」
予想外の返答に顔を上げると、ディランは海のように深い碧い瞳を細めた。
「竜人は【番】の匂いに敏感だ。だからいくら隠そうとも、無駄だ」
「そ、それでは、どうして私と結婚したのですか?」
「【番】など、いてもいなくても構わない。オレは皇位には興味がないからな。……だから、誰でもよかった」
凪いだ海のように静かな声だった。
彼は表情の変わらない顔のまま、どこか疲れたようにため息をつく。
「父上から【番】を見つけろと言われたからそうしたまでだ。……あなたの妹は、騒がしい女だった。顔を合わせたら、怖い怖いと繰り返して、しまいには泣き出してしまった。だから、どうせ結婚するなら静かなほうがいいと思い、あなたと結婚したんだ」
【番】に対する竜人の執着はすさまじいと聞いたことがあるのに、淡々とした言葉からはそれを感じなかった。
「あなたもいやいや嫁がされたのだろう? 一年は我慢してもらうことになるが、一年経ったら離婚しても構わない。無理強いするつもりはないからな」
離婚したらどうなるのだろうか。
スカイン王国に帰っても、セレサに居場所はない。
それなら、たとえ偽りの婚姻だとしても、セレサはここにいたかった。
「あなた様さえよろしければ、このままおそばにいさせてください」
「……そうか」
ディランは短くうなずくと、その日はそのまま何事もなく眠ることになった。
それからの結婚生活は、静かだったけれど、どこか満ち足りていた。
生家にいたころには味わえなかった日常。
冷たいと思っていた碧い瞳は、実際はそんなことはなく、セレサに向けられる眼差しはいつしか温かくなっていた。
ディランはセレサを冷遇することなく、妻として大切にしてくれた。
だからいつの間にか惹かれていた。
自分は偽物でしかないというのに。
セレサは自分の気持ちを隠して、ディランとの日々を大切に、静かに送っていたのだ。
一年後、ディランから告白されて、やっと本当の意味で結ばれることになった。
これからは、もう、この愛情を手放さないと。
幸せに生きていきたいと、そう思っていた矢先のことだった。
フィーナが帝国にやってきたのは。
「ディラン様は騙されているのです。私の姉が【番】だと偽って、この国に嫁いできました。本当の【番】は、私だというのに。――どうか、姉を追放してください。そして、私を本当の妻にしてくださいませ」
久しぶりに耳にする妹の声は、記憶にあるまま変わっていなかった。自分の言葉には間違いなんてないと、自信に満ちている声。
皇城では少し騒ぎになったが、ディランが相手にしなかったからか、フィーナの言葉が嘘なのだとほとんどの人がそう思った。
お得意のわがままも隣国では通用しないようだ。
だけど――それも、少しの間だけだった。
ある夜、ディランの部屋に向かったセレサは、見てしまったのだ。
ベッドに仰向けに寝転がっているフィーナに覆い被さるようにしている、【番】に対する熱情に支配されそうになっているディランの姿を。
「ディラン」
セレサが呼びかけると、ディランはハッと正気に戻って、慌ててベッドから降りた。
フィーナが勝ち誇った笑みを浮かべる。
(いくらディランが私のことを思ってくれていても、【番】に対する熱情には抗えないのね)
それなら――。
セレサがすることはひとつだけだった。
ディランが苦しむ姿はもう見たくはない。
フィーナのそばに――いや、この国にいる限り、ディランは【番】からは逃れられないだろう。
それならこの国を出て、遠くに行こう。
【番】の力なんて及ばないほど遠くに。
ディランと一緒に生きていけるのであれば、セレサはそれだけでよかった。
海のような澄んだ碧い瞳は、嘘を言っているようには思えなかった。
その瞳は、まぎれもなく目の前にいるセレサを見つめている。
(ああ、これはもう、間違いないのね……)
彼の言葉に、喜ぶ自分がいる。
自分の内から溢れる思いを、もうセレサは我慢できなかった。
「ディラン」
勢いのまま呼びかける。
一瞬、言葉が喉の奥で絡まった。
だけど、これは必ず伝えなければいけない。
最初は、ただ身代わりで婚姻したに過ぎなかった。
一年という月日の中で、セレサは彼の優しさや温かさを知った。
ディランは、セレサが偽物だということを知っていながらも、大切な宝物のように扱ってくれた。
はじめは隠していた気持ちも、彼のまっすぐな眼差しを見てしまったら、もう隠すことはできなくなる。
「私も、あなたのことが好きよ」
「……本当か?」
疑うような言葉をかけながらも、彼の相好が嬉しそうにほころぶ。
「ええ、あなたを愛しているの」
口にした瞬間、体中が熱くなる。
思ったよりも、緊張していたのかもしれない。
「これは、夢のようだ!」
いつもは冷静沈着なディランが子供のようにはしゃぐ声をあげる。
そのままセレサの腰に手を伸ばし、高い高いするように体を持ち上げてくる。
「ちょっと、ディラン!」
足が空中に浮いて慌てるセレサを地面に降ろすと、彼の逞しい腕にセレサの体は包まれていた。
腰に伸ばされた手に温もりを感じて、その温もりをもう離さないとセレサ自身も手を伸ばす。
お互いがお互いを離すまいとする抱擁は、決意の表れだった。
(絶対に、この温もりは離さないわ)
たとえ何があろうとも、彼のそばに居続けるのだと。
もう誰にも奪わせはしないと。
そして、その日――婚姻をしてから一年後、セレサとディランは本当の意味で結ばれたのだった。
◇◆◇
澄んだ空気と綺麗な星空が魅力的で、観光名所としても名を馳せている、スカイン王国。
魔術師を多く輩出している国としても有名なその国で、セレサはアスター公爵家の長女として生まれた。
公爵家の長女として何不自由ない生活が約束されていたセレサは、三歳のころまで家族の愛情を独占してすくすくと成長した。
そんなセレサの日常に暗雲が立ち込めたのは、次女であるフィーナが生まれたころだろうか。
フィーナはセレサと同じ桜色の髪をしていたが、その瞳は魔力が豊富な証と謂われる「金色」だった。
それを喜んだ両親は、次第にセレサに対する関心が薄まり、フィーナに心頭していくことになった。
セレサのお世話は使用人に任せ、両親はフィーナのことばかり。
甘やかされて育ったフィーナは、いつしかわがままが叶えられて当然の子供に成長していた。
両親の愛情も周りの関心も、フィーナのもの。
両親がセレサに求めるのは、王太子の婚約者として優秀であることのみ。
セレサは常に奪われる人生を送っていた。
フィーナが欲しいといったぬいぐるみもお気に入りのドレスも、誕生日のケーキだって、すべて妹に奪われてきた。
だから、きっと必然だったのだと思う。
「お姉様、羨ましいわ。私も、王太子殿下の婚約者になりたい」
そんなフィーナの言葉により、王太子の婚約者の座まで奪われてしまったのは。
王太子とセレサの婚約は、生まれる前から決まっていたことだった。
セレサが一足先に生まれただけで、フィーナにもその資格はあった。
だから王家は、公爵家からの申し出に悩むこともなく承諾した。
フィーナの瞳が金色だから、というのも大きかったのかもしれない。
幼い頃から王太子に嫁ぐために受けてきた厳しい教育。
真面目に、貞淑に。
両親の愛が得られないのなら、せめてこれだけはと。
いつも優先される妹よりも、優秀でありたいとそう思っていたのに。
その座はあまりにもあっけなく奪われてしまった。
両親はどうしてフィーナのわがままは聞いて、セレサのお願いは聞いてくれないのだろうか。
子供の頃から何度も考えたその答えを、突きつけられたような気がした。
(私は、これからも妹に奪われ続けるのね)
自分の未来には暗雲しかないと、セレサが絶望しかけた頃だった。
スカイン王国に、隣国リュータイン帝国の第三皇子が来訪したのは。
リュータイン帝国の皇族は竜人だ。
竜人の強力な力により帝国を治めており、スカイン王国はかの国の属国でもあった。
竜人には【番】が必要とされていて、皇族は自国だけではなく、他国にまでその【番】を求めにやってくる。
第三皇子のために、王国では連日のようにパーティーが行われた。
王国中から貴族や平民問わず、娘たちが日替わりで集められたそのパーティーにより、第三皇子の【番】は無事に見つかった。
しかもその【番】というのが、驚くことにフィーナだったのだ。
だが――。
「いやよ。どうして私が【番】なの? あんな……あんな冷たい瞳の男に嫁いだら、殺されるに決まっているわっ。……ねえ、セレサお姉様も知っているでしょう?」
フィーナは第三皇子との婚姻を拒んだ。
竜人には、悪い噂があったからだ。
「竜人は、【番】に子供ができたら、殺すのでしょう?」
「……それは、ただの噂よ」
「噂でもいやよ。それに私には、王太子殿下がいるのよ」
噂は噂だと、そう言いきれればよかったのだけれど、竜人の【番】になった娘が早くに亡くなっているのは本当のことだった。
もう十五歳になるのに、いやいやと首を振って駄々をこねる子供のような姿に、セレサはため息をつくことしかできない。
だが、いくらわがままを言おうとも、今回ばかりは両親も簡単に首を振ることはできないようだ。
帝国との関係が悪くなることを恐れているのだろう。
王国としては、帝国に恩を売っておきたい。
そのためにも、第三皇子との婚姻だけは何としても成し遂げたいようだった。
(かわいそうだけど、こればかりはどうしようもないわ)
同情しながらも、どこか胸がすくような気分だった。
いやいやと泣いていたフィーナは、ふと顔を上げた。
泣き腫らした金色の双眸でセレサを見つめると、いいことを思いついた子供のように顔を輝かせた。
「そうだ。お姉様が嫁げばいいのよ」
「……え?」
「だって、お姉様は私と同じ髪色で、身長もたいして変わらないから、きっと顔を隠せば気づかれないわ。ねえ、いいでしょう、お父様?」
「……しかし」
「私はずっとお父様のそばにいたいわ。帝国に嫁いだら会えなくなるのよ? だから、お願い」
父は眉を顰めたが、フィーナのお願い攻撃には抗えなかったようだ。
「わかった。セレサを嫁がせよう」
両親の中ではもう決まってしまったようだった。
フィーナがこっそりと、セレサに聞こえる声で言う。
「今回は、お姉様に譲るわ」
悪戯を企むような声だった。
こうして、セレサは妹の身代わりとして嫁ぐことになった。
それも、リュータイン帝国第三皇子ディランの身代わりの【番】として。
◇
スカイン王国での結婚式は滞りなく終えることができた。
顔はベールで覆われたままだったけれど、ディランには気づかれなかったようだ。
その日の内に、多くの王国民たちに見送られて、セレサとディランを乗せた馬車はスカイン王国を出た。
帝国に向かう馬車の中で、ディランはセレサに告げた。
「帰国したら、パレードがある。そのあと、空中庭園で帝国流の結婚式を行うことになる」
ふと顔をあげる。ベール越しで合った碧い瞳はひんやりとするほど冷たく、こちらを値踏みしているようでもあった。
バレるのを恐れて慌てて俯くが、ディランはそのあと口を開くことなく、馬車の中は静かだった。
帝国の国境を越えて、ひとつ目の村からすでにお祭りムードだった。
どの村や町でもセレサは【番】として歓迎されて、帝都に着く頃には第三皇子の婚姻をお祝いするパレードは人数も増えて盛大になっていた。
第三皇子殿下、おめでとうございます。
妃殿下、帝国にようこそ。
今更、自分が偽物だとは言えない雰囲気だった。
空中庭園は、帝都の中心にあった。
皇族である竜人やその伴侶のみがしか立ち入れないそこで、セレサたちは改めて結婚式を挙げた。
魔法で咲き乱れる青色の花たち。まるで海の中のような光景だったけれど、セレサは感動する余裕なんてなかった。
海のように深い碧い瞳は、セレサに向けられていたが、肝心な言葉はかけられなかった。安堵と共に、不安が押し寄せてくる。
その不安は、初夜の席まで続いた。
竜人にとって、【番】とは替えが効かないものだ。
なぜなら、竜人は【番】との婚姻によって、その力の真価を発揮するからだ。
初夜は、竜人にとって神聖な儀式だ。
その大切な儀式を、偽りの嘘で汚すわけにはいかない。
だから、セレサはとうとう告げることにした。
薄暗い部屋の中、ほのかな明かりに照らされたベッドの上で。
セレサは、自分の正体を明かした。
「私の名前は、セレサです。アスター公爵家の長女で、フィーナの姉の。……私は、あなた様の【番】ではないのです。騙してしまい、申し訳ございません。どんな罰だろうと、甘んじて受けるつもりです」
頭を下げながら紡いだ言葉の後、部屋の中には静寂だけが残った。
怒って殺されるかもしれないと、そうされるだけの罪は犯しているのだと、体を震えさせることしかできなかった。
長いようにも思える静寂の後、ディランの静かな声が聞こえてきた。
「知っている」
予想外の返答に顔を上げると、ディランは海のように深い碧い瞳を細めた。
「竜人は【番】の匂いに敏感だ。だからいくら隠そうとも、無駄だ」
「そ、それでは、どうして私と結婚したのですか?」
「【番】など、いてもいなくても構わない。オレは皇位には興味がないからな。……だから、誰でもよかった」
凪いだ海のように静かな声だった。
彼は表情の変わらない顔のまま、どこか疲れたようにため息をつく。
「父上から【番】を見つけろと言われたからそうしたまでだ。……あなたの妹は、騒がしい女だった。顔を合わせたら、怖い怖いと繰り返して、しまいには泣き出してしまった。だから、どうせ結婚するなら静かなほうがいいと思い、あなたと結婚したんだ」
【番】に対する竜人の執着はすさまじいと聞いたことがあるのに、淡々とした言葉からはそれを感じなかった。
「あなたもいやいや嫁がされたのだろう? 一年は我慢してもらうことになるが、一年経ったら離婚しても構わない。無理強いするつもりはないからな」
離婚したらどうなるのだろうか。
スカイン王国に帰っても、セレサに居場所はない。
それなら、たとえ偽りの婚姻だとしても、セレサはここにいたかった。
「あなた様さえよろしければ、このままおそばにいさせてください」
「……そうか」
ディランは短くうなずくと、その日はそのまま何事もなく眠ることになった。
それからの結婚生活は、静かだったけれど、どこか満ち足りていた。
生家にいたころには味わえなかった日常。
冷たいと思っていた碧い瞳は、実際はそんなことはなく、セレサに向けられる眼差しはいつしか温かくなっていた。
ディランはセレサを冷遇することなく、妻として大切にしてくれた。
だからいつの間にか惹かれていた。
自分は偽物でしかないというのに。
セレサは自分の気持ちを隠して、ディランとの日々を大切に、静かに送っていたのだ。
一年後、ディランから告白されて、やっと本当の意味で結ばれることになった。
これからは、もう、この愛情を手放さないと。
幸せに生きていきたいと、そう思っていた矢先のことだった。
フィーナが帝国にやってきたのは。
「ディラン様は騙されているのです。私の姉が【番】だと偽って、この国に嫁いできました。本当の【番】は、私だというのに。――どうか、姉を追放してください。そして、私を本当の妻にしてくださいませ」
久しぶりに耳にする妹の声は、記憶にあるまま変わっていなかった。自分の言葉には間違いなんてないと、自信に満ちている声。
皇城では少し騒ぎになったが、ディランが相手にしなかったからか、フィーナの言葉が嘘なのだとほとんどの人がそう思った。
お得意のわがままも隣国では通用しないようだ。
だけど――それも、少しの間だけだった。
ある夜、ディランの部屋に向かったセレサは、見てしまったのだ。
ベッドに仰向けに寝転がっているフィーナに覆い被さるようにしている、【番】に対する熱情に支配されそうになっているディランの姿を。
「ディラン」
セレサが呼びかけると、ディランはハッと正気に戻って、慌ててベッドから降りた。
フィーナが勝ち誇った笑みを浮かべる。
(いくらディランが私のことを思ってくれていても、【番】に対する熱情には抗えないのね)
それなら――。
セレサがすることはひとつだけだった。
ディランが苦しむ姿はもう見たくはない。
フィーナのそばに――いや、この国にいる限り、ディランは【番】からは逃れられないだろう。
それならこの国を出て、遠くに行こう。
【番】の力なんて及ばないほど遠くに。
ディランと一緒に生きていけるのであれば、セレサはそれだけでよかった。