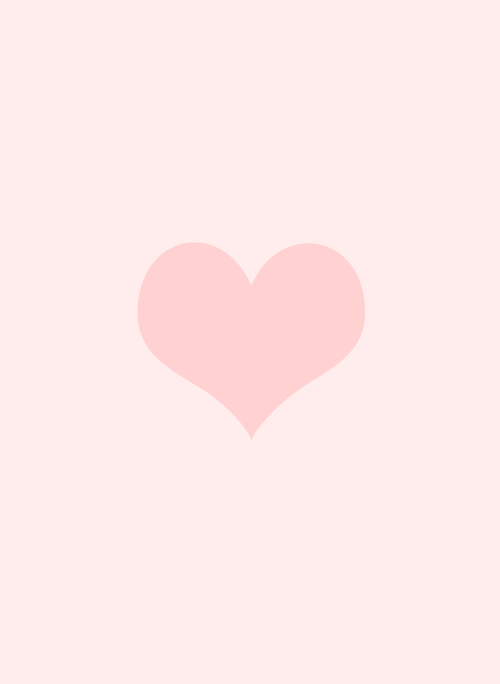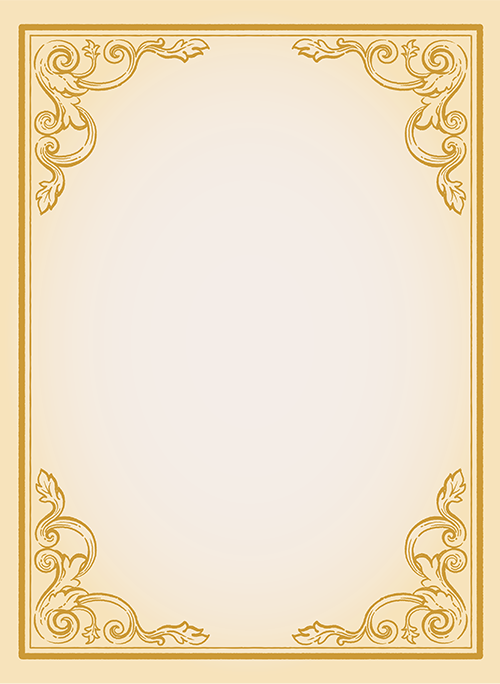孤独な令嬢と、ある教師の話。
遂に学園入学の日が明日に迫る。オリヴィアはリカと共に荷造りを進めていた。基本的に制服で過ごすだろうし、リカも連れて行けないから自分で脱ぎ着出来るタイプのドレスばかりなので鞄に詰めてもあまり嵩張らない。問題は服ではなく書物の方だった。しかし置いていったら父か姉によって処分されてしまう。だからどれも置いて行くことは出来ず、結局鞄の数が多くなってしまい馬車まで運ぶのに一苦労だった。
馬車の側には試験の日に同行してくれた若い騎士が控えていた。今回も彼が道中の護衛をしてくれるらしい。とても無口でオリヴィアはどんな声だったか思い出せないほどだが、リカはあの日以来時折話すようで「真面目で、まともな人ですよ」と教えてくれた。名前はオリバーと言うらしい。常々使用人の勤務態度に関し不満を抱いているリカが断言するということは、警戒する必要のない人なのだろう。彼は軽々と荷物を馬車に運び込んでくれる。細身に見えて力持ちのようだ。
「…お嬢様、落ち着いた頃にお手紙書いても良いですか?」
「ええ、勿論」
リカは今日付で辞めると父に伝えている。オリヴィアが居なくなった途端辞めることを咎められることもなく、紹介状も書いてもらってと教えてくれた。
「これで紹介状書かないとか言い出したら、然るべき機関に訴えてやろうかと思いましたよ。旦那様、そういうところだけはまともなんですよね」
辞めるとはいえ雇い主に対して辛辣なリカにオリヴィアの方がヒヤヒヤした。側にいたオリバーも小さく頷き同意していた。すると2人は互いに見つめ合い、リカだけがにっこりと笑う。この2人、オリヴィアの知らないうちに随分と仲良くなっているらしい。そしてオリバーもリカに負けず劣らず怖いもの知らずで、「まともな」感性を持っている。仲良くなるはずであった。何故だろう、根拠もないのにいつの日か「良い知らせ」が聞ける予感がしたオリヴィアだった。いよいよ時間が迫っているとオリバーに教えられ、後ろ髪引かれる思いで馬車に乗り込んだ。見送りは当然誰も居ない。
こうしてオリヴィアは12年間育った邸を後にしたのだった。