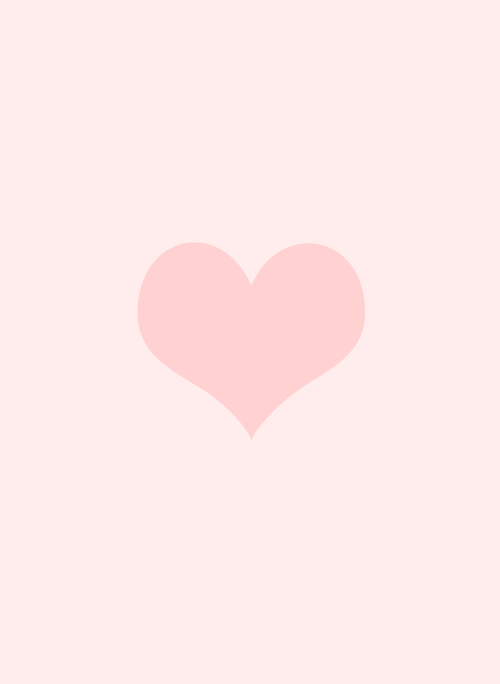白い結婚2年目に白ネコになったら、冷血王と噂の旦那様との溺愛生活がはじまりました
最終回表 ユリアside/ヴァレンスside
「ユリア……」
そうして――ヴァレンスがそっと口づけてくる。
――ふわりと、暖かな春のような光と風がお互いを中心にふわりと巻き起こった。
「なんだ?」
「これは……?」
しばらくすると、光の粒子がキラキラと私たちを取り囲む。
なんだか幻想的な光景になっていた。
「綺麗……」
「ああ、綺麗だな……」
ヴァレンス様がふわりと笑った。
「――?」
彼がそっと私の耳元に近付いてくる。
「ああ、ユリア――ネコのお前のままでも十分可愛かったが……」
彼に囁かれ、私ははっと気づいた。
(ネコ耳が人間の耳に戻っている……!)
見れば尻尾も消えているではないか――。
「どういう理由かは分からないが――ちゃんと人間に戻れたようだな」
「は……はい……! そうみたいですね……!」
少しだけ名残惜しい気もするが、ちゃんと人間の姿に戻れてほっとする。
私たちは結ばれたまま、しばらく過ごす。
彼が私の髪を何度も梳いてくる。
「初めてで疲れただろう? 今日は眠ると良い……」
「はい……」
言われた通り、なんだか眠くてしょうがなかった。
彼の分身が身体の中から出て行くと、少しだけ寂しさもある。
そうして――彼がまた私の唇をそっと塞いできた。
優しい優しい口付け。
「どんな姿のお前でも愛しているよ――ユリア……」
冷血王と呼ばれる彼の――とっても温かな言葉を聞きながら――初めて夫婦になった日の私は、とっても幸せな気持ちに包みこまれながら眠りに就いたのだった。
***
ユリアが眠りに就いた直後――。
数年前――王位簒奪のために叔父の寝首をかく際以上の緊張感が彼を支配していたと言えよう。
(頼れる夫の振るまいができただろうか……?)
そうして――。
「ユリア、俺の妻になってくれて――本当にありがとう……」
人間の姿に戻った彼女に、彼は再び口づけたのだった。
空には上弦の月がかかっているのだった。
***
そうして――――約半月後。
王妃の部屋の窓辺に立ち、天にいる最高神へと向かって、日課である祈りを捧げていると――。
「ユリア、今日も祈りか?」
「あ……」
振り向くと、そこには大好きな夫の姿があった。
これまでの二年とは違う。
彼の姿を見ると――これから起こる出来事に対して、気恥ずかしいやら嬉しいやら――期待で胸がドキドキと高鳴っていく。
彼が私に近付いてきて、私の白髪ひと房にちゅっと口付けを落としてくる。
「ユリア……」
「ヴァレンス様……」
今までと違うのは――そこで彼が私に口付けを落としてくれて――。
そうして、お姫様抱っこをしてベッドに連れて行ってくれるところだ。
丁寧な所作で夜着の薄衣を脱がされると――彼との夜の営みになる。
――初めて結ばれて以来、私たちは順調に愛を育んでいた。
「ああ、ユリア……いつも伝えられているが……」
至極幸福に満ちた声でヴァレンスは続ける。
「ネコだろうが人だろうが……年上だろうが年下だろうが……俺はお前のことを愛しているよ……今度はずっと俺のそばにいてくれ……愛しているよ、俺の白猫――ユリア」
――大好きな相手からそう言われて、とっても幸せでしょうがない。
だけれど――問題がいくつかあった。
一つは、私の頭の上のネコ耳と尻尾が時々ひょっこり現われること。
(だけれど、実害はないし、ヴァレンス様も気に入ってくれてるみたいだから良しとしましょう)
二つ目は――。
(お部屋の中がキラキラした宝石やドレスなんかの贈り物でいっぱいなのはさておき……ヴァレンス様に慈しまれるのは幸せで幸せでしょうがないのだけれど……)
三つ目――最大の問題は――。
「ユリア……すまない俺は我慢弱い男のようで――良かったら、もう一度、お前と……」
そう――。
(ヴァレンス様には終わりがない……!)
――毎日毎日私が眠りに就くまで――延々と夜の営みが続くのだ。
あれだけ子どもが出来ないで側室でも娶れと言われていたはずなのに、近頃では――。
『御子が見れるのも間近でしょう』
そんな風に言われている。
ついでに言えば――。
後日、ヴァレンス様の側室の話が上がっていた公爵令嬢が現われて、ドギマギしたりもしたけれど―ー。
『ああ……! やっと、ユリア様にお近づきになれる……! ヴァレンス陛下ったら、男だろうと女だろうとなかなか人間をユリア様に近づけたがらなかったのですよ……!』
『――え?』
(――ヴァレンス様と私がなんとか結ばれるようにと発破をかけるために、周囲も側室の話を持ち出したりして危機感を煽っていたらしい……)
そんなこんなで私たち夫婦は幸せな生活を送っていたのだった。
「さて、ユリア――」
彼の一声で私は現実に思考を戻す。
「愛しているよ、ユリア――さあ――」
そうして再び彼に身体を捧げる。
そう思った瞬間――。
「なんだ……?」
目映い光に包みこまれる。
(この感じは……!?)
あまりのまぶしさに目を開けられない。
しばらくして光が収束していく。
そうして、私ははっと夜空を見上げた。
(もしかして……!)
――今日は満月だった。
(まさか……!?)
また私は白猫になってしまったのだろうか――!?
戦々恐々と自身の身体を見るが――。
「あれ……?」
どうやら私の身体には異変がないようだった。
「ヴァレンス様、今回は大丈夫なようで――」
そのとき――。
私は相手の異変に気づいた。
白く乱れたベッドの上――そこにいたのは――。
「ヴァレンス様……!?」
「にゃお……?」
――ヴァレンス様の半身だとかいう黒猫の姿だった。
「今度はヴァレンス様が完全な黒猫ちゃんに……!?」
一瞬動揺したが――。
ネコは仕草で私に落ち着けと伝えてくる。
なんとなく相手が話していることが分かった。
(私の時と同じような対処で元に戻るから安心しろ……そんな風に言っているみたい)
それなら安心だと、私はほっと胸をなで下ろす。
そうして、ふわふわの黒猫を私はそっと腕の中に抱き寄せた。
「ヴァレンス様可愛い」
「にゃあ……」
頬ずりすると、黒猫ヴァレンス様もまんざらではないようだった。
私は彼に伝える。
「私が元に戻して差し上げます……! だけれど、その前に……!」
自然と笑みがこぼれた。
「にゃ?」
(最近は――ヴァレンス様に翻弄されっぱなしだったけれど……)
「私が大好きなヴァレンス様をたっぷり可愛がってさしあげます!!」
「にゃ? にゃ……」
黒猫のもふもふした頭や顎や背中を撫でさする。
「にゃあああんっ……」
――その晩、黒猫の恍惚とした叫びが城内には響き渡ったのだった。
翌朝、人間に戻ったヴァレンスから――夜に可愛がられ返すのは――また別の話である……。
***
大陸の北東・セルツェ王国。
叔父から王位を簒奪した冷血王ヴァレンスには魔力がなく、聖女ユリアを娶ったと伝えられている。
ヴァレンスは人間に対しても動物に対しても容赦がない人物だとの伝承が残っており、満月の頃になると度々、城内にネコの叫びが響いたという。
妻のユリアは清廉潔白な人物であり、ヴァレンスが悪行に手を染めると――まるでネコのように失踪し、王が正気に戻ると城に戻って加護を授けたと――古文書では伝えられている。
***
二十年近く前――。
薄暗くて狭い部屋の中、小さな黒猫の世話を白い成猫がしていた。
その側には、流麗な黒髪の少年の姿があった。
綺麗な身なりをしているが――数日間食べ物を与えられておらず、ぼんやりと過ごしていた。
「良いな、黒猫の君には仲間がいて……僕は叔父上に嫌われて邪魔者扱いされて、城の皆に腫れ物扱いされて……いつも暗いところに追いやられてばかりだ……」
少年が物心ついた時から現われるようになった黒猫は、白猫に甘やかされて幸せそうにしている。
それがひどく羨ましかった。
そんな中、白猫が少年の頬の涙の跡をペロペロと舐めてくる。
「ふふっ、くすぐったいな……」
「にゃあ……」
少年よりも年上の白猫も、彼が生まれた時からそばにいてくれる唯一無二の存在だ。
何かを話しても否定してくることはなく、いつも少年を肯定してくれる優しい優しいネコ。
だけれど、彼女もあまり良い食事は与えられていないのか――やせっぽちの姿になってしまっていた。
「黒猫くんと白猫のお姉さんはさ、年が離れているけれど、あれなのかな? 運命の番ってやつなのかな? 親子に見えなくもないんだけれど……なんでだか、そんな風に思うんだよね……僕の夢かな」
痩せ衰えた白猫は、じっと少年の姿を見ていた。
「……ねえ、白猫のお姉さん、僕がこの世の中で信じられるのは君だけだ。きっと、その黒猫くんにとってもそうだと思う。もしあなたが死んじゃったら、黒猫君が可哀想だよ、だからどうか――」
――生きて。
――僕のためにとは、少年は言わなかった。
すると――。
『私も優しい貴方を愛しています。いつか貴方のそばにいきます。だから、黒猫と共に強く生き抜いて』
なぜだか白猫がそんな風に語ってきている気がした。
そのとき――。
衰弱した白猫はどこに力が残っていたのか、その場を駆けて、窓の外へと飛び出した。
「あ――! 待って、行かないで! 今のままだと死んじゃうよ!」
だけれど、雪の中――白猫が少年の元に帰ってくることは二度となかった。
待てど暮らせど、帰ってこない。
やっと食事を与えられた頃――。
黒髪長髪の人物が――少年の前に姿を現した。
『未来の王よ――お前の育ての親からの願いを聞いて、私はここにやってきた』
後に魔術の師となる人物がそう問いかけてくる。
『未来の王?』
『ああ。そうだ――お前の願いはなんだ? 白猫の命をかけた願いを叶えるための手助けをしよう』
『白猫が命をかけて?』
『ああ……お前のことを気遣っていたよ』
――ネコがしゃべるわけないだろう、とかそんなことは思わなかった。
人間よりもあの白猫の方が遙かに信用できたのだ。
魔術師の言う言葉はきっと本当だろうと、少年は漠然と思った。
『王だとか興味がありません。叔父上は僕を殺す機会ばかりをうかがってくる。だけど、もし願いがあるとするならば……――』
白猫の言葉を思い返す。
『私も優しい貴方を愛しています。いつか貴方のそばにいきます。だから、黒猫と共に強く生き抜いて』
少年の紫水晶の瞳に決意の光が宿る。
『僕を育ててくれた、親代わりの白猫にまた会いたい……そのために強くなって、生き延びたい』
その願いを魔術師は聞き入れた。
白猫の命がけの願いと少年の祈りは、数年後に叶えられ、彼らは再び運命の再会を果たす。
――ネコと人間――義理の親子という間柄ではなく――。
――人間同士の夫婦として。
「ユリア……」
そうして――ヴァレンスがそっと口づけてくる。
――ふわりと、暖かな春のような光と風がお互いを中心にふわりと巻き起こった。
「なんだ?」
「これは……?」
しばらくすると、光の粒子がキラキラと私たちを取り囲む。
なんだか幻想的な光景になっていた。
「綺麗……」
「ああ、綺麗だな……」
ヴァレンス様がふわりと笑った。
「――?」
彼がそっと私の耳元に近付いてくる。
「ああ、ユリア――ネコのお前のままでも十分可愛かったが……」
彼に囁かれ、私ははっと気づいた。
(ネコ耳が人間の耳に戻っている……!)
見れば尻尾も消えているではないか――。
「どういう理由かは分からないが――ちゃんと人間に戻れたようだな」
「は……はい……! そうみたいですね……!」
少しだけ名残惜しい気もするが、ちゃんと人間の姿に戻れてほっとする。
私たちは結ばれたまま、しばらく過ごす。
彼が私の髪を何度も梳いてくる。
「初めてで疲れただろう? 今日は眠ると良い……」
「はい……」
言われた通り、なんだか眠くてしょうがなかった。
彼の分身が身体の中から出て行くと、少しだけ寂しさもある。
そうして――彼がまた私の唇をそっと塞いできた。
優しい優しい口付け。
「どんな姿のお前でも愛しているよ――ユリア……」
冷血王と呼ばれる彼の――とっても温かな言葉を聞きながら――初めて夫婦になった日の私は、とっても幸せな気持ちに包みこまれながら眠りに就いたのだった。
***
ユリアが眠りに就いた直後――。
数年前――王位簒奪のために叔父の寝首をかく際以上の緊張感が彼を支配していたと言えよう。
(頼れる夫の振るまいができただろうか……?)
そうして――。
「ユリア、俺の妻になってくれて――本当にありがとう……」
人間の姿に戻った彼女に、彼は再び口づけたのだった。
空には上弦の月がかかっているのだった。
***
そうして――――約半月後。
王妃の部屋の窓辺に立ち、天にいる最高神へと向かって、日課である祈りを捧げていると――。
「ユリア、今日も祈りか?」
「あ……」
振り向くと、そこには大好きな夫の姿があった。
これまでの二年とは違う。
彼の姿を見ると――これから起こる出来事に対して、気恥ずかしいやら嬉しいやら――期待で胸がドキドキと高鳴っていく。
彼が私に近付いてきて、私の白髪ひと房にちゅっと口付けを落としてくる。
「ユリア……」
「ヴァレンス様……」
今までと違うのは――そこで彼が私に口付けを落としてくれて――。
そうして、お姫様抱っこをしてベッドに連れて行ってくれるところだ。
丁寧な所作で夜着の薄衣を脱がされると――彼との夜の営みになる。
――初めて結ばれて以来、私たちは順調に愛を育んでいた。
「ああ、ユリア……いつも伝えられているが……」
至極幸福に満ちた声でヴァレンスは続ける。
「ネコだろうが人だろうが……年上だろうが年下だろうが……俺はお前のことを愛しているよ……今度はずっと俺のそばにいてくれ……愛しているよ、俺の白猫――ユリア」
――大好きな相手からそう言われて、とっても幸せでしょうがない。
だけれど――問題がいくつかあった。
一つは、私の頭の上のネコ耳と尻尾が時々ひょっこり現われること。
(だけれど、実害はないし、ヴァレンス様も気に入ってくれてるみたいだから良しとしましょう)
二つ目は――。
(お部屋の中がキラキラした宝石やドレスなんかの贈り物でいっぱいなのはさておき……ヴァレンス様に慈しまれるのは幸せで幸せでしょうがないのだけれど……)
三つ目――最大の問題は――。
「ユリア……すまない俺は我慢弱い男のようで――良かったら、もう一度、お前と……」
そう――。
(ヴァレンス様には終わりがない……!)
――毎日毎日私が眠りに就くまで――延々と夜の営みが続くのだ。
あれだけ子どもが出来ないで側室でも娶れと言われていたはずなのに、近頃では――。
『御子が見れるのも間近でしょう』
そんな風に言われている。
ついでに言えば――。
後日、ヴァレンス様の側室の話が上がっていた公爵令嬢が現われて、ドギマギしたりもしたけれど―ー。
『ああ……! やっと、ユリア様にお近づきになれる……! ヴァレンス陛下ったら、男だろうと女だろうとなかなか人間をユリア様に近づけたがらなかったのですよ……!』
『――え?』
(――ヴァレンス様と私がなんとか結ばれるようにと発破をかけるために、周囲も側室の話を持ち出したりして危機感を煽っていたらしい……)
そんなこんなで私たち夫婦は幸せな生活を送っていたのだった。
「さて、ユリア――」
彼の一声で私は現実に思考を戻す。
「愛しているよ、ユリア――さあ――」
そうして再び彼に身体を捧げる。
そう思った瞬間――。
「なんだ……?」
目映い光に包みこまれる。
(この感じは……!?)
あまりのまぶしさに目を開けられない。
しばらくして光が収束していく。
そうして、私ははっと夜空を見上げた。
(もしかして……!)
――今日は満月だった。
(まさか……!?)
また私は白猫になってしまったのだろうか――!?
戦々恐々と自身の身体を見るが――。
「あれ……?」
どうやら私の身体には異変がないようだった。
「ヴァレンス様、今回は大丈夫なようで――」
そのとき――。
私は相手の異変に気づいた。
白く乱れたベッドの上――そこにいたのは――。
「ヴァレンス様……!?」
「にゃお……?」
――ヴァレンス様の半身だとかいう黒猫の姿だった。
「今度はヴァレンス様が完全な黒猫ちゃんに……!?」
一瞬動揺したが――。
ネコは仕草で私に落ち着けと伝えてくる。
なんとなく相手が話していることが分かった。
(私の時と同じような対処で元に戻るから安心しろ……そんな風に言っているみたい)
それなら安心だと、私はほっと胸をなで下ろす。
そうして、ふわふわの黒猫を私はそっと腕の中に抱き寄せた。
「ヴァレンス様可愛い」
「にゃあ……」
頬ずりすると、黒猫ヴァレンス様もまんざらではないようだった。
私は彼に伝える。
「私が元に戻して差し上げます……! だけれど、その前に……!」
自然と笑みがこぼれた。
「にゃ?」
(最近は――ヴァレンス様に翻弄されっぱなしだったけれど……)
「私が大好きなヴァレンス様をたっぷり可愛がってさしあげます!!」
「にゃ? にゃ……」
黒猫のもふもふした頭や顎や背中を撫でさする。
「にゃあああんっ……」
――その晩、黒猫の恍惚とした叫びが城内には響き渡ったのだった。
翌朝、人間に戻ったヴァレンスから――夜に可愛がられ返すのは――また別の話である……。
***
大陸の北東・セルツェ王国。
叔父から王位を簒奪した冷血王ヴァレンスには魔力がなく、聖女ユリアを娶ったと伝えられている。
ヴァレンスは人間に対しても動物に対しても容赦がない人物だとの伝承が残っており、満月の頃になると度々、城内にネコの叫びが響いたという。
妻のユリアは清廉潔白な人物であり、ヴァレンスが悪行に手を染めると――まるでネコのように失踪し、王が正気に戻ると城に戻って加護を授けたと――古文書では伝えられている。
***
二十年近く前――。
薄暗くて狭い部屋の中、小さな黒猫の世話を白い成猫がしていた。
その側には、流麗な黒髪の少年の姿があった。
綺麗な身なりをしているが――数日間食べ物を与えられておらず、ぼんやりと過ごしていた。
「良いな、黒猫の君には仲間がいて……僕は叔父上に嫌われて邪魔者扱いされて、城の皆に腫れ物扱いされて……いつも暗いところに追いやられてばかりだ……」
少年が物心ついた時から現われるようになった黒猫は、白猫に甘やかされて幸せそうにしている。
それがひどく羨ましかった。
そんな中、白猫が少年の頬の涙の跡をペロペロと舐めてくる。
「ふふっ、くすぐったいな……」
「にゃあ……」
少年よりも年上の白猫も、彼が生まれた時からそばにいてくれる唯一無二の存在だ。
何かを話しても否定してくることはなく、いつも少年を肯定してくれる優しい優しいネコ。
だけれど、彼女もあまり良い食事は与えられていないのか――やせっぽちの姿になってしまっていた。
「黒猫くんと白猫のお姉さんはさ、年が離れているけれど、あれなのかな? 運命の番ってやつなのかな? 親子に見えなくもないんだけれど……なんでだか、そんな風に思うんだよね……僕の夢かな」
痩せ衰えた白猫は、じっと少年の姿を見ていた。
「……ねえ、白猫のお姉さん、僕がこの世の中で信じられるのは君だけだ。きっと、その黒猫くんにとってもそうだと思う。もしあなたが死んじゃったら、黒猫君が可哀想だよ、だからどうか――」
――生きて。
――僕のためにとは、少年は言わなかった。
すると――。
『私も優しい貴方を愛しています。いつか貴方のそばにいきます。だから、黒猫と共に強く生き抜いて』
なぜだか白猫がそんな風に語ってきている気がした。
そのとき――。
衰弱した白猫はどこに力が残っていたのか、その場を駆けて、窓の外へと飛び出した。
「あ――! 待って、行かないで! 今のままだと死んじゃうよ!」
だけれど、雪の中――白猫が少年の元に帰ってくることは二度となかった。
待てど暮らせど、帰ってこない。
やっと食事を与えられた頃――。
黒髪長髪の人物が――少年の前に姿を現した。
『未来の王よ――お前の育ての親からの願いを聞いて、私はここにやってきた』
後に魔術の師となる人物がそう問いかけてくる。
『未来の王?』
『ああ。そうだ――お前の願いはなんだ? 白猫の命をかけた願いを叶えるための手助けをしよう』
『白猫が命をかけて?』
『ああ……お前のことを気遣っていたよ』
――ネコがしゃべるわけないだろう、とかそんなことは思わなかった。
人間よりもあの白猫の方が遙かに信用できたのだ。
魔術師の言う言葉はきっと本当だろうと、少年は漠然と思った。
『王だとか興味がありません。叔父上は僕を殺す機会ばかりをうかがってくる。だけど、もし願いがあるとするならば……――』
白猫の言葉を思い返す。
『私も優しい貴方を愛しています。いつか貴方のそばにいきます。だから、黒猫と共に強く生き抜いて』
少年の紫水晶の瞳に決意の光が宿る。
『僕を育ててくれた、親代わりの白猫にまた会いたい……そのために強くなって、生き延びたい』
その願いを魔術師は聞き入れた。
白猫の命がけの願いと少年の祈りは、数年後に叶えられ、彼らは再び運命の再会を果たす。
――ネコと人間――義理の親子という間柄ではなく――。
――人間同士の夫婦として。