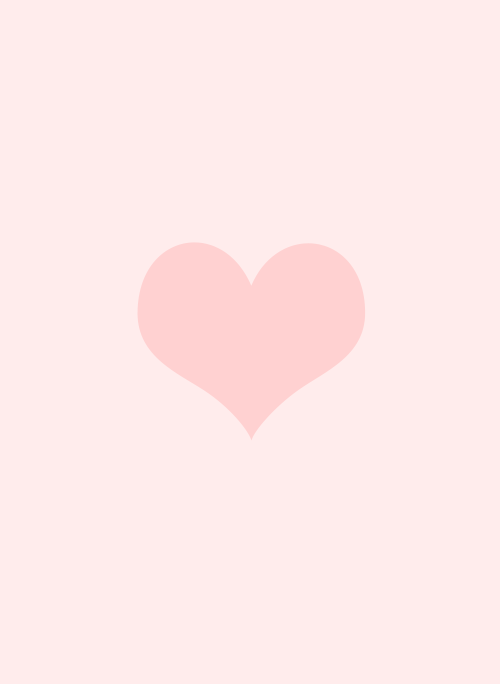転生したら捨てられ公爵夫人になったので放置生活を楽しみます~使えない才女ですので、どうぞお気になさらず~
ルイスが図書室を出ていってから、わたしとシータリアは一緒になってヴァンと遊んであげた。ヴァンはとても頭の良い子で、わたしたちの話す言葉をよく聞き、丁寧に話をするとちゃんと理解する。そのうえ同じ言葉を何度も繰り返しているとすぐに覚えてしまう。
会話をする人がいなかっただけで、言葉が遅いわけじゃなかったのね。
よけいにヴァンの身元が気になってしまうが、今はまだ彼がゆっくりと過ごしてここに慣れるのが一番だ。
夕食を一緒に部屋で取り、ヴァンが満足して眠くなるまで一緒に本を開いて読んであげた。
図書室に置いてあった子ども向けの、女神様の絵本をニコニコと嬉しそうに見ている。
しばらくそうしているうちに目をこすり始めたヴァンを、わたしは抱っこして寝室の大きなベッドの真ん中に下ろす。
くぅくぅと寝息を立てて眠っているヴァンの後ろ髪がぴょこんとはねている。手ぐしでちょいちょいと直すのだがなかなか直ってくれない。
「まあいいわ。明日になったらこれくらい直っているでしょう」
ヴァンの体にそっと布団を掛ける。
「おやすみなさい、ヴァン。明日もよい一日でありますように」
昔、寝ぐずりした妹へ掛けてあげた言葉を呟きながら、わたしは窓の外を見た。
月が綺麗な夜空。王都へと続く空の下で。
わたしを使えないと言って捨てたあの人たち、トリステット殿下や妹のクリスティアは今ごろ何をしているのだろうか。
このレトラシカ公爵家に来てから初めて、ふと彼らのことを思い出したが、柔らかな布団の魅力に勝てず、早々に意識を手放した。
***
軽やかなダンスのための演奏が響き渡る広間で、俺はシャンパンを片手に仮面越しにダンスに興じる婚約者を見ていた。
「ああ、楽しい。ねえ、わたくしにも飲み物を持ってきてちょうだい」
ふわりと蝶が舞うようにドレスの裾を優雅にひるがえしながら、婚約者のクリスティアが俺の隣へとやってきて使用人へ声をかけた。
グラスを受け取り、クイッと一口飲み込むと、汗に光る喉がコクンと音を立てて動く。
クリスティアのこういう華奢で清楚な見た目のくせに、どこか色気を感じさせる姿は好きだ。
しかしこう頻繁にパーティーへ出席して、他の男と踊り、はしゃぐ姿を見ていると苦々しい気持ちにもなる。
お前は俺の女だろう、と。これはアリアージュには少しも湧かなかった感情だ。
それだけクリスティアが美しく優越感を覚えさせる女性だということか。
「どうしましたの? トリス様」
「いや。俺にも飲み物を」
俺が新しいグラスを持ってくるように言うと、後ろに立っていた侍従がそっと耳打ちをしてきた。
「そろそろ王宮へお戻りになる時刻です。お帰りの支度をしていただきますよう」 今日はジエラ伯爵家での仮面パーティー。普段よりも緩い風紀のせいか、まだまだ遊び足りない気分だった。
それはクリスティアも同じ気持ちだったようで、俺の腕に抱きつきながらもう少しとねだってきた。
「ええ……っ!? まだ来たばかりではありませんか。わたくし、シャンパンも一杯しかいただいていませんのよ。それに、トリス様ともまだ踊り足りないわ。ねえ、もう少しだけでも」
王族のプレッシャーともなればその辺の貴族程度では考えもつかないほど厳しいものだ。それを癒すためにもこういった場は必要だった。
しかし、侍従は冷静に答える。
「殿下、執務官のコンフィス卿から五日前の書類の提出を急いでいただけるように言われております。さすがにこれ以上は待てないとも」
「……あれはクリスティアに任せてある」
俺の責任ではない。俺の言葉にクリスティアは頬を膨らませて「酷いです」と言いだした。
「そんな……トリス様。わたくしに全部押し付けるなんて……」
「しかし、事実……」
「それに、あんな小国の言葉をわざわざ調べて返事を書かなければならないなんて、王子妃のすることではありません。外交事務がすればいいのではないですか」
俺はグッと息を呑んだ。それは確かにそうなのだが、こんなこともできないということになればそれが俺の王子としての能力が低く見られてしまうことになる。それに、王族同士の書簡は、基本王族が確認するものだ。
俺には今まで何ひとつ苦労することなく維持してきた第一王子としての評判を、落とすなどはあり得ない。だから、そろそろクリスティアには本気で執務に取り組んでほしいのだが。
アリアージュ程度の者ができたのだから、クリスティアなら大丈夫に決まっている。
横を向いて口を尖らすクリスティア。こうなったらテコでも動かないといった様子だ。仕方がない、慣れぬ俺の補佐で疲れているだろうから、少しはガス抜きをしてやることも大事だ。
「わかった、クリスティア。次は俺とダンスを踊ろう。今日はじゅうぶん仮面パーティーを楽しんで、明日からはまた俺の手伝いをしてくれ」
俺の言葉にクリスティアは目をパッと輝かせた。そして腕を絡ませ胸を押し付ける。
「勿論ですわ。じゃあ、早くフロアに出ましょう、トリス様」
猫の目のように変わるクリスティアの機嫌に俺も引きずられた。
まあいい、もう少しだけだ。クリスティアも確かに返事をしたのだから、明日からは彼女もきっちりと仕事をするだろう。
俺も今だけは頭の痛くなるようなことは忘れてパーティーを楽しむことにした。
会話をする人がいなかっただけで、言葉が遅いわけじゃなかったのね。
よけいにヴァンの身元が気になってしまうが、今はまだ彼がゆっくりと過ごしてここに慣れるのが一番だ。
夕食を一緒に部屋で取り、ヴァンが満足して眠くなるまで一緒に本を開いて読んであげた。
図書室に置いてあった子ども向けの、女神様の絵本をニコニコと嬉しそうに見ている。
しばらくそうしているうちに目をこすり始めたヴァンを、わたしは抱っこして寝室の大きなベッドの真ん中に下ろす。
くぅくぅと寝息を立てて眠っているヴァンの後ろ髪がぴょこんとはねている。手ぐしでちょいちょいと直すのだがなかなか直ってくれない。
「まあいいわ。明日になったらこれくらい直っているでしょう」
ヴァンの体にそっと布団を掛ける。
「おやすみなさい、ヴァン。明日もよい一日でありますように」
昔、寝ぐずりした妹へ掛けてあげた言葉を呟きながら、わたしは窓の外を見た。
月が綺麗な夜空。王都へと続く空の下で。
わたしを使えないと言って捨てたあの人たち、トリステット殿下や妹のクリスティアは今ごろ何をしているのだろうか。
このレトラシカ公爵家に来てから初めて、ふと彼らのことを思い出したが、柔らかな布団の魅力に勝てず、早々に意識を手放した。
***
軽やかなダンスのための演奏が響き渡る広間で、俺はシャンパンを片手に仮面越しにダンスに興じる婚約者を見ていた。
「ああ、楽しい。ねえ、わたくしにも飲み物を持ってきてちょうだい」
ふわりと蝶が舞うようにドレスの裾を優雅にひるがえしながら、婚約者のクリスティアが俺の隣へとやってきて使用人へ声をかけた。
グラスを受け取り、クイッと一口飲み込むと、汗に光る喉がコクンと音を立てて動く。
クリスティアのこういう華奢で清楚な見た目のくせに、どこか色気を感じさせる姿は好きだ。
しかしこう頻繁にパーティーへ出席して、他の男と踊り、はしゃぐ姿を見ていると苦々しい気持ちにもなる。
お前は俺の女だろう、と。これはアリアージュには少しも湧かなかった感情だ。
それだけクリスティアが美しく優越感を覚えさせる女性だということか。
「どうしましたの? トリス様」
「いや。俺にも飲み物を」
俺が新しいグラスを持ってくるように言うと、後ろに立っていた侍従がそっと耳打ちをしてきた。
「そろそろ王宮へお戻りになる時刻です。お帰りの支度をしていただきますよう」 今日はジエラ伯爵家での仮面パーティー。普段よりも緩い風紀のせいか、まだまだ遊び足りない気分だった。
それはクリスティアも同じ気持ちだったようで、俺の腕に抱きつきながらもう少しとねだってきた。
「ええ……っ!? まだ来たばかりではありませんか。わたくし、シャンパンも一杯しかいただいていませんのよ。それに、トリス様ともまだ踊り足りないわ。ねえ、もう少しだけでも」
王族のプレッシャーともなればその辺の貴族程度では考えもつかないほど厳しいものだ。それを癒すためにもこういった場は必要だった。
しかし、侍従は冷静に答える。
「殿下、執務官のコンフィス卿から五日前の書類の提出を急いでいただけるように言われております。さすがにこれ以上は待てないとも」
「……あれはクリスティアに任せてある」
俺の責任ではない。俺の言葉にクリスティアは頬を膨らませて「酷いです」と言いだした。
「そんな……トリス様。わたくしに全部押し付けるなんて……」
「しかし、事実……」
「それに、あんな小国の言葉をわざわざ調べて返事を書かなければならないなんて、王子妃のすることではありません。外交事務がすればいいのではないですか」
俺はグッと息を呑んだ。それは確かにそうなのだが、こんなこともできないということになればそれが俺の王子としての能力が低く見られてしまうことになる。それに、王族同士の書簡は、基本王族が確認するものだ。
俺には今まで何ひとつ苦労することなく維持してきた第一王子としての評判を、落とすなどはあり得ない。だから、そろそろクリスティアには本気で執務に取り組んでほしいのだが。
アリアージュ程度の者ができたのだから、クリスティアなら大丈夫に決まっている。
横を向いて口を尖らすクリスティア。こうなったらテコでも動かないといった様子だ。仕方がない、慣れぬ俺の補佐で疲れているだろうから、少しはガス抜きをしてやることも大事だ。
「わかった、クリスティア。次は俺とダンスを踊ろう。今日はじゅうぶん仮面パーティーを楽しんで、明日からはまた俺の手伝いをしてくれ」
俺の言葉にクリスティアは目をパッと輝かせた。そして腕を絡ませ胸を押し付ける。
「勿論ですわ。じゃあ、早くフロアに出ましょう、トリス様」
猫の目のように変わるクリスティアの機嫌に俺も引きずられた。
まあいい、もう少しだけだ。クリスティアも確かに返事をしたのだから、明日からは彼女もきっちりと仕事をするだろう。
俺も今だけは頭の痛くなるようなことは忘れてパーティーを楽しむことにした。