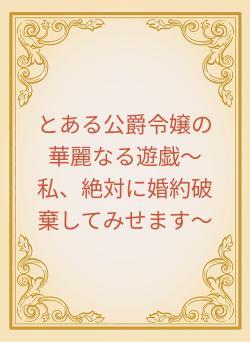声を失った私と、音を失ったキミ
第1話 声を失った私と、音を失ったキミ
「もう嫌っ……!」
――バシッ!
私は気づけば持っていた参考書を床に投げつけていた。
いくら頑張っても伸びない成績にイライラがつのる。
「どうして!?こんなに頑張ってるのに……」
不安で押し潰されそうな毎日に気が狂いそうだった。
中学3年の7月、受験生にとっては追い込みの時期。
塾から返却されたテストの成績表をクシャクシャにした私は、目の前が真っ暗になる。
志望高校が不合格の判定しかでない……。
この時期にこんな成績じゃ、絶対受かりっこない。どうしよう、もう少しレベルを下げるべき?
でも、お姉ちゃんと同じかそれ以上の高校じゃないとダメなのに⋯⋯。
ううん、今さらそんなこと考えててもしょうがないよ。時間がない。次のテストに向けて勉強しないと……。
つい投げつけてしまった参考書を拾い、勉強机へと向かう私は、シャーペンを握る手がかすかに震えていることに気づいた。
そして、広げた参考書にはポタポタと涙がこぼれ落ちる。
「……ッ」
私はその日、声を押し殺して泣いた。
泣くのはこれが最後。明日からまた頑張ろう。
そんな決意を胸に秘め、小さく嗚咽をもらす私。
けど、その翌日。
泣きつかれて目を覚ました私に、追い打ちをかける"あの"出来事が起こるなんて、この時はまだ想像もしていなかった――。
**
ジリリ、ジリリリ――。
けたたましいスマホのアラーム音で私、香澄美雨はムクリと重たい身体を起こす。
あれ……?
そっか。私、あのまま寝ちゃったんだ。
うわ、顔もぐちゃぐちゃ……。
近くにあった鏡を手に取ると、泣き腫らしたせいでまぶたは倍以上腫れており、奥二重がすっかり一重になってしまっていた。
スマホで時間を確認すると、朝の7時。
今日は土曜日だから10時から塾の講習がある。
とりあえず顔を洗って、保冷剤で少し目を冷やそう……。
そう考え、自室がある二階から一階の洗面所へと足を進めた。
洗面所へ向かう前に一階のリビングをのぞくと、すでに両親の姿はない。
ダイニングのテーブルには、トーストと目玉焼き、サラダが準備されていて、千円札が2枚と置き手紙が添えられていた。
【今日は、お父さんもお母さんも仕事で早く出ます。お姉ちゃんが帰って来るみたいだから久しぶりに夜は家族でご飯でも行きましょうね。PS.お昼ごはん代を置いておきます。朝ごはんはテーブルに準備してます。今日も塾、頑張って。母より】
お姉ちゃんが帰って来る時は、2人とも早く帰って来るんだな……。
そんなことを考え、憂鬱な気分になっていた時、スマホの着信を告げるメロディーが流れる。
画面を確認すると、姉の舞衣からだった。
スマホをスライドし、耳を近づけると明るい舞衣の声が聞こえてきた。
『あ!美雨?おはよー!今日、久しぶりの家に帰って来るんだけど、塾が終わったあとにカフェでも行かない?頑張ってる美雨にお姉ちゃんが美味しいものおごちゃう』
姉なりに受験勉強で忙しい私に気をつかってくれているのだろう。
姉の香澄舞衣は、私より5歳上の大学2年生。
現在は、隣県にある国立大学の薬学部に在籍している。
昔から優秀な姉は、学校の成績も常にトップ。当然のように志望高校、志望大学へと順調に進んできた。
かくいう私は、そんな姉と常に比べられてきた。
両親からは、少しでも成績が下がると『舞衣は常に学年3位以内をキープしてたわ』とため息をつかれるし。
『おぉ!あの香澄さんの妹さんか、それならさぞ優秀なんだろうね』
姉を知る中学の先生たちからはそんな変な期待をかけられ、正直気が重かった。
そもそも私はお姉ちゃんほど優秀じゃないのに……。
ハァ⋯⋯と思わず心の中でため息をつく。
よし!日頃のストレス解消もかねて、高いもの頼んじゃおうっと。
「じゃあ、駅前のに新しくできたカフェがいい!」そう声に出そうとした。
その瞬間。
「……??……はっ、ッ」
声が、出ない……?
まるで話し方を忘れてしまったかのように言葉が出てこない。一生懸命になればなるほど、出てくるのは微かな吐息と、単語だけだ。
『ん、美雨?なんて??聞こえないよ?』
「お、……ッハァ、ちゃ」
『美雨……?大丈夫!?どうかしたの!?』
事態の深刻さに気付いたのか、姉の声がいちだんと大きくる。
「…こ……で、い」
「声が出ない」そう姉に伝えるのも必死だった。
『ちょっと待ってて、今すぐそっちに行くから!』
今まで聞いたことないくらい慌てた様子の姉の声は今でも耳にこびりついている。
その日を境に、私の声は出なくなってしまった――。
**
「妹さんの声帯には問題なさそうなので、おそらく原因は精神的なものでしょう。近くの心療内科を紹介しますのでそちらに行ってみてください」
カタカタとパソコンを操作しながら、淡々とした口調で説明する先生の言葉に私はサーッと血の気が引くのを感じていた。
あの後、私の異変に気づいた姉が家にやって来たのは、一時間ほど経った頃だった。
「美雨!大丈夫!?どうしたの!?」
『声が出ないの』
私に詰め寄る姉に向かって、スマホで文字を打ち、声が出ないことを伝える。
心配そうな姉に付き添われ、近くの耳鼻咽喉科を受診した私は、色々検査を受けたのだが……。
心療内科……?
まさかの診断結果に私の顔色が青くなった。
「あの先生……。そしたら妹の声が出なくなったのは心理的な要因でということでしょうか?それは今後、よくなるんですか……?」
そんな私の代わりに姉が、先生へと質問をしてくれる。
「そうですね。私も精神分野は専門じゃないので一概には言えませんが、おそらくストレスなどからくる一過性のものかとは思います……。治るかどうかも踏まえて、そこは専門家に診てもらったほうがいいでしょう」
最後に「お大事に」と告げた先生に頭を下げ、私は姉と2人で診察室をあとにした。
病院からの帰り道、ズシンとまるで鉛でも背負わされたかのように身体が重い。
『お姉ちゃん、今日は急にゴメンね。せっかくのお休みだったのに迷惑かけて⋯⋯。それと病院に連れてきてくれてありがとう』
スマホを操作し、メモ欄にそんなメッセージを書く。
「……っ」
画面を見て、複雑そうな表情になった姉は、何か言いかけて口を閉ざす。
しばらくその場に重たい沈黙が流れた。
「……美雨、あのさ、心療内科の受診、私もついていこうか?大学の授業休んでも大丈夫だし、1人で不安じゃない?」
ようやく口を開いた姉の言葉に、少し考えて私は小さく首を横に振る。
私としては姉にこれ以上心配をかけたくないと言う配慮からくるものだったのだが……。
「そっか、そうだよね……」
なぜか少し傷ついたような表情を浮かべた姉の姿に、私はその時なんと声をかけていいのかわからなくなってしまった。
**
「ねぇ、なんか三年の香澄さん、突然声が出なくなっちゃったらしいよ」
「あ!それ聞いた!かわいそうだよね。ストレスらしいよ」
「頭良いから県立の進学校受験するんだったよね?受験大丈夫なのかな?」
声が出なくなって一週間が経つ頃には、学校内にそんなウワサが広がっていた。
それもそのはず、あんな出来事があれば嫌でもウワサは回るだろう。
それは声が出なくなった翌日、学校に登校した日のホームルームでの出来事だった――。
『実は香澄さんのことでみなさんにお話があります』
ドクン。
教壇に立つ担任の四十代半ばの女性教師と目が合った瞬間、私は血の気が引くのを感じる。
朝、登校前に母から「担任の先生には美雨のことちゃんと伝えてあるから安心してね」と言われたことが脳裏をよぎった。
悪い予感は当たるものだ。
心配そうな表情で先生は口を開くと、
『今、香澄さんは病気で声が出なくなっています。みなさん、香澄さんが困っていたら助けてあげましょうね』
クラスメイトみんなの前でそんなことを言ってのけた。
――ザワッ。
その時、クラス内がざわつく。そして、一斉にみんなの視線が私に集まるのを感じた。
もともと友達もそんなに多くないし、おしゃべりなほうじゃないから登校してから今のところうまく隠し通せていたのに⋯⋯。
みんなの視線を感じながら、私は少しうつむいてギュッと拳を握りしめた。
先生としては私を気づかっての発言なのだろう。
それか私の両親に頼まれていたのかもしれない。
でも、私はこんなことまったく望んでいなかった。
っ、放っておいてほしかったのに…⋯。
なんとも言えない思いがぐるぐると頭の中をかけめぐる。
そして、案の定、翌日には隣のクラスにまで私の声が出なくなった事実は広がり、一週間もする頃には学校全体に広がってしまったのだ。
唯一の救いは、すぐに夏休みに突入したこと。
おかげでわずらわしいウワサを聞くのは、短期間ですんだ。
でも、次の始業式、はたして私はちゃんと何事もなかったかのように学校へ行けるのだろうか。
ううん、もしかしたら夏休みの間に声が戻るかもしれない。そしたら今までどおりだし、みんなもすぐに忘れちゃうよ。
そんな不安と淡い期待が私の胸の中にうずまいていた。
**
「ねぇ!来週、うちの大学のオープンキャンパスがあるんだけど美雨も来ない?」
夏休みに入って数日が過ぎた頃、突然、実家に帰ってきた姉が私に見せてきたのは、オープンキャンパスのチラシだった。
『⋯⋯お姉ちゃんの大学の?』
スマホのメモ欄に文字を打ちながら、姉と話をする。
声が出ないから、基本的にはスマホでコミュニケーションをとる生活にもすっかり慣れつつあった。
今のところまだ私の声は戻っていない――。
「そう!色々企画もあって楽しいよ〜」
『でも、それって高校生の人が行くんじゃない?』
「中学生だって、来ていいのよ。それに美雨もうちの大学気になってるって言ってたじゃない」
ニコニコと満面の笑みを浮かべる姉に私は内心複雑な思いをかかえていた。
私がお姉ちゃんの大学を気になるって言ってたのはただ、お姉ちゃんが通ってるからだった。
私の姉、舞衣は妹の私から見ても優秀だった。
勉強も運動も要領よく何でもこなす。
高校受験も大学受験も姉が苦労している姿なんか見たことがない。
もちろん姉なりに勉強はしていたのだろうが、やった分だけ成果が出るタイプなんだと思う。
昔はそんな姉に憧れて「私もお姉ちゃんみたいになる!」って言っていたっけ?
でも、いつからだろう、「姉と同じようにならなくちゃ」とプレッシャーを感じ始めたのは⋯⋯。
「美雨⋯⋯?体調悪いなら無理しなくていいのよ?気分転換にと思っただけだから」
表情がさえない私に気づいたのか少し口ごもりながら姉はそう答える。
これ以上、お姉ちゃんに心配をかけたくないのに⋯⋯。
姉のさみしそうな表情を見て、ハッとした私はあわてて手元のスマホに文字を打ち込んだ。
『ううん、いきたい。お姉ちゃん誘ってくれてありがとう』
「そう?よかった〜〜。じゃあ、明後日だから一緒に行こうね!お母さんに車借りよっと」
私の返答を見てホッとした様子の姉。
私もそんな姉をみて、内心胸を撫でおろしていた。
**
「ジャジャーン!ここがうちの大学だよ〜!」
『すごい、大きいね』
「学部も色々あるからね!気になるところあったらなんでも言って」
隣で大学内を案内してくれる姉にコクリとうなずく。
広い大学内は、オープンキャンパスということもあって、制服を着た学生の姿が目についた。
ちなみに私も今日は中学の制服を来て参加している。
「うちは食堂もおいしいって有名だから、お昼の時間はそこに行こうね」
楽しそうに話す姉につられて私が小さくほほ笑んだ時。
「あら??香澄さんじゃない、オープンキャンパスの手伝い?」
突然、後ろからそう声をかけられ、私たち思わず振り返っていた。
そこに立っていたのは、優しそうな五十代くらいの上品な女の人。穏やかな笑みを浮かべて姉の舞衣を見つめている。
「あ、渡辺先生お疲れ様です。今日は妹に大学内を案内してるんですよ。美雨、紹介するね。うちのゼミの渡辺先生」
お姉ちゃんの先生⋯⋯!
姉に言われて、あわててペコリと会釈をした。
「あらあら!香澄さんの妹さん?その制服はどこの高校??」
挨拶しなければと、
『香澄美雨です。中学生です。姉がいつもお世話になっています』
急いでスマホの画面に打ち込んで私はサッとその女の人に見せる。
「⋯⋯あ、えーっと⋯⋯。こちらこそお姉さんにはお世話になってるのよ?ご丁寧にありがとう。じゃあ、オープンキャンパス楽しんでね」
一瞬、その女の人が戸惑った表情を浮かべたのを私は見逃さなかった。
ほんの少し早足で去っていく先生の後ろ姿を見つめ、私はチクンと胸に鈍い痛みを感じる。
あからさまではないけれど、きっとあの先生は私をかわいそうな子とでも思っているのだろう。
些細な仕草からそう感じ取ってしまった。
「美雨、そろそろ行こうか」
何も気づいていない様子の姉が声をかけてくる。
私の声が戻るまで今日みたいな思いを何回もするんだろうか⋯⋯。
やるせない気持ちになりながらも、私は姉の後ろに続き歩き出していた。
大学内から外に出ると部活紹介をしているのか中庭で音楽の演奏が行われていた。
ドラムやギターの軽快な音色と綺麗な歌声に歓声が上がっている。
「あれは軽音部よ!うちの軽音有名なんだ〜」
姉の説明に私は小さくうなずいた。
音楽かぁ〜⋯⋯。今までやったことないけど楽しそう。
手拍子をしながら盛り上がる人たちを遠目で見つめていると。
「そういえば美雨って部活やってないよね?高校では何かしたいことないの?」
姉が思い出したように問いかけてくる。
悪気なくそう聞いてくる姉に内心私は苦笑いを浮かべた。
⋯⋯私はお姉ちゃんと違って、部活する余裕まではなかったんだよ。勉強で精いっぱいだったから――。
『何かやりたいことがあれば高校では部活も考えるよ』
当たり障りのない言葉を打ち、スマホを姉に見せようとしたその時だった。
「ねぇ、美雨!あの子高校生かな?軽音部にまざって何かやるみたいよ!」
姉の声に思わず視線をそちらにうつす。
そこにいたのは、見慣れない制服を着た少年の姿。
ギターを演奏していた大学生のお兄さんから、ギターを借りた彼は、楽しげにひき始める。
それは最近流行りのJポップだった。
音楽に詳しくない私ですら知ってるくらいのメジャーな曲。
ドラムのお姉さんと、ベースのお兄さんが彼のギターに合わせ、演奏を始める。
「あの子、うまいわね〜〜」
感心したような姉のつぶやきに私もついうなずいてしまった。
音楽のことは詳しくないけれど、なんだか惹きつけられ、思わず聴き入ってしまう。
それは周りも同じだったようで、さっきまで興味なさげに歩いていた人たちも足を止めている姿が目に飛び込んできた。
すごい、あっという間に人だかりができちゃった!
しかも、演奏が終わるとパチパチと大きな拍手が巻き起こり、アンコールの声も飛ぶ。
そんな様子を見て、照れたようにはにかんでいる少年からなぜか私は目が離せなくなっていた。
――バシッ!
私は気づけば持っていた参考書を床に投げつけていた。
いくら頑張っても伸びない成績にイライラがつのる。
「どうして!?こんなに頑張ってるのに……」
不安で押し潰されそうな毎日に気が狂いそうだった。
中学3年の7月、受験生にとっては追い込みの時期。
塾から返却されたテストの成績表をクシャクシャにした私は、目の前が真っ暗になる。
志望高校が不合格の判定しかでない……。
この時期にこんな成績じゃ、絶対受かりっこない。どうしよう、もう少しレベルを下げるべき?
でも、お姉ちゃんと同じかそれ以上の高校じゃないとダメなのに⋯⋯。
ううん、今さらそんなこと考えててもしょうがないよ。時間がない。次のテストに向けて勉強しないと……。
つい投げつけてしまった参考書を拾い、勉強机へと向かう私は、シャーペンを握る手がかすかに震えていることに気づいた。
そして、広げた参考書にはポタポタと涙がこぼれ落ちる。
「……ッ」
私はその日、声を押し殺して泣いた。
泣くのはこれが最後。明日からまた頑張ろう。
そんな決意を胸に秘め、小さく嗚咽をもらす私。
けど、その翌日。
泣きつかれて目を覚ました私に、追い打ちをかける"あの"出来事が起こるなんて、この時はまだ想像もしていなかった――。
**
ジリリ、ジリリリ――。
けたたましいスマホのアラーム音で私、香澄美雨はムクリと重たい身体を起こす。
あれ……?
そっか。私、あのまま寝ちゃったんだ。
うわ、顔もぐちゃぐちゃ……。
近くにあった鏡を手に取ると、泣き腫らしたせいでまぶたは倍以上腫れており、奥二重がすっかり一重になってしまっていた。
スマホで時間を確認すると、朝の7時。
今日は土曜日だから10時から塾の講習がある。
とりあえず顔を洗って、保冷剤で少し目を冷やそう……。
そう考え、自室がある二階から一階の洗面所へと足を進めた。
洗面所へ向かう前に一階のリビングをのぞくと、すでに両親の姿はない。
ダイニングのテーブルには、トーストと目玉焼き、サラダが準備されていて、千円札が2枚と置き手紙が添えられていた。
【今日は、お父さんもお母さんも仕事で早く出ます。お姉ちゃんが帰って来るみたいだから久しぶりに夜は家族でご飯でも行きましょうね。PS.お昼ごはん代を置いておきます。朝ごはんはテーブルに準備してます。今日も塾、頑張って。母より】
お姉ちゃんが帰って来る時は、2人とも早く帰って来るんだな……。
そんなことを考え、憂鬱な気分になっていた時、スマホの着信を告げるメロディーが流れる。
画面を確認すると、姉の舞衣からだった。
スマホをスライドし、耳を近づけると明るい舞衣の声が聞こえてきた。
『あ!美雨?おはよー!今日、久しぶりの家に帰って来るんだけど、塾が終わったあとにカフェでも行かない?頑張ってる美雨にお姉ちゃんが美味しいものおごちゃう』
姉なりに受験勉強で忙しい私に気をつかってくれているのだろう。
姉の香澄舞衣は、私より5歳上の大学2年生。
現在は、隣県にある国立大学の薬学部に在籍している。
昔から優秀な姉は、学校の成績も常にトップ。当然のように志望高校、志望大学へと順調に進んできた。
かくいう私は、そんな姉と常に比べられてきた。
両親からは、少しでも成績が下がると『舞衣は常に学年3位以内をキープしてたわ』とため息をつかれるし。
『おぉ!あの香澄さんの妹さんか、それならさぞ優秀なんだろうね』
姉を知る中学の先生たちからはそんな変な期待をかけられ、正直気が重かった。
そもそも私はお姉ちゃんほど優秀じゃないのに……。
ハァ⋯⋯と思わず心の中でため息をつく。
よし!日頃のストレス解消もかねて、高いもの頼んじゃおうっと。
「じゃあ、駅前のに新しくできたカフェがいい!」そう声に出そうとした。
その瞬間。
「……??……はっ、ッ」
声が、出ない……?
まるで話し方を忘れてしまったかのように言葉が出てこない。一生懸命になればなるほど、出てくるのは微かな吐息と、単語だけだ。
『ん、美雨?なんて??聞こえないよ?』
「お、……ッハァ、ちゃ」
『美雨……?大丈夫!?どうかしたの!?』
事態の深刻さに気付いたのか、姉の声がいちだんと大きくる。
「…こ……で、い」
「声が出ない」そう姉に伝えるのも必死だった。
『ちょっと待ってて、今すぐそっちに行くから!』
今まで聞いたことないくらい慌てた様子の姉の声は今でも耳にこびりついている。
その日を境に、私の声は出なくなってしまった――。
**
「妹さんの声帯には問題なさそうなので、おそらく原因は精神的なものでしょう。近くの心療内科を紹介しますのでそちらに行ってみてください」
カタカタとパソコンを操作しながら、淡々とした口調で説明する先生の言葉に私はサーッと血の気が引くのを感じていた。
あの後、私の異変に気づいた姉が家にやって来たのは、一時間ほど経った頃だった。
「美雨!大丈夫!?どうしたの!?」
『声が出ないの』
私に詰め寄る姉に向かって、スマホで文字を打ち、声が出ないことを伝える。
心配そうな姉に付き添われ、近くの耳鼻咽喉科を受診した私は、色々検査を受けたのだが……。
心療内科……?
まさかの診断結果に私の顔色が青くなった。
「あの先生……。そしたら妹の声が出なくなったのは心理的な要因でということでしょうか?それは今後、よくなるんですか……?」
そんな私の代わりに姉が、先生へと質問をしてくれる。
「そうですね。私も精神分野は専門じゃないので一概には言えませんが、おそらくストレスなどからくる一過性のものかとは思います……。治るかどうかも踏まえて、そこは専門家に診てもらったほうがいいでしょう」
最後に「お大事に」と告げた先生に頭を下げ、私は姉と2人で診察室をあとにした。
病院からの帰り道、ズシンとまるで鉛でも背負わされたかのように身体が重い。
『お姉ちゃん、今日は急にゴメンね。せっかくのお休みだったのに迷惑かけて⋯⋯。それと病院に連れてきてくれてありがとう』
スマホを操作し、メモ欄にそんなメッセージを書く。
「……っ」
画面を見て、複雑そうな表情になった姉は、何か言いかけて口を閉ざす。
しばらくその場に重たい沈黙が流れた。
「……美雨、あのさ、心療内科の受診、私もついていこうか?大学の授業休んでも大丈夫だし、1人で不安じゃない?」
ようやく口を開いた姉の言葉に、少し考えて私は小さく首を横に振る。
私としては姉にこれ以上心配をかけたくないと言う配慮からくるものだったのだが……。
「そっか、そうだよね……」
なぜか少し傷ついたような表情を浮かべた姉の姿に、私はその時なんと声をかけていいのかわからなくなってしまった。
**
「ねぇ、なんか三年の香澄さん、突然声が出なくなっちゃったらしいよ」
「あ!それ聞いた!かわいそうだよね。ストレスらしいよ」
「頭良いから県立の進学校受験するんだったよね?受験大丈夫なのかな?」
声が出なくなって一週間が経つ頃には、学校内にそんなウワサが広がっていた。
それもそのはず、あんな出来事があれば嫌でもウワサは回るだろう。
それは声が出なくなった翌日、学校に登校した日のホームルームでの出来事だった――。
『実は香澄さんのことでみなさんにお話があります』
ドクン。
教壇に立つ担任の四十代半ばの女性教師と目が合った瞬間、私は血の気が引くのを感じる。
朝、登校前に母から「担任の先生には美雨のことちゃんと伝えてあるから安心してね」と言われたことが脳裏をよぎった。
悪い予感は当たるものだ。
心配そうな表情で先生は口を開くと、
『今、香澄さんは病気で声が出なくなっています。みなさん、香澄さんが困っていたら助けてあげましょうね』
クラスメイトみんなの前でそんなことを言ってのけた。
――ザワッ。
その時、クラス内がざわつく。そして、一斉にみんなの視線が私に集まるのを感じた。
もともと友達もそんなに多くないし、おしゃべりなほうじゃないから登校してから今のところうまく隠し通せていたのに⋯⋯。
みんなの視線を感じながら、私は少しうつむいてギュッと拳を握りしめた。
先生としては私を気づかっての発言なのだろう。
それか私の両親に頼まれていたのかもしれない。
でも、私はこんなことまったく望んでいなかった。
っ、放っておいてほしかったのに…⋯。
なんとも言えない思いがぐるぐると頭の中をかけめぐる。
そして、案の定、翌日には隣のクラスにまで私の声が出なくなった事実は広がり、一週間もする頃には学校全体に広がってしまったのだ。
唯一の救いは、すぐに夏休みに突入したこと。
おかげでわずらわしいウワサを聞くのは、短期間ですんだ。
でも、次の始業式、はたして私はちゃんと何事もなかったかのように学校へ行けるのだろうか。
ううん、もしかしたら夏休みの間に声が戻るかもしれない。そしたら今までどおりだし、みんなもすぐに忘れちゃうよ。
そんな不安と淡い期待が私の胸の中にうずまいていた。
**
「ねぇ!来週、うちの大学のオープンキャンパスがあるんだけど美雨も来ない?」
夏休みに入って数日が過ぎた頃、突然、実家に帰ってきた姉が私に見せてきたのは、オープンキャンパスのチラシだった。
『⋯⋯お姉ちゃんの大学の?』
スマホのメモ欄に文字を打ちながら、姉と話をする。
声が出ないから、基本的にはスマホでコミュニケーションをとる生活にもすっかり慣れつつあった。
今のところまだ私の声は戻っていない――。
「そう!色々企画もあって楽しいよ〜」
『でも、それって高校生の人が行くんじゃない?』
「中学生だって、来ていいのよ。それに美雨もうちの大学気になってるって言ってたじゃない」
ニコニコと満面の笑みを浮かべる姉に私は内心複雑な思いをかかえていた。
私がお姉ちゃんの大学を気になるって言ってたのはただ、お姉ちゃんが通ってるからだった。
私の姉、舞衣は妹の私から見ても優秀だった。
勉強も運動も要領よく何でもこなす。
高校受験も大学受験も姉が苦労している姿なんか見たことがない。
もちろん姉なりに勉強はしていたのだろうが、やった分だけ成果が出るタイプなんだと思う。
昔はそんな姉に憧れて「私もお姉ちゃんみたいになる!」って言っていたっけ?
でも、いつからだろう、「姉と同じようにならなくちゃ」とプレッシャーを感じ始めたのは⋯⋯。
「美雨⋯⋯?体調悪いなら無理しなくていいのよ?気分転換にと思っただけだから」
表情がさえない私に気づいたのか少し口ごもりながら姉はそう答える。
これ以上、お姉ちゃんに心配をかけたくないのに⋯⋯。
姉のさみしそうな表情を見て、ハッとした私はあわてて手元のスマホに文字を打ち込んだ。
『ううん、いきたい。お姉ちゃん誘ってくれてありがとう』
「そう?よかった〜〜。じゃあ、明後日だから一緒に行こうね!お母さんに車借りよっと」
私の返答を見てホッとした様子の姉。
私もそんな姉をみて、内心胸を撫でおろしていた。
**
「ジャジャーン!ここがうちの大学だよ〜!」
『すごい、大きいね』
「学部も色々あるからね!気になるところあったらなんでも言って」
隣で大学内を案内してくれる姉にコクリとうなずく。
広い大学内は、オープンキャンパスということもあって、制服を着た学生の姿が目についた。
ちなみに私も今日は中学の制服を来て参加している。
「うちは食堂もおいしいって有名だから、お昼の時間はそこに行こうね」
楽しそうに話す姉につられて私が小さくほほ笑んだ時。
「あら??香澄さんじゃない、オープンキャンパスの手伝い?」
突然、後ろからそう声をかけられ、私たち思わず振り返っていた。
そこに立っていたのは、優しそうな五十代くらいの上品な女の人。穏やかな笑みを浮かべて姉の舞衣を見つめている。
「あ、渡辺先生お疲れ様です。今日は妹に大学内を案内してるんですよ。美雨、紹介するね。うちのゼミの渡辺先生」
お姉ちゃんの先生⋯⋯!
姉に言われて、あわててペコリと会釈をした。
「あらあら!香澄さんの妹さん?その制服はどこの高校??」
挨拶しなければと、
『香澄美雨です。中学生です。姉がいつもお世話になっています』
急いでスマホの画面に打ち込んで私はサッとその女の人に見せる。
「⋯⋯あ、えーっと⋯⋯。こちらこそお姉さんにはお世話になってるのよ?ご丁寧にありがとう。じゃあ、オープンキャンパス楽しんでね」
一瞬、その女の人が戸惑った表情を浮かべたのを私は見逃さなかった。
ほんの少し早足で去っていく先生の後ろ姿を見つめ、私はチクンと胸に鈍い痛みを感じる。
あからさまではないけれど、きっとあの先生は私をかわいそうな子とでも思っているのだろう。
些細な仕草からそう感じ取ってしまった。
「美雨、そろそろ行こうか」
何も気づいていない様子の姉が声をかけてくる。
私の声が戻るまで今日みたいな思いを何回もするんだろうか⋯⋯。
やるせない気持ちになりながらも、私は姉の後ろに続き歩き出していた。
大学内から外に出ると部活紹介をしているのか中庭で音楽の演奏が行われていた。
ドラムやギターの軽快な音色と綺麗な歌声に歓声が上がっている。
「あれは軽音部よ!うちの軽音有名なんだ〜」
姉の説明に私は小さくうなずいた。
音楽かぁ〜⋯⋯。今までやったことないけど楽しそう。
手拍子をしながら盛り上がる人たちを遠目で見つめていると。
「そういえば美雨って部活やってないよね?高校では何かしたいことないの?」
姉が思い出したように問いかけてくる。
悪気なくそう聞いてくる姉に内心私は苦笑いを浮かべた。
⋯⋯私はお姉ちゃんと違って、部活する余裕まではなかったんだよ。勉強で精いっぱいだったから――。
『何かやりたいことがあれば高校では部活も考えるよ』
当たり障りのない言葉を打ち、スマホを姉に見せようとしたその時だった。
「ねぇ、美雨!あの子高校生かな?軽音部にまざって何かやるみたいよ!」
姉の声に思わず視線をそちらにうつす。
そこにいたのは、見慣れない制服を着た少年の姿。
ギターを演奏していた大学生のお兄さんから、ギターを借りた彼は、楽しげにひき始める。
それは最近流行りのJポップだった。
音楽に詳しくない私ですら知ってるくらいのメジャーな曲。
ドラムのお姉さんと、ベースのお兄さんが彼のギターに合わせ、演奏を始める。
「あの子、うまいわね〜〜」
感心したような姉のつぶやきに私もついうなずいてしまった。
音楽のことは詳しくないけれど、なんだか惹きつけられ、思わず聴き入ってしまう。
それは周りも同じだったようで、さっきまで興味なさげに歩いていた人たちも足を止めている姿が目に飛び込んできた。
すごい、あっという間に人だかりができちゃった!
しかも、演奏が終わるとパチパチと大きな拍手が巻き起こり、アンコールの声も飛ぶ。
そんな様子を見て、照れたようにはにかんでいる少年からなぜか私は目が離せなくなっていた。