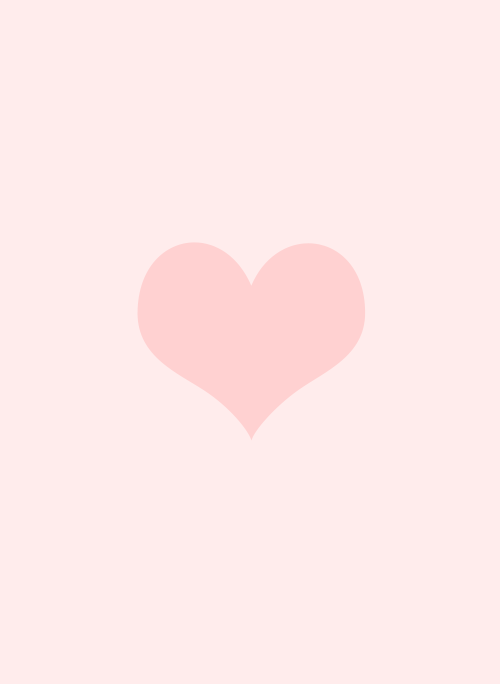公爵令嬢は創作仲間と甘い時間を楽しみたい
べルターニュ王国のとある屋敷で舞踏会が開かれていた。舞踏会は貴族が集まる社交の場である。その一角に何やら人だかりができていた。
「ヴァイオレット様、ぜひ今度伯爵家のお茶会にいらしてください!」
「わたくも! 入所困難な異国の茶葉がようやく手に入りましたの。一度いらしてくだされば光栄ですわ」
「ヴァイオレット様、それでしたらわたくしも……」
公爵令嬢ヴァイオレット・ヴァスールは困惑していた。しかしそれを表情に出すことはない。今回は久しぶりに舞踏会へと足を運んだわけなのだが、会が始まって早々にたくさんのご令嬢に囲まれている。
正直貴族たちに見向きもされず壁の花になりながら、様子を伺いつつすぐに屋敷へ帰ろうと目論んでいたのだ。しかしそれはかなわなそうだ。
(これではわたくしが悪役令嬢になった意味がないわ!)
ヴァイオレットは囲んで話しかけてきた令嬢たちを適当に言いくるめてバルコニーに退散した。
「ねえ、ヴィーそこにいるわよね」
「はい、お嬢様。何か御用でしょうか」
「うわ、なにその話し方。今このバルコニーには私たちしかいないのよ。普段通り話してちょうだい」
「お嬢様がそうおっしゃるなら遠慮なく。……早々に舞踏会から抜け出してきてどうしたんだよ」
影に身を潜めていたヴィクトル・バロンが姿を表した。彼は男爵家の次男であるが、家通しのつながりで幼い頃からヴァイオレットの従者をしている。
「どうしたもこうしたもないわ! 私は今日舞踏会の壁になるつもりで来たのよ。それなのにたくさんの令嬢たちに囲まれたの」
「あーそれはそうっすよね」
「何? 何か知ってるの?」
「何か知ってるも何も……。お嬢様は貴族のご令嬢たちに今すごく人気があるんですよ」
「どうして!? わたくしは悪役令嬢になったのよ。今はたくさんの貴族たちに嫌われているはずなのに」
ヴァイオレットはここ数ヶ月、悪役令嬢になるために勤めてきた。
定期的に出席していた社交の場に姿を見せなくしたり、貴族たちからの誘いを断ったり、無断欠席をしてみたり手は尽くしてきた。
「それが、うまくいっていないんですよねー」
ヴィクトルはある一冊の雑誌を差し出した。ヴァイオレットはそれを受け取る。
「これ、私が投稿している文芸雑誌のライバル誌じゃない!」
「そう。お嬢様、表紙をよく見てみてください」
「えーと、『集中連載! 白蝶の君は黒に染まる』何かしらこれ」
ページをめくると、一面に小説の特集が出てきた。大胆にも挿絵が掲載されている。黒蝶と黒薔薇をモチーフにしたドレスに身を包み、偉そうにふんぞりかえっている令嬢がいる。そしてその絵には見覚えがあった。
「これ、わたくしだわ!」
「そうなんですよね。お嬢様をモデルにして書かれた小説のようです。白蝶として社交界のトップに君臨していた主人公が実は魔法使いで、国を守る時間を作るために悪女を演じるストーリーらしくて。これを読んだご令嬢たちはお嬢様に夢中なんですよ」
魔法使いはベルターニュ王国では憧れの職業のうちの一つだ。しかし魔法使いになるには生まれつきの才能が最も必要であり、魔力量が多ければ多いほど実力は上がっていく。
根性論で魔力量をあげていく方法はあるにはあるがほとんどの人はそれを選択しない。
その一つの理由としてベルターニュ王国では魔力を持たない人が大半を占めておりわざわざ魔力を上げる必要がないからだ。
「そんな! というかあなた、どうしてそんなに内容に詳しいのよ」
「俺もその小説のファンの一人ですから」
「以前からこの小説を知っていたの? それなら教えてくれてもいいじゃない」
「執筆の時間が惜しいからと、俺の話を普段から聞いていないのはどこのご令嬢でしょうねー」
そう言われてしまえばヴァイレットはぐうの音も出なかった。
ヴァイオレット・ヴァスールは公爵令嬢として社交界を代表する存在として有名だった。涼しげな目元。美しい濃紺色の髪に、スッと伸びた背筋。純白の刺繍が施されたドレスはまるで優雅に舞う蝶を想起させた。ついた通称は『白蝶の君』。
公爵令嬢としての役割を忠実に果たし、ご令嬢たちの憧れの的だった。
一方で本人は公爵家で割り当てられた役割をこなす日々を過ごし、内心飽き飽きしていた。そんなある日、整理していた書類の中に一冊の雑誌『純白のあなたへ』が紛れ込んでいたのだ。『純白のあなたへ』は女性向け雑誌で主に市民のたちの娯楽としてベルターニュ王国全土に普及している。
ヴァイオレットもそのことは噂好きの侍女から聞いていたものの本物を見るのは初めてだった。仕事の息抜きにでもと軽い気持ちで手に取った。
それがいけなかった。専属作家の連載作品、有名作家の短編など心躍る話の世界に没頭し、仕事を忘れて読みふけってしまった。特に興味をそそられたのは『純白のあなたへ』の読者が投書をする投稿欄だった。
投稿欄では読者が独自のペンネームを使用し、その人物になりきってやり取りをするのだ。
......
わたくしは辺境に住まう、小さな乙女ですの。瞬きするまもなく、薫風と共にわたくしの日々が過ぎ去っていくのです。その毎日に飽き飽きしているというわけではなく、むしろ幸運だとさえ思っているのです。ああ、しかしどこか物寂しいと思ってしまうのは我儘なことでしょうか。
PN 辺境の乙女
辺境の乙女さん、ごきげんよう。わたしは王都の片隅に住む未亡人ですわ。片隅にはおりますけれども、家の外には王都特有の喧騒があります。わたしは外出することがほとんどありませんから、ゆったりとした時間を過ごしております。しかし時々わたしだけが時の流れに取り残されているのではないかと、思いがくすぶるのです。きっとわたしたちいい友人になれるでしょう。
PN 小さな窓辺の未亡人
......
「な、何かしらこれは」
ヴァイオレットは初めて投稿文を読んだ時、まさに晴天の霹靂を受けた。優美な文章、それでいてつかみどころのない少女と大人の女性の様子。
あなたは、どんな人なの教えて。これが流行りの萌えというやつか。
読むたびに彼女たちの魅力に取り込まれていった。
ヴァイオレットはそれからすぐに仕事の整理を始めた。できるだけ無駄を省き、自分の時間を創作活動に充てたいと思ったからだ。
悪役令嬢を演じ始めたこともその一環だ。無駄な関係を省き、物事がより円滑に進むようにしようと動いていた。
まさかそれが失敗するとは考えていなかったけれども。
「こうなったら作者に連載をやめるように言うしかないわね」
創作の時間を確保するためだ。やるしかない。ヴァイオレットは決意した。
「公爵家の権力を使うんですか?」
「そんな卑怯なことはしない。やるなら正攻法でよ」
ヴァイオレットは卑怯なことは好きではない。政治のことなら致し方ないと割り切ることができるが、創作活動はあくまで趣味だ。だから権力は行使しない。
これは彼女の美学であり、頑固な性格の現れでもある。
ヴィクトルもそれは理解しているため、特に反対はしなかった。そういうところが悪役令嬢になりきれない理由だとわかっているが口にはしない。
「わかりました。それで具体的に何をするんです?」
「お茶会という名のオフ会よ」
「オフ会?」
「ええ、創作活動をしている作家たちが集まって、お茶やお菓子を楽しみながら好みの作品について語り合うの。雑誌の投稿欄に主催者からの募集が載ってるわ」
表向きにお茶会としている理由は創作活動をしていることを知られたくない人も参加しやすくするためだ。
ヴァイオレットは雑誌の最後のページを指差した。確かに広告の下に小さくオフ会(お茶会)の告知が載っている。
「ではお嬢様はここに告知を載せて『白蝶の君は黒に染まる』の作者に会うんですね」
「そうよ」
「でも、お嬢様『黒鳥の歌』は『純白のあなたへ』のライバル誌でしょ。それに急にライバル誌から作家がやってきてオフ会の宣伝をするなんて、どう考えても怪しまれると思うんですけど」
「問題はそこなの。そんなことしたら100%怪しまれる」
だからヴァイオレットは考えた。
誰にも怪しまれることなくオフ会を開催し、『白蝶の君は黒に染まる』の作者に会う方法を。
やはりこれしか思い浮かばない。この方法が一番確実で穏便に済ませられる方法だ。一つ懸念点を挙げるなら、ヴァイオレットへの負担がものすごいことになること。
「私、『黒鳥の歌』に別名義で投稿する」
「え? でも、お嬢様は『純白のあなたへ』は小説を連載してますよね。それでいっつも、執務に追われた後に執筆しているせいで締め切りギリギリになって、焦って徹夜してますよね! お嬢様が倒れたら旦那様に怒られるの俺なんですよ!!」
ヴィクトルは嘆いた。彼ははヴァイオレットの従者とはいえ、雇い主は公爵だ。だから公爵の対応が気になるのは理解できる。けれどここまで露骨に訴えることはいかがなものか。
けれどこの会話をすることはいつものことなので、ヴァイオレットは気にしない。
「関係ないわ。私は私がやりたいことをやるだけよ」
「急にお金に物言わせる嫌味な令嬢みたいなこと言わないでくださいよ!」
「それはそうよ。私は今悪役令嬢なのだから」
「ニセモノのですよ!」
ヴァイオレットは自らの濃紺の髪を指先でくるくると遊んだ。
この髪色も涼しげな目と称される吊り目も、人々には冷酷なイメージを植え付けているのではないかと本人は思っている。
けれどそれは逆でその洗練された容姿と仕事が出来過ぎる内面が多くの人々を惹きつける魅力になっているのだ。
「ヴィクトル、善は急げよ。公爵家に帰りましょう」
そう言って颯爽と舞踏会会場に戻っていく。ヴィクトルは急いでその背中を追いかけた。
バルコニーから一足舞踏会会場に足を踏み入れると、ただのヴァイオレットはいなくなる。
正真正銘の公爵令嬢ヴァイオレット・ヴァスールになるのだ。公爵令嬢として幼少期から身につけた礼儀作法、彼女の実績からくる自信、生まれもった気品がこれでもかというほど発揮される。
(さすが、公爵令嬢ヴァイオレット、だな)
そしてヴィクトルもそんな彼女に相応しい従者の顔をつくる。できるだけ彼女にとって相応しい人間であるために。
......
舞踏会会場に戻ると何やら様子が変化していた。合奏隊の音楽が止み、貴族たちが一つの方向を見つめている。
ヴァイオレットもそれに習うようにして視線を向けた。
(ああ、そういうことね)
会場の中に作られたバルコニーには、べルターニュ王国王太子リオネル・べルターニュがいた。
金髪に碧眼という物語の中に出てきそうな容姿をしている。まさに王道ヒーローのような見た目だ。しかし愛想が悪く、表情筋が硬い。
じっと見つめているとリオネルはその視線に気がついたのか少し首を動かしてヴァイオレットの方を見た。そして目を細めてふっと微笑んで見せる。
すると貴族たちの視線がヴァイオレットに集中した。無理もない。笑わないと噂の王太子が彼女にだけ微笑んで見せたのだから。
(リオネル、何してくれているの......!)
心の中で頭を抱える。そして、動揺を微塵も感じさせないのがヴァイオレットの特技だった。
リオネルの微笑みにヴァイオレットは動揺しなかった。それを見た貴族たちはリオネル王太子は公爵令嬢ヴァイオレットに微笑んだわけではなさそうだと錯覚し、視線を外した。
その反応にヴァイオレットは安堵した。
ベルターニュ王国では王家と公爵家はとても近い地位に収まっている。ゆえに国王と公爵の距離も公私共に近いため、ヴァイオレットとリオネルは幼い頃から交流があった。
気が強いヴァイオレットと泣き虫のリオネル。王宮では彼女の後ろを弟のようにしてついてまわるリオネルの姿が度々目撃されていた。
それが今では氷の王太子と呼ばれている。人間はどう変わるかわからないものだと、ヴァイオレットは思った。
「ま、こんなところで足止めを喰らっている暇はないのだけれど」
ヴァイオレットは誰にも聞かれないようにそっと呟いた。
現在の目標は公爵家に帰り、オフ会(お茶会)の準備を進めること。雑誌『黒鳥の歌』へ投稿する作品の執筆も進めなければならない。
『黒鳥の歌』に掲載されるには数多くの作品の中から編集部に選ばれなければいけない。そこが第一関門だ。
(やってやるわよ)
それがヴァイオレットの現役作家魂に火をつけた。壁に当たってからが勝負本番。それは社交界だろうが、作家の世界だろうが変わりはない。
今頃、ヴィクトルが帰りの馬車を用意してくれているはずだ。
ヴァイオレットは一礼をして舞踏会会場を後にした。
……
「ヴァスール公爵令嬢!」
馬車に向かうために廊下を歩いているとヴァイオレットを引き止める声が聞こえた。
急いでいるとはいえ無視することはできず、振り返った。
「ご機嫌よう。何か御用でしょうか」
声をかけてきたのは黒の燕尾服に身を包んだ若い男性だった。かなり緊張しているようで頬が赤くなっている。
「失礼致します、公爵令嬢。私は先の辞令でリオネル王太子殿下の従者となりました、ハエルと申します。リオネル王太子殿下より、会って話がしたいと言付けを預かっております」
(なんの用事かしら)
内心疑問に思ったが、今はそれよりもやらなければならないことがある。
「申し訳ないのですけれど、私は今急いでおりまして。お会いすることは難しいのです。王太子殿下にもそうお伝えください。もし緊急のお話ならば改めて連絡をいただきたく存じます」
「か、かしこまりました。王太子殿下にもそうお伝えいたします」
一礼をするとハエルは舞踏会会場へと戻っていった。
王太子付きの従者も大変だとヴァイオレットは思った。
......
「戻ったわよ!」
「え? お嬢様お早いお戻りで」
ヴァイオレットの侍女、リラは驚きながらも彼女の荷物を受け取る。
「ええ、やることができてしまったの。急いで準備に取りかかるわ」
「......まさか、また創作関連でございますか」
「ええそうね」
軽く返事をしてしまってからヴァイオレットは後悔した。
リラはまだ16歳と18歳であるヴァイオレットよりも若いが、侍女としての教養をしっかりと兼ね備えている女性だ。ゆえに責任感も強い。
顔を見ずともわかる。彼女は静かな顔で起こっていると。
「ヴァイオレット様、私はヴァイオレット様の侍女でございます。旦那様よりヴァイオレット様の身の回りの管理を任されている立場です。寝不足でくまをこしらえることを許すことはできないのです」
「で、でも、どうしてもやりたいことなのよ」
「でも、ではございません。体調に影響が出るようなことをなさるつもりなら私は見過ごすわけにはいきません」
「きちんと寝て体調には気をつけるって約束するわ」
ヴァイオレットが懇願するとリラは少し呆れたような顔をした。
「お約束できますか?」
「できるわ」
「では私はお嬢様をお支えいたしましょう」
「ありがとう、リラ!」
感情を表には出さないことで有名な主人が嬉しそうに笑う姿を見て、全くどちらが年上なのかわかったものではないとリラは思うのだった。
二ヶ月後、ヴァイオレットは普段着ている豪奢なドレスではなく、質素なワンピースに身を包んでいた。
長い濃紺の髪はリラに手伝ってもらって三つ編みにした。
「どうかしら。変ではない? リラ」
「ええ、バッチリでございます、お嬢様。ですがお顔や仕草で貴族とバレてしまう可能性がございますので、ご注意くださいね」
「わかってる」
「それならばよろしいのです」
本日はヴァイオレットの念願が叶う日だ。そう、オフ会(お茶会)が開かれる日なのである。
2ヶ月の準備期間を考えると我ながらよくやったと自画自賛したいほどだった。
公爵令嬢としての執務をこなしつつ、『黒鳥の歌』への投稿作を完成させた。それに加えて寝不足による体調不良は避けるというリラとの約束も果たした。
数日徹夜をしてしまった日もあるがそれはご愛嬌だ。
完成した原稿を『黒鳥の歌』の出版社へ送り読み切りではあったものの、掲載されることが決定した。
めでたく『黒鳥の歌』にオフ会の参加を募集することができ、大満足だった。
(それに『白蝶の君は黒に染まる』の作者もオフ会に参加をする)
これは嬉しい誤算だ。ヴァイオレットは初めて開いたオフ会(お茶会)に作者本人がやってきてくれるとは思っていなかった。今後何度かオフ会を開いたうちの一回でも参加をしてくれればいいと考えていたから。
机の上に置いてある参加者リストを手に取った。
今回のオフ会の参加者はヴァイオレットを含めて6名。
参加者リスト
『白蝶の君は黒に染まる』の作者 R.S
『白蝶の君は黒に染まる』の作者の付き添い人
一般投稿者 エリ
一般投稿者 K
ここにヴァイオレットが加わる。そしてなんとヴィクトルも参加することになっていた。
ヴィクトルにオフ会の日は従者としてついてこなくていいからと休暇を言い渡したはずだが、どうしても行くと言い張りヴァイオレットの友人としてついていくことになったのだ。
本人曰く、いつでもどんな時でもお嬢様の安全をお守りすることが俺の仕事ですから!! と言っていた。
いつもの彼なら休暇を言い渡されれば、剣の腕を上げる目的でヴァスール公爵家の騎士たちの訓練に参加をするか、街に遊びにいくかのどちらかをするのだ。
間違っても休暇を拒否するようなことはしない。
それなのにどうしてついていくと言っているかというと、
(たぶん、『白蝶の君は黒に染まる』の作者に会いたいのよね)
彼は素直な男だ。以前の舞踏会で『白蝶の君は黒に染まる』の話をしてくれた時もこの作品のファンだと言っていた。
「お嬢様、準備はできましたか?」
ヴァイオレットの部屋と扉を開けてヴィクトルがひょこっと顔を出した。
口角が上がっている。相当今日のオフ会を楽しみにしていたようだ。
「ヴィクトル様、部屋の扉を開ける際は必ずノックをしてくださいと申し上げているはずでございます! お嬢様がお着替え中でなかったからよかったものの......」
「はいはい、リラ。わかってるって」
「わかっておられないから毎回ノックをしないのでしょう!」
リラが怒っているのに対してヴィクトルは素知らぬ顔だ。
「リラ、あんまり怒らないで。怒るのも体力がいるのよ」
「確かに、無駄なことに使う労力はそれこそ無駄ですものね。さすがお嬢様です」
「ちょっと二人とも会話が全部聞こえてますけど?」
いつも通りの三人の会話だ。
一歩外に出てしまえば三人の間には決定的な身分差が生まれてしまう。けれど扉の内側では暗黙の了解で許されている。
この空気感はヴァイオレットにとって安らぎだ。
「準備は整ったことだし、オフ会に向かうわよヴィクトル。言ってくるわねリラ」
「はいお嬢様」
「お二人とも置きおつけて。......ヴィクトル様、お嬢様をよろしくお願いいたします」
「任されました」
ヴァイオレットとヴィクトルは裏門から出て、徒歩でオフ会会場へ向かった。
オフ会(お茶会)会場は街の角にある煉瓦造りの建物の一室を借りていた。
隠れ家のような雰囲気のある部屋で物語好きにはたまらない空間だ。ヴァイオレットも好奇心が刺激されている。
色付きガラスがあしらわれたテーブルには花模様をモチーフにしたケーキスタンドが並ぶ。そこに白い陶器で作られたティーカップが添えられていた。
リラに頼んでオフ会の会場を手配してもらったが予想以上に素敵な場所だった。
(帰ったらお礼を言わないとね)
今回のオフ会の主催者はヴァイオレットだ。参加者たちを出迎えるために扉に一番近い席で待つ。隣にはヴィクトルが立っていた。
「ところでお嬢様、今日のオフ会ではなんとお呼びすればよろしいですか」
変装をしてオフ会にやってきたというのに、お嬢様と呼んでしまっては意味がない。貴族の令嬢だということがバレてしまうから。
「今日は私が使っているペンネームのベルと呼んでちょうだい」
「ベルですね、わかりました。お嬢様は......ベルさんは本当にその名前がお好きなようで」
ヴァイオレットのペンネームはベルだ。
この名前はかつてベルターニュ王国にいた魔法使い、ベル・シャリエから取ったものだ。
ベル・シャリエは王国初の女性魔法使いで、現在の魔法使いブームの火付け役。女性という立場でありながら、男性優位の社会の中で躍進し、王国専属の魔法使いとなった。
ベル・シャリエの活躍により、女性の地位が飛躍的に上昇。ヴァイオレットが公爵令嬢として名を馳せてるのもその影響が大きい。ベル・シャリエの存在がなければどれだけ優秀な女性であっても、その能力を発揮することは難しかっただろうから。
「そうよ、私の憧れだもの」
「ベルさんはベル・シャリエについての絵本を幼い頃からかじりついて見ていましたしね」
「ヴィーその言い方どうにかできないの」
「おっとすみません。俺の口が失礼をしました」
すると、トントンと部屋の扉をノックする音が聞こえた。オフ会の参加者が到着したのだろう。タイミングがいい男だとヴァイオレットは肩をすくめた。
ヴィクトルがはーいと返事をして扉を開ける。
「お待ちしていました。主催者のベルはすでに到着しております。どうぞお入りください」
ヴィクトルはよそ行きの顔で微笑んだ。
扉の外に立っていたのは二人の男性だった。
一人は黒色の短髪にシャツととてもラフな格好の男性で、もう一人の男性は背は高そうなものの体の線が出ないようなブカブカの服を着ていた。顔を隠すためなのか帽子を一番深くまで被っていた。
「出迎えありがとうございます。俺は『白蝶の君は黒に染まる』の作者の付き添い人 です。俺の隣にいるのが作者本人です」
黒髪の男性はヴィクトルに向かって自己紹介をした。切長の目で堂々とした立ち振る舞いをしている。ブカブカの服の男性は紹介に同意するようにこくこくと頷くだけだった。
(これがお嬢様が言ってた身分を明かされたくない貴族ってやつか)
声を出さず、体のつきを曖昧にし、顔まで隠している。それほどまでに名の知れた人なのだろう。
(でもどっかで見たことある気がするんだよなー)
帽子を深くまで被っていてもところどころから金髪がはみ出している。あと少しで思い出せそうなのだが、どこかに引っかかっているかのように出てこない。
「ヴィーどうしたの? 参加者の方が来たならお通しして」
ヴァイオレットが言った。その言葉にブカブカの服を着た男が反応した。
「ヴィー? ......もしかしてヴァイオレットが来ているのか」
声は小さかったが、ヴィクトルの耳には確かに届いた。
その瞬間懐に携えていた短剣を抜いた。このオフ会は匿名性のものだ。主催者や参加者の身分や名前が漏れることはない。だからこの男がヴァイオレットの名前を口にすることはないはずなのだ。
「ヴァイオレット様、ぜひ今度伯爵家のお茶会にいらしてください!」
「わたくも! 入所困難な異国の茶葉がようやく手に入りましたの。一度いらしてくだされば光栄ですわ」
「ヴァイオレット様、それでしたらわたくしも……」
公爵令嬢ヴァイオレット・ヴァスールは困惑していた。しかしそれを表情に出すことはない。今回は久しぶりに舞踏会へと足を運んだわけなのだが、会が始まって早々にたくさんのご令嬢に囲まれている。
正直貴族たちに見向きもされず壁の花になりながら、様子を伺いつつすぐに屋敷へ帰ろうと目論んでいたのだ。しかしそれはかなわなそうだ。
(これではわたくしが悪役令嬢になった意味がないわ!)
ヴァイオレットは囲んで話しかけてきた令嬢たちを適当に言いくるめてバルコニーに退散した。
「ねえ、ヴィーそこにいるわよね」
「はい、お嬢様。何か御用でしょうか」
「うわ、なにその話し方。今このバルコニーには私たちしかいないのよ。普段通り話してちょうだい」
「お嬢様がそうおっしゃるなら遠慮なく。……早々に舞踏会から抜け出してきてどうしたんだよ」
影に身を潜めていたヴィクトル・バロンが姿を表した。彼は男爵家の次男であるが、家通しのつながりで幼い頃からヴァイオレットの従者をしている。
「どうしたもこうしたもないわ! 私は今日舞踏会の壁になるつもりで来たのよ。それなのにたくさんの令嬢たちに囲まれたの」
「あーそれはそうっすよね」
「何? 何か知ってるの?」
「何か知ってるも何も……。お嬢様は貴族のご令嬢たちに今すごく人気があるんですよ」
「どうして!? わたくしは悪役令嬢になったのよ。今はたくさんの貴族たちに嫌われているはずなのに」
ヴァイオレットはここ数ヶ月、悪役令嬢になるために勤めてきた。
定期的に出席していた社交の場に姿を見せなくしたり、貴族たちからの誘いを断ったり、無断欠席をしてみたり手は尽くしてきた。
「それが、うまくいっていないんですよねー」
ヴィクトルはある一冊の雑誌を差し出した。ヴァイオレットはそれを受け取る。
「これ、私が投稿している文芸雑誌のライバル誌じゃない!」
「そう。お嬢様、表紙をよく見てみてください」
「えーと、『集中連載! 白蝶の君は黒に染まる』何かしらこれ」
ページをめくると、一面に小説の特集が出てきた。大胆にも挿絵が掲載されている。黒蝶と黒薔薇をモチーフにしたドレスに身を包み、偉そうにふんぞりかえっている令嬢がいる。そしてその絵には見覚えがあった。
「これ、わたくしだわ!」
「そうなんですよね。お嬢様をモデルにして書かれた小説のようです。白蝶として社交界のトップに君臨していた主人公が実は魔法使いで、国を守る時間を作るために悪女を演じるストーリーらしくて。これを読んだご令嬢たちはお嬢様に夢中なんですよ」
魔法使いはベルターニュ王国では憧れの職業のうちの一つだ。しかし魔法使いになるには生まれつきの才能が最も必要であり、魔力量が多ければ多いほど実力は上がっていく。
根性論で魔力量をあげていく方法はあるにはあるがほとんどの人はそれを選択しない。
その一つの理由としてベルターニュ王国では魔力を持たない人が大半を占めておりわざわざ魔力を上げる必要がないからだ。
「そんな! というかあなた、どうしてそんなに内容に詳しいのよ」
「俺もその小説のファンの一人ですから」
「以前からこの小説を知っていたの? それなら教えてくれてもいいじゃない」
「執筆の時間が惜しいからと、俺の話を普段から聞いていないのはどこのご令嬢でしょうねー」
そう言われてしまえばヴァイレットはぐうの音も出なかった。
ヴァイオレット・ヴァスールは公爵令嬢として社交界を代表する存在として有名だった。涼しげな目元。美しい濃紺色の髪に、スッと伸びた背筋。純白の刺繍が施されたドレスはまるで優雅に舞う蝶を想起させた。ついた通称は『白蝶の君』。
公爵令嬢としての役割を忠実に果たし、ご令嬢たちの憧れの的だった。
一方で本人は公爵家で割り当てられた役割をこなす日々を過ごし、内心飽き飽きしていた。そんなある日、整理していた書類の中に一冊の雑誌『純白のあなたへ』が紛れ込んでいたのだ。『純白のあなたへ』は女性向け雑誌で主に市民のたちの娯楽としてベルターニュ王国全土に普及している。
ヴァイオレットもそのことは噂好きの侍女から聞いていたものの本物を見るのは初めてだった。仕事の息抜きにでもと軽い気持ちで手に取った。
それがいけなかった。専属作家の連載作品、有名作家の短編など心躍る話の世界に没頭し、仕事を忘れて読みふけってしまった。特に興味をそそられたのは『純白のあなたへ』の読者が投書をする投稿欄だった。
投稿欄では読者が独自のペンネームを使用し、その人物になりきってやり取りをするのだ。
......
わたくしは辺境に住まう、小さな乙女ですの。瞬きするまもなく、薫風と共にわたくしの日々が過ぎ去っていくのです。その毎日に飽き飽きしているというわけではなく、むしろ幸運だとさえ思っているのです。ああ、しかしどこか物寂しいと思ってしまうのは我儘なことでしょうか。
PN 辺境の乙女
辺境の乙女さん、ごきげんよう。わたしは王都の片隅に住む未亡人ですわ。片隅にはおりますけれども、家の外には王都特有の喧騒があります。わたしは外出することがほとんどありませんから、ゆったりとした時間を過ごしております。しかし時々わたしだけが時の流れに取り残されているのではないかと、思いがくすぶるのです。きっとわたしたちいい友人になれるでしょう。
PN 小さな窓辺の未亡人
......
「な、何かしらこれは」
ヴァイオレットは初めて投稿文を読んだ時、まさに晴天の霹靂を受けた。優美な文章、それでいてつかみどころのない少女と大人の女性の様子。
あなたは、どんな人なの教えて。これが流行りの萌えというやつか。
読むたびに彼女たちの魅力に取り込まれていった。
ヴァイオレットはそれからすぐに仕事の整理を始めた。できるだけ無駄を省き、自分の時間を創作活動に充てたいと思ったからだ。
悪役令嬢を演じ始めたこともその一環だ。無駄な関係を省き、物事がより円滑に進むようにしようと動いていた。
まさかそれが失敗するとは考えていなかったけれども。
「こうなったら作者に連載をやめるように言うしかないわね」
創作の時間を確保するためだ。やるしかない。ヴァイオレットは決意した。
「公爵家の権力を使うんですか?」
「そんな卑怯なことはしない。やるなら正攻法でよ」
ヴァイオレットは卑怯なことは好きではない。政治のことなら致し方ないと割り切ることができるが、創作活動はあくまで趣味だ。だから権力は行使しない。
これは彼女の美学であり、頑固な性格の現れでもある。
ヴィクトルもそれは理解しているため、特に反対はしなかった。そういうところが悪役令嬢になりきれない理由だとわかっているが口にはしない。
「わかりました。それで具体的に何をするんです?」
「お茶会という名のオフ会よ」
「オフ会?」
「ええ、創作活動をしている作家たちが集まって、お茶やお菓子を楽しみながら好みの作品について語り合うの。雑誌の投稿欄に主催者からの募集が載ってるわ」
表向きにお茶会としている理由は創作活動をしていることを知られたくない人も参加しやすくするためだ。
ヴァイオレットは雑誌の最後のページを指差した。確かに広告の下に小さくオフ会(お茶会)の告知が載っている。
「ではお嬢様はここに告知を載せて『白蝶の君は黒に染まる』の作者に会うんですね」
「そうよ」
「でも、お嬢様『黒鳥の歌』は『純白のあなたへ』のライバル誌でしょ。それに急にライバル誌から作家がやってきてオフ会の宣伝をするなんて、どう考えても怪しまれると思うんですけど」
「問題はそこなの。そんなことしたら100%怪しまれる」
だからヴァイオレットは考えた。
誰にも怪しまれることなくオフ会を開催し、『白蝶の君は黒に染まる』の作者に会う方法を。
やはりこれしか思い浮かばない。この方法が一番確実で穏便に済ませられる方法だ。一つ懸念点を挙げるなら、ヴァイオレットへの負担がものすごいことになること。
「私、『黒鳥の歌』に別名義で投稿する」
「え? でも、お嬢様は『純白のあなたへ』は小説を連載してますよね。それでいっつも、執務に追われた後に執筆しているせいで締め切りギリギリになって、焦って徹夜してますよね! お嬢様が倒れたら旦那様に怒られるの俺なんですよ!!」
ヴィクトルは嘆いた。彼ははヴァイオレットの従者とはいえ、雇い主は公爵だ。だから公爵の対応が気になるのは理解できる。けれどここまで露骨に訴えることはいかがなものか。
けれどこの会話をすることはいつものことなので、ヴァイオレットは気にしない。
「関係ないわ。私は私がやりたいことをやるだけよ」
「急にお金に物言わせる嫌味な令嬢みたいなこと言わないでくださいよ!」
「それはそうよ。私は今悪役令嬢なのだから」
「ニセモノのですよ!」
ヴァイオレットは自らの濃紺の髪を指先でくるくると遊んだ。
この髪色も涼しげな目と称される吊り目も、人々には冷酷なイメージを植え付けているのではないかと本人は思っている。
けれどそれは逆でその洗練された容姿と仕事が出来過ぎる内面が多くの人々を惹きつける魅力になっているのだ。
「ヴィクトル、善は急げよ。公爵家に帰りましょう」
そう言って颯爽と舞踏会会場に戻っていく。ヴィクトルは急いでその背中を追いかけた。
バルコニーから一足舞踏会会場に足を踏み入れると、ただのヴァイオレットはいなくなる。
正真正銘の公爵令嬢ヴァイオレット・ヴァスールになるのだ。公爵令嬢として幼少期から身につけた礼儀作法、彼女の実績からくる自信、生まれもった気品がこれでもかというほど発揮される。
(さすが、公爵令嬢ヴァイオレット、だな)
そしてヴィクトルもそんな彼女に相応しい従者の顔をつくる。できるだけ彼女にとって相応しい人間であるために。
......
舞踏会会場に戻ると何やら様子が変化していた。合奏隊の音楽が止み、貴族たちが一つの方向を見つめている。
ヴァイオレットもそれに習うようにして視線を向けた。
(ああ、そういうことね)
会場の中に作られたバルコニーには、べルターニュ王国王太子リオネル・べルターニュがいた。
金髪に碧眼という物語の中に出てきそうな容姿をしている。まさに王道ヒーローのような見た目だ。しかし愛想が悪く、表情筋が硬い。
じっと見つめているとリオネルはその視線に気がついたのか少し首を動かしてヴァイオレットの方を見た。そして目を細めてふっと微笑んで見せる。
すると貴族たちの視線がヴァイオレットに集中した。無理もない。笑わないと噂の王太子が彼女にだけ微笑んで見せたのだから。
(リオネル、何してくれているの......!)
心の中で頭を抱える。そして、動揺を微塵も感じさせないのがヴァイオレットの特技だった。
リオネルの微笑みにヴァイオレットは動揺しなかった。それを見た貴族たちはリオネル王太子は公爵令嬢ヴァイオレットに微笑んだわけではなさそうだと錯覚し、視線を外した。
その反応にヴァイオレットは安堵した。
ベルターニュ王国では王家と公爵家はとても近い地位に収まっている。ゆえに国王と公爵の距離も公私共に近いため、ヴァイオレットとリオネルは幼い頃から交流があった。
気が強いヴァイオレットと泣き虫のリオネル。王宮では彼女の後ろを弟のようにしてついてまわるリオネルの姿が度々目撃されていた。
それが今では氷の王太子と呼ばれている。人間はどう変わるかわからないものだと、ヴァイオレットは思った。
「ま、こんなところで足止めを喰らっている暇はないのだけれど」
ヴァイオレットは誰にも聞かれないようにそっと呟いた。
現在の目標は公爵家に帰り、オフ会(お茶会)の準備を進めること。雑誌『黒鳥の歌』へ投稿する作品の執筆も進めなければならない。
『黒鳥の歌』に掲載されるには数多くの作品の中から編集部に選ばれなければいけない。そこが第一関門だ。
(やってやるわよ)
それがヴァイオレットの現役作家魂に火をつけた。壁に当たってからが勝負本番。それは社交界だろうが、作家の世界だろうが変わりはない。
今頃、ヴィクトルが帰りの馬車を用意してくれているはずだ。
ヴァイオレットは一礼をして舞踏会会場を後にした。
……
「ヴァスール公爵令嬢!」
馬車に向かうために廊下を歩いているとヴァイオレットを引き止める声が聞こえた。
急いでいるとはいえ無視することはできず、振り返った。
「ご機嫌よう。何か御用でしょうか」
声をかけてきたのは黒の燕尾服に身を包んだ若い男性だった。かなり緊張しているようで頬が赤くなっている。
「失礼致します、公爵令嬢。私は先の辞令でリオネル王太子殿下の従者となりました、ハエルと申します。リオネル王太子殿下より、会って話がしたいと言付けを預かっております」
(なんの用事かしら)
内心疑問に思ったが、今はそれよりもやらなければならないことがある。
「申し訳ないのですけれど、私は今急いでおりまして。お会いすることは難しいのです。王太子殿下にもそうお伝えください。もし緊急のお話ならば改めて連絡をいただきたく存じます」
「か、かしこまりました。王太子殿下にもそうお伝えいたします」
一礼をするとハエルは舞踏会会場へと戻っていった。
王太子付きの従者も大変だとヴァイオレットは思った。
......
「戻ったわよ!」
「え? お嬢様お早いお戻りで」
ヴァイオレットの侍女、リラは驚きながらも彼女の荷物を受け取る。
「ええ、やることができてしまったの。急いで準備に取りかかるわ」
「......まさか、また創作関連でございますか」
「ええそうね」
軽く返事をしてしまってからヴァイオレットは後悔した。
リラはまだ16歳と18歳であるヴァイオレットよりも若いが、侍女としての教養をしっかりと兼ね備えている女性だ。ゆえに責任感も強い。
顔を見ずともわかる。彼女は静かな顔で起こっていると。
「ヴァイオレット様、私はヴァイオレット様の侍女でございます。旦那様よりヴァイオレット様の身の回りの管理を任されている立場です。寝不足でくまをこしらえることを許すことはできないのです」
「で、でも、どうしてもやりたいことなのよ」
「でも、ではございません。体調に影響が出るようなことをなさるつもりなら私は見過ごすわけにはいきません」
「きちんと寝て体調には気をつけるって約束するわ」
ヴァイオレットが懇願するとリラは少し呆れたような顔をした。
「お約束できますか?」
「できるわ」
「では私はお嬢様をお支えいたしましょう」
「ありがとう、リラ!」
感情を表には出さないことで有名な主人が嬉しそうに笑う姿を見て、全くどちらが年上なのかわかったものではないとリラは思うのだった。
二ヶ月後、ヴァイオレットは普段着ている豪奢なドレスではなく、質素なワンピースに身を包んでいた。
長い濃紺の髪はリラに手伝ってもらって三つ編みにした。
「どうかしら。変ではない? リラ」
「ええ、バッチリでございます、お嬢様。ですがお顔や仕草で貴族とバレてしまう可能性がございますので、ご注意くださいね」
「わかってる」
「それならばよろしいのです」
本日はヴァイオレットの念願が叶う日だ。そう、オフ会(お茶会)が開かれる日なのである。
2ヶ月の準備期間を考えると我ながらよくやったと自画自賛したいほどだった。
公爵令嬢としての執務をこなしつつ、『黒鳥の歌』への投稿作を完成させた。それに加えて寝不足による体調不良は避けるというリラとの約束も果たした。
数日徹夜をしてしまった日もあるがそれはご愛嬌だ。
完成した原稿を『黒鳥の歌』の出版社へ送り読み切りではあったものの、掲載されることが決定した。
めでたく『黒鳥の歌』にオフ会の参加を募集することができ、大満足だった。
(それに『白蝶の君は黒に染まる』の作者もオフ会に参加をする)
これは嬉しい誤算だ。ヴァイオレットは初めて開いたオフ会(お茶会)に作者本人がやってきてくれるとは思っていなかった。今後何度かオフ会を開いたうちの一回でも参加をしてくれればいいと考えていたから。
机の上に置いてある参加者リストを手に取った。
今回のオフ会の参加者はヴァイオレットを含めて6名。
参加者リスト
『白蝶の君は黒に染まる』の作者 R.S
『白蝶の君は黒に染まる』の作者の付き添い人
一般投稿者 エリ
一般投稿者 K
ここにヴァイオレットが加わる。そしてなんとヴィクトルも参加することになっていた。
ヴィクトルにオフ会の日は従者としてついてこなくていいからと休暇を言い渡したはずだが、どうしても行くと言い張りヴァイオレットの友人としてついていくことになったのだ。
本人曰く、いつでもどんな時でもお嬢様の安全をお守りすることが俺の仕事ですから!! と言っていた。
いつもの彼なら休暇を言い渡されれば、剣の腕を上げる目的でヴァスール公爵家の騎士たちの訓練に参加をするか、街に遊びにいくかのどちらかをするのだ。
間違っても休暇を拒否するようなことはしない。
それなのにどうしてついていくと言っているかというと、
(たぶん、『白蝶の君は黒に染まる』の作者に会いたいのよね)
彼は素直な男だ。以前の舞踏会で『白蝶の君は黒に染まる』の話をしてくれた時もこの作品のファンだと言っていた。
「お嬢様、準備はできましたか?」
ヴァイオレットの部屋と扉を開けてヴィクトルがひょこっと顔を出した。
口角が上がっている。相当今日のオフ会を楽しみにしていたようだ。
「ヴィクトル様、部屋の扉を開ける際は必ずノックをしてくださいと申し上げているはずでございます! お嬢様がお着替え中でなかったからよかったものの......」
「はいはい、リラ。わかってるって」
「わかっておられないから毎回ノックをしないのでしょう!」
リラが怒っているのに対してヴィクトルは素知らぬ顔だ。
「リラ、あんまり怒らないで。怒るのも体力がいるのよ」
「確かに、無駄なことに使う労力はそれこそ無駄ですものね。さすがお嬢様です」
「ちょっと二人とも会話が全部聞こえてますけど?」
いつも通りの三人の会話だ。
一歩外に出てしまえば三人の間には決定的な身分差が生まれてしまう。けれど扉の内側では暗黙の了解で許されている。
この空気感はヴァイオレットにとって安らぎだ。
「準備は整ったことだし、オフ会に向かうわよヴィクトル。言ってくるわねリラ」
「はいお嬢様」
「お二人とも置きおつけて。......ヴィクトル様、お嬢様をよろしくお願いいたします」
「任されました」
ヴァイオレットとヴィクトルは裏門から出て、徒歩でオフ会会場へ向かった。
オフ会(お茶会)会場は街の角にある煉瓦造りの建物の一室を借りていた。
隠れ家のような雰囲気のある部屋で物語好きにはたまらない空間だ。ヴァイオレットも好奇心が刺激されている。
色付きガラスがあしらわれたテーブルには花模様をモチーフにしたケーキスタンドが並ぶ。そこに白い陶器で作られたティーカップが添えられていた。
リラに頼んでオフ会の会場を手配してもらったが予想以上に素敵な場所だった。
(帰ったらお礼を言わないとね)
今回のオフ会の主催者はヴァイオレットだ。参加者たちを出迎えるために扉に一番近い席で待つ。隣にはヴィクトルが立っていた。
「ところでお嬢様、今日のオフ会ではなんとお呼びすればよろしいですか」
変装をしてオフ会にやってきたというのに、お嬢様と呼んでしまっては意味がない。貴族の令嬢だということがバレてしまうから。
「今日は私が使っているペンネームのベルと呼んでちょうだい」
「ベルですね、わかりました。お嬢様は......ベルさんは本当にその名前がお好きなようで」
ヴァイオレットのペンネームはベルだ。
この名前はかつてベルターニュ王国にいた魔法使い、ベル・シャリエから取ったものだ。
ベル・シャリエは王国初の女性魔法使いで、現在の魔法使いブームの火付け役。女性という立場でありながら、男性優位の社会の中で躍進し、王国専属の魔法使いとなった。
ベル・シャリエの活躍により、女性の地位が飛躍的に上昇。ヴァイオレットが公爵令嬢として名を馳せてるのもその影響が大きい。ベル・シャリエの存在がなければどれだけ優秀な女性であっても、その能力を発揮することは難しかっただろうから。
「そうよ、私の憧れだもの」
「ベルさんはベル・シャリエについての絵本を幼い頃からかじりついて見ていましたしね」
「ヴィーその言い方どうにかできないの」
「おっとすみません。俺の口が失礼をしました」
すると、トントンと部屋の扉をノックする音が聞こえた。オフ会の参加者が到着したのだろう。タイミングがいい男だとヴァイオレットは肩をすくめた。
ヴィクトルがはーいと返事をして扉を開ける。
「お待ちしていました。主催者のベルはすでに到着しております。どうぞお入りください」
ヴィクトルはよそ行きの顔で微笑んだ。
扉の外に立っていたのは二人の男性だった。
一人は黒色の短髪にシャツととてもラフな格好の男性で、もう一人の男性は背は高そうなものの体の線が出ないようなブカブカの服を着ていた。顔を隠すためなのか帽子を一番深くまで被っていた。
「出迎えありがとうございます。俺は『白蝶の君は黒に染まる』の作者の付き添い人 です。俺の隣にいるのが作者本人です」
黒髪の男性はヴィクトルに向かって自己紹介をした。切長の目で堂々とした立ち振る舞いをしている。ブカブカの服の男性は紹介に同意するようにこくこくと頷くだけだった。
(これがお嬢様が言ってた身分を明かされたくない貴族ってやつか)
声を出さず、体のつきを曖昧にし、顔まで隠している。それほどまでに名の知れた人なのだろう。
(でもどっかで見たことある気がするんだよなー)
帽子を深くまで被っていてもところどころから金髪がはみ出している。あと少しで思い出せそうなのだが、どこかに引っかかっているかのように出てこない。
「ヴィーどうしたの? 参加者の方が来たならお通しして」
ヴァイオレットが言った。その言葉にブカブカの服を着た男が反応した。
「ヴィー? ......もしかしてヴァイオレットが来ているのか」
声は小さかったが、ヴィクトルの耳には確かに届いた。
その瞬間懐に携えていた短剣を抜いた。このオフ会は匿名性のものだ。主催者や参加者の身分や名前が漏れることはない。だからこの男がヴァイオレットの名前を口にすることはないはずなのだ。