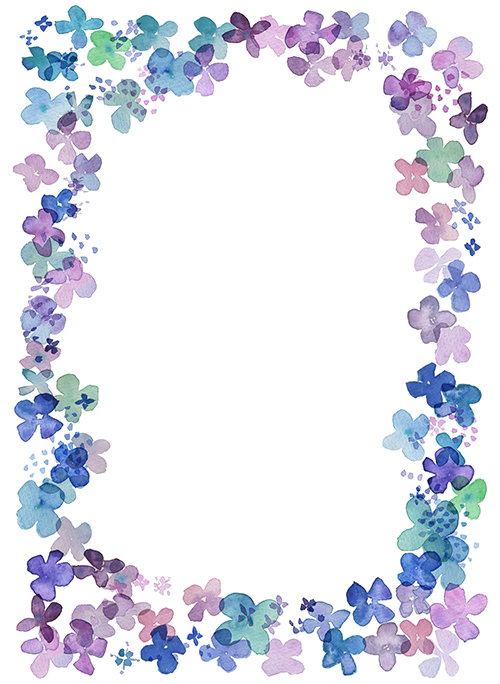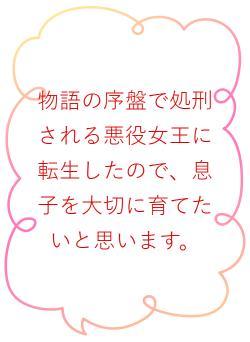美貌の伯爵子息に求婚されましたが、そもそもクレーマーは願い下げですから
第1話 最悪な求婚
「ずっと、エミリーのことを愛していたんだ。僕と結婚してほしい!」
赤い薔薇の花束を向けられて求婚されたら、普通の女性ならときめくのだろうか?
頭の片隅でそんなことを考えながら、エミリーは恭しく跪く男を見下ろし
た。
男は金髪碧眼でいかにも貴族然とした装いをしている。目尻はおっとりと垂れていて、穏やかに微笑む姿は多くの女性を虜にさせるだろう。
エミリーも彼の本性を知らなければ、彼に気を許していたかもしれない。
碧い瞳は海のようにキラキラと輝いていて、自分の美貌に絶対の自信を持っている男は、エミリーが自分の求婚を断るはずがないと考えているに違いない。
返事なんて決まっているとばかりのその姿に、エミリーの顔が見る見るうちに赤くなっていく。
これは照れなどではない。
胸の内から湧き上がるのは、衝動的な怒りだ。
決意して、エミリーは口を開く。
もう後には引けないし、後に引く必要もなかった。
「お断りします!」
期待していた返事が返ってこなかったことに、男が目を剥く。
「なんで!? 僕のどこが駄目なんだ?」
ああ、本当に何もわかっていないという顔だ。
さらに怒りが込み上げる。
相手は貴族だ。それも伯爵家の長男。ゆくゆくはここら一帯を取り仕切る、地主になる男。
平民の女性が、伯爵子息に見初められた。
そう言葉にすると夢のようなことだが、現実はそうではない。
特にエミリーにとって、彼との結婚なんて悍ましさすら覚えるほど最悪なことだった。
「父上にはもう許可をもらっているから、遠慮しなくてもいいんだ。僕は君を愛人ではなく、夫人として迎えるつもりだ。だから、自分の気持ちに正直になってくれ」
反吐が出る。
怒りで震えるエミリーを見て何を勘違いしたのか、近寄ってきた男が薔薇の花束を押し付けるように渡してくる。
エミリーは、その花束を叩き落とした。
地面に落ちた薔薇を見ると胸が痛む。この美しい花に罪はない。
罪があるのは、目の前にいるこの厚顔無恥な男だけだ。
「あなたは、勘違いしています」
「僕がいったい何を勘違いしているって?」
「私はあなたのことを愛していません。それどころか、呪ってすらいるんですよ」
怒りで震える言葉に、男が首を傾げる。
「僕が何をしたっていうんだ?」
「……ほんとうに、それすら理解していないんですね」
エミリーは振り返ると、自分の店の前に掲げられている木製のプレートをバンと叩いた。
「ここに書いてあることが、わかりますか?」
「ああ、このカフェは廃業したと書いてあるな」
「ええ、その通りです。この店の廃業の原因に、何か心当たりは?」
エミリーの言葉に、男は首を傾げる。その顔はやはり何もわかっていないようだった。
この男がエミリーのカフェにやってくるようになってから、いままでエミリーがどんな思いをしてきたのか。
それすらわからずに求婚してくるのだ。理解しているはずがない。
エミリーは、心の中で目の前にいる男を罵った。
(このクレーマー野郎が)
◇
クレーマー野郎――もとい伯爵子息ヨーゼフがカフェにやってくるようになったのは、いまから一年前のことだった。
エミリーの両親が開業したこのカフェは、町の人たちから人気があった。
両親が事故で亡くなってからエミリーはカフェを引き継ぎ、大切に経営してきた。
でも、クレーマー野郎――ヨーゼフが通うようになってから、すべてが変わってしまった。
どうして伯爵家の長男がこのカフェに来るようになったのかはわからない。
けれど、ヨーゼフが初めてこのカフェにやってきた日のことは、嫌でも脳裏にこびりついている。
「なんだ、このまずいコーヒーは」
ヨーゼフの吐き捨てるような言葉に、エミリーは衝撃を受けた。
父から受け継いだ方法で豆を挽いている、当店一番人気のコーヒーだった。誰もが手軽に飲めるように値段も控えめなこともあり、このコーヒーを求めてやってくる人も多い。
だけど、相手は貴族だ。最初は名乗らなかったけれど、装いだけですぐにわかった。
貴族と庶民とでは味覚が違うから合わなかったのだろうと、エミリーは素直に頭を下げた。貴族を敵に回してもいいことはないし、接客業として体面は大切だ。
彼はエミリーの姿を見ると、すぐに人の好い笑みを浮かべて、「君が悪いわけではない」と口にした。
「悪いのはこのコーヒーだ。君のような美しい人が頭を下げる必要はないよ」
ヨーゼフの言葉に、笑みを貼り付かせたままエミリーは耐える。
ギュッと握りしめた手に、この男が来るのはおそらく今日だけだと言い聞かせながら。
でも、ヨーゼフは、それからもよく来店するようになった。
「このパンケーキもおいしくないね。薄いし、クリームも甘すぎる。僕の家で出るものはもっと分厚くって、クリームも僕好みでおいしいのに。バターも安物を使っているのか、なんか変な味がするよ」
パンケーキのレシピは、母から譲り受けたものだった。朝は即完売するほど売れ行きの良いパンケーキだけれど、これも元々庶民向けだ。材料もそうで、貴族向けの高級食材は使われていない。
これもやはり、貴族であるヨーゼフには合わないのだろうと、エミリーはそう思うことで気持ちを落ち着けた。
ヨーゼフはさんざん文句を垂れ流しながらも、多めのお代を置いて店から出て行った。
これでもっといいものを作ってよと、甘いマスクで囁きながら。
もう頼むから来ないでくれと思ったけれど、なぜかヨーゼフは文句を言いながらも毎日のように店にやってきた。
カフェの品に文句を言うだけでは飽き足らず、内装にまでケチをつけはじめた。
やれ古臭い建物だの、カーテンが薄くて風が入ってくるだの、椅子の座り心地が悪いだの。散々な言いようだ。
その度にエミリーの精神はすり減った。
両親から受け継いだ大切なレシピを馬鹿にされて、毎日丁寧に掃除をしている店内を貶されて、それでずっと笑顔でいられるほど寛容ではない。
最初の頃こそ自分に実力が足りないのかと悩んだけれど、次第にそれがおかしいことに気づいた。
常連客からも、「あなたが入れてくれるコーヒーは特別なんだ」とか、「あなたの焼くパンケーキは一級品だよ」とか、「朝はここのコーヒーを飲まないと元気が出ないんだ。あの男のいうことは気にすることはないよ」と温かい言葉をかけられていたから、どうにか耐えることができた。
だけど毎日のようにヨーゼフが店に入り浸っては文句ばかり言うものだから、客足がどんどん遠のいていってしまい、常連客も遠慮して店に訪れなくなった。
残されたのは閑古鳥が鳴く店と、エミリーの両親の死と入れ替わりで拾った、大きな黒い犬だけ。
黒い犬の毛に顔をうずめると、少しは気が楽になる。
でも、ズタズタにされた自尊心が元に戻ることはない。
これまで培ってきたものを、クレーマー野郎によってすべて破壊されてしまったのだから。
カフェの経営は次第に立ち行かなくなっていき、お金も心許なくなった。
だから、エミリーは店を閉めることにしたのだ。
廃業という、最悪な看板を掲げて。
◇
(それなのに、この男は……! 私を愛しているですって? いままで散々、私の大切なものをコケにしてきたくせに。馬鹿にするのもいい加減にしてほしいわ)
ヨーゼフはケロッとした顔をして言う。
「どうして廃業が僕のせいなんだ?」
「あなたが毎日のように店に入り浸って、カフェのメニューをさんざん貶してきたからですよ」
エミリーの言葉に、ヨーゼフが大きく目を見開いた。
やっと自分の行動を理解したのかと思いきや、彼の口から出たのはお花畑のような言葉だった。
「どうしても君に会いたかったんだ。街で見かけたときに一目惚れして、それを伝える勇気がなかったから」
エミリーは怒りと共に混乱する。
(一目惚れをした相手を、貶したというの?)
愛情の裏返しに人を傷つけるなんて、そんなこと子供でもやらないだろう。愚か者のすることだ。
相手を馬鹿にしたらそのぶん傷つくだけで、自分の気持ちに振り向いてくれるわけがない。むしろ余計に嫌いになる行為だろう。
「とうぜん君も気づいていると思ったんだ。だって、君はいつも僕に笑顔で接してくれていただろ?」
「営業スマイルですけど?」
接客業の笑顔を自分への好意と錯覚するなんて、頭が痛くなる。
ヨーゼフ以外の客は、心の底からエミリーのカフェを気に入って、来店してくれた。だから他の客たちには純粋な笑顔で接することができたけれど、このクレーマー野郎だけは違う。
ただの作り物の笑みを好意と勘違いするなんて、なんてめんどくさい男なのだろうか。
「そ、それでも、僕は毎日ここに来ていたんだぞ。君の笑顔を見てコーヒーを飲むと元気になれたし……」
「いつも文句ばかり言っていたのに、それで元気になっていたなんて信じられません。あなたが毎日カフェに入り浸って文句ばかり言うから、ここ数か月ですっかり客足が途絶えてしまったというのに」
「……それは、僕のせいなのか?」
ヨーゼフが首を傾げる。
「客足が途絶えたのは、単純にこのカフェの評判が悪かったからだと思うが……。確か、噂で聞いたことがある。この店のコーヒーがまずいって」
「……それは、あなたのせいでしょう」
また怒りで声が震えてきた。
「なんで僕のせいなんだ?」
「この店のこと、誰かに話しませんでしたか?」
「ああ、そういえば! みんなにこの店のことを知ってもらいたくてな、知人に話したんだ」
「その時に、どう説明したのですか?」
「それは……。コーヒーはまずいが、かわ、かわいい店主のいるカフェがあるって」
なぜかヨーゼフの顔が赤くなる。
(なんで照れてるのよ、気持ち悪い)
この男がただの迷惑客であれば、出禁にすることもできただろう。
だが相手が悪かった。ここら一帯の地主である伯爵家の息子だ。叩き出すことなんてできなかった。
広まった悪評は消すことはできないし、常連客もどんどん足が遠のいてしまい、ヨーゼフ以外に店に訪れる人もいなかった。
悪評を広めた相手が誰なのかは正確には分かっていなかったけれど、おおよその見当はついていた。
(まさか、本当にこの男だったなんて……!)
照れ隠しでコーヒーをまずいと言ったのか、それとも本心だったのかなんてもう関係ない。
この男が流した悪評のせいで、貴族を中心に広まっていき、いつの間にか町の中にも浸透してしまった。
噂というものは不思議なもので、たとえ真実ではなくても一度流れたものが元に戻ることはない。
特に影響力のある人が口にしてしまえば、それはもう取り消せないのだ。
(この男がいなければ、カフェは無事だったはずなのに……)
目の前がぼんやりしてきたと思うと、涙が頬を伝っていく。
「泣いているのか? 悪評は気にするな。君の笑顔とコーヒーは、いつも僕を癒してくれたんだから。……それに僕は、君の泣いている姿ではなく、笑顔が好きだ!」
目の前でおろおろしているこの男が憎い。
もし彼が貴族でなければ、蹴りのひとつでもお見舞いしてやったというのに。
「いいからもう帰ってください。あなたと話すことなんてありません」
「待ってくれ、エミリー。僕は本気で君のことを愛しているんだ」
「私はあなたのことなんて、大っ嫌いです!」
「なっ。……平民の君が、貴族夫人になれるんだぞ。それなのに、僕の求婚を断ったら絶対に後悔するぞ!」
乱暴に袖で涙をぬぐうと、エミリーはただ心底軽蔑した瞳で、目の前で喚くクレーマー野郎をにらみつけた。
「帰れ」
一言に、すべての怒りを込めながら。
エミリーはさっと背を向けると、急いで店内に戻る。
扉の向こうからはまだ何かを喚く声が聞こえてくるが、もう何も聞きたくなかった。
耳を塞いでしゃがみ込む。
(あのクレーマー野郎。地獄に落ちろ)
しばらくそうしていると、鼻先を何かがくすぐった。
目を開けると、ぼんやりとした視界に大きな黒い犬の姿が映った。
『……大丈夫か?』
「ルン!」
エミリーは大きな犬に抱きついた。その黒い毛に顔をうずめる。
柔らかい毛に顔を押しつけると、先ほど止まったと思っていた涙が、後から後から流れていく。
「明日はお引越しだね」
『そうか。オレは、いつまでもエミリーと一緒だ』
伯爵子息の求婚を断ったのだ。もうこの町にはいられない。
カフェの家具などはもうすでに売っている。
借金を返して余ったお金でどこまで行けるかはわからないけれど、エミリーはこの町を出ていくつもりだった。
赤い薔薇の花束を向けられて求婚されたら、普通の女性ならときめくのだろうか?
頭の片隅でそんなことを考えながら、エミリーは恭しく跪く男を見下ろし
た。
男は金髪碧眼でいかにも貴族然とした装いをしている。目尻はおっとりと垂れていて、穏やかに微笑む姿は多くの女性を虜にさせるだろう。
エミリーも彼の本性を知らなければ、彼に気を許していたかもしれない。
碧い瞳は海のようにキラキラと輝いていて、自分の美貌に絶対の自信を持っている男は、エミリーが自分の求婚を断るはずがないと考えているに違いない。
返事なんて決まっているとばかりのその姿に、エミリーの顔が見る見るうちに赤くなっていく。
これは照れなどではない。
胸の内から湧き上がるのは、衝動的な怒りだ。
決意して、エミリーは口を開く。
もう後には引けないし、後に引く必要もなかった。
「お断りします!」
期待していた返事が返ってこなかったことに、男が目を剥く。
「なんで!? 僕のどこが駄目なんだ?」
ああ、本当に何もわかっていないという顔だ。
さらに怒りが込み上げる。
相手は貴族だ。それも伯爵家の長男。ゆくゆくはここら一帯を取り仕切る、地主になる男。
平民の女性が、伯爵子息に見初められた。
そう言葉にすると夢のようなことだが、現実はそうではない。
特にエミリーにとって、彼との結婚なんて悍ましさすら覚えるほど最悪なことだった。
「父上にはもう許可をもらっているから、遠慮しなくてもいいんだ。僕は君を愛人ではなく、夫人として迎えるつもりだ。だから、自分の気持ちに正直になってくれ」
反吐が出る。
怒りで震えるエミリーを見て何を勘違いしたのか、近寄ってきた男が薔薇の花束を押し付けるように渡してくる。
エミリーは、その花束を叩き落とした。
地面に落ちた薔薇を見ると胸が痛む。この美しい花に罪はない。
罪があるのは、目の前にいるこの厚顔無恥な男だけだ。
「あなたは、勘違いしています」
「僕がいったい何を勘違いしているって?」
「私はあなたのことを愛していません。それどころか、呪ってすらいるんですよ」
怒りで震える言葉に、男が首を傾げる。
「僕が何をしたっていうんだ?」
「……ほんとうに、それすら理解していないんですね」
エミリーは振り返ると、自分の店の前に掲げられている木製のプレートをバンと叩いた。
「ここに書いてあることが、わかりますか?」
「ああ、このカフェは廃業したと書いてあるな」
「ええ、その通りです。この店の廃業の原因に、何か心当たりは?」
エミリーの言葉に、男は首を傾げる。その顔はやはり何もわかっていないようだった。
この男がエミリーのカフェにやってくるようになってから、いままでエミリーがどんな思いをしてきたのか。
それすらわからずに求婚してくるのだ。理解しているはずがない。
エミリーは、心の中で目の前にいる男を罵った。
(このクレーマー野郎が)
◇
クレーマー野郎――もとい伯爵子息ヨーゼフがカフェにやってくるようになったのは、いまから一年前のことだった。
エミリーの両親が開業したこのカフェは、町の人たちから人気があった。
両親が事故で亡くなってからエミリーはカフェを引き継ぎ、大切に経営してきた。
でも、クレーマー野郎――ヨーゼフが通うようになってから、すべてが変わってしまった。
どうして伯爵家の長男がこのカフェに来るようになったのかはわからない。
けれど、ヨーゼフが初めてこのカフェにやってきた日のことは、嫌でも脳裏にこびりついている。
「なんだ、このまずいコーヒーは」
ヨーゼフの吐き捨てるような言葉に、エミリーは衝撃を受けた。
父から受け継いだ方法で豆を挽いている、当店一番人気のコーヒーだった。誰もが手軽に飲めるように値段も控えめなこともあり、このコーヒーを求めてやってくる人も多い。
だけど、相手は貴族だ。最初は名乗らなかったけれど、装いだけですぐにわかった。
貴族と庶民とでは味覚が違うから合わなかったのだろうと、エミリーは素直に頭を下げた。貴族を敵に回してもいいことはないし、接客業として体面は大切だ。
彼はエミリーの姿を見ると、すぐに人の好い笑みを浮かべて、「君が悪いわけではない」と口にした。
「悪いのはこのコーヒーだ。君のような美しい人が頭を下げる必要はないよ」
ヨーゼフの言葉に、笑みを貼り付かせたままエミリーは耐える。
ギュッと握りしめた手に、この男が来るのはおそらく今日だけだと言い聞かせながら。
でも、ヨーゼフは、それからもよく来店するようになった。
「このパンケーキもおいしくないね。薄いし、クリームも甘すぎる。僕の家で出るものはもっと分厚くって、クリームも僕好みでおいしいのに。バターも安物を使っているのか、なんか変な味がするよ」
パンケーキのレシピは、母から譲り受けたものだった。朝は即完売するほど売れ行きの良いパンケーキだけれど、これも元々庶民向けだ。材料もそうで、貴族向けの高級食材は使われていない。
これもやはり、貴族であるヨーゼフには合わないのだろうと、エミリーはそう思うことで気持ちを落ち着けた。
ヨーゼフはさんざん文句を垂れ流しながらも、多めのお代を置いて店から出て行った。
これでもっといいものを作ってよと、甘いマスクで囁きながら。
もう頼むから来ないでくれと思ったけれど、なぜかヨーゼフは文句を言いながらも毎日のように店にやってきた。
カフェの品に文句を言うだけでは飽き足らず、内装にまでケチをつけはじめた。
やれ古臭い建物だの、カーテンが薄くて風が入ってくるだの、椅子の座り心地が悪いだの。散々な言いようだ。
その度にエミリーの精神はすり減った。
両親から受け継いだ大切なレシピを馬鹿にされて、毎日丁寧に掃除をしている店内を貶されて、それでずっと笑顔でいられるほど寛容ではない。
最初の頃こそ自分に実力が足りないのかと悩んだけれど、次第にそれがおかしいことに気づいた。
常連客からも、「あなたが入れてくれるコーヒーは特別なんだ」とか、「あなたの焼くパンケーキは一級品だよ」とか、「朝はここのコーヒーを飲まないと元気が出ないんだ。あの男のいうことは気にすることはないよ」と温かい言葉をかけられていたから、どうにか耐えることができた。
だけど毎日のようにヨーゼフが店に入り浸っては文句ばかり言うものだから、客足がどんどん遠のいていってしまい、常連客も遠慮して店に訪れなくなった。
残されたのは閑古鳥が鳴く店と、エミリーの両親の死と入れ替わりで拾った、大きな黒い犬だけ。
黒い犬の毛に顔をうずめると、少しは気が楽になる。
でも、ズタズタにされた自尊心が元に戻ることはない。
これまで培ってきたものを、クレーマー野郎によってすべて破壊されてしまったのだから。
カフェの経営は次第に立ち行かなくなっていき、お金も心許なくなった。
だから、エミリーは店を閉めることにしたのだ。
廃業という、最悪な看板を掲げて。
◇
(それなのに、この男は……! 私を愛しているですって? いままで散々、私の大切なものをコケにしてきたくせに。馬鹿にするのもいい加減にしてほしいわ)
ヨーゼフはケロッとした顔をして言う。
「どうして廃業が僕のせいなんだ?」
「あなたが毎日のように店に入り浸って、カフェのメニューをさんざん貶してきたからですよ」
エミリーの言葉に、ヨーゼフが大きく目を見開いた。
やっと自分の行動を理解したのかと思いきや、彼の口から出たのはお花畑のような言葉だった。
「どうしても君に会いたかったんだ。街で見かけたときに一目惚れして、それを伝える勇気がなかったから」
エミリーは怒りと共に混乱する。
(一目惚れをした相手を、貶したというの?)
愛情の裏返しに人を傷つけるなんて、そんなこと子供でもやらないだろう。愚か者のすることだ。
相手を馬鹿にしたらそのぶん傷つくだけで、自分の気持ちに振り向いてくれるわけがない。むしろ余計に嫌いになる行為だろう。
「とうぜん君も気づいていると思ったんだ。だって、君はいつも僕に笑顔で接してくれていただろ?」
「営業スマイルですけど?」
接客業の笑顔を自分への好意と錯覚するなんて、頭が痛くなる。
ヨーゼフ以外の客は、心の底からエミリーのカフェを気に入って、来店してくれた。だから他の客たちには純粋な笑顔で接することができたけれど、このクレーマー野郎だけは違う。
ただの作り物の笑みを好意と勘違いするなんて、なんてめんどくさい男なのだろうか。
「そ、それでも、僕は毎日ここに来ていたんだぞ。君の笑顔を見てコーヒーを飲むと元気になれたし……」
「いつも文句ばかり言っていたのに、それで元気になっていたなんて信じられません。あなたが毎日カフェに入り浸って文句ばかり言うから、ここ数か月ですっかり客足が途絶えてしまったというのに」
「……それは、僕のせいなのか?」
ヨーゼフが首を傾げる。
「客足が途絶えたのは、単純にこのカフェの評判が悪かったからだと思うが……。確か、噂で聞いたことがある。この店のコーヒーがまずいって」
「……それは、あなたのせいでしょう」
また怒りで声が震えてきた。
「なんで僕のせいなんだ?」
「この店のこと、誰かに話しませんでしたか?」
「ああ、そういえば! みんなにこの店のことを知ってもらいたくてな、知人に話したんだ」
「その時に、どう説明したのですか?」
「それは……。コーヒーはまずいが、かわ、かわいい店主のいるカフェがあるって」
なぜかヨーゼフの顔が赤くなる。
(なんで照れてるのよ、気持ち悪い)
この男がただの迷惑客であれば、出禁にすることもできただろう。
だが相手が悪かった。ここら一帯の地主である伯爵家の息子だ。叩き出すことなんてできなかった。
広まった悪評は消すことはできないし、常連客もどんどん足が遠のいてしまい、ヨーゼフ以外に店に訪れる人もいなかった。
悪評を広めた相手が誰なのかは正確には分かっていなかったけれど、おおよその見当はついていた。
(まさか、本当にこの男だったなんて……!)
照れ隠しでコーヒーをまずいと言ったのか、それとも本心だったのかなんてもう関係ない。
この男が流した悪評のせいで、貴族を中心に広まっていき、いつの間にか町の中にも浸透してしまった。
噂というものは不思議なもので、たとえ真実ではなくても一度流れたものが元に戻ることはない。
特に影響力のある人が口にしてしまえば、それはもう取り消せないのだ。
(この男がいなければ、カフェは無事だったはずなのに……)
目の前がぼんやりしてきたと思うと、涙が頬を伝っていく。
「泣いているのか? 悪評は気にするな。君の笑顔とコーヒーは、いつも僕を癒してくれたんだから。……それに僕は、君の泣いている姿ではなく、笑顔が好きだ!」
目の前でおろおろしているこの男が憎い。
もし彼が貴族でなければ、蹴りのひとつでもお見舞いしてやったというのに。
「いいからもう帰ってください。あなたと話すことなんてありません」
「待ってくれ、エミリー。僕は本気で君のことを愛しているんだ」
「私はあなたのことなんて、大っ嫌いです!」
「なっ。……平民の君が、貴族夫人になれるんだぞ。それなのに、僕の求婚を断ったら絶対に後悔するぞ!」
乱暴に袖で涙をぬぐうと、エミリーはただ心底軽蔑した瞳で、目の前で喚くクレーマー野郎をにらみつけた。
「帰れ」
一言に、すべての怒りを込めながら。
エミリーはさっと背を向けると、急いで店内に戻る。
扉の向こうからはまだ何かを喚く声が聞こえてくるが、もう何も聞きたくなかった。
耳を塞いでしゃがみ込む。
(あのクレーマー野郎。地獄に落ちろ)
しばらくそうしていると、鼻先を何かがくすぐった。
目を開けると、ぼんやりとした視界に大きな黒い犬の姿が映った。
『……大丈夫か?』
「ルン!」
エミリーは大きな犬に抱きついた。その黒い毛に顔をうずめる。
柔らかい毛に顔を押しつけると、先ほど止まったと思っていた涙が、後から後から流れていく。
「明日はお引越しだね」
『そうか。オレは、いつまでもエミリーと一緒だ』
伯爵子息の求婚を断ったのだ。もうこの町にはいられない。
カフェの家具などはもうすでに売っている。
借金を返して余ったお金でどこまで行けるかはわからないけれど、エミリーはこの町を出ていくつもりだった。