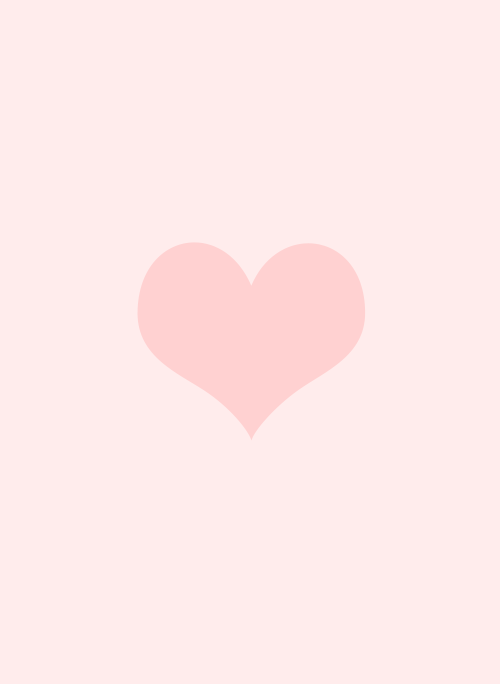世界一の××を君に
幸せすぎる。しばらく手を洗えない。
気候は春と夏を行ったり来たりしている五月下旬の日曜日。会場を後にして外に出てからも、私はひたすら余韻に浸っていた。毛先を緑に染めた髪が風に吹かれ、セットが乱れそうになるが、気にしない。ミッションはもう達成したから。私、桂木美都は今、最推しのYukiちゃんに会えて、誰よりも幸せだ。
「か、可愛かったー」
右手の手ひらに残る感触を噛みしめ、その場でくるりと回る。
傍から見ると頭のおかしい女かもしれないが、行き交う大勢の人々はそこまで他人に興味はない。なにより今は、誰も私が桂木美都だと気付かないだろう。
会社ではいつも眼鏡に事務服で、髪はひとつに束ね、化粧も最低限。けれど今日は違う。
シャンプーで落とせるヘアカラーで毛先を推しカラーに染め、眼鏡ではなくグリーンのカラーコンタクトを入れてネイルも気合いを入れている。メイクも髪型もばっちりだ。
Yukiちゃんが動画でおすすめしていたブランドのワンピースを着て、ふだんの私とはまったく違っている。誰かのために洒落をするのっていいな。
Yukiはネットを中心に活躍している2.5次元アイドルだ。イベントでも顔出しはほぼせず、アニメや3Dを使ったアバターを中心に露出するもののその人気は界隈ではすさまじい。グッズもしてたくさん出していて、今日は新作公開を記念した握手会だったのだ。
必死で握手券をゲットし、Yukiのアバターにメインで使われている緑をふんだんに取り入れたファッションでまとめた。
顔を見えないようにするためか、くもりガラス越しの握手ではあったものの差し出された手はピアノをしているだけあって大きく、指はすらりと長かった。
「生のYukiちゃんに会えたし、明日からも仕事、頑張るぞ!」
気合いを入れ、今日が日曜日の午後という現実に胸が痛くなる。 そのとき不意に、見慣れた人物が視界に入った。
え?
ボサボサ頭に癖のある髪が拍車をかけ、寝起きでももう少しマシなのではと思う髪型。中途半端に長く鬱陶しそうな前髪の合間からのぞく、おそろしく似合っていないツーブリッジの黒眼鏡。
見間違うはずがない。彼は千島誠一郎。職場に出入りしているシステムエンジニアだ。
どこで買ったのかと言いたくなる柄物のトレーナーにジーンズを組み合わせ、相変わらず壊滅的なファッションセンスで、そのうえ背が高いのである意味目を引く。
職場では愛想もなく雰囲気も暗いので、女子社員からの評判は、あまりよろしくない。おかげで私も仕事で必要ない会話を二言、三言、交わしたことがあるだけだ。
そんなどうして彼がここにいるのか……は、考えるまでもないし驚かない。
なぜなら千島さんも大のYukiファンだからだ。職場に持ってきている鞄にもYukiのキーホルダーがたくさんついていて、スマホのストラップもそうだ。
同胞がいる!と内心で大喜びしたが、私は職場でYukiのファンを明言していないので素知らぬ顔でいつつ千島さんの持っているグッズを気にしていた。
千島さんも握手会に来ていたのだろう。
もちろん声をかける真似などしない。向こうも私には気づかないだろう。
さっと踵を返そうとしたが、どうも様子がおかしい。なぜか彼はなにかから逃げるようにして足早にこちらに向かってくる。
な、なに?
身構えていると、私のすぐそばで千島さんは追いかけてきた出あろう男性に捕まった。
「受け取ってもらえませんか? 本人に言われまして」
追いかけてきたスーツの男性は、なにかメモのようなものを千島さんに渡そうと必死だ。
「結構です。お引き取りください」
いつもぼそぼそと喋る千島さんが珍しくきっぱりとした物言いで拒否をする。一体、なにがあったのか。
「ですが……」
「早く戻った方がいいんじゃないですか?」
さらに冷たく千島さんは返した。そこで千島さんを追いかけてきた男性にも見覚えがあると気付く。
もしかして彼って……。
「では、処分していただいてかまいませんからひとまず受け取ってください。渡さずに帰ると私の立場が……」
懇願するような男性の言い方に千島さんは渋々とメモを受け取る。男性は安堵めいた表情で来た道を戻っていった。
私はすかさず千島さんの方に一歩近づいた。
「千島さん」
「うわぁ!って、桂木さん?」
突然声がかかって不意討ちだったのか。千島さんが私の名前を知っていたとは驚きだ。すぐに私だと認識したのも。けれど、今はそれよりもたしかめないとならないことがある。
「さっきの男性……Yukiちゃんのマネージャーですよね?」
私の指摘に千島さんは目を見張った。
間違いない。動画の配信とイベントで何度か見たことがある。彼はyukiのマネージャーだ。そうるすと、なぜ……
「マネージャーが千島さんに?」
「それは……」
詰め寄る私に千島さんはしばし目を泳がせた後、あきらめたように大きくため息をついた。
「彼女の連絡先を渡されたんだ」
ん? 彼女って……。
一瞬の間が空き、彼がメモをこちらに向ける。
そこには【Yuki】の文字と共に電話番号とLIMEのIDがあった。
「す、すごいじゃないですか! え、そんなことあるんですね。しかも向こうから?」
飛び跳ねる勢いで私は千島さんに笑顔を向ける。しかもマネージャー経由なんて。
そんな私を千島さんは意外そうな表情で見た。そこで彼の視線の意味を自分なりに解釈する。
「だ、大丈夫です。私、誰にも言いませんから」
「連絡なんてしないよ」
間髪を入れずに返事があり、目を瞬かせる。
そうか、千島さんは、推しはいつまでも手の届かない存在でいてほしいんだ。連絡したらスキャンダルの可能性だってあるわけで……。
「千島さん、ファンの鏡ですね」
「全然」
尊敬の眼差しで見つめたのに冷たく返される。
「俺は彼女のファンじゃないんだ」
「え……」
だってYukiのグッズだってたくさん持っていて、今日も握手会に参加して……
「Yukiのファンだってアピールしていたら、周りが引くと思ったんだ。一部の層に人気だって聞いたし、そういう偏見って多少あるから。今日も友人に無理やり連れて来られただけで、まさかこんな目に合うなんて……」
肩を落として落胆する千島さんに対し、私はすーっとなにかが冷めて、続けてマグマのような熱いなにかがお腹の底から湧き出した。
「なんですか、それ」
呟いた声は震えていた。千島さんがこちらをハッとした顔で見る。私は真っすぐに彼を見据えた。
「千島さんがなにをどう思おうと勝手ですけれど、Yukiちゃんや真面目に応援しているファンを侮辱することを言わないでください。握手会だって当たらなかったファンもいるのに……」
そこで彼を思いっきり睨みつける。
「最っ低!」
吐き捨てて私はすぐさま踵を返し、その場を駆け出す。
せっかくYukiちゃんに会えたのは最悪の気分だ。
重い体をひきずり、仕事に向かう。シンプルな通勤服を着て会社に着いてから制服に着替える。染めていた毛先もいつも通りの黒に戻り、頑張ったグリーンのネイルも綺麗に落とした。肩より少し下にある髪をひとつにまとめ、一応鏡でチェックするが、そこにはいつも通りの私がいた。
自分のデスクで、まずはメールを確認する。
もうすぐ二十五歳になろうとしているが、彼氏はおろか好きな人もおらず、仕事もお金を稼ぐための手段と割り切って、ひたすらアイドルに注ぎ込む日々。
そのうえ、ほぼ喋ったことがない会社関係者の人にとんでもない姿で馴れ馴れしく話しかけたうえ、逆ギレするなんて……。
痛い。痛すぎる!!!
穴があったら入りたい。いっそのこと埋めてほしい。
思わず机に突っ伏す。
「桂木さん」
ところが次の瞬間、聞き覚えのある声が聞こえがばりと身を起こす。今。一番会いたくない人ナンバーワンの千島さんが私のそばに立っていた。
相変わらず前髪で隠れた目。私が座っていて彼が立っているうえ背が高い分、迫力がある。
「お、おはようございます」
顔を引きつらせ、何事もなかったかのように挨拶する。
「少し、いいかな?」
「あ、いえ。ここで聞きますよ? どのようなご用件でしょう?」
もう彼とは正直、関わりたくない。
「桂木さんが熱心なYukiのファンだとは知らずに昨日は――」
「わーーーーーー。お話、お話を聞きます!!」
千島さんの発言を遮るように叫び、立ち上がる。
「取引先の資料ですね。ご案内します」
必死で取り繕い、部長に鍵を借りて資料室へ向かう。
千島さんは私の後を黙ってついてくるが、その間も私の思考はフル回転していた。
もしかして昨日のことで、逆に脅されるのでは?
どんどん悪い想像が広がり血の気が引く中、資料室についたので鍵を開けて中に入る。
「昨日はごめん」
ドアを閉め電気をつけた瞬間、千島さんが頭を下げ謝罪をしてきた。
「自分のことばかりで、純粋にYukiを応援している桂木さんの気持ちを踏みにじる真似をして申し訳なかった」
まさかここまでストレートに謝れるとは思わず、逆に私は狼狽える。
「いいです。謝らないでください。私の方こそ自分の価値観で一方的なことを言って……」
そこで一度言葉を止める。
「私、本当は千島さんが羨ましかったんです」
続けて漏らしたのは、私の本音だった。
「堂々とYukiちゃんのグッズをつけて、周りにどう思われるとか関係なく自分の姿を貫いている姿が眩しくて、いいなって……私はできないから」
昨日は強く批判したけれど、千島さんを責める資格など私にはない。私は堂々とYukiが好きだと周りに言えず、グッズだって持っているものの家でコレクションするのが精々。
私よりも立派なファンだと千島さんに勝手に尊敬していて彼の本音を聞いて勝手に裏切られた気になって……。どこまで自分勝手なんだろう。
Yukiのファンなのに、ファンなのを隠している。それって本当のファンなの?
「自分のために怒ってくれる桂木さんみたいなファンがいてYukiは幸せだと思うよ」
千島さんの言葉に顔を上げると、珍しく彼の口元は緩やかな弧を描き微笑んでいた。淀んでいた心が軽くなってじんわりと温かくなった。
「もしかして何度か俺を見ていたのは、Yukiのファンだと思っていたから?」
彼の質問に私は素直に頷いた。
「はい。勝手に同士がいる!って喜んでました」
彼に見ていたのがバレるほど視線を送っていたのか。なんだか恥ずかしい。
「よかった。てっきり好意を抱かれているのかと」
しかし続けられた彼の発言に耳を疑う。
「……はっ?」
なにかの冗談かと思ったが、千島さんは真面目に安堵した顔をしている。逆に私は腹立たしくなってきた。
「さすがに自惚れすぎですよ! 千島さんの持っているYukiちゃんのグッズ、最新のものやレアなものが多くていいなぁーって見ていただけです」
昨日も思ったけれど、千島さんって自意識過剰すぎない? 自分を客観視できていないというか。
その考えは顔に出ていたらしい。
千島さんは途端に気まずそうな面持ちになる。しばしの部屋に沈黙が降り、千島さんが口を開く。
「俺、女運がありすぎるんだ」
「……はい?」
今、なんて? 女運?
意味が理解できず混乱する私をよそに、千島さんは語り出す。
「一番古い記憶は幼稚園の頃、俺と結婚するのは自分だと女の子同士のけんかが絶えず、お遊戯会の配役で俺が王子に選ばれたときには、お姫様役を巡って保護者を巻き込む大騒動になった」
「へ、へー」
幼少期のモテエピソードはそう珍しくない。
「結局、俺が王子役を降りて背景の木の役になることで話はまとまったんだ、小学校では違うクラスはもちろん他の学年の女子まで休みに時間ごとにやってきては、声をかけられ、プレゼントを渡され告白も絶えず――」
「つまりモテてモテてしょうがないと」
面倒くさくなった私は端的にまとめる。
「そういう話じゃない」
しかし千島さんに真面目に否定された。
「桂木さん。自分を巡って異性が争い、警察沙汰になった経験ある?」
「……ないです」
落ち着きつつも迫力のある問いかけに私は静かに答えた。
「ちょっとコーヒーを淹れただけで自分に惚れていると勘違いされてストーカー化されたことは?」
「…………ないです」
どんどん質問がマニアックかつ細かくなっているのは気のせいだろうか。
「友達に彼女を紹介されて、その彼女に言い寄られて友情が壊れたことは一度や二度……ではない。おかげで恋人ができた、もしくは結婚した途端に疎遠になる友人は数知れず……」
声にはどんどん悲壮感が増していく。さすがにモテていいね。ではすまない話だ。
「苦労されたんですね」
「ああ。だから極力、女性に意識されないようにわざと距離を置かれる格好と振る舞いをしているんだ」
そう言ってから千島さんはハッとした表情になった。
「だから、その……Yukiのファンを装ったのも……」
「なるほど。そういう理由ですか」
彼の言いたいことを悟る。最初は憤りしかなかったが、彼の過去のエピソードを聞いて少しだけ納得する。そこで私の考えは別の角度に移った。
「え、じゃあ、その似合っていない眼鏡もボサボサの頭も千島さんの好みではないんですか?」
私の質問に千島さんはふっと微笑んだ。どこか自嘲めいたものだけれど。
「元の俺から極力かけ離れるように、髪は三十分かけてわざと癖をつけてボサボサにセットしているんだ。眼鏡は、極力似合わなくて老けて見えるものをってわざわざオーダーして……」
「指名手配犯じゃないんですから」
すかさずツッコむ。
少女漫画によくある、異性に言い寄られるのが面倒だからわざとダサい格好しているというヒーローやヒロインの域を超えている。
そこで千島さんは困惑気味に笑った。
「自意識過剰だって笑ってくれていいよ。理解されないのも信じられないのもわかっているから。変なこと言ってごめん」
そう言って千島さんは部屋を出ていこうとする。
私自身、千島さんを自意識過剰だって思った。正直、異性に言い寄られるからってそこまでするのか?って。
でも――。
「待ってください」
思わず千島さんのシャツの裾を掴んで呼び止める。
「千島さんが本当の自分でいられるときってあるんですか?」
「それは……」
言いよどむ姿だけで答えはわかる。私はそっと手を離した。
「わかりました、信じますよ。なにか私に協力できることがあれば言ってください」
彼がなにか言う前に、今度は私が千島さんに微笑んだ。
「だって、Yukiちゃんがわざわざ自分から連絡先を渡したいと思ったんですもん。千島さんの魅力は……女運は相当ですね」
茶目っ気混じりに言うと、眼鏡の奥にある彼の瞳が丸くなる。続けて彼の目が細められた。
「ありがとう」
たしかに。前髪と眼鏡に隠れてよく見たことがなかったけれど、切れ長で整った綺麗な目だ。
とくに私が彼のためになにかできるとは思わないけれど、本当のことを知っている人間が一人でもいると違うだろう。
なにより、周りの目を気にして自分の好きな格好ができない苦しさは私もよく知っているから。
ちょっと待って。だからってなんでこんなことになったの?
次の土曜日の朝、私は指定された場所へ向かっていた。目指すは国際展示ホールだ。コンサートやイベントで何度か足を運んだことがあるが、今日はそのどちらでもない。
『私と、展示会にですか?』
千島さんからお願いされたのは、国際展示ホールで開催しているITテクノロジーエキスポへの同行だった。
『うん。仕事で何度か行ったことはあるんだけれど、プライベートで行ってゆっくり見たくて』
『私と一緒だとゆっくり見られなくないですか?』
素朴な疑問を口にすると、千島さんの表情が無になった。
『ひとりだといろいろと声をかけられて、集中できなくて……』
それは担当者に、だろうか。異性に、だろうか。
『一緒に行ってくれたらYukiの限定アクスタ、桂木さんが持っていないものをあげるよ』
『行きます!』
そんなわけでYukiちゃんのアクスタにつられてしまった。
いや、でも。千島さんの力になるって決めたわけだし。
動き回ることや半ば仕事の延長線上だと思い、ピンクベージュのブラウスにデニムジーンズとシンプルに組み合わせる。さすがにワンピースを着る度胸はなかった。コンタクトにするか迷ったが結局はいつも通り眼鏡のままだ。
大体、私はあくまでも千島さんが異性から絡まれないようにする、いわば盾でしかないんだから。盾にお洒落は必要ない!
言い聞かせつつ待ち合わせ場所に着く。会場前の大きな観覧車がちょっとしたデートスポットにもなっている広場の一角。すぐそばに地下駐車場への出入り口があって、千島さんは車で来ると行っていたから、ちょうどいい。
十時十分前。私が先に来たらしい。
それにしても千島さんの自然な姿ってどんな格好なんだろう?
「桂木さん」
「あっ」
名前を呼ばれた方向を向いて目を疑う。
背が高くモデルか俳優かと間違うほど整った顔立ちの男性がこちらにやってくる。艶の黒髪がさらりと揺れ、ネイビーのテーラードジャケットにテーパードパンツのセットアップ、インナーは白と爽やかですっきりした装いだ。
だ、誰?
「もしかしてこれからエキスポに行かれます?」
「私たちも仕事の関係で来たんですけど、よかったら一緒に回りませんか?」
そして、見るからにシゴデキ女子たちにすでに囲まれてる――!?
駐車場からここへ来るまでになにがあったのか。目に飛び込んでくる情報量が多くて処理できない。
呆然としている私に千島さん(と思しき人)が真っすぐに近づいて来てさりげなく私の肩を抱いた。
「ごめんね。彼女とふたりで回る約束をしているんだ」
こ、こういう役回り!?
硬直している私に女性たちの痛い視線が浴びせられ、彼女たちは納得いかない面持ちでその場を去っていく。ややあって千島さんのため息が漏れた。
「おはようございます、千島さん」
「おはよう。今日はよろしく」
苦笑する千島さんに私は正直に告げる。
「最初、誰かと思いましたよ」
「驚いた?」
「はい」
頷くと、千島さんが頬に手を遣って首を傾げた。
「でも、この前の桂木さんほどじゃないと思うけれど」
「あ、あれは……」
まさかあのときの格好を持ち出されるとは思ってもみなかった。今日の比ではないほど、彼にとっては意外だっただろう。
恥ずかしさで肩を縮めていると頭に温もりを感じた。
「似合ってたよ。じゃあ、行こうか」
ちょ、ちょっと待って。本当に誰?
心臓がバクバクとうるさい。私の知っている千島さんは、背が高いけれど猫背で、髪もボサボサ。鬱陶しい前髪の間に瞳を隠すようにしてかけられた黒眼鏡が印象的でいつも格好も適当だ。
目の前のイケメンとはまるで別人。それはきっと、今の彼の表情が、本当に生き生きしているからなのもあるのかもしれない。
「……桂木さん。やっとふたりきりになれたね」
「セリフと表情が合っていない気がします」
今の千島さんに言われたら、とんでもなく破壊力のある言葉だけれど私は冷静に返す。そう言った彼の顔にはあきらかな疲労が滲んでいた。
エキスポ会場に行ったものの予想通り千島さんは来場者やブース担当者など行く先々で女性に声をかけられ、それは外に出てからも続いた。
そんなわけで声をかけられずにすむ場所を求め、気分転換と休憩も兼ねてふたりで観覧車に乗ることになった。これで十五分は、彼は自由の身だ。
「私、まったくお役に立てずに申し訳ありません」
私が千島さんに釣り合う美女だったら遠慮して声をかけない女性もいるかもしれないが、私が彼の隣にいたところで盾どころか、かえって女性たちの自信を増幅させるだけだ。
「そんなことない。桂木さんがいてよかった」
モテる男はこうやってフォローも欠かさないらしい。
「とはいえ、迷惑かけたね。やっぱり俺は自分の好きな格好をするのは控えた方がいいのかもしれない」
彼の呟きに私は目を見張った。千島さんはさりげなく外の景色に視線を遣る。
「女運はあるって言いながら、気持ちに応えられるのはひとりだけだから。彼女がいたこともあったけれど、不安を募らせ、疑われて、束縛が激しくなって……最後はだめになる。結局俺は女の子みんな不幸にするんだよね」
自嘲というよりも悲しそうな端整な横顔。思わず私は口を開く。
「千島さんと違って、私はとことん男運がないんです」
私の発言に千島さんがこちらを向いた。少しだけ迷って私は続ける。
「昔、男の子にいじめられて……『ブス』から始まり、ちょっと髪飾りをつけたり可愛い服を着たりしたら『似合わない』『ダサい』って……」
胸の奥にしまっていた記憶がチクチクと小さい痛みと共によみがえる。
「おかげでお洒落するのが怖くなって、いつも無難な格好ばかり選ぶようになりました」
誰かに、ましてや異性にどう思われるかで自分の着たいものを決めているわけではないのに。自分のために自分の好きな格好をするのがこんなにも勇気がいるなんて。千島さんとは理由が違正反対だけれど、気持ちは痛いほどわかる。
「そんな私が盾だとしても、今日千島さんの隣に立てて光栄でした。不幸にするばかりじゃないですよ。男の人とふたりで出かける経験ができてうれしかったです」
自分の好きな格好で過ごす千島さんを応援したい。純粋にそう思う。
観覧車を降りて、千島さんを駐車場まで送ることにする。
「送っていこうか?」
「大丈夫です。他に寄るところがあるので」
気を使う千島さんにすかさず断りを入れる。今日、私は千島さんの盾として来たのだから。すると千島さんはなにか言いたそうな面持ちになった。
「あのカップル全然、釣り合ってなくね?」
小馬鹿にした声が聞こえ私と千島さんの視線が自然とそちらを向く。髪を派手な色に染めている若い男女がこちらをちらちらと見ている。男性の方はニヤニヤと下品な笑みを浮かべ、あきらかに私の苦手なタイプだ。
「やめなよ」
女性が小声でたしなめるものの男性は鼻を鳴らした。
「男の方、趣味悪すぎだろ」
私と千島さんはカップルでもなんでもない。だから、釣り合いとか気にする必要はないはずなのに……。
胸が痛くなる。どうして第三者に勝手に値踏みされないといけないの。
「素敵な彼氏だね」
そのとき千島さんの柔らかい声が響く。驚きで目を瞬かせたのは私だけではなく、声をかけられたカップルもだ。
千島さんがにこりと微笑むと。女性は頬を赤らめこちらに歩み寄ってきた。
「あ、いえ。カップルじゃありません」
「おい」
男性が止めよと女性の方に触れたが、すぐさま払いのけられる。
「触らないで。あんたと別れる」
「はぁ?」
突然の展開に男性が間抜けな声を漏らした。しかし女性は辛辣に言い放つ。
「自信家で自己中。性格悪すぎ。付き合ってらんないわ」
呆然とする男性をよそに女性の関心は千島さんに移る。
「あの、せっかくですしよかったら連絡先とか教えてもらえませんか?インスタとかしてます?」
彼に迫る女性の押しの強さは今日さんざん見てきたけれど、やはりすごい。
感心していたら、不意に肩を抱かれ顔を寄せられた。
「ごめんね。俺は彼女一筋だから」
顔の近さと触れられた手の感触に私は硬直した。女性は残念そうになにか言いながらも千島さんの笑顔に圧されたのかその場を去っていく。
彼女に振られた男性は、情けない顔でまだ突っ立っていた。
「人にケチつけているひまがあったら、自分の心配をしろよ。……それに俺の彼女は世界一なんだ」
言い切られ、肩を抱かれたまま先を促される。ややあって彼の手が離れ、この雰囲気に堪えられず自分から口火を切る。
「す、すみません。なんか千島さんには気を使わせてばっかりで……」
「桂木さん」
名前を呼ばれ口をつぐみ、おそるおそる彼の方に顔を向ける。
「ずっと女性と関わるのが面倒でわざと自分を偽っていたけれど、桂木さんが女性を不幸にするばかりじゃないって言ってくれてうれしかった」
観覧車でのやりとりを思い出す。千島さんはまっすぐに私を見つめてきた。
「だから、桂木さんで証明させてほしい。女性を幸せにできるんだって」
ずっと男性が好きではなかった。男運なんてまるでない。
けれど千島さんと出会って、私の男運が本当にないのかどうか改めて考える必要があるのかもしれない。
気候は春と夏を行ったり来たりしている五月下旬の日曜日。会場を後にして外に出てからも、私はひたすら余韻に浸っていた。毛先を緑に染めた髪が風に吹かれ、セットが乱れそうになるが、気にしない。ミッションはもう達成したから。私、桂木美都は今、最推しのYukiちゃんに会えて、誰よりも幸せだ。
「か、可愛かったー」
右手の手ひらに残る感触を噛みしめ、その場でくるりと回る。
傍から見ると頭のおかしい女かもしれないが、行き交う大勢の人々はそこまで他人に興味はない。なにより今は、誰も私が桂木美都だと気付かないだろう。
会社ではいつも眼鏡に事務服で、髪はひとつに束ね、化粧も最低限。けれど今日は違う。
シャンプーで落とせるヘアカラーで毛先を推しカラーに染め、眼鏡ではなくグリーンのカラーコンタクトを入れてネイルも気合いを入れている。メイクも髪型もばっちりだ。
Yukiちゃんが動画でおすすめしていたブランドのワンピースを着て、ふだんの私とはまったく違っている。誰かのために洒落をするのっていいな。
Yukiはネットを中心に活躍している2.5次元アイドルだ。イベントでも顔出しはほぼせず、アニメや3Dを使ったアバターを中心に露出するもののその人気は界隈ではすさまじい。グッズもしてたくさん出していて、今日は新作公開を記念した握手会だったのだ。
必死で握手券をゲットし、Yukiのアバターにメインで使われている緑をふんだんに取り入れたファッションでまとめた。
顔を見えないようにするためか、くもりガラス越しの握手ではあったものの差し出された手はピアノをしているだけあって大きく、指はすらりと長かった。
「生のYukiちゃんに会えたし、明日からも仕事、頑張るぞ!」
気合いを入れ、今日が日曜日の午後という現実に胸が痛くなる。 そのとき不意に、見慣れた人物が視界に入った。
え?
ボサボサ頭に癖のある髪が拍車をかけ、寝起きでももう少しマシなのではと思う髪型。中途半端に長く鬱陶しそうな前髪の合間からのぞく、おそろしく似合っていないツーブリッジの黒眼鏡。
見間違うはずがない。彼は千島誠一郎。職場に出入りしているシステムエンジニアだ。
どこで買ったのかと言いたくなる柄物のトレーナーにジーンズを組み合わせ、相変わらず壊滅的なファッションセンスで、そのうえ背が高いのである意味目を引く。
職場では愛想もなく雰囲気も暗いので、女子社員からの評判は、あまりよろしくない。おかげで私も仕事で必要ない会話を二言、三言、交わしたことがあるだけだ。
そんなどうして彼がここにいるのか……は、考えるまでもないし驚かない。
なぜなら千島さんも大のYukiファンだからだ。職場に持ってきている鞄にもYukiのキーホルダーがたくさんついていて、スマホのストラップもそうだ。
同胞がいる!と内心で大喜びしたが、私は職場でYukiのファンを明言していないので素知らぬ顔でいつつ千島さんの持っているグッズを気にしていた。
千島さんも握手会に来ていたのだろう。
もちろん声をかける真似などしない。向こうも私には気づかないだろう。
さっと踵を返そうとしたが、どうも様子がおかしい。なぜか彼はなにかから逃げるようにして足早にこちらに向かってくる。
な、なに?
身構えていると、私のすぐそばで千島さんは追いかけてきた出あろう男性に捕まった。
「受け取ってもらえませんか? 本人に言われまして」
追いかけてきたスーツの男性は、なにかメモのようなものを千島さんに渡そうと必死だ。
「結構です。お引き取りください」
いつもぼそぼそと喋る千島さんが珍しくきっぱりとした物言いで拒否をする。一体、なにがあったのか。
「ですが……」
「早く戻った方がいいんじゃないですか?」
さらに冷たく千島さんは返した。そこで千島さんを追いかけてきた男性にも見覚えがあると気付く。
もしかして彼って……。
「では、処分していただいてかまいませんからひとまず受け取ってください。渡さずに帰ると私の立場が……」
懇願するような男性の言い方に千島さんは渋々とメモを受け取る。男性は安堵めいた表情で来た道を戻っていった。
私はすかさず千島さんの方に一歩近づいた。
「千島さん」
「うわぁ!って、桂木さん?」
突然声がかかって不意討ちだったのか。千島さんが私の名前を知っていたとは驚きだ。すぐに私だと認識したのも。けれど、今はそれよりもたしかめないとならないことがある。
「さっきの男性……Yukiちゃんのマネージャーですよね?」
私の指摘に千島さんは目を見張った。
間違いない。動画の配信とイベントで何度か見たことがある。彼はyukiのマネージャーだ。そうるすと、なぜ……
「マネージャーが千島さんに?」
「それは……」
詰め寄る私に千島さんはしばし目を泳がせた後、あきらめたように大きくため息をついた。
「彼女の連絡先を渡されたんだ」
ん? 彼女って……。
一瞬の間が空き、彼がメモをこちらに向ける。
そこには【Yuki】の文字と共に電話番号とLIMEのIDがあった。
「す、すごいじゃないですか! え、そんなことあるんですね。しかも向こうから?」
飛び跳ねる勢いで私は千島さんに笑顔を向ける。しかもマネージャー経由なんて。
そんな私を千島さんは意外そうな表情で見た。そこで彼の視線の意味を自分なりに解釈する。
「だ、大丈夫です。私、誰にも言いませんから」
「連絡なんてしないよ」
間髪を入れずに返事があり、目を瞬かせる。
そうか、千島さんは、推しはいつまでも手の届かない存在でいてほしいんだ。連絡したらスキャンダルの可能性だってあるわけで……。
「千島さん、ファンの鏡ですね」
「全然」
尊敬の眼差しで見つめたのに冷たく返される。
「俺は彼女のファンじゃないんだ」
「え……」
だってYukiのグッズだってたくさん持っていて、今日も握手会に参加して……
「Yukiのファンだってアピールしていたら、周りが引くと思ったんだ。一部の層に人気だって聞いたし、そういう偏見って多少あるから。今日も友人に無理やり連れて来られただけで、まさかこんな目に合うなんて……」
肩を落として落胆する千島さんに対し、私はすーっとなにかが冷めて、続けてマグマのような熱いなにかがお腹の底から湧き出した。
「なんですか、それ」
呟いた声は震えていた。千島さんがこちらをハッとした顔で見る。私は真っすぐに彼を見据えた。
「千島さんがなにをどう思おうと勝手ですけれど、Yukiちゃんや真面目に応援しているファンを侮辱することを言わないでください。握手会だって当たらなかったファンもいるのに……」
そこで彼を思いっきり睨みつける。
「最っ低!」
吐き捨てて私はすぐさま踵を返し、その場を駆け出す。
せっかくYukiちゃんに会えたのは最悪の気分だ。
重い体をひきずり、仕事に向かう。シンプルな通勤服を着て会社に着いてから制服に着替える。染めていた毛先もいつも通りの黒に戻り、頑張ったグリーンのネイルも綺麗に落とした。肩より少し下にある髪をひとつにまとめ、一応鏡でチェックするが、そこにはいつも通りの私がいた。
自分のデスクで、まずはメールを確認する。
もうすぐ二十五歳になろうとしているが、彼氏はおろか好きな人もおらず、仕事もお金を稼ぐための手段と割り切って、ひたすらアイドルに注ぎ込む日々。
そのうえ、ほぼ喋ったことがない会社関係者の人にとんでもない姿で馴れ馴れしく話しかけたうえ、逆ギレするなんて……。
痛い。痛すぎる!!!
穴があったら入りたい。いっそのこと埋めてほしい。
思わず机に突っ伏す。
「桂木さん」
ところが次の瞬間、聞き覚えのある声が聞こえがばりと身を起こす。今。一番会いたくない人ナンバーワンの千島さんが私のそばに立っていた。
相変わらず前髪で隠れた目。私が座っていて彼が立っているうえ背が高い分、迫力がある。
「お、おはようございます」
顔を引きつらせ、何事もなかったかのように挨拶する。
「少し、いいかな?」
「あ、いえ。ここで聞きますよ? どのようなご用件でしょう?」
もう彼とは正直、関わりたくない。
「桂木さんが熱心なYukiのファンだとは知らずに昨日は――」
「わーーーーーー。お話、お話を聞きます!!」
千島さんの発言を遮るように叫び、立ち上がる。
「取引先の資料ですね。ご案内します」
必死で取り繕い、部長に鍵を借りて資料室へ向かう。
千島さんは私の後を黙ってついてくるが、その間も私の思考はフル回転していた。
もしかして昨日のことで、逆に脅されるのでは?
どんどん悪い想像が広がり血の気が引く中、資料室についたので鍵を開けて中に入る。
「昨日はごめん」
ドアを閉め電気をつけた瞬間、千島さんが頭を下げ謝罪をしてきた。
「自分のことばかりで、純粋にYukiを応援している桂木さんの気持ちを踏みにじる真似をして申し訳なかった」
まさかここまでストレートに謝れるとは思わず、逆に私は狼狽える。
「いいです。謝らないでください。私の方こそ自分の価値観で一方的なことを言って……」
そこで一度言葉を止める。
「私、本当は千島さんが羨ましかったんです」
続けて漏らしたのは、私の本音だった。
「堂々とYukiちゃんのグッズをつけて、周りにどう思われるとか関係なく自分の姿を貫いている姿が眩しくて、いいなって……私はできないから」
昨日は強く批判したけれど、千島さんを責める資格など私にはない。私は堂々とYukiが好きだと周りに言えず、グッズだって持っているものの家でコレクションするのが精々。
私よりも立派なファンだと千島さんに勝手に尊敬していて彼の本音を聞いて勝手に裏切られた気になって……。どこまで自分勝手なんだろう。
Yukiのファンなのに、ファンなのを隠している。それって本当のファンなの?
「自分のために怒ってくれる桂木さんみたいなファンがいてYukiは幸せだと思うよ」
千島さんの言葉に顔を上げると、珍しく彼の口元は緩やかな弧を描き微笑んでいた。淀んでいた心が軽くなってじんわりと温かくなった。
「もしかして何度か俺を見ていたのは、Yukiのファンだと思っていたから?」
彼の質問に私は素直に頷いた。
「はい。勝手に同士がいる!って喜んでました」
彼に見ていたのがバレるほど視線を送っていたのか。なんだか恥ずかしい。
「よかった。てっきり好意を抱かれているのかと」
しかし続けられた彼の発言に耳を疑う。
「……はっ?」
なにかの冗談かと思ったが、千島さんは真面目に安堵した顔をしている。逆に私は腹立たしくなってきた。
「さすがに自惚れすぎですよ! 千島さんの持っているYukiちゃんのグッズ、最新のものやレアなものが多くていいなぁーって見ていただけです」
昨日も思ったけれど、千島さんって自意識過剰すぎない? 自分を客観視できていないというか。
その考えは顔に出ていたらしい。
千島さんは途端に気まずそうな面持ちになる。しばしの部屋に沈黙が降り、千島さんが口を開く。
「俺、女運がありすぎるんだ」
「……はい?」
今、なんて? 女運?
意味が理解できず混乱する私をよそに、千島さんは語り出す。
「一番古い記憶は幼稚園の頃、俺と結婚するのは自分だと女の子同士のけんかが絶えず、お遊戯会の配役で俺が王子に選ばれたときには、お姫様役を巡って保護者を巻き込む大騒動になった」
「へ、へー」
幼少期のモテエピソードはそう珍しくない。
「結局、俺が王子役を降りて背景の木の役になることで話はまとまったんだ、小学校では違うクラスはもちろん他の学年の女子まで休みに時間ごとにやってきては、声をかけられ、プレゼントを渡され告白も絶えず――」
「つまりモテてモテてしょうがないと」
面倒くさくなった私は端的にまとめる。
「そういう話じゃない」
しかし千島さんに真面目に否定された。
「桂木さん。自分を巡って異性が争い、警察沙汰になった経験ある?」
「……ないです」
落ち着きつつも迫力のある問いかけに私は静かに答えた。
「ちょっとコーヒーを淹れただけで自分に惚れていると勘違いされてストーカー化されたことは?」
「…………ないです」
どんどん質問がマニアックかつ細かくなっているのは気のせいだろうか。
「友達に彼女を紹介されて、その彼女に言い寄られて友情が壊れたことは一度や二度……ではない。おかげで恋人ができた、もしくは結婚した途端に疎遠になる友人は数知れず……」
声にはどんどん悲壮感が増していく。さすがにモテていいね。ではすまない話だ。
「苦労されたんですね」
「ああ。だから極力、女性に意識されないようにわざと距離を置かれる格好と振る舞いをしているんだ」
そう言ってから千島さんはハッとした表情になった。
「だから、その……Yukiのファンを装ったのも……」
「なるほど。そういう理由ですか」
彼の言いたいことを悟る。最初は憤りしかなかったが、彼の過去のエピソードを聞いて少しだけ納得する。そこで私の考えは別の角度に移った。
「え、じゃあ、その似合っていない眼鏡もボサボサの頭も千島さんの好みではないんですか?」
私の質問に千島さんはふっと微笑んだ。どこか自嘲めいたものだけれど。
「元の俺から極力かけ離れるように、髪は三十分かけてわざと癖をつけてボサボサにセットしているんだ。眼鏡は、極力似合わなくて老けて見えるものをってわざわざオーダーして……」
「指名手配犯じゃないんですから」
すかさずツッコむ。
少女漫画によくある、異性に言い寄られるのが面倒だからわざとダサい格好しているというヒーローやヒロインの域を超えている。
そこで千島さんは困惑気味に笑った。
「自意識過剰だって笑ってくれていいよ。理解されないのも信じられないのもわかっているから。変なこと言ってごめん」
そう言って千島さんは部屋を出ていこうとする。
私自身、千島さんを自意識過剰だって思った。正直、異性に言い寄られるからってそこまでするのか?って。
でも――。
「待ってください」
思わず千島さんのシャツの裾を掴んで呼び止める。
「千島さんが本当の自分でいられるときってあるんですか?」
「それは……」
言いよどむ姿だけで答えはわかる。私はそっと手を離した。
「わかりました、信じますよ。なにか私に協力できることがあれば言ってください」
彼がなにか言う前に、今度は私が千島さんに微笑んだ。
「だって、Yukiちゃんがわざわざ自分から連絡先を渡したいと思ったんですもん。千島さんの魅力は……女運は相当ですね」
茶目っ気混じりに言うと、眼鏡の奥にある彼の瞳が丸くなる。続けて彼の目が細められた。
「ありがとう」
たしかに。前髪と眼鏡に隠れてよく見たことがなかったけれど、切れ長で整った綺麗な目だ。
とくに私が彼のためになにかできるとは思わないけれど、本当のことを知っている人間が一人でもいると違うだろう。
なにより、周りの目を気にして自分の好きな格好ができない苦しさは私もよく知っているから。
ちょっと待って。だからってなんでこんなことになったの?
次の土曜日の朝、私は指定された場所へ向かっていた。目指すは国際展示ホールだ。コンサートやイベントで何度か足を運んだことがあるが、今日はそのどちらでもない。
『私と、展示会にですか?』
千島さんからお願いされたのは、国際展示ホールで開催しているITテクノロジーエキスポへの同行だった。
『うん。仕事で何度か行ったことはあるんだけれど、プライベートで行ってゆっくり見たくて』
『私と一緒だとゆっくり見られなくないですか?』
素朴な疑問を口にすると、千島さんの表情が無になった。
『ひとりだといろいろと声をかけられて、集中できなくて……』
それは担当者に、だろうか。異性に、だろうか。
『一緒に行ってくれたらYukiの限定アクスタ、桂木さんが持っていないものをあげるよ』
『行きます!』
そんなわけでYukiちゃんのアクスタにつられてしまった。
いや、でも。千島さんの力になるって決めたわけだし。
動き回ることや半ば仕事の延長線上だと思い、ピンクベージュのブラウスにデニムジーンズとシンプルに組み合わせる。さすがにワンピースを着る度胸はなかった。コンタクトにするか迷ったが結局はいつも通り眼鏡のままだ。
大体、私はあくまでも千島さんが異性から絡まれないようにする、いわば盾でしかないんだから。盾にお洒落は必要ない!
言い聞かせつつ待ち合わせ場所に着く。会場前の大きな観覧車がちょっとしたデートスポットにもなっている広場の一角。すぐそばに地下駐車場への出入り口があって、千島さんは車で来ると行っていたから、ちょうどいい。
十時十分前。私が先に来たらしい。
それにしても千島さんの自然な姿ってどんな格好なんだろう?
「桂木さん」
「あっ」
名前を呼ばれた方向を向いて目を疑う。
背が高くモデルか俳優かと間違うほど整った顔立ちの男性がこちらにやってくる。艶の黒髪がさらりと揺れ、ネイビーのテーラードジャケットにテーパードパンツのセットアップ、インナーは白と爽やかですっきりした装いだ。
だ、誰?
「もしかしてこれからエキスポに行かれます?」
「私たちも仕事の関係で来たんですけど、よかったら一緒に回りませんか?」
そして、見るからにシゴデキ女子たちにすでに囲まれてる――!?
駐車場からここへ来るまでになにがあったのか。目に飛び込んでくる情報量が多くて処理できない。
呆然としている私に千島さん(と思しき人)が真っすぐに近づいて来てさりげなく私の肩を抱いた。
「ごめんね。彼女とふたりで回る約束をしているんだ」
こ、こういう役回り!?
硬直している私に女性たちの痛い視線が浴びせられ、彼女たちは納得いかない面持ちでその場を去っていく。ややあって千島さんのため息が漏れた。
「おはようございます、千島さん」
「おはよう。今日はよろしく」
苦笑する千島さんに私は正直に告げる。
「最初、誰かと思いましたよ」
「驚いた?」
「はい」
頷くと、千島さんが頬に手を遣って首を傾げた。
「でも、この前の桂木さんほどじゃないと思うけれど」
「あ、あれは……」
まさかあのときの格好を持ち出されるとは思ってもみなかった。今日の比ではないほど、彼にとっては意外だっただろう。
恥ずかしさで肩を縮めていると頭に温もりを感じた。
「似合ってたよ。じゃあ、行こうか」
ちょ、ちょっと待って。本当に誰?
心臓がバクバクとうるさい。私の知っている千島さんは、背が高いけれど猫背で、髪もボサボサ。鬱陶しい前髪の間に瞳を隠すようにしてかけられた黒眼鏡が印象的でいつも格好も適当だ。
目の前のイケメンとはまるで別人。それはきっと、今の彼の表情が、本当に生き生きしているからなのもあるのかもしれない。
「……桂木さん。やっとふたりきりになれたね」
「セリフと表情が合っていない気がします」
今の千島さんに言われたら、とんでもなく破壊力のある言葉だけれど私は冷静に返す。そう言った彼の顔にはあきらかな疲労が滲んでいた。
エキスポ会場に行ったものの予想通り千島さんは来場者やブース担当者など行く先々で女性に声をかけられ、それは外に出てからも続いた。
そんなわけで声をかけられずにすむ場所を求め、気分転換と休憩も兼ねてふたりで観覧車に乗ることになった。これで十五分は、彼は自由の身だ。
「私、まったくお役に立てずに申し訳ありません」
私が千島さんに釣り合う美女だったら遠慮して声をかけない女性もいるかもしれないが、私が彼の隣にいたところで盾どころか、かえって女性たちの自信を増幅させるだけだ。
「そんなことない。桂木さんがいてよかった」
モテる男はこうやってフォローも欠かさないらしい。
「とはいえ、迷惑かけたね。やっぱり俺は自分の好きな格好をするのは控えた方がいいのかもしれない」
彼の呟きに私は目を見張った。千島さんはさりげなく外の景色に視線を遣る。
「女運はあるって言いながら、気持ちに応えられるのはひとりだけだから。彼女がいたこともあったけれど、不安を募らせ、疑われて、束縛が激しくなって……最後はだめになる。結局俺は女の子みんな不幸にするんだよね」
自嘲というよりも悲しそうな端整な横顔。思わず私は口を開く。
「千島さんと違って、私はとことん男運がないんです」
私の発言に千島さんがこちらを向いた。少しだけ迷って私は続ける。
「昔、男の子にいじめられて……『ブス』から始まり、ちょっと髪飾りをつけたり可愛い服を着たりしたら『似合わない』『ダサい』って……」
胸の奥にしまっていた記憶がチクチクと小さい痛みと共によみがえる。
「おかげでお洒落するのが怖くなって、いつも無難な格好ばかり選ぶようになりました」
誰かに、ましてや異性にどう思われるかで自分の着たいものを決めているわけではないのに。自分のために自分の好きな格好をするのがこんなにも勇気がいるなんて。千島さんとは理由が違正反対だけれど、気持ちは痛いほどわかる。
「そんな私が盾だとしても、今日千島さんの隣に立てて光栄でした。不幸にするばかりじゃないですよ。男の人とふたりで出かける経験ができてうれしかったです」
自分の好きな格好で過ごす千島さんを応援したい。純粋にそう思う。
観覧車を降りて、千島さんを駐車場まで送ることにする。
「送っていこうか?」
「大丈夫です。他に寄るところがあるので」
気を使う千島さんにすかさず断りを入れる。今日、私は千島さんの盾として来たのだから。すると千島さんはなにか言いたそうな面持ちになった。
「あのカップル全然、釣り合ってなくね?」
小馬鹿にした声が聞こえ私と千島さんの視線が自然とそちらを向く。髪を派手な色に染めている若い男女がこちらをちらちらと見ている。男性の方はニヤニヤと下品な笑みを浮かべ、あきらかに私の苦手なタイプだ。
「やめなよ」
女性が小声でたしなめるものの男性は鼻を鳴らした。
「男の方、趣味悪すぎだろ」
私と千島さんはカップルでもなんでもない。だから、釣り合いとか気にする必要はないはずなのに……。
胸が痛くなる。どうして第三者に勝手に値踏みされないといけないの。
「素敵な彼氏だね」
そのとき千島さんの柔らかい声が響く。驚きで目を瞬かせたのは私だけではなく、声をかけられたカップルもだ。
千島さんがにこりと微笑むと。女性は頬を赤らめこちらに歩み寄ってきた。
「あ、いえ。カップルじゃありません」
「おい」
男性が止めよと女性の方に触れたが、すぐさま払いのけられる。
「触らないで。あんたと別れる」
「はぁ?」
突然の展開に男性が間抜けな声を漏らした。しかし女性は辛辣に言い放つ。
「自信家で自己中。性格悪すぎ。付き合ってらんないわ」
呆然とする男性をよそに女性の関心は千島さんに移る。
「あの、せっかくですしよかったら連絡先とか教えてもらえませんか?インスタとかしてます?」
彼に迫る女性の押しの強さは今日さんざん見てきたけれど、やはりすごい。
感心していたら、不意に肩を抱かれ顔を寄せられた。
「ごめんね。俺は彼女一筋だから」
顔の近さと触れられた手の感触に私は硬直した。女性は残念そうになにか言いながらも千島さんの笑顔に圧されたのかその場を去っていく。
彼女に振られた男性は、情けない顔でまだ突っ立っていた。
「人にケチつけているひまがあったら、自分の心配をしろよ。……それに俺の彼女は世界一なんだ」
言い切られ、肩を抱かれたまま先を促される。ややあって彼の手が離れ、この雰囲気に堪えられず自分から口火を切る。
「す、すみません。なんか千島さんには気を使わせてばっかりで……」
「桂木さん」
名前を呼ばれ口をつぐみ、おそるおそる彼の方に顔を向ける。
「ずっと女性と関わるのが面倒でわざと自分を偽っていたけれど、桂木さんが女性を不幸にするばかりじゃないって言ってくれてうれしかった」
観覧車でのやりとりを思い出す。千島さんはまっすぐに私を見つめてきた。
「だから、桂木さんで証明させてほしい。女性を幸せにできるんだって」
ずっと男性が好きではなかった。男運なんてまるでない。
けれど千島さんと出会って、私の男運が本当にないのかどうか改めて考える必要があるのかもしれない。