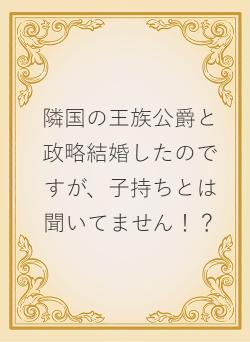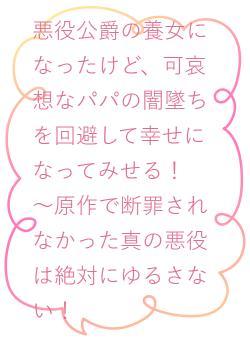新米侍女は魔塔主殿下のお気に入り ~なぜか初恋の天使様と勘違いされて寵愛されています~
「シオン。お母様に会いに来てくれたの?」
「……お母様?」
第二王子ハルティシオンの母親は、天界と取引をしていた。
天に代償を捧げ、奇跡を与えてもらう。そんな取引だ。
幼いハルティシオンは、母親の死を理解していた。
なのに、目の前で微笑む優しい姿は。
「お母様……!」
ハルティシオンは、母の腕へと飛び込んだ。
母の蒼銀色の髪が視界で揺れる。火の粉のように、淡い光の粒を空中にちらちらと舞わせながら。
ハルティシオンはなんとなく察した。母は人間ではない。幽霊だ。
「シオン。つらい思いをさせてしまって、ごめんなさいね」
「ううん……」
幽霊の母は、優しかった。愛情深くハルティシオンの髪を撫で、頬にキスをして、謝ってくれた。
未練を抱えた魂は、地上に留まり、苦しんでしまうのだという。母の未練は何かは、子供の心でも想像できた。
ハルティシオンは母に苦しんでほしくなかった。だから、精一杯の笑顔を咲かせた。
「お母様。ぼく、つらくない。絶対、全然、つらくないよ」
母の未練を消化させ、天に召される手伝いをしてくれたのは、天から舞い降りてきた天使だった。
天使は、ハルティシオンから見るとちょっとだけ『お姉さん』な姿をしていた。
煌めく金糸の髪、美しいすみれ色の瞳。
背には純白の翼がある。
とても綺麗で、優しくて、神聖で……触ってはいけない、汚してはいけない、特別な存在だ。
天使は教えてくれた。
お空には瘴気竜がいて、この国を滅ぼそうと狙っている。
天使はその瘴気竜を倒しに行く予定なのだった。けれど、瘴気竜を倒しに行くと、天使は消えてしまうらしい。
「私、まだ生まれて日が浅いの。未練を覚えるようなものがなんにもない。人々を救って消えられるなら、本望です」
正義感と使命感でいっぱいの、まっすぐな天使の瞳は美しかった。
ハルティシオンは強烈にその崇高な志に魅了された。その眼差しから、目を逸らすことができなかった。
「……やだ」
この天使様に、いなくなってほしくない。
ただでさえお母様が亡くなったのに、天使様もこの世から消えてしまうのは、やだ。
ぼくのそばにいなくてもいい。生きていてほしい。
未練を覚えるようなものを、いっぱいもってほしい。
幸せになってほしい。
だから王子は、母を真似して天に願った。
母がいつもしていたことだ。
手のひらに光を生み出し、指先で想いをつづる。
初めての行為は、簡単だった。
「こんなに幼いのに契約魔法陣を編めるなんて……あなたは天才ですわね」
聖獣ケイティは驚いた様子で近寄り、小声で言う。
「あたくしもあの子が好きですの」
猫の手が光を足して、手伝ってくれる。
こうして王子と聖獣は共犯関係を結んだ。
天界からの返答が魔法陣に組み込まれていく。双方の条件が出そろい、合意がされて、取引は成立する。
願いの代償は大きく、王子は右目を失うだけでなく、天界との取引についての詳細を自分の口から他の人間に教えることを禁じられた。
そして、天使を生かす代わりに瘴気竜を人間たちの力で対処するようにと求められた。
「天使様はどこに行ったんだろう。契約したのだから、消えてはいないんだよね?」
きっとどこかで生きている。
それは信仰にも似た、王子にとっての救済の光だった。
心身を病み、悪評に甘んじて背を丸めて眠る夜。
代償に怯えながらも他に選択肢がなく、追いつめられて天に祈る夜。
研究に睡眠時間を捧げるも進捗が芳しくなく、自分の余命を思って焦燥に駆られる夜。
つらい時も、悲しい時も。初恋の天使が幸せに生きていると思うと、シオンも幸せになれた。頑張れる気がした。
自分のそばにいなくても、どこかで笑っているなら、それでいい。
そう思いながら命を削り、弱った心が本音を吐き出す。
『でも本当は』
本当は、死ぬ前に、少しだけ。
『ほんの少しだけでいいから、あなたに会いたい』
そして――王子の願いは、叶った。
◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
ラクリマリア王国に、晴れ空が戻ってきた。
瘴気竜の脅威が消え、長く国を覆っていた不安が晴れた朝―― 王都の人々は、頭上に広がる眩い青色に、ただ立ち尽くした。
「晴れてる」
「雲はどこに行ったんだ?」
「こんな空、見たことがない……」
誰もが同じ言葉をこぼし、指さし、笑い合う。
子どもたちは雲の形を追い、大人たちでさえ仕事の手を止めて空を眺め続けた。
一日中、王都の話題は、彼らの頭上に広がる無限の蒼穹だった。
数日が過ぎると、人々は少しずつ青空のある日常に慣れ始める。
当然のように頭上に広がる空の澄んだ青は、これからずっと見られるのだ。みんなが奇跡のような現実を喜び、安堵した。
――もう大丈夫だ。
そんな確信が、王都の隅々にまで満ちていった。
そして、『残念な王子』第二王子ハルティシオンへの評価も、覆されていった。
主に魔塔の魔法使いたちが、「これまでは情報を秘匿していたが、うちの殿下のおかげなんだぞ」と誇らしげに吹聴するようになったからだ。
「ハルティシオン殿下は、ずっと我が国を救う研究を主導していらしたんだ!」
「秘密裡に命がけで瘴気竜と戦い続けてきたんだぞ!」
「……なんだって?」
王族としての特質を活かし、表に出ることなく天と交渉を重ね、瘴気竜の脅威を遠ざけてきた立役者。
そのすべてが、命を削る代償の上に成り立っていた。
――そうした噂は、酒場から工房へ、やがて王都全体へと滲むように広がっていった。
「……王子殿下は、そんなことを……」
「俺たちは、何も知らずに無礼なことばかり言ってしまった……」
臣民たちは、口々にそう呟いた。
これまで軽んじ、陰で好き勝手に評してきた自分たちの愚かさを思い知り、顔を伏せる者も少なくない。
後悔とともに広がったのは、静かな敬意だった。
季節の花々の梢を撫でゆく風が希望を感じさせる香りをたっぷり含み、きららかに降り注ぐ陽射しは薫る風をも煌かせる。
いつしか人々は、第二王子ハルティシオンの名を、感謝とともに誇らしげに語るようになっていった。
「晴れ空を取り戻した英雄、我らが第二王子ハルティシオン殿下に感謝を!」
◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
冬の名残が薄れ、春めいた空気に満ちた穏やかな夜、王城では祝典が開かれた。
瘴気竜の脅威が去ったことを祝い、国の未来を寿ぐための宴だ。
英雄王子として讃えられるようになったシオンは、婚約者リエルを大切にエスコートし、会場へと歩み入った。
同時に、儀礼官がふたりを紹介する。
「第二王子ハルティシオン殿下、ならびに、リンデンベルク伯爵令嬢のご入場です」
拍手が起こり、やがて歓声へと変わっていく。
シオンはその中心で、達成感に包まれていた。
――愛する国を。民を。天使様を。守ることができたのだ。
幼い頃から積み重ねてきた努力。
理解されない時間。
命を削る選択の数々。
すべてが、今この瞬間につながっている。
隣にいるリエルの存在が、その実感をより確かなものにしてくれた。
彼女は少し緊張した面持ちで、それでもまっすぐ前を向いている。
――愛しい。
彼女に選んでもらえたことが、嬉しくてたまらない。
壇上に進み出ると、自然と会場は静まり返った。
「これまで、俺が頼りない第二王子だと、皆に心配をかけてきたことは承知しています」
シオンはこれまで、多くの人々に「第二王子は大丈夫なのか」と心配させてきた。
自らの行いを積極的に公表しなかったのは、不確かな研究で過度な期待を抱かせたくなかったからだ。
命を削る選択に、無用な反対や過剰な称賛を向けられ、歩みを乱されたくなかったという思いもある。
そして何より、自分自身をさらけ出し、理解されることへの躊躇があった。
けれど、今にして思えば、他にも選び得た道はあったのではないか?
そんな考えが、胸にある。
「天使を幸せにしたい」と願ったのは、シオンがまだ八歳の頃だった。
天界との取引も、瘴気竜への対策も、その願いを起点として始まっている。
それから長い年月が流れ、シオン自身も少しずつ成長してきた。
だからこそ今は、幼い日の自分の判断を振り返り、「幼稚で軽率だったのではないか」と反省することもある。
内省するシオンを気遣うように、リエルがそっと手を握ってくれる。
まるで応援するように、支えるような瞳は、聖母のように慈愛に溢れている。
それに励まされる気持ちと、「俺を子供みたいに見て心配しないでくれ!」という反発心が同時に湧く。
――リエルに「頼れる男だ」と思ってもらいたい。
シオンは人々が期待する英雄王子らしく、堂々と声を張り上げた。
「兄上を支え、この国の復興のために、改めて力を尽くしていくつもりです。これからも、どうぞよろしくお願いします」
――大切なのは、これからの生き方だ。
シオンが過去を振り切るように晴れやかに未来への展望を語ると、一拍の静寂のあと、割れんばかりの歓声が湧き起こった。
音楽が始まり、ダンスフロアが開かれる。
「一緒に踊ろう。俺がリードするから」
リエルに「下手」と思われないよう、ダンスを練習してきたのは秘密だ。
顔の角度も、表情も、鏡の前で「大人っぽく見えるように」と練習してきた。
その努力を悟られぬよう、洗練された所作で誘うと、リエルは小さく頷いてくれた。
ああっ――可愛い。
シオンは表情を緩めそうになる自分を叱咤しつつ、リエルの手を取り、歩き出す。
視界の隅で揺れる彼女のドレスも、白い髪も、愛しくて仕方ない。
この現在の幸福を自分がこの手で掴み取ったのだと思うと、誇らしくなる。
「おふたりさん。あたくしの存在も、忘れずに!」
小さな白猫の姿をした聖獣ケイティが、ふたりの後をついてくる。
自分の目には見えないが、きっと国を案じていた先祖たちもたくさんいて、見守っていてくれるのだろう。
踊るシオンとリエルの足元で、ケイティはご機嫌なステップを踏んでいる。
「ふふっ、サラ。うらやましいでしょう?」
「きゅうー」
ケイティに挑戦的に問いかけの声を投げられて、壁際でロザミアに抱っこされているサラマンダーのサラが悔しそうに鳴いた。
赤ちゃんサラマンダー相手にお姉さんぶるケイティを見ていると、過去の自分が思い出される。
幼いシオンが現在に至るまで、ケイティはずっとそばで見守り、助言をしてくれたのだ。
「シオン様。あとでサラも躍らせてあげたいですね」
「リエルが望むなら」
幸せなステップを刻み、可憐なパートナーが満開の花のように微笑む。
なんて綺麗なんだろう。
くるり、とリードに合わせて回転する彼女のドレスが花のように広がるのが、奇跡のように麗しい。
ああ――曲がもう終わってしまう。
シオンは彼女の手を大切に持ち上げた。
指先に煌めく特別な指輪は、ハッピーエンドの象徴めいていた。
指先にキスを落とすと、彼女は幸せそうに微笑んでくれる。
「シオン様、ダンスが以前よりもお上手になりましたね」
「……そうか。まあ、俺はなんでもできるからな」
「ふふっ、そうですね」
リエルがくすっと笑う。華奢な首が傾いて、柔らかな頬に白雪のような繊細な髪がかかる。
可憐なすみれ色の瞳は、優しい愛情を湛えていた。
――くっ……。
俺のことを「微笑ましい」と思っている時の目だ。
胸の奥がちりちり疼いて、シオンは落ち着かない気分になった。
――今すぐ目の前の婚約者を抱き上げて自室に連れ去り、キスの雨を降らしたい。
――いいんじゃないか?
俺のことを無自覚に子供扱いする彼女に、強引にわからせてやりたい。無茶苦茶にしたい。
――お、俺の馬鹿。なんてことを考えるんだ。
天使様にそんな不埒なことをしてはならない……!
胸の内では、婚約者に成人男性として意識されたい欲と天使を崇拝する心、二つの感情がせめぎ合った。
葛藤する王子の背後、会場の壁にある四角い窓の外では、晴れ渡る夜空の星が綺麗に瞬き、やがて静かにすべり落ちた。
せめぎ合いの結果や、いかに。