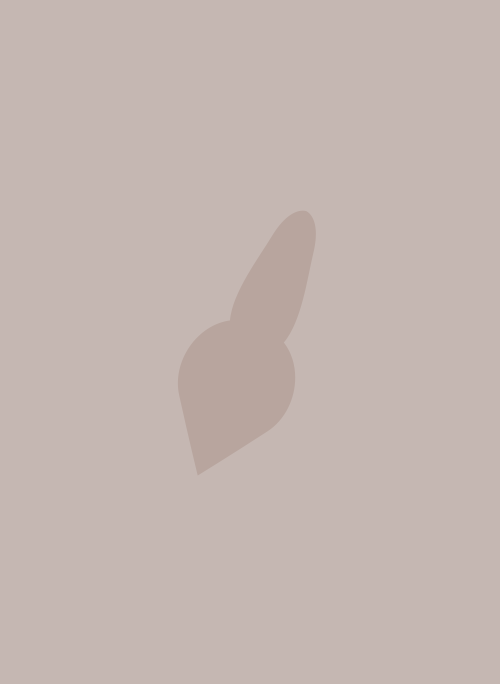もしも僕に。
そのあと、拓真っていうバカが詳しい事情を南桜に話した。
話を聞き終わった南桜はケラケラ高らかに笑い出した。
「みゆちゃん凄ぇ」
は?何がよ。
私は南桜を睨みつけた。
「あのタクに喧嘩売るとか」
ククッと腹を抱えて再び笑い出した。
「……何が言いたいの?」
「タクに、あんな態度取る奴見たことなかったから、根性あるなーって」
南桜は時折、クスっと笑いながら説明をした。
「南桜、笑いすぎだ。ただのむかつく女だけだろ」
「な…!」
なによ、全部私が悪いわけ?
そりゃあ下を向いて歩いてたのは事実だけど、ほ私をったらかしにしたのは南桜じゃない…。
「タクは言い過ぎ!」
むかつく女という言葉に対し、私をフォローする発言をした。
しかし、それとは裏腹に表情はバカにしたような笑みを散りばめている。
私は何も言わずさっき蹴った所をもう一度蹴った。
「っい!?」
顔を歪めて私を見てきた。
もたろん私は唇を突き出し誰がどう見ても“不機嫌”。
「さっきからなんだよ?」
「…っ…な゙ん゙で…私ばっがぁ゙…?」
泣き出してしまった。
南桜のまえで泣きすぎだ。
「え!?み、みゆ…?」
「おいっ…どうしたんだよ…」
南桜だけじゃなくバカも動揺し始めた。
「…ば、バカぁあ…っ」
私は南桜の背中をバシバシ叩いた。
「落ち着けって…!」
私の腕を阻止したのはあのバカだった。
_