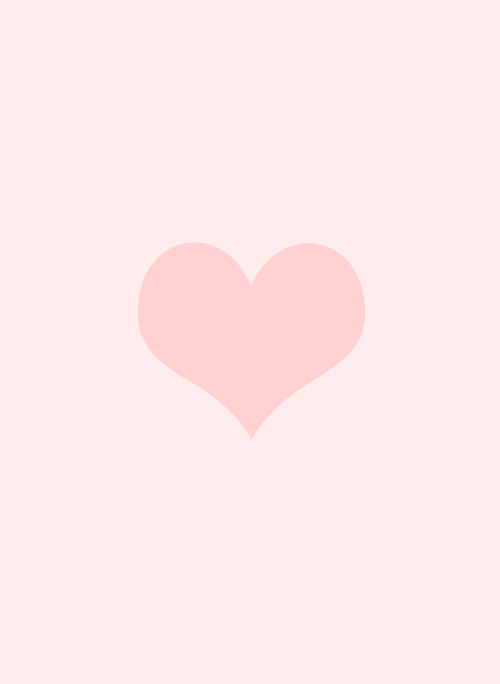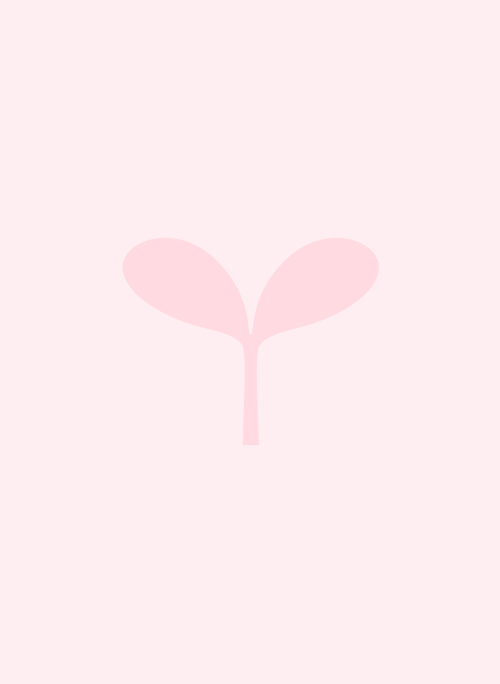わたしの姫君
何をするでもなく、リュクスはただ茫然と立ち尽くしていた。
ルシアが消えた空間を――時おりひらりと舞い落ちる花びらを、リュクスは惜しむように眺めている。
背後では、聞き慣れた噴水の飛沫の音が絶え間なく続く。そのことが、なんだかとても悲しかった。もうルシアはいないのに、リュクスの周りの日常は何ひとつとして変わりはないのだ。
もしかしたら、もう二度と会えないのかもしれない。
そんな恐怖が、ルシアの誘いに頷きそうになった。本音を吐きだしてしまえば、何もかもを捨ててでも、ルシアと共にいられるのならよかった。けれど、自分の中に育ててきた「責任」という言葉が頭を縦に振らせなかったのだ。
リュクスは泣きそうな笑顔を浮かべながら、自分自身を褒めた。よく耐えたと自分でも驚く。
気がつけば、遠くの空が少しずつ白み始めていた。
ルシアが去って、どれほどの時を過ごしたのだろう。
もう花びらは跡形もなく消えている。風が流れた瞬間、懐かしい香りがしたのは、花の香りか、それともルシアの香りか。
そんなことを考えながら、無意識のうちに力強く握っていたこぶしを開いて目を見開く。手のひらから花びらが一枚、ひらひらと舞い落ちた。
地面に落ち切ってしまう前に、慌てて掬いあげると、真っ赤な花びらをリュクスは自分の上着ポケットにそっとしまった。
シーツの下にいるのが自分ではなく、動物のぬいぐるみだとそろそろ気付かれてもおかしくない時刻だろう。その前にそっと戻らなくてはいけない。日常からルシアが消えても、リュクスの日常は、変わらないのだから。
リュクスは、消える瞬間のルシアの笑顔を思い浮かべながら、それでもゆっくりとした足取りで歩き出した。