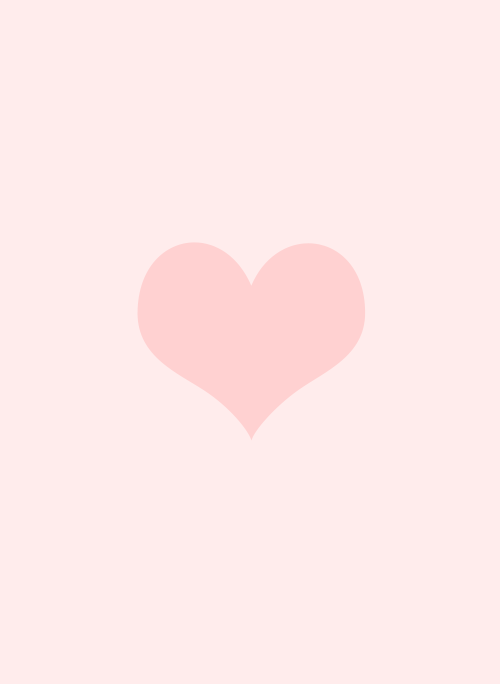恋衣 ~呉服屋さんに恋して~
展望台までは道が細くなっているために、駐車場から砂利道を歩いて行かなくてはいけない。だから十夜さんは、私に片付けをさせず先に帰して、着替えさせてから一緒に行こうとしていたようだった。
どこまでも配慮してくれていたというのに、マイナスにばかり考えていた自分が恥ずかしくなる。
「ここから見えるようですね」
展望台は何か施設があるわけではなく、外に開けた形の吹きっ晒しの展望台だった。
大きくて丸い石畳みでできた場所に、いくつか双眼鏡が設置されている。ただ、今は双眼鏡を使わなくても、小さくではあるが花火が見えた。
何人かカップルがいるらしいが、花火大会の場所に比べればかなり空いていて、皆それぞれに二人きりの世界を作っているようだった。
「……あ、」
その幾人かのカップルの中に、見知った二人がいた。
「翠さん……」
翠さんと御茶屋さんであった男の店員さんが肩を寄せ合って花火を見上げていた。二人も私達に気付いたらしく、こちらを振り返った。
「どうやら、上手くいったようですね」
「おかげさまで」
翠さんは十夜さんに、何もかも分っていたような笑みを見せた。十夜さんも頷きながら微笑む。
「別れたらよろしかったのに。そうすれば私が十夜さんのお嫁さんでした」
私に冗談めかして言ってきた。だけど、それに慌てたように反応したのは、私よりも翠さんの隣にいた男の人だった。
「み、翠さん……! それはどういう……」
「もう、冗談に決まっているでしょう」
そういうと翠さんは、焦っている男の人の横腹を肘で小突いた。
翠さんも照れたように口を尖らせていて、この二人は想い合っているということがよくわかった。
「凛子さん、少し離れた場所へ行きましょうか」
「はい」
二人から離れ、少し花火が見えにくいけれど、近くに誰もいない場所まで行く。
遠くでドンッと音が響き、夜空に七色の花が咲いた。
「……綺麗」
「ええ、とても」
「十夜さん……あの、見ている方向が違うと思いますが……」
「そうですか?」
「わ、私ではなく、花火を見てくださいっ」
十夜さんの顔は、夜空ではなく私の方へ向いている。花火を見るようにお願いしてみても、にっこりと微笑むだけでこちらを向いたまま。
「花火より、凛子さんが見たい」
「十夜さん……」
十夜さんがそっと手を伸ばして、長い指で頬を撫ぜてくる。身体の奥にじわりと炎を灯すような行為に、私の胸は今にも張り裂けそうだった。
「来年はもっと近くで見ましょうか」
「……はい」
お花見に続いて、花火の約束。来年のスケジュール帳でも作ろうか。きっと幸せな予定ばかりで埋まるはず。
「どこか旅行にでかけた先で楽しむのもいいですね。旅館の露天風呂から眺めたりして」
「その時は、ちゃんと花火を見てくださいね」
「うーん、困りましたね。それは約束できそうにありません」
「どうしてですか?」
「花火より露天風呂より、きっと貴女が一番魅力的だから」
「そ、それは……十夜さんも同じです」
照れてしまい、つい俯いてしまう。十夜さんは相変わらず私の方を向いたまま、楽しそうに笑っていた。
そうして二人で会話しているうちに、花火大会は終わってしまった。二十分も経っていなかったけれど、途中から来たのでそれも仕方ない。
「では凛子さん、十夜さんと別れたらすぐに私に連絡をくださいね」
「み、翠さん……!」
「冗談です。連絡が来ないことを願っています」
翠さんは私をからかうと、彼の腕を絡め取って帰って行った。
* * *
展望台でしばらく夜景を楽しんだ後、私達は十夜さんの家に帰ってきた。
朝から閉め切ったままだったからか、家の中はムンとしている。
「熱い……」
掌で首元を仰いでみるが、汗がじわりと浮いてくる。空気の入れ替えをしようと窓を開けていると、縁側から十夜さんに呼びかけられた。
「凛子さん」
弾むような声。何か楽しいことでもあったのだろうか。
「どうしました?」
私が駆け寄ると、十夜さんはにっこりと笑って、手に持っていた袋をヒラヒラと揺らしてみせた。
「凛子さん、花火しませんか?」
「花火……ですか?」
「はい。ショッピングモールの人にもらったんです」
十夜さんが持っているのは線香花火が五本入った袋だった。浴衣の袂を探り、ライターを取り出すと嬉しそうに白い歯を見せた。
煙草は吸わない人なので、花火はもらったのだとしても、ライターは私と花火をするために用意してくれたのだろう。
わかり合う前の私なら申し訳なく思ったかもしれないけど、今は素直に嬉しい。
「ちゃんとバケツに水も汲みましたよ。一緒にやりましょう、線香花火」
十夜さんの足元には、水色のバケツに八分目くらいの水が張ってあった。しかも私の下駄を、玄関から庭の方へ持って来てくれている。
「準備がいいんですね」
普段落ち着いている彼のはしゃぐ姿に思わず頬が緩んだ。
楽しみにしてくれている。私と過ごす時間を、大切にしてくれている。それだけで、嬉しかった。
庭に降りると、風を遮るように二人でしゃがみ込んだ。
「はい、凛子さん」
「あ、ありがとうございます」
ライターで付けた線香花火を手渡される。辺りは暗く、手元だけにオレンジの明りが灯ってパチパチと弾けた。
「綺麗……あっ、終わっちゃった」
「うーん、なかなか早いですね」
十夜さんが持ったものもすぐに終わってしまった。残った3本も同じように終わってしまったら悲しい。せっかくじっくりと十夜さんとの時間を楽しもうと思っていたのに。
「当たり外れがあるんでしょうか。これはどうですか?」
「あ……さっきのよりは……」
十夜さんから手渡され、パチパチと幾何学な模様に燃える線香花火を見つめた。先ほどのものよりは長持ちしている。
「十夜さんも今回は長そうですね」
「ええ……」
優しく瞳を細める十夜さんの顔が、線香花火の明りに照らし出される。オレンジに染まった顔は穏やかでいて、とても色っぽくも見えた。
私が自分の線香花火が消えたのも気付かずに見つめていると、十夜さんは線香花火を見つめたまま口を開いた。
「凛子さん、線香花火が落ちずに消えたら願い事が叶うって知っていますか?」
「そう言われれば……小さいころに聞いたことがあります」
十夜さんが持った線香花火は最後の灯を燃やすかのように、激しく火花を散らしている。これが燃え尽きれば、あとは玉となり火が消える。その時に玉が落ちなければ、願いが叶うという。
「願い事をしようと思います」
「……十夜さん?」
十夜さんが線香花火から視線を逸らして、私を見つめてきた。線香花火のオレンジが映り込んだ瞳は、夏の風より熱を孕んでいて、胸がトクンと大きく高鳴る。
「凛子さん、僕と結婚してください」
「――っ」
私が十夜さんの瞳に捕えられたまま動けずにいると、線香花火はゆっくりと玉を落とさず消えて行った。
夜空の星も、頬を撫でる風も、遠くで聞こえる虫の声も。全てが現実だと教えてくれているのに、夢のようで。頭の中は真っ白となり、身体はフワフワと浮いているようだった。
「……よろしく、お願いします」
私が答えることができたのは、オレンジの明りが消えて随分と経ってから。十夜さんは胸に詰まったものを全て吐き出すように、大きく息を吐いた。
「よかった……! 心臓が飛び出しそうなほど緊張しました。最後は線香花火がどうやって消えたのか、よくわからなかった」
胸元を押さえた十夜さんは、安堵したように笑う。全く緊張しているように見えなかったので、その様子が意外だった。
十夜さんがそれほどまで、思い詰めて告げてくれたプロポーズ。そう思うと、知らず知らずのうちに目尻から涙が零れてきた。
「り、凛子さん? どうしました、驚かせすぎましたか?」
「すごく、嬉しいです……っ」
「ええ、僕も……とても嬉しい」
十夜さんは私をそっと胸に抱き寄せ、涙が流れた頬に口づけをしてくれた。
それはとても温かく、今までの不安も、これからの未来も。全てを明るく照らしてくれる気がした。
「最後の線香花火、一緒にやりませんか?」
私が落ち着くと、十夜さんは最後の一本を取り出して私に尋ねた。
「一緒に……ですか?」
「はい」
十夜さんは私に答えながら、最後の線香花火にライターで火を付けた。
十夜さんが熱くない部分を差し出してくれ、私が指でつまむと、十夜さんは細くなった上の部分を摘まんだ。
線香花火はゆっくりと燃えながら、やがて激しく弾けながら燃えだした。
この花火も玉となって、落ちずに消えてくれるだろうか。もし、そうだとすれば――。
「十夜さん。一緒に、願い事をしませんか?」
私が提案すると、十夜さんは花火を見つめていた瞳をこちらに向けた。
「わかりました。どういった願い事にしますか?」
十夜さんがゆっくりと顔を覗きこんでくる。オレンジ色が映り込んだ艶めく瞳に吸いこまれそうになる瞬間、私は願い事を口にした。
「十夜さんと……幸せな家庭が作れますように」
まだまだ未来は長いから。何があるかわからない。だけど、十夜さんと一緒なら……。
「では僕も、凛子さんと幸せな毎日が送れますように」
十夜さんは優しい声音で返事をしてくれる。ゆっくりと唇が近づき、私のそれにそっと重なった。
星が輝く空の下、二人で持ったままの線香花火は、玉を落とすことなく静かに燃えて消えていった――。
【夏の花火編・完】
どこまでも配慮してくれていたというのに、マイナスにばかり考えていた自分が恥ずかしくなる。
「ここから見えるようですね」
展望台は何か施設があるわけではなく、外に開けた形の吹きっ晒しの展望台だった。
大きくて丸い石畳みでできた場所に、いくつか双眼鏡が設置されている。ただ、今は双眼鏡を使わなくても、小さくではあるが花火が見えた。
何人かカップルがいるらしいが、花火大会の場所に比べればかなり空いていて、皆それぞれに二人きりの世界を作っているようだった。
「……あ、」
その幾人かのカップルの中に、見知った二人がいた。
「翠さん……」
翠さんと御茶屋さんであった男の店員さんが肩を寄せ合って花火を見上げていた。二人も私達に気付いたらしく、こちらを振り返った。
「どうやら、上手くいったようですね」
「おかげさまで」
翠さんは十夜さんに、何もかも分っていたような笑みを見せた。十夜さんも頷きながら微笑む。
「別れたらよろしかったのに。そうすれば私が十夜さんのお嫁さんでした」
私に冗談めかして言ってきた。だけど、それに慌てたように反応したのは、私よりも翠さんの隣にいた男の人だった。
「み、翠さん……! それはどういう……」
「もう、冗談に決まっているでしょう」
そういうと翠さんは、焦っている男の人の横腹を肘で小突いた。
翠さんも照れたように口を尖らせていて、この二人は想い合っているということがよくわかった。
「凛子さん、少し離れた場所へ行きましょうか」
「はい」
二人から離れ、少し花火が見えにくいけれど、近くに誰もいない場所まで行く。
遠くでドンッと音が響き、夜空に七色の花が咲いた。
「……綺麗」
「ええ、とても」
「十夜さん……あの、見ている方向が違うと思いますが……」
「そうですか?」
「わ、私ではなく、花火を見てくださいっ」
十夜さんの顔は、夜空ではなく私の方へ向いている。花火を見るようにお願いしてみても、にっこりと微笑むだけでこちらを向いたまま。
「花火より、凛子さんが見たい」
「十夜さん……」
十夜さんがそっと手を伸ばして、長い指で頬を撫ぜてくる。身体の奥にじわりと炎を灯すような行為に、私の胸は今にも張り裂けそうだった。
「来年はもっと近くで見ましょうか」
「……はい」
お花見に続いて、花火の約束。来年のスケジュール帳でも作ろうか。きっと幸せな予定ばかりで埋まるはず。
「どこか旅行にでかけた先で楽しむのもいいですね。旅館の露天風呂から眺めたりして」
「その時は、ちゃんと花火を見てくださいね」
「うーん、困りましたね。それは約束できそうにありません」
「どうしてですか?」
「花火より露天風呂より、きっと貴女が一番魅力的だから」
「そ、それは……十夜さんも同じです」
照れてしまい、つい俯いてしまう。十夜さんは相変わらず私の方を向いたまま、楽しそうに笑っていた。
そうして二人で会話しているうちに、花火大会は終わってしまった。二十分も経っていなかったけれど、途中から来たのでそれも仕方ない。
「では凛子さん、十夜さんと別れたらすぐに私に連絡をくださいね」
「み、翠さん……!」
「冗談です。連絡が来ないことを願っています」
翠さんは私をからかうと、彼の腕を絡め取って帰って行った。
* * *
展望台でしばらく夜景を楽しんだ後、私達は十夜さんの家に帰ってきた。
朝から閉め切ったままだったからか、家の中はムンとしている。
「熱い……」
掌で首元を仰いでみるが、汗がじわりと浮いてくる。空気の入れ替えをしようと窓を開けていると、縁側から十夜さんに呼びかけられた。
「凛子さん」
弾むような声。何か楽しいことでもあったのだろうか。
「どうしました?」
私が駆け寄ると、十夜さんはにっこりと笑って、手に持っていた袋をヒラヒラと揺らしてみせた。
「凛子さん、花火しませんか?」
「花火……ですか?」
「はい。ショッピングモールの人にもらったんです」
十夜さんが持っているのは線香花火が五本入った袋だった。浴衣の袂を探り、ライターを取り出すと嬉しそうに白い歯を見せた。
煙草は吸わない人なので、花火はもらったのだとしても、ライターは私と花火をするために用意してくれたのだろう。
わかり合う前の私なら申し訳なく思ったかもしれないけど、今は素直に嬉しい。
「ちゃんとバケツに水も汲みましたよ。一緒にやりましょう、線香花火」
十夜さんの足元には、水色のバケツに八分目くらいの水が張ってあった。しかも私の下駄を、玄関から庭の方へ持って来てくれている。
「準備がいいんですね」
普段落ち着いている彼のはしゃぐ姿に思わず頬が緩んだ。
楽しみにしてくれている。私と過ごす時間を、大切にしてくれている。それだけで、嬉しかった。
庭に降りると、風を遮るように二人でしゃがみ込んだ。
「はい、凛子さん」
「あ、ありがとうございます」
ライターで付けた線香花火を手渡される。辺りは暗く、手元だけにオレンジの明りが灯ってパチパチと弾けた。
「綺麗……あっ、終わっちゃった」
「うーん、なかなか早いですね」
十夜さんが持ったものもすぐに終わってしまった。残った3本も同じように終わってしまったら悲しい。せっかくじっくりと十夜さんとの時間を楽しもうと思っていたのに。
「当たり外れがあるんでしょうか。これはどうですか?」
「あ……さっきのよりは……」
十夜さんから手渡され、パチパチと幾何学な模様に燃える線香花火を見つめた。先ほどのものよりは長持ちしている。
「十夜さんも今回は長そうですね」
「ええ……」
優しく瞳を細める十夜さんの顔が、線香花火の明りに照らし出される。オレンジに染まった顔は穏やかでいて、とても色っぽくも見えた。
私が自分の線香花火が消えたのも気付かずに見つめていると、十夜さんは線香花火を見つめたまま口を開いた。
「凛子さん、線香花火が落ちずに消えたら願い事が叶うって知っていますか?」
「そう言われれば……小さいころに聞いたことがあります」
十夜さんが持った線香花火は最後の灯を燃やすかのように、激しく火花を散らしている。これが燃え尽きれば、あとは玉となり火が消える。その時に玉が落ちなければ、願いが叶うという。
「願い事をしようと思います」
「……十夜さん?」
十夜さんが線香花火から視線を逸らして、私を見つめてきた。線香花火のオレンジが映り込んだ瞳は、夏の風より熱を孕んでいて、胸がトクンと大きく高鳴る。
「凛子さん、僕と結婚してください」
「――っ」
私が十夜さんの瞳に捕えられたまま動けずにいると、線香花火はゆっくりと玉を落とさず消えて行った。
夜空の星も、頬を撫でる風も、遠くで聞こえる虫の声も。全てが現実だと教えてくれているのに、夢のようで。頭の中は真っ白となり、身体はフワフワと浮いているようだった。
「……よろしく、お願いします」
私が答えることができたのは、オレンジの明りが消えて随分と経ってから。十夜さんは胸に詰まったものを全て吐き出すように、大きく息を吐いた。
「よかった……! 心臓が飛び出しそうなほど緊張しました。最後は線香花火がどうやって消えたのか、よくわからなかった」
胸元を押さえた十夜さんは、安堵したように笑う。全く緊張しているように見えなかったので、その様子が意外だった。
十夜さんがそれほどまで、思い詰めて告げてくれたプロポーズ。そう思うと、知らず知らずのうちに目尻から涙が零れてきた。
「り、凛子さん? どうしました、驚かせすぎましたか?」
「すごく、嬉しいです……っ」
「ええ、僕も……とても嬉しい」
十夜さんは私をそっと胸に抱き寄せ、涙が流れた頬に口づけをしてくれた。
それはとても温かく、今までの不安も、これからの未来も。全てを明るく照らしてくれる気がした。
「最後の線香花火、一緒にやりませんか?」
私が落ち着くと、十夜さんは最後の一本を取り出して私に尋ねた。
「一緒に……ですか?」
「はい」
十夜さんは私に答えながら、最後の線香花火にライターで火を付けた。
十夜さんが熱くない部分を差し出してくれ、私が指でつまむと、十夜さんは細くなった上の部分を摘まんだ。
線香花火はゆっくりと燃えながら、やがて激しく弾けながら燃えだした。
この花火も玉となって、落ちずに消えてくれるだろうか。もし、そうだとすれば――。
「十夜さん。一緒に、願い事をしませんか?」
私が提案すると、十夜さんは花火を見つめていた瞳をこちらに向けた。
「わかりました。どういった願い事にしますか?」
十夜さんがゆっくりと顔を覗きこんでくる。オレンジ色が映り込んだ艶めく瞳に吸いこまれそうになる瞬間、私は願い事を口にした。
「十夜さんと……幸せな家庭が作れますように」
まだまだ未来は長いから。何があるかわからない。だけど、十夜さんと一緒なら……。
「では僕も、凛子さんと幸せな毎日が送れますように」
十夜さんは優しい声音で返事をしてくれる。ゆっくりと唇が近づき、私のそれにそっと重なった。
星が輝く空の下、二人で持ったままの線香花火は、玉を落とすことなく静かに燃えて消えていった――。
【夏の花火編・完】