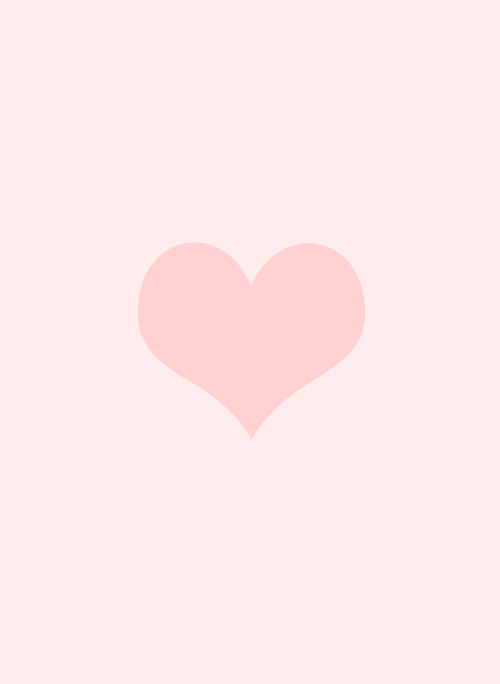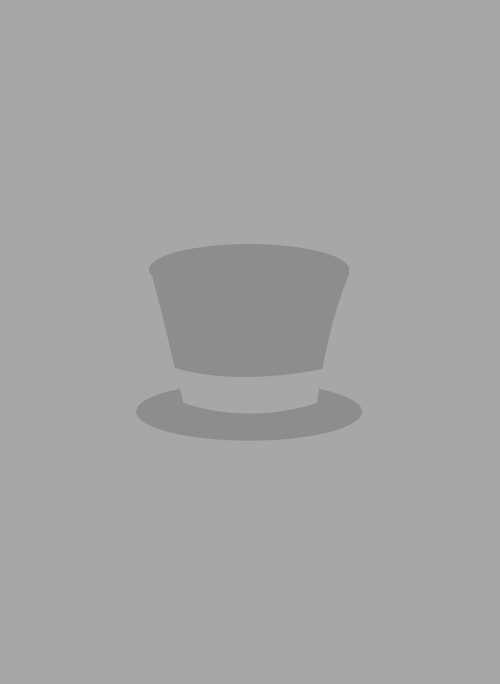goldscull・不完全な完全犯罪Ⅲ
MAIは、ゴールドスカルのペンダントヘッドが付いたチェーンが木暮敦士の首を切断したとは思っていなかった。
勿論、木暮敦士の死因がチェーンによる物だと聞いてはいたのだが……
だから……
ボンドー原っぱの告別式の日、カフェで会った彼の首にそれが掛かっているのを見て驚いてしまったのだ。
MAIが逮捕された時、彼女は本当にゴールドスカルの手に入れたいきさつを知りたいと思っただけだったのだ。
自分の購入したゴールドスカルのペンダントヘッドとそのチェーンが如何なるルートで彼に渡ったのか知りたかっただけなのだ。
MAIは木暮の兄貴の恋人だった。
ボンドー原っぱは、其処のギタリストだったのだ。
二人は幼なじみだったのだが、両親の離婚で原田学が引っ越ししていたのだ。
だから原田学の母は、地元で葬儀をしたのだった。
介護ヘルパーの養成所で二人は再会したようだ。
そして、ロックグループを立ち上げたのだ。
最初は施設でのパフォーマンスで披露したようだ。
それが評判を呼び、次々とお呼びがかかるようになる。
そしてインディーズとしての活躍が始まったのだった。
叔父さんの探偵事務所にMAIが居た。
警察から釈放された報告だった。
(――やっぱり可愛い!)
俺はときめいていた。
でもMAIは新しく恋人とやり直したいと言う。
「私やっぱりロッカーが大好きなの」
MAIは精一杯明るく笑った。
浮気者だと言う彼。
でもMAIなら大丈夫だと俺は思った。
(――でも何故、新しい彼もスキンヘッドだったんだろう?
――きっとそれもマネージャーが企んたんだ。
――もしかしたら、彼まで殺す気だったのだろうか?)
俺はゾクッとして、思わずみずほのコンパクトを握り締めていた。
「あぁ、言い忘れてました。彼ね、私を脅かすためにスキンヘッドにしたんだって。でも本当は解っていたの。原田君との噂を気にしていたんだと。本当に何でもないのよ」
MAIは明るく言い放った。
でも本当は違っていたようだ。
彼はマネージャーからスキンヘッドを勧められていたのだ。
ゴールドスカルのペンダントヘッドもマネージャーが彼に託した物だった。
『彼女の気持ちを確かめるには、これをするのが一番よ』
そう言ってたそうだ。
それを身に付けることによって、二人を仲違いさせようとしていたのに違いない。
俺は後日、MAIの彼氏と会っていた。
その言葉を聞いた時そう思った。
ストーカーはマネージャーだった。
木暮敦士の時も、原田学の時も。
原田学は木暮敦士がスキンヘッドで殺されていたことを知っていた。
何故なら彼はあの現場を見ていたからだ。
ライブイベントパフォーマンスで、あのデパートにギタリストとして参加していたからだ。
だから原田学は自分がスキンヘッドになっていると気付いた時震え上がったのだろう。
あまりに慌てていたから、ゴールドスカルのペンダントヘッドの付いたチェーンが自分の首に掛けられていたことにも気付かなかったのだ。
そのチェーンで、殺されることになるなんて……
原田学はマネージャーにとってただの玩具だったのだろうか?
原田学は自分の携帯で木暮敦士に電話した。
思考回路が絶不調だったに違いない。
でもそのお陰でイワキ探偵事務所にたどり着いたのだ。
俺の親友、木暮敦士の弟の機転で。
叔父さんが元凄腕の刑事だったと、俺は自慢していたからだ。
でも、ストーカーになったマネージャーはその一部始終を見ていたのだ。
だから帰りのバスで襲えたのだ。
バスの映像の中に、ゴールドスカルのペンダントヘッドを手に取った人が写っていた。
きっとそれがマネージャーに違いないと俺は思った。
その事実を知ったMAIの彼氏はすっかり意気消沈した。
もしかしたら、ラブデスゲームの被害者になるかも知れなっかたからだ。
自分が好きになった男の気持ちを掴むためには手段を選ばない。
彼女もきっと邪悪になっていたのだろう。
MAIやみずほは別として、女性は怖いと思った。
でも何時かは俺も恋をしたい。
みずほのことを忘れるつもりはないけれど、いつまでもウジウジしていたらみずほが悲しむと思ったんだ。
街はクリスマスツリーが輝いている。
俺に新しい恋人でも出来たらきっと二人で……
何て思いながら木暮と見ていた。
でも一つ困ったことが起きた。
すっかり女装に木暮が嵌まってしまったのだ。
『今後はもっと上手くやるから又手伝わせてくれ』
木暮がはそう言いながら叔父さんにウインクした。
(――えっー!?
もしかしたら俺の相棒?
――やだ、益々サッカーが出来なくなる。
――あぁ、俺の夢が……
――でも、それもいいかも?)
『なぁ、また女子会に潜入しようよ』
木暮が俺の耳元で囁く。
「でも学校に知れたら大変だぞ」
俺はさも知り尽くしたように言ってやった。
「女装なんて、仕事だけで充分だ』
俺はそう言いながら、叔父さんの奥さんのワンピースを見ていた。
(――そうだよ。浮かれている場合じゃなかった。
――叔母さんの敵討ちが先決だったんだ)
形見のワンピースにそっと触れる。
(――叔母さん待ってて、必ず叔父さんと一緒に犯人を探して出してみせるから)
心がジンジンと疼き、新たな闘志に掻き乱さられていく。
俺は改めて、事件解決を誓っていた。
完。
勿論、木暮敦士の死因がチェーンによる物だと聞いてはいたのだが……
だから……
ボンドー原っぱの告別式の日、カフェで会った彼の首にそれが掛かっているのを見て驚いてしまったのだ。
MAIが逮捕された時、彼女は本当にゴールドスカルの手に入れたいきさつを知りたいと思っただけだったのだ。
自分の購入したゴールドスカルのペンダントヘッドとそのチェーンが如何なるルートで彼に渡ったのか知りたかっただけなのだ。
MAIは木暮の兄貴の恋人だった。
ボンドー原っぱは、其処のギタリストだったのだ。
二人は幼なじみだったのだが、両親の離婚で原田学が引っ越ししていたのだ。
だから原田学の母は、地元で葬儀をしたのだった。
介護ヘルパーの養成所で二人は再会したようだ。
そして、ロックグループを立ち上げたのだ。
最初は施設でのパフォーマンスで披露したようだ。
それが評判を呼び、次々とお呼びがかかるようになる。
そしてインディーズとしての活躍が始まったのだった。
叔父さんの探偵事務所にMAIが居た。
警察から釈放された報告だった。
(――やっぱり可愛い!)
俺はときめいていた。
でもMAIは新しく恋人とやり直したいと言う。
「私やっぱりロッカーが大好きなの」
MAIは精一杯明るく笑った。
浮気者だと言う彼。
でもMAIなら大丈夫だと俺は思った。
(――でも何故、新しい彼もスキンヘッドだったんだろう?
――きっとそれもマネージャーが企んたんだ。
――もしかしたら、彼まで殺す気だったのだろうか?)
俺はゾクッとして、思わずみずほのコンパクトを握り締めていた。
「あぁ、言い忘れてました。彼ね、私を脅かすためにスキンヘッドにしたんだって。でも本当は解っていたの。原田君との噂を気にしていたんだと。本当に何でもないのよ」
MAIは明るく言い放った。
でも本当は違っていたようだ。
彼はマネージャーからスキンヘッドを勧められていたのだ。
ゴールドスカルのペンダントヘッドもマネージャーが彼に託した物だった。
『彼女の気持ちを確かめるには、これをするのが一番よ』
そう言ってたそうだ。
それを身に付けることによって、二人を仲違いさせようとしていたのに違いない。
俺は後日、MAIの彼氏と会っていた。
その言葉を聞いた時そう思った。
ストーカーはマネージャーだった。
木暮敦士の時も、原田学の時も。
原田学は木暮敦士がスキンヘッドで殺されていたことを知っていた。
何故なら彼はあの現場を見ていたからだ。
ライブイベントパフォーマンスで、あのデパートにギタリストとして参加していたからだ。
だから原田学は自分がスキンヘッドになっていると気付いた時震え上がったのだろう。
あまりに慌てていたから、ゴールドスカルのペンダントヘッドの付いたチェーンが自分の首に掛けられていたことにも気付かなかったのだ。
そのチェーンで、殺されることになるなんて……
原田学はマネージャーにとってただの玩具だったのだろうか?
原田学は自分の携帯で木暮敦士に電話した。
思考回路が絶不調だったに違いない。
でもそのお陰でイワキ探偵事務所にたどり着いたのだ。
俺の親友、木暮敦士の弟の機転で。
叔父さんが元凄腕の刑事だったと、俺は自慢していたからだ。
でも、ストーカーになったマネージャーはその一部始終を見ていたのだ。
だから帰りのバスで襲えたのだ。
バスの映像の中に、ゴールドスカルのペンダントヘッドを手に取った人が写っていた。
きっとそれがマネージャーに違いないと俺は思った。
その事実を知ったMAIの彼氏はすっかり意気消沈した。
もしかしたら、ラブデスゲームの被害者になるかも知れなっかたからだ。
自分が好きになった男の気持ちを掴むためには手段を選ばない。
彼女もきっと邪悪になっていたのだろう。
MAIやみずほは別として、女性は怖いと思った。
でも何時かは俺も恋をしたい。
みずほのことを忘れるつもりはないけれど、いつまでもウジウジしていたらみずほが悲しむと思ったんだ。
街はクリスマスツリーが輝いている。
俺に新しい恋人でも出来たらきっと二人で……
何て思いながら木暮と見ていた。
でも一つ困ったことが起きた。
すっかり女装に木暮が嵌まってしまったのだ。
『今後はもっと上手くやるから又手伝わせてくれ』
木暮がはそう言いながら叔父さんにウインクした。
(――えっー!?
もしかしたら俺の相棒?
――やだ、益々サッカーが出来なくなる。
――あぁ、俺の夢が……
――でも、それもいいかも?)
『なぁ、また女子会に潜入しようよ』
木暮が俺の耳元で囁く。
「でも学校に知れたら大変だぞ」
俺はさも知り尽くしたように言ってやった。
「女装なんて、仕事だけで充分だ』
俺はそう言いながら、叔父さんの奥さんのワンピースを見ていた。
(――そうだよ。浮かれている場合じゃなかった。
――叔母さんの敵討ちが先決だったんだ)
形見のワンピースにそっと触れる。
(――叔母さん待ってて、必ず叔父さんと一緒に犯人を探して出してみせるから)
心がジンジンと疼き、新たな闘志に掻き乱さられていく。
俺は改めて、事件解決を誓っていた。
完。