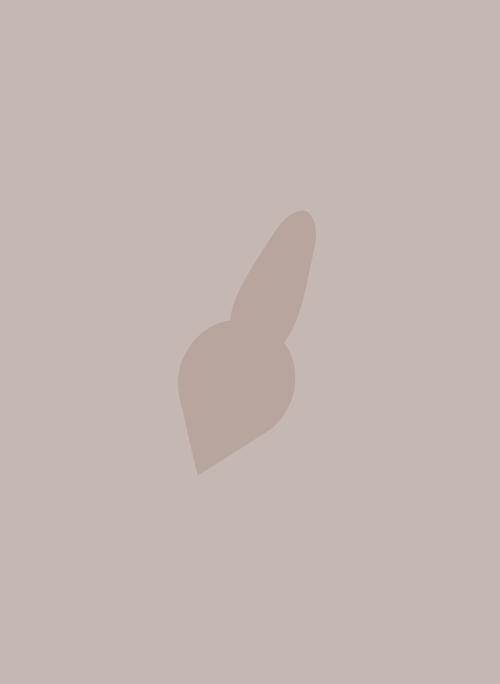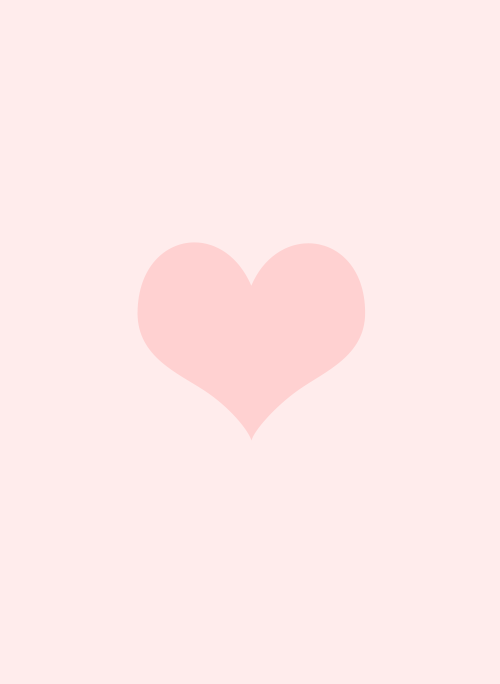真夜中の魔法使い
「ハルト、お前がこれまでウチに手が回らないようにしていたのか。」
いきなりなにを言っているのか、と首を傾げたのは、ミユウ1人だけだった。
「手が回らなかった、というのは結果に過ぎませんが。
幾つか嘘の報告を挙げただけです。」
「そうか。
では、そっちのおじさんは?」
何が、「そうか。」なのですかと質問をしようとしたのにそんな暇も与えず、今度は矛先をヨウさんに向けたミナト。
「て、てゆうかお兄ちゃん、失礼だよ!!」
「いーのいーの!天才君はそうでなくっちゃ!」
今度こそ口を挟んでしまったけれど、ヨウさんはいたってご機嫌そうである。ここまでくると寛容、というよりは変わり者のレベルだ。
「このふたりのおじにあたるから、本当に、おじさんだしね。まあこの通り、家のことは兄さんに任せて悠々自適な生活を送らせてもらってる。呪詛の分解薬の開発者、と言えば少しは信頼してくれるかな?」
「ええっ!分解薬、って、あの?」
あまりの驚きに、普段出さないような大きな声が出てしまい、そんな自分に対しても驚いていた。