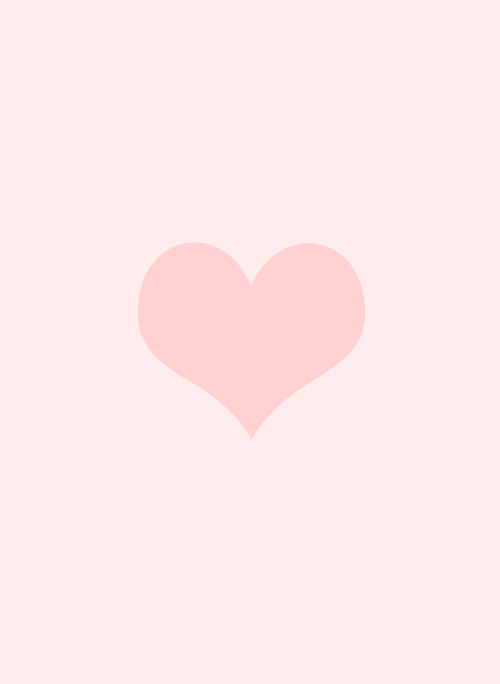およしなさいよ、うさぎさん。
◇
それから程なくして、重永家第三の邸宅では篤と菖の祝言の準備が着々とすすめられていた。
この第三の邸宅というのも、何か味気なくてつまらないものなので、篤はこの家を「白兎(はくと)邸」と改名した。そもそも、父が生きてた頃にわかりやすいように、一、二、三と数を当てはめただけなのであって、その第三は、一とも二とも所有者が違ってしまったのでちょうどよかったのだ。篤の母は「おかしな名前だこと」と笑っていたが、噂のうさぎ娘とお会いして息子が言っていたことの大半が理解できた。
そして、この白兎邸に篤が欲しがった風呂も出来た。大工を呼んで、家族で入れるようにと少し大きめの木の風呂をつくったのだ。多江は「祝言の日を迎えるまでは別々にいたしてください。駄目でございますからね」と口うるさく言っておいたのに、篤は完成初日にさっさと菖の手を引きお着物を脱がし、二人でご入浴してしまう。外で薪をくべて火を起こしていた多江は「あぁ……篤さま……」という聞き慣れた菖の艶声を聞かされ、「ですから……声が……」と叱ろうとしたが、まあ……それでもお二人とも幸せそうですし……と思い直し「篤さま、お湯加減よろしいですか? 多江は布団を敷いて参りますよ!」と薪をいくつかくべて、私も幸せにございます、と思うことにしたのだ。
祝言の日は多江もハツもユウも大忙しで屋敷の中を駆け回っていた。重永本邸の女中に、秋田家の使用人たちも手伝にいらしてくれたのだが、勝手をしっているのが三人しかいないために結局は大忙しとなった。
篤の母と、菖の両親は一度お顔見せをしたのでこの日は和やかな雰囲気だった。多江が走る縁側で三人で祝い茶を飲んだのだ。菖の両親は最初は自分たちなど……と遠慮していたが、篤の母はそんなことは過去のことと気にする素振りは微塵もみせなかった。
「重永様のご主人様は、さぞ次男の篤様をお可愛がりいたしてたと聞きました。この祝いの日をどんなに待ち望んだことでしょうね」と菖の母はなんともおっとりと話す。篤の母は、「きっとお空から見ておりますよ。いつも、いつも、篤、篤とあれを気にかけておりましたので」と答え空を見上げた。
親同士の話をしながら、新郎新婦のおしたくが整うのを今か今かと待ちわびていた。
白無垢姿で化粧を終えた菖が「篤さま……」と恥ずかしそうに俯き、長い睫がよりいっそう魅力的になってしまわれたので、篤は腰を抜かしそうになった。
「あや……め…………」と息も絶え絶えになりながら、なんとかその手を握りしめてやったが、自分の手の方が震えてしまっていた。それではいけないと咳払いして背をただす。
「準備はもういいかい?」
「はい。今日(こんにち)より、あなたのおそばで妻として生きてゆきます。準備は整いました、あなた」
篤は気が狂いそうなほどの至福が次から次へと押し寄せてくるので、どうにかなってしまいそうだ。
しかし、ここは男なので「よし」と低く勇ましい声を出し、菖の半歩先を歩いた。
床の間では、両家の親と、篤の兄さまと嫁さま、それから菖の姉さまとその夫の秋田さまが顔を合わせて座っており、二人は高砂の掛け軸の前に並ばされ、鶴と亀の縁起物の前で盃事をおこなった。
その後の祝宴には様々な人が招待され、塔野や荘司さんなども酒を飲みにやってきた。
篤の兄は、秋田家との親戚付き合いができてとても喜び「でかした! 篤」と結婚祝いを奮発してくれたが、篤にとってはこちらの古くからの兄より、新しい秋田という兄の方が話も合い、信頼できるお相手だと考えていた。
新しい兄は、お忙しい傍ら文学にも興味がおありで篤が見たことも読んだこともない西洋の書物などを貸してくださったりもした。篤があまりに「兄上、兄上」と秋田家に通うものだから、菖が妬いたくらいだ。
秋田も教師をしている篤は、学があり最高の話し相手となっていたので、仕事に暇ができては妻を連れて白兎邸に遊びに来たのだ。
菖の姉 百合(ゆり)は、菖から健気さを引いてそこに華美さを付け加えた女だ。華やかでいて優雅な心を持っている。伝説の遊女とうたわれていたことにも大層頷けてしまう。
とくに祝言のことなどは、つい最近したばかりですので、と仰りとかくよく菖の面倒をみてくださる。百合の腹には待望の御子がいるのだが、その優美さはかわらず篤はいつも新しい姉さまに感心させられていた。
宴(うたげ)は遅くまで続き、篤は浴びるほど祝いの酒を飲まされ菖の膝に頭をのせて心地良さそうに眠ってしまうので、困ったのは菖の方だ。
皆から冷やかされ、顔を真っ赤にしてしまう。その姿に男たちは悔しがり、酔っ払いの花婿を川に放り投げようと良からぬ悪巧みをはじめたくらいであった。
朝日がのぼる少し前に宴は終わり、菖は最後のお客様までをしっかり見送ると眠っている夫に寄りかかって目を閉じた。幸せすぎて、全部が幻影になって消えてしまわないか怖くてたまらなくなったのだが、寝ぼけた篤が「菖……」と自分を抱きしめてくれるので、菖はまた幸せの真ん中にいれたのだ。
祝言が終わり、また幾日があっという間に過ぎてゆき、内祝いなどを配り歩いて、ようやく日常を取り戻した頃。二人は菖が作ったとても甘すぎる牛鍋をつついてから、縁側で夜風にあたっていた。
篤の肩に頭を預けていた菖が「篤さま、明日はお仕事でございましょう。そろそろ床に入りましょうか」と囁くので、篤はさっそく「そうしよう」と菖の手を引いた。
篤は女学校でのお勤めを終えても、家に書物を持ち込み菖に読み書きなどを教えてくださるのだ。忙しそうな篤を菖は気遣ったつもりだったのだが、篤の思惑は別のところにあった。
「あぁ……篤さま、先ほど風呂場でいたしたではないですか……」
菖の腰紐をしゅっと引き抜くと、篤は「風呂場は風呂場。布団は布団」と納得に苦しむ言い訳をなさり、菖の胸を両の手で優しく包む。
「……ぁん、篤さま、また朝寝坊をしてしまいますよ……結婚したから朝寝坊ばかり、と塔野さまに文句を言われてしまいますゆえ」
「あいつも、下世話な男でございましょう」
篤は、つんと尖った胸の先を舌で柔らかく刺激する。
「ああぁぁ……」
「菖が喜んでいるのだから、仕方ないのですよ。満足させてやるが夫の役目」
篤は「こうがいいですか?」と胸の形がかわるほどぐいっと揉み上げて、尖った部分を口に含んだ。
「そんなぁ……そんなお役目など菖は聞いたことがございません……あっ」
菖の表情を見逃さないように篤はゆっくり丁寧に愛撫を繰り返す。そのもどかしさが、いつも菖をたまらなくさせてしまうとも知らずに、じっと菖を観察しながら深く深く愛すので毎度月が高く上がるまで菖は全身を痙攣させながら何度も絶頂に導かれてしまうのだ。
すっかり薄い寝間着をはぎ取られた菖は月の光を浴びて白い肌を全て篤に見られてしまい「あん」と甲高い声をあげる。
絶頂の合図だ、と篤は嬉しくなって、菖の割れ目を探り、十分すぎるほど濡れている密所に男根の先端を押し当てた。
ぐちゅりと卑猥な音がして「あぁ」と恥ずかしさから菖は両の手で顔を覆った。
篤は「だめですよ」と手を布団に押し付けて、そしてずぶずぶと沈み込む。
最後は少し強引に押し込むようにしてやると、ぱんと皮膚をうつ音がして菖がびくんびくんと体を揺らして目が虚ろにちゅうを舞う。
そのような菖を見ているだけで篤は射精してしまいたくなるのだが、まだ少し楽しもうと、喉仏を上下させ射精にたえると、ずっずっと腰を動かしはじめる。
「あっ……あっ……」
虚ろな瞳に光が戻り、菖はまた別の絶頂を探しはじめたので、それを導くように優しく抽出を繰り返し、だんだんと激しくしていく。
菖の首筋に浮かんだ汗を味わい、耳を甘噛みして、篤はそこに「愛しています」と囁いた。
菖は、こくこく頷いているようだが、篤が動きをやめないので声がうまく出せないのか「ふぁ………は……い」と喘いで篤の首にきゅうと抱きついてきた。
これは絶品だ…………と思うと、もう射精は耐えられず、菖も布団もがくんがくんと乱しながら激しく男根を打ちつけて、頭が真っ白になるほどの快楽を全身で味わう。
何度いたしてもやめられぬのは……腕の中で可愛らしく丸まる菖がいるから……
「菖は……厭らしい女でございましょう。何度いたしても、もっと、もっと、もっと、と篤さまが欲しくなってしまいます」
菖が瞳から涙をこぼし、ひっ、と肩を揺らした。
「私も同じです。何度いたしても、もっと、もっと、もっと、菖を泣かせたくなります」
菖が、もう篤さまは意地悪にございます、と弱々しくおっしゃるので、その細い体を抱きしめると、恥ずかしそうに泣く菖を見つめた。
なんとお可愛らしい存在なのだろう……篤が目を細めると、菖は恥ずかしさに耐えきれなくなり顔を隠した。
─────およしなさいよ、うさぎさん。
篤は菖の顎に手をそえて自分の方に向かせると、赤くなった目の縁を指で拭い、唇を押し付け、もう逃がしません、と優しく微笑むのだった。
それから程なくして、重永家第三の邸宅では篤と菖の祝言の準備が着々とすすめられていた。
この第三の邸宅というのも、何か味気なくてつまらないものなので、篤はこの家を「白兎(はくと)邸」と改名した。そもそも、父が生きてた頃にわかりやすいように、一、二、三と数を当てはめただけなのであって、その第三は、一とも二とも所有者が違ってしまったのでちょうどよかったのだ。篤の母は「おかしな名前だこと」と笑っていたが、噂のうさぎ娘とお会いして息子が言っていたことの大半が理解できた。
そして、この白兎邸に篤が欲しがった風呂も出来た。大工を呼んで、家族で入れるようにと少し大きめの木の風呂をつくったのだ。多江は「祝言の日を迎えるまでは別々にいたしてください。駄目でございますからね」と口うるさく言っておいたのに、篤は完成初日にさっさと菖の手を引きお着物を脱がし、二人でご入浴してしまう。外で薪をくべて火を起こしていた多江は「あぁ……篤さま……」という聞き慣れた菖の艶声を聞かされ、「ですから……声が……」と叱ろうとしたが、まあ……それでもお二人とも幸せそうですし……と思い直し「篤さま、お湯加減よろしいですか? 多江は布団を敷いて参りますよ!」と薪をいくつかくべて、私も幸せにございます、と思うことにしたのだ。
祝言の日は多江もハツもユウも大忙しで屋敷の中を駆け回っていた。重永本邸の女中に、秋田家の使用人たちも手伝にいらしてくれたのだが、勝手をしっているのが三人しかいないために結局は大忙しとなった。
篤の母と、菖の両親は一度お顔見せをしたのでこの日は和やかな雰囲気だった。多江が走る縁側で三人で祝い茶を飲んだのだ。菖の両親は最初は自分たちなど……と遠慮していたが、篤の母はそんなことは過去のことと気にする素振りは微塵もみせなかった。
「重永様のご主人様は、さぞ次男の篤様をお可愛がりいたしてたと聞きました。この祝いの日をどんなに待ち望んだことでしょうね」と菖の母はなんともおっとりと話す。篤の母は、「きっとお空から見ておりますよ。いつも、いつも、篤、篤とあれを気にかけておりましたので」と答え空を見上げた。
親同士の話をしながら、新郎新婦のおしたくが整うのを今か今かと待ちわびていた。
白無垢姿で化粧を終えた菖が「篤さま……」と恥ずかしそうに俯き、長い睫がよりいっそう魅力的になってしまわれたので、篤は腰を抜かしそうになった。
「あや……め…………」と息も絶え絶えになりながら、なんとかその手を握りしめてやったが、自分の手の方が震えてしまっていた。それではいけないと咳払いして背をただす。
「準備はもういいかい?」
「はい。今日(こんにち)より、あなたのおそばで妻として生きてゆきます。準備は整いました、あなた」
篤は気が狂いそうなほどの至福が次から次へと押し寄せてくるので、どうにかなってしまいそうだ。
しかし、ここは男なので「よし」と低く勇ましい声を出し、菖の半歩先を歩いた。
床の間では、両家の親と、篤の兄さまと嫁さま、それから菖の姉さまとその夫の秋田さまが顔を合わせて座っており、二人は高砂の掛け軸の前に並ばされ、鶴と亀の縁起物の前で盃事をおこなった。
その後の祝宴には様々な人が招待され、塔野や荘司さんなども酒を飲みにやってきた。
篤の兄は、秋田家との親戚付き合いができてとても喜び「でかした! 篤」と結婚祝いを奮発してくれたが、篤にとってはこちらの古くからの兄より、新しい秋田という兄の方が話も合い、信頼できるお相手だと考えていた。
新しい兄は、お忙しい傍ら文学にも興味がおありで篤が見たことも読んだこともない西洋の書物などを貸してくださったりもした。篤があまりに「兄上、兄上」と秋田家に通うものだから、菖が妬いたくらいだ。
秋田も教師をしている篤は、学があり最高の話し相手となっていたので、仕事に暇ができては妻を連れて白兎邸に遊びに来たのだ。
菖の姉 百合(ゆり)は、菖から健気さを引いてそこに華美さを付け加えた女だ。華やかでいて優雅な心を持っている。伝説の遊女とうたわれていたことにも大層頷けてしまう。
とくに祝言のことなどは、つい最近したばかりですので、と仰りとかくよく菖の面倒をみてくださる。百合の腹には待望の御子がいるのだが、その優美さはかわらず篤はいつも新しい姉さまに感心させられていた。
宴(うたげ)は遅くまで続き、篤は浴びるほど祝いの酒を飲まされ菖の膝に頭をのせて心地良さそうに眠ってしまうので、困ったのは菖の方だ。
皆から冷やかされ、顔を真っ赤にしてしまう。その姿に男たちは悔しがり、酔っ払いの花婿を川に放り投げようと良からぬ悪巧みをはじめたくらいであった。
朝日がのぼる少し前に宴は終わり、菖は最後のお客様までをしっかり見送ると眠っている夫に寄りかかって目を閉じた。幸せすぎて、全部が幻影になって消えてしまわないか怖くてたまらなくなったのだが、寝ぼけた篤が「菖……」と自分を抱きしめてくれるので、菖はまた幸せの真ん中にいれたのだ。
祝言が終わり、また幾日があっという間に過ぎてゆき、内祝いなどを配り歩いて、ようやく日常を取り戻した頃。二人は菖が作ったとても甘すぎる牛鍋をつついてから、縁側で夜風にあたっていた。
篤の肩に頭を預けていた菖が「篤さま、明日はお仕事でございましょう。そろそろ床に入りましょうか」と囁くので、篤はさっそく「そうしよう」と菖の手を引いた。
篤は女学校でのお勤めを終えても、家に書物を持ち込み菖に読み書きなどを教えてくださるのだ。忙しそうな篤を菖は気遣ったつもりだったのだが、篤の思惑は別のところにあった。
「あぁ……篤さま、先ほど風呂場でいたしたではないですか……」
菖の腰紐をしゅっと引き抜くと、篤は「風呂場は風呂場。布団は布団」と納得に苦しむ言い訳をなさり、菖の胸を両の手で優しく包む。
「……ぁん、篤さま、また朝寝坊をしてしまいますよ……結婚したから朝寝坊ばかり、と塔野さまに文句を言われてしまいますゆえ」
「あいつも、下世話な男でございましょう」
篤は、つんと尖った胸の先を舌で柔らかく刺激する。
「ああぁぁ……」
「菖が喜んでいるのだから、仕方ないのですよ。満足させてやるが夫の役目」
篤は「こうがいいですか?」と胸の形がかわるほどぐいっと揉み上げて、尖った部分を口に含んだ。
「そんなぁ……そんなお役目など菖は聞いたことがございません……あっ」
菖の表情を見逃さないように篤はゆっくり丁寧に愛撫を繰り返す。そのもどかしさが、いつも菖をたまらなくさせてしまうとも知らずに、じっと菖を観察しながら深く深く愛すので毎度月が高く上がるまで菖は全身を痙攣させながら何度も絶頂に導かれてしまうのだ。
すっかり薄い寝間着をはぎ取られた菖は月の光を浴びて白い肌を全て篤に見られてしまい「あん」と甲高い声をあげる。
絶頂の合図だ、と篤は嬉しくなって、菖の割れ目を探り、十分すぎるほど濡れている密所に男根の先端を押し当てた。
ぐちゅりと卑猥な音がして「あぁ」と恥ずかしさから菖は両の手で顔を覆った。
篤は「だめですよ」と手を布団に押し付けて、そしてずぶずぶと沈み込む。
最後は少し強引に押し込むようにしてやると、ぱんと皮膚をうつ音がして菖がびくんびくんと体を揺らして目が虚ろにちゅうを舞う。
そのような菖を見ているだけで篤は射精してしまいたくなるのだが、まだ少し楽しもうと、喉仏を上下させ射精にたえると、ずっずっと腰を動かしはじめる。
「あっ……あっ……」
虚ろな瞳に光が戻り、菖はまた別の絶頂を探しはじめたので、それを導くように優しく抽出を繰り返し、だんだんと激しくしていく。
菖の首筋に浮かんだ汗を味わい、耳を甘噛みして、篤はそこに「愛しています」と囁いた。
菖は、こくこく頷いているようだが、篤が動きをやめないので声がうまく出せないのか「ふぁ………は……い」と喘いで篤の首にきゅうと抱きついてきた。
これは絶品だ…………と思うと、もう射精は耐えられず、菖も布団もがくんがくんと乱しながら激しく男根を打ちつけて、頭が真っ白になるほどの快楽を全身で味わう。
何度いたしてもやめられぬのは……腕の中で可愛らしく丸まる菖がいるから……
「菖は……厭らしい女でございましょう。何度いたしても、もっと、もっと、もっと、と篤さまが欲しくなってしまいます」
菖が瞳から涙をこぼし、ひっ、と肩を揺らした。
「私も同じです。何度いたしても、もっと、もっと、もっと、菖を泣かせたくなります」
菖が、もう篤さまは意地悪にございます、と弱々しくおっしゃるので、その細い体を抱きしめると、恥ずかしそうに泣く菖を見つめた。
なんとお可愛らしい存在なのだろう……篤が目を細めると、菖は恥ずかしさに耐えきれなくなり顔を隠した。
─────およしなさいよ、うさぎさん。
篤は菖の顎に手をそえて自分の方に向かせると、赤くなった目の縁を指で拭い、唇を押し付け、もう逃がしません、と優しく微笑むのだった。