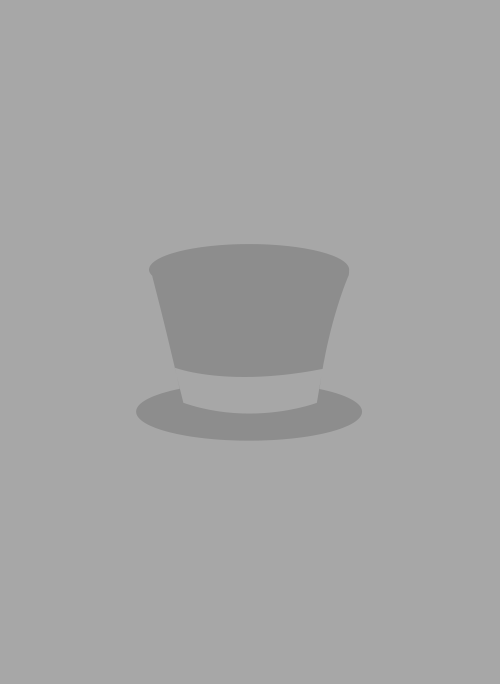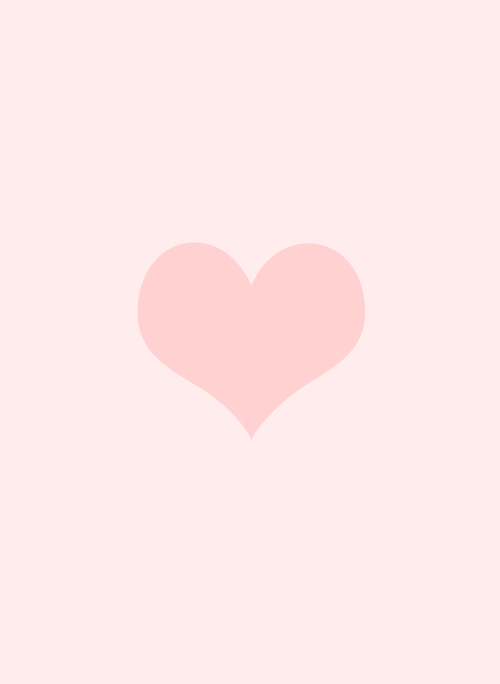ストックホルム・シンドローム
床に広がるコーヒーは、青年が生き絶えたその瞬間に茶色い波紋を広げた。
波紋はゆっくりと輪を大きく変化させ、白いワンピースを羽織った少女の裸足へと達する。
少女のまとう白いワンピースには、少量の返り血が付いていた。
少女は呆然と立ち尽くし、しばらくの間、微笑みを残し死んだ青年のことを感情のない目で見下げていた。
「…やっと帰れる。元の生活に」
少女は、口元を弓なりに歪めた。
監禁生活の始まった日から、少女は青年の元から逃げるタイミングを伺っていた。
青年が眠ったであろう夜になればベッドから起き上がり、音を立てないように歩を進め、ほんの少しの望みをかけドアノブを回す日々。
しかし、鍵のかけられていない日は一日たりともなかった。
(このままじゃ、殺されるかも…)
どんなことをしてでも、少女は家に帰りたかった。
そして思いついたのが、青年自身に拘束を外させ、油断した彼を殺して逃げる方法。
何度も頭の中でシミュレーションし、時期が来るのを待った。
手錠を鳴らし部屋に来させ、相手の心を揺さぶり、好きだと伝え、信頼してもらい、殺す。
それが計画の全てだった。
ふとした好奇心から訊いたチアキという女性の話を聞き、青年には多少の同情を抱いたが、ここに居ようとは思わなかった。
そして、監禁生活三ヶ月目となる今日、
計画を実行するに至った。
計画の途中、青年にナイフを突きつけられた時は一瞬 死を覚悟したが、少女は無意識のうちに言葉をなうていた。
『好きだよ。愛してる』と。
それは青年がいつも、少女にかけていた
言葉だった。
「…帰ろう」
少女は青年の死体をまたぎ、扉に手をか
け、何気なしに後ろを見る。
青年の最期の言葉を思い出す。
『あいしてる』
その言葉を、
少女はしっかりと聞いていた。
「…バカ、みたい」
首を振り、少女はふらふらと部屋の外に出る。
玄関を探し当て、扉を開けると、目に飛び込む鮮やかな色。
三ヶ月の暗闇の中で、その色は少女には眩しすぎるほどだった。
道を辿り、森の中を歩き出す。
懐かしい鳥の声、葉の香り。
頬を撫でる涼やかな風。
日付は、五月へと移り変わっていた。
(なんでわたし…知らないうちに
『愛してる』なんて言ったんだろう)
監禁されていた少女の瞳には、
溢れんばかりの涙が溜まっていた。
【Stockholm Syndrome】 end