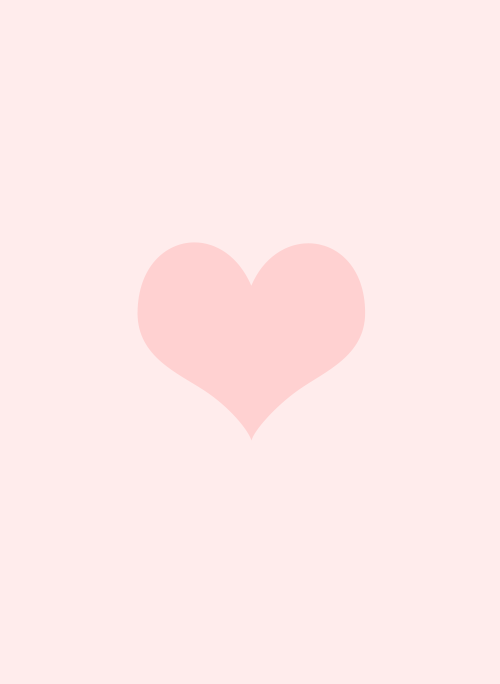最後の瞬間まで、きみと笑っていたいから。
「あー、地に足がついてるって素晴らしいな。地上最高」
多賀宮くんはいつもの調子で、首を回し、腕を伸ばしながら空を見上げる。
「もう観覧車は無理だからな」
「わかってるよ。高所恐怖症だもんね」
「うるせー、内緒だぞ」
さっぱりして、ちょっと意地悪っぽくて。いつもの多賀宮くんだ。
「帰るか」
彼は指をジーンズのポケットにねじ込んで、振り返る。
「うん」
私は歩き出した彼の背中を追いかけた。
彼に私はどんな風に映っているんだろう。
せめて私が彼を見る百分の一でもいいから、きれいに見えたらいいのに……。
大好きな多賀宮くんに出会えなかった人生なんて、もう考えられないほど、私は彼を自分にとってとても大事な人だと、思い始めていた。