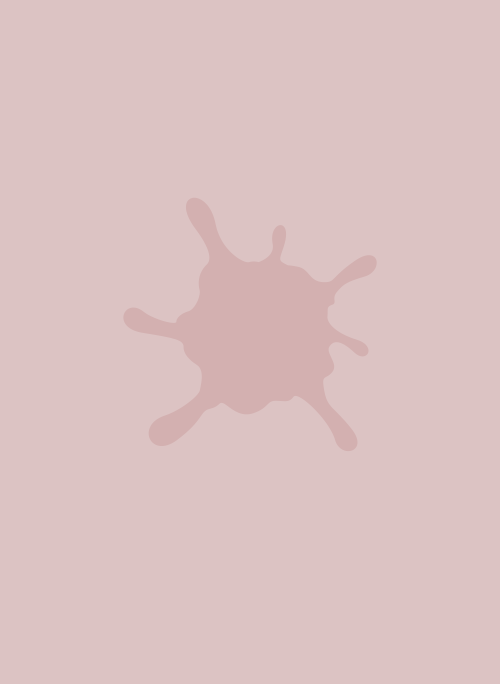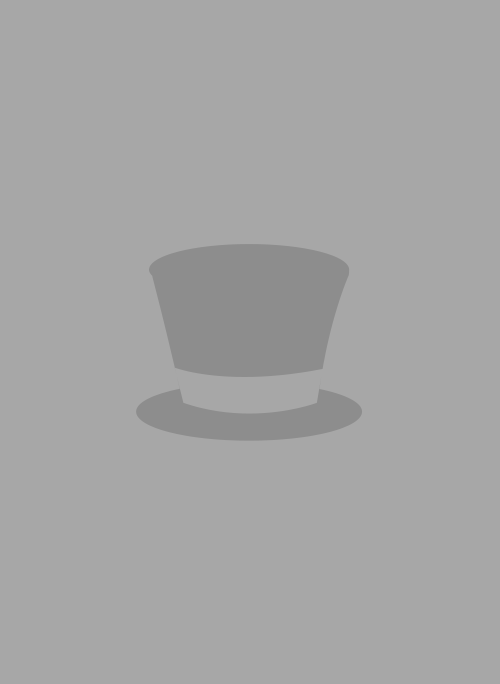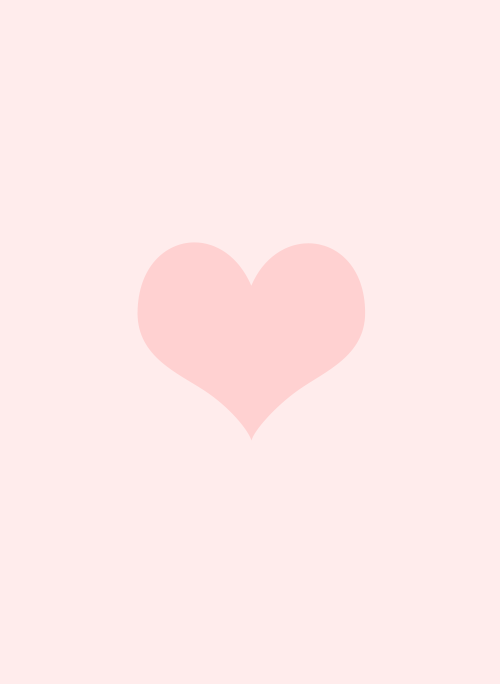Stockholm Syndrome【狂愛】
「……バカ、みたい」
首を振り、少女はふらふらと部屋の外に出る。
玄関を探し当て、扉を開けると、目に飛び込む鮮やかな色。まばゆいほどの太陽が目に刺さり、三ヶ月間の暗闇の中で、その色は痛みを感じるほどの鮮烈さを持っていた。
鳥の声が聞こえ、風が頬を撫でる。
葉の香りが鼻をつき、青い空が遠い。
日付は、五月へと移り変わっていた。
(なんでわたし……
『愛してる』なんて言ったんだろう)
監禁されていた少女の瞳には、
溢れんばかりの涙が溜まっていた。
【Stockholm Syndrome】 end