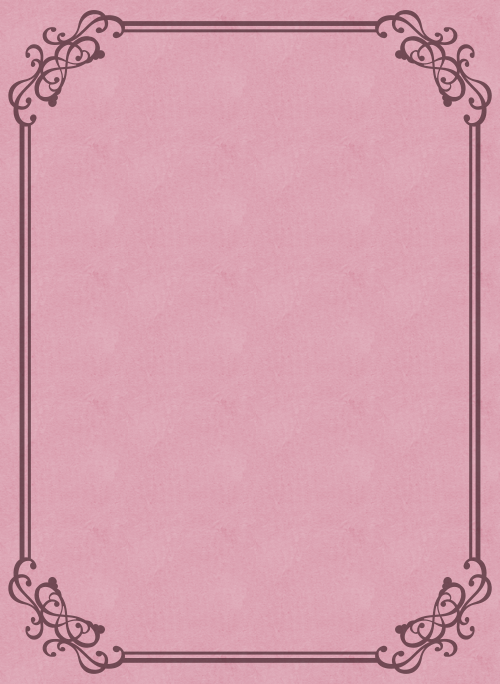我慢ばかりの「お姉様」をやめさせていただきます~追放された出来損ない聖女、実は魔物を従わせて王都を守っていました。追放先で自由気ままに村づくりを謳歌します~
ジェシカの納得いかない原因が〝色〟だとは思っていなかったので、私は驚いて間抜けな声で返事をしてしまった。
「こんな真っ黒なポーション、魔物さんはともかく、人間は絶対誰も飲んでくれません。でもどうアレンジしても黒くなってしまうんです……!」
両手で顔を覆い、ジェシカは今にも泣きそうな声でそう言った。見た目が悪いことは、ジェシカも重々わかっていたのね。それも、こんな深刻に。
「たしかに黒色はどんな色も塗り潰すけど、黒色を上から塗り潰すのは至難の業よね……あっ! ジェシカ、いい方法があるわ!」
むしろ、ずっと色のせいで薬の開発が遅れていたのなら、もっと早く相談してくれたらよかったのに。だって――。
「聖女の魔力をポーションに込めたらいいのよ。知ってる? 聖女の魔力が込められたポーションは金色になるの」
幼い頃からアンジェリカがポーション作りをしているのを見ていたし、私自身もやったことがある。
「金色のポーション……話を聞いたことはありますが、私の住んでた田舎では見たことのない上等品です」
聖女の魔力入りポーションは、普通のポーションよりも効果が倍と言われており値段も高い。上流階級の人間や戦績を残した冒険者たちでなければ、まず手に入れることはできない。
「そっか。アナスタシア様の力をポーションに込めればこの闇みたいな真っ黒ポーションもきっと……!」
両手で覆われていたジェシカの目が、再度見えるようになる。その瞳には、さっきまでなかった一筋の光が差し込んでいた。私はジェシカに向かって強く頷くと、ポーションの入った瓶を持って魔力を込める。瓶は光に包まれると、液体の色を金色に変えた。
「……わぁ! 綺麗……こんなに神秘的なポーションになるなんて」
ジェシカは瓶を手に取ると、瓶を回して様々な角度からポーションを観察し始めた。
「ありがとうございますアナスタシア様! これでやっと納得がいく出来になりました。万能薬草とアナスタシア様の力が込められたポーション……きっとすごいものになりますよ!」
「私もそう思うわ。これからは仕上げは私が担当するから、いつでも呼んでちょうだい」
「はいっ! ……でも、こんな素晴らしいポーションをこの村だけに留めておくのは、とてももったいないですね」
終末の村は、私が来たことによって魔物と人間の争いがない村になった。だから、回復に特化したポーションはそこまで使う機会がない。せっかく作ったのだから、必要としている人の手に届けたいと、ジェシカは考えているのだろう。そしてそれは――私も同じだ。
「ねぇジェシカ。このポーションを量産して、終末の村発のポーションとして売りに出しましょう! それでお金を作って、村の資金にするの」
この村での生活は基本的に自給自足。今はそれで成り立ってはいるが、安定した暮らしはできない。そもそも安定した暮らしなど与えないためにここへ追放されているので、そういう場所なのは当然のことっていうのは置いといて――もしこの村でしか作れないもので商売ができたら、それは村にとって大きな利益になる。
「⁉ そ、そんなことできるわけ……! 終末の村の住人が作ったものなど、誰も買ってはくれません」
「大丈夫。私に任せて。……いい考えがあるの」
私はジェシカの肩に手を置いて、にっこりと微笑んだ。
「こんな真っ黒なポーション、魔物さんはともかく、人間は絶対誰も飲んでくれません。でもどうアレンジしても黒くなってしまうんです……!」
両手で顔を覆い、ジェシカは今にも泣きそうな声でそう言った。見た目が悪いことは、ジェシカも重々わかっていたのね。それも、こんな深刻に。
「たしかに黒色はどんな色も塗り潰すけど、黒色を上から塗り潰すのは至難の業よね……あっ! ジェシカ、いい方法があるわ!」
むしろ、ずっと色のせいで薬の開発が遅れていたのなら、もっと早く相談してくれたらよかったのに。だって――。
「聖女の魔力をポーションに込めたらいいのよ。知ってる? 聖女の魔力が込められたポーションは金色になるの」
幼い頃からアンジェリカがポーション作りをしているのを見ていたし、私自身もやったことがある。
「金色のポーション……話を聞いたことはありますが、私の住んでた田舎では見たことのない上等品です」
聖女の魔力入りポーションは、普通のポーションよりも効果が倍と言われており値段も高い。上流階級の人間や戦績を残した冒険者たちでなければ、まず手に入れることはできない。
「そっか。アナスタシア様の力をポーションに込めればこの闇みたいな真っ黒ポーションもきっと……!」
両手で覆われていたジェシカの目が、再度見えるようになる。その瞳には、さっきまでなかった一筋の光が差し込んでいた。私はジェシカに向かって強く頷くと、ポーションの入った瓶を持って魔力を込める。瓶は光に包まれると、液体の色を金色に変えた。
「……わぁ! 綺麗……こんなに神秘的なポーションになるなんて」
ジェシカは瓶を手に取ると、瓶を回して様々な角度からポーションを観察し始めた。
「ありがとうございますアナスタシア様! これでやっと納得がいく出来になりました。万能薬草とアナスタシア様の力が込められたポーション……きっとすごいものになりますよ!」
「私もそう思うわ。これからは仕上げは私が担当するから、いつでも呼んでちょうだい」
「はいっ! ……でも、こんな素晴らしいポーションをこの村だけに留めておくのは、とてももったいないですね」
終末の村は、私が来たことによって魔物と人間の争いがない村になった。だから、回復に特化したポーションはそこまで使う機会がない。せっかく作ったのだから、必要としている人の手に届けたいと、ジェシカは考えているのだろう。そしてそれは――私も同じだ。
「ねぇジェシカ。このポーションを量産して、終末の村発のポーションとして売りに出しましょう! それでお金を作って、村の資金にするの」
この村での生活は基本的に自給自足。今はそれで成り立ってはいるが、安定した暮らしはできない。そもそも安定した暮らしなど与えないためにここへ追放されているので、そういう場所なのは当然のことっていうのは置いといて――もしこの村でしか作れないもので商売ができたら、それは村にとって大きな利益になる。
「⁉ そ、そんなことできるわけ……! 終末の村の住人が作ったものなど、誰も買ってはくれません」
「大丈夫。私に任せて。……いい考えがあるの」
私はジェシカの肩に手を置いて、にっこりと微笑んだ。