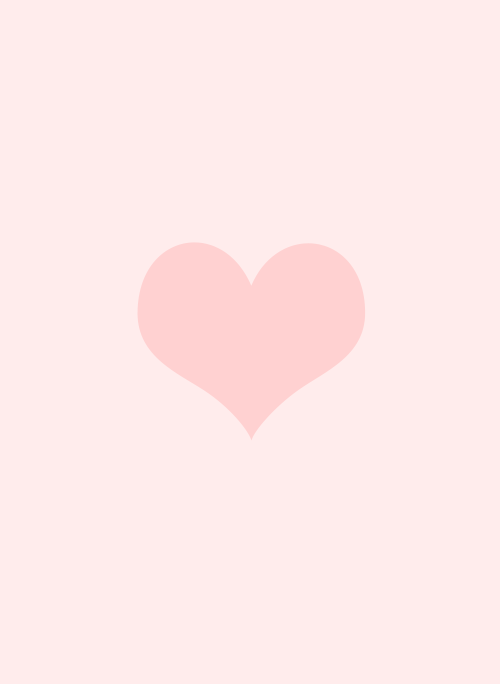恋はひと匙の魔法から
「私の料理には魔法がかかってるから、特別美味しいんです」
「魔法?……確かに、透子の料理は魔法みたいに美味いな」
遼太は冗談を笑い飛ばすように肩を竦めた。その反応は想定内だが、透子は敢えて唇を尖らせ、ムッとした表情を作る。
「あ、信じてないですね?本当ですよ」
「はいはい、分かったよ」
「もう!」
やっぱり軽くあしらわれ、透子はプクッと頬を膨らませた。だが内心ではこの軽口の応酬を楽しんでいる。
さして重要なことでもないのだ。
二人の関係が即物的に結ばれているのではないと、透子はもう何度も彼から教えてもらっている。
透子は顔を綻ばせてご飯を頬張った。
向かい合って食事を共にする。そんな何でもない日常全てが透子にとっては幸せそのもので、自然と笑みが浮かんでくる。
そんな中、不意に遼太が腹落ちしたように頷いた。
「でも確かに、魔法にはかけられてたかもな。最初に透子の弁当貰った時から、俺は透子に魅了されっぱなしだよ」
「じゃあ、ずっと好きでいてもらえるようにこれからも頑張らなきゃ」
「またそんなこと言ってる。あんまり夢中にさせすぎると、四六時中一緒にいたくなって、その内透子を膝に乗せて仕事し始めるぞ」
「えっ。それは嫌です」
何の罰ゲームだろう。
オフィスにあるまじきシュールすぎる光景が目に浮かび、思わず真顔になって拒絶すると、遼太は声を上げて笑った。
「好きだよ、透子。たとえ何にもなくたって、そのままの透子が好きだ」
爽やかに笑いながら遼太は率直に愛を囁いた。その言葉は真っ直ぐに透子の胸を打ち、多幸感をもたらしてくれる。
透子は心からの笑顔を遼太に向けた。
「私も大好きです、遼太さん」
「魔法?……確かに、透子の料理は魔法みたいに美味いな」
遼太は冗談を笑い飛ばすように肩を竦めた。その反応は想定内だが、透子は敢えて唇を尖らせ、ムッとした表情を作る。
「あ、信じてないですね?本当ですよ」
「はいはい、分かったよ」
「もう!」
やっぱり軽くあしらわれ、透子はプクッと頬を膨らませた。だが内心ではこの軽口の応酬を楽しんでいる。
さして重要なことでもないのだ。
二人の関係が即物的に結ばれているのではないと、透子はもう何度も彼から教えてもらっている。
透子は顔を綻ばせてご飯を頬張った。
向かい合って食事を共にする。そんな何でもない日常全てが透子にとっては幸せそのもので、自然と笑みが浮かんでくる。
そんな中、不意に遼太が腹落ちしたように頷いた。
「でも確かに、魔法にはかけられてたかもな。最初に透子の弁当貰った時から、俺は透子に魅了されっぱなしだよ」
「じゃあ、ずっと好きでいてもらえるようにこれからも頑張らなきゃ」
「またそんなこと言ってる。あんまり夢中にさせすぎると、四六時中一緒にいたくなって、その内透子を膝に乗せて仕事し始めるぞ」
「えっ。それは嫌です」
何の罰ゲームだろう。
オフィスにあるまじきシュールすぎる光景が目に浮かび、思わず真顔になって拒絶すると、遼太は声を上げて笑った。
「好きだよ、透子。たとえ何にもなくたって、そのままの透子が好きだ」
爽やかに笑いながら遼太は率直に愛を囁いた。その言葉は真っ直ぐに透子の胸を打ち、多幸感をもたらしてくれる。
透子は心からの笑顔を遼太に向けた。
「私も大好きです、遼太さん」