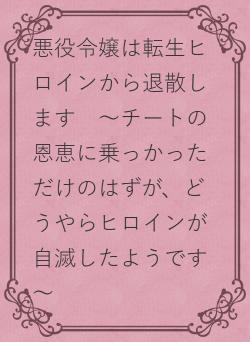『運命の相手』を探すあなたと落選した私
「……俺は、こうしてまた目が見えるようになった。けど、もし生まれつき盲目だったなら、相手が誰でも一目惚れしなかったわけだ。見えないんだから。だったらその場合、運命の相手ってどうやって探すんだろう。そう考えたとき――これ以上ないってくらい納得の行く、答が出た。俺はカエナに……一聞き惚れしてた」
「? どういう……?」
耳慣れない単語に、まだ夢見心地のまま反射的に聞き返す。
私の両腕にあったルシアンの手が離れる。その手が、今度は私の頬に添えられる。
彼に向ける目がどこかぼんやりしているのがわかったのだろう、私を現実に引き戻すようにルシアンの指先が私の頬の表面を滑った。
けれど――今、私にそうしているルシアンは、本当に現実の彼なのだろうか? そんなことを考えてしまうほど、熱を持った瞳で私を見つめるルシアンというのは現実味がなかった。
「俺たちが初めて会った日、挨拶を交わす前に俺はカエナの歌に魅せられてた。何度でもそれが聞きたくて、よく君の家に遊びに行ってた。五年ぶりにここへ戻ってきたときも、カエナだけは声を聞いただけで誰なのかわかった。カエナの想いには応えられないのに、カエナから離れたくない。君が同居していいか聞いてきたときも、罪悪感より喜びが勝ってしまった。正直言ってカエナ、君の男の趣味は悪いと思う」
「自分で言っちゃうんだ」
「言うだろ。こうやって暴露してもまだ、君が俺を好きって顔をしてるなら」
言ってルシアンが、私の肩にポンと手を置く。
見覚えのある、彼の癖。しかしそうされる心当たりはなくて、私は首を傾げた。
「何の励まし?」
「……この状況で逃げる素振りも見せないカエナが、可愛いを通り越して可哀想に思えてきての励まし」
「? 一体、何の話――ひゃあっ⁉」
突如ルシアンに腰を抱き寄せられ、私は慌てふためいた。
さらに私の肩口に彼が顔を寄せてきて、ただでさえドキドキしていた心臓がバクバクと余計に激しく鳴り出す。
「……あの、ルシアン?」
よくわからない励ましの延長線上でのハグかと思いきや、そこから一向に動こうとしない彼の名を呼んでみる。
それにルシアンが身動ぎという反応を見せて、ようやく彼が離れるとほっとしたのも束の間。ルシアンは何故か、さらに私を抱き締めてきた。
「だからその俺が好きって声、まずいから。この状態で俺の名前を呼ぶとか本当にまずい。冗談抜きで襲いかねない」
「ふふっ、私に興味を示すルシアンだなんて、見てみたいかも」
「ああもうっ、その口、塞ぐしかないな⁉」
「え」
ルシアンが顔を上げたかと思えば、それは直ぐさま私の眼前に降りてきた。
今度は青い瞳に見惚れる間もなく、気づけばゼロ距離。彼の瞳以上に鮮烈な感触が唇に来て、それが私のすべての感覚を攫っていった。
頭がぼうっとなったまま、近すぎて見えないルシアンの顔を見る。
(よく見えなくても、やっぱり好きだなあ)
そうしているうちに、長いようで短かったキスは終わりを告げた。
表情がわかるくらいまでルシアンが離れて、そのせいで耳まで真っ赤になった彼の顔が目に入る。
「またそんな顔して……。自覚がなかっただけで、俺も十二年好きだったんだ。これで終われると思うなよ?」
どこか不貞腐れたようにして言うルシアンに、私はおかしくて声を上げて笑ってしまった。
「ぐっ……笑ってるだけでも良い声だな、本当」
「ルシアンだって、ムスッとしていても良い顔よ」
私がそう返す間にも、ルシアンが再び距離を詰めてくる。
二回目のキスが来る前に、私は瞼を閉じた。
優しいキスを交わしたまま、静かな時間が流れる。
今、私はルシアンの顔が見えなくて、彼もまた私の声が発せられるのを彼自身が止めていて。
(それでもルシアンが好きだし、ルシアンからも好きって気持ちが伝わってくる)
十二年前、私はルシアンの運命の相手に落選した。
けれど、どうやらいつの間にか敗者復活を果たしていたらしい。
―END―
「? どういう……?」
耳慣れない単語に、まだ夢見心地のまま反射的に聞き返す。
私の両腕にあったルシアンの手が離れる。その手が、今度は私の頬に添えられる。
彼に向ける目がどこかぼんやりしているのがわかったのだろう、私を現実に引き戻すようにルシアンの指先が私の頬の表面を滑った。
けれど――今、私にそうしているルシアンは、本当に現実の彼なのだろうか? そんなことを考えてしまうほど、熱を持った瞳で私を見つめるルシアンというのは現実味がなかった。
「俺たちが初めて会った日、挨拶を交わす前に俺はカエナの歌に魅せられてた。何度でもそれが聞きたくて、よく君の家に遊びに行ってた。五年ぶりにここへ戻ってきたときも、カエナだけは声を聞いただけで誰なのかわかった。カエナの想いには応えられないのに、カエナから離れたくない。君が同居していいか聞いてきたときも、罪悪感より喜びが勝ってしまった。正直言ってカエナ、君の男の趣味は悪いと思う」
「自分で言っちゃうんだ」
「言うだろ。こうやって暴露してもまだ、君が俺を好きって顔をしてるなら」
言ってルシアンが、私の肩にポンと手を置く。
見覚えのある、彼の癖。しかしそうされる心当たりはなくて、私は首を傾げた。
「何の励まし?」
「……この状況で逃げる素振りも見せないカエナが、可愛いを通り越して可哀想に思えてきての励まし」
「? 一体、何の話――ひゃあっ⁉」
突如ルシアンに腰を抱き寄せられ、私は慌てふためいた。
さらに私の肩口に彼が顔を寄せてきて、ただでさえドキドキしていた心臓がバクバクと余計に激しく鳴り出す。
「……あの、ルシアン?」
よくわからない励ましの延長線上でのハグかと思いきや、そこから一向に動こうとしない彼の名を呼んでみる。
それにルシアンが身動ぎという反応を見せて、ようやく彼が離れるとほっとしたのも束の間。ルシアンは何故か、さらに私を抱き締めてきた。
「だからその俺が好きって声、まずいから。この状態で俺の名前を呼ぶとか本当にまずい。冗談抜きで襲いかねない」
「ふふっ、私に興味を示すルシアンだなんて、見てみたいかも」
「ああもうっ、その口、塞ぐしかないな⁉」
「え」
ルシアンが顔を上げたかと思えば、それは直ぐさま私の眼前に降りてきた。
今度は青い瞳に見惚れる間もなく、気づけばゼロ距離。彼の瞳以上に鮮烈な感触が唇に来て、それが私のすべての感覚を攫っていった。
頭がぼうっとなったまま、近すぎて見えないルシアンの顔を見る。
(よく見えなくても、やっぱり好きだなあ)
そうしているうちに、長いようで短かったキスは終わりを告げた。
表情がわかるくらいまでルシアンが離れて、そのせいで耳まで真っ赤になった彼の顔が目に入る。
「またそんな顔して……。自覚がなかっただけで、俺も十二年好きだったんだ。これで終われると思うなよ?」
どこか不貞腐れたようにして言うルシアンに、私はおかしくて声を上げて笑ってしまった。
「ぐっ……笑ってるだけでも良い声だな、本当」
「ルシアンだって、ムスッとしていても良い顔よ」
私がそう返す間にも、ルシアンが再び距離を詰めてくる。
二回目のキスが来る前に、私は瞼を閉じた。
優しいキスを交わしたまま、静かな時間が流れる。
今、私はルシアンの顔が見えなくて、彼もまた私の声が発せられるのを彼自身が止めていて。
(それでもルシアンが好きだし、ルシアンからも好きって気持ちが伝わってくる)
十二年前、私はルシアンの運命の相手に落選した。
けれど、どうやらいつの間にか敗者復活を果たしていたらしい。
―END―